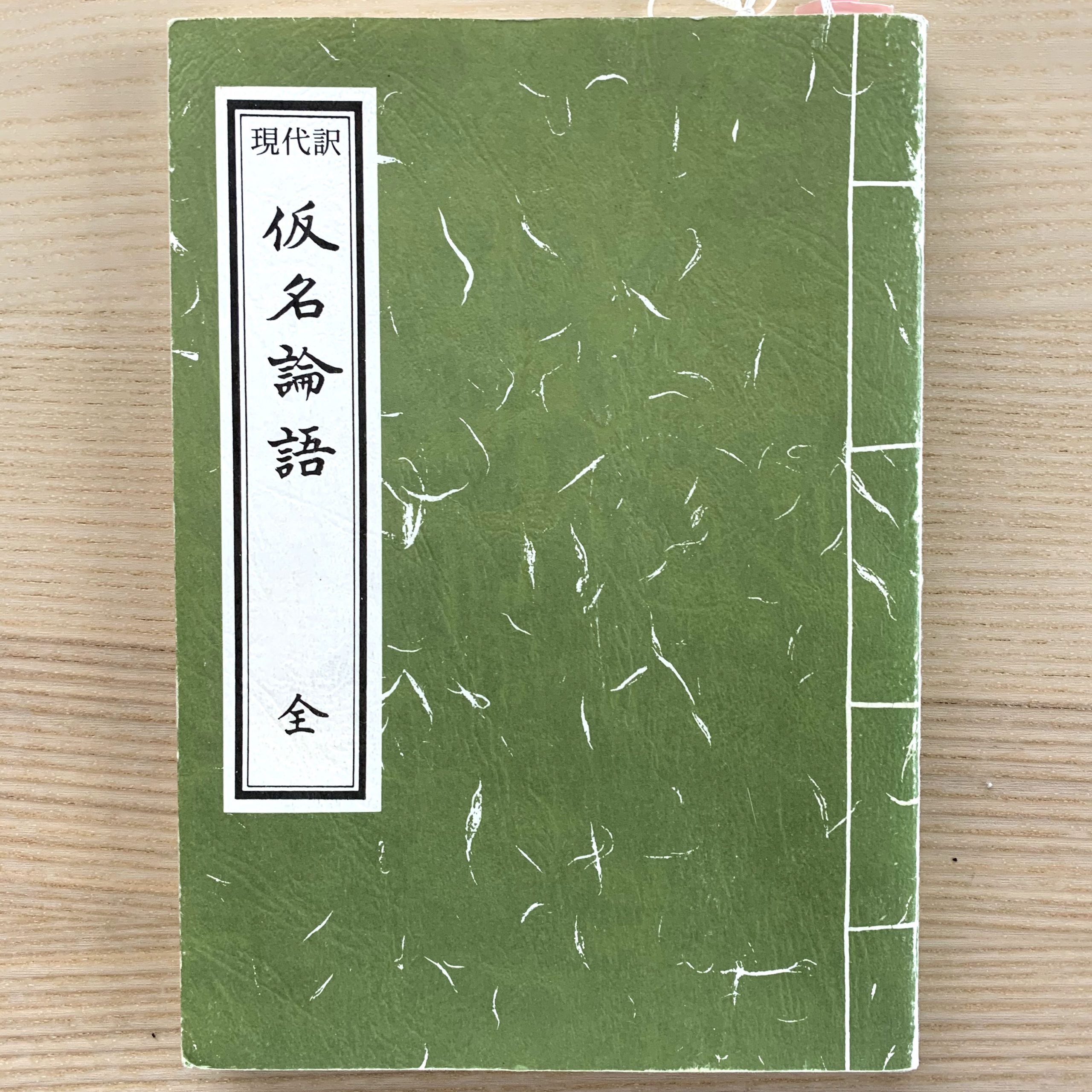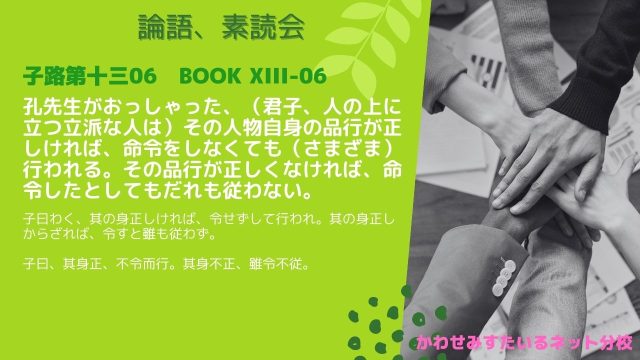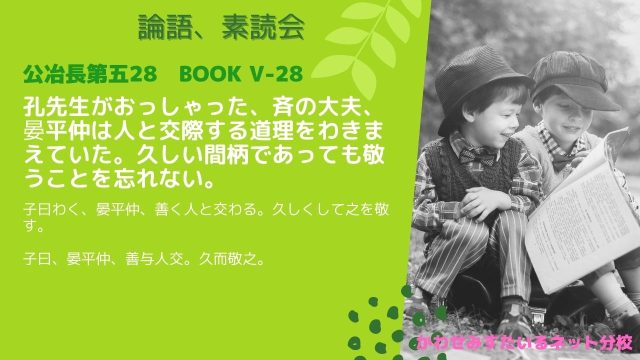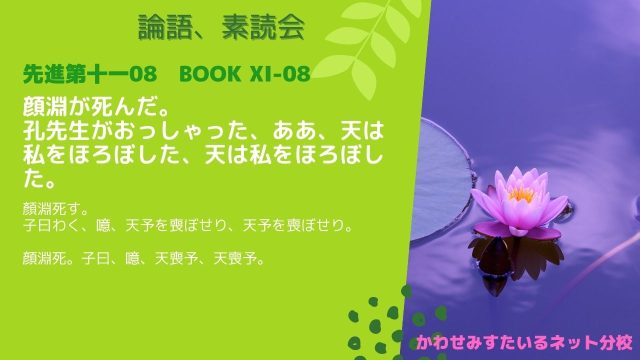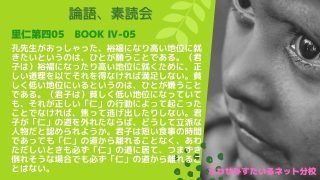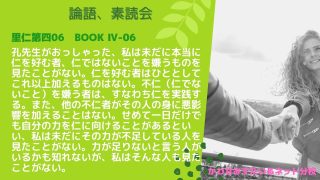孔子(こうし)孔丘(こうきゅう)丘(きゅう)仲尼(ちゅうじ)
姓は孔、名は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。仲は次男のこと。
魯(ろ)の襄公(じょうこう)の二十二年(前五五一)十月二十七日(新暦九月二十八日)生まれ。尼丘(じきゅう)にちなんで、「丘」と名づけた。厳密にいえば「尼丘」を分けて、名を丘(きゅう)、字を尼(じ)とし、次男なので「仲」をつけて「仲尼」と呼んだのである。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
左丘明之を恥ず、丘も亦之を恥ず|「論語」公冶長第五25
※友だちとの付き合いについて語っています。
丘の学を好むに如かざるなり|「論語」公冶長第五28
※孔子が自身のことをはっきりと明言している章句です。
吾行うとして二三子と与にせざる者無し。是れ丘なり|「論語」述而第七23
※それが私なのだと孔子は言います。
苟くも過有れば、人必ず之を知る|「論語」述而第七30
※過ちがあれば人から知らされるので、幸せであると孔子がいいます。
丘の祈ること久し|「論語」述而第七34
※病床の孔子と子路のやり取りです。
再拝して之を送る|「論語」郷党第十11
※季康子からの薬を試していないと言います。
由の瑟、奚為れぞ丘の門に於てせん|「論語」先進第十一14
※子路の大琴について批評しています。
固を疾めばなり|「論語」憲問第十四34
※孔子に直接意見をしています。
吾季孫の憂は、顓臾に在らずして、蕭牆の内に在るを恐るるなり。|「論語」季氏第十六01
※季氏が顓臾に戦争を起こそうとすると、冉有と季路が孔子に相談します。
丘は与に易えざるなり|「論語」微子第十八06
※世の中で道理が行われていれば、人々と一緒に世の中を変える必要がないと言っています。
夫子焉にか学ばざらん|「論語」子張第十九22
※孔子がどこで誰に学んだのか、公孫朝が子貢に尋ねています。
子貢は仲尼より賢れり|「論語」子張第十九23
※叔孫武叔が孔子より子貢が優れているという評を聞いた子貢が反論しています。
仲尼は日月なり|「論語」子張第十九24
※叔孫武叔が孔子を悪く言うので、子貢がたしなめています。
之を如何ぞ其れ及ぶべけんや|「論語」子張第十九25
※孔子より子貢が優れているという陳子禽に対して、言葉を尽くして孔子を評しています。
孔子および門人(弟子)たち
・孔子(こうし)孔丘(こうきゅう)丘(きゅう)仲尼(ちゅうじ)
・曾子(そうし)曽子(そうし)
・有子(ゆうし)有若(ゆうじゃく)
・顔淵(がんえん)回(かい)
・公西華(こうせいか)赤(せき)子華(しか)
・子貢(しこう)賜(し)
・子路(しろ)季路(きろ)由(ゆう)仲由(ちゅうゆう)
・子夏(しか)商(しょう)
・子游(しゆう)言游(げんゆう)偃(えん)
・子張(しちょう)
・子賤(しせん)
・子禽(しきん)陳亢(ちんこう)陳子禽(ちんしきん)
・子羔(しこう)髙柴(こうさい)柴(さい)
・漆彫開(しっちょうかい)
・冉有(ぜんゆう)求(きゅう)冉求(ぜんきゅう)
・冉伯牛(ぜんはくぎゅう)伯牛(はくぎゅう)
・仲弓(ちゅうきゅう)雍(よう)
・閔子騫(びんしけん)
・巫馬期(ふばき)
・樊遅(はんち)
・原思(げんし)
・宰我(さいが)宰予(さいよ)予(よ)
・申棖(しんとう)棖(とう)
・林放(りんぽう)
殷(いん)の国
周(しゅう)の国
魯(ろ)の国
・周公(しゅうこう)
・魯公(ろこう)
・定公(ていこう)
・昭公(しょうこう)
・哀公(あいこう)
衛(えい)の国
・霊公(れいこう)
・王孫賈(おうそんか)
・出公輒(しゅっこうちょう)衛君(えいくん、えいのきみ)
斉(せい)の国
・桓公(かんこう)
・荘公(そうこう)
・景公(けいこう)
・簡公(かんこう)
・晏平仲(あんへいちゅう・あんぺいちゅう)
・管仲(かんちゅう)
晋(しん)の国
五十音順
あ行 △ ▽
哀公(あいこう)
魯(ろ)の君主。名は蒋(しょう)。十歳で即位した。孔子を重用した定公(ていこう)の後に即位して二十七年在位した。
魯(ろ)の君。前四九四年に即位し、在位二十七年。名は蒋(しょう)。まったくのおぼっちゃん育ちで、「自分は、哀(かなしみ)も憂(うれい)も懼(おそれも)も危(あやうさ)も知らない」と言っていた。〔荀子・哀公〕。十歳ほどで即位し、三桓(さんかん)氏の横暴を抑え滅ぼそうとしたが失敗し、邾(ちゅ)〔魯の属国で、後の鄒(すう)国〕から楚(そ)に逃れた。のち魯の人々に抑えられたが、間もなく死んだ。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
直きを挙げて諸を枉れるに錯けば、則ち民服す|「論語」為政第二19
※どうすれば人民が従ってくれるか相談しています。
成事は説かず、遂事は諫めず、既往は咎めず|「論語」八佾第三21
※土地の神を祀る「社」について孔子の弟子の宰我に尋ねています。
顔回なる者有り学を好めり|「論語」雍也第六02
※弟子の中でだれが一番学問好きか尋ねています。
百姓足らば、君孰と与にか足らざらん|「論語」顔淵第十二09
※有子に財政の悩みを相談しています。
敢て告げずんばあらざるなり|「論語」憲問第十四22
※陳成子の討伐を告げています。
亜飯干(あはんかん)
亜飯(あはん)は、楽官の名。干(かん)は名。
亜飯(あはん)は、楽官の名。諸侯の飲食の際に、音楽を奏して興を添える役で、亜飯は、二番めの食を勧める役という。干(かん)は、魯(ろ)国の衰乱とともに楚(そ)に去った。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※楚に至りました。
晏平仲(あんへいちゅう・あんぺいちゅう)
晏嬰(あんえい)。姓は晏(あん)、名は嬰(えい)、字は仲(ちゅう)、贈り名は平(へい)。斉(せい)の大夫。霊公(れいこう)、荘公(そうこう)、景公(けいこう)の三代に仕えた。
(? – 前五00)姓は晏(あん)、名は嬰(えい)、字は仲(ちゅう)、贈り名はは平(へい)。普通、晏平仲と呼ぶ。斉(せい)の大夫。霊公(れいこう)、荘公(そうこう)、景公(けいこう)の三代に仕え、節倹力行の忠臣とたたえられる。孔子が斉に仕えるのを妨げたという。鄭(てい)の子産(しさん)とともに孔子に影響を与え、孔子は「長く交際するほど尊敬される人」と評している。彼の言行を記した本に『晏子春秋』がある。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
久しくして之を敬す|「論語」公冶長第五17
※孔子は、久しい間柄であっても敬うことを忘れないと評価しています。
夷逸(いいつ)
伝記不明
孔子の挙げる逸民(いつみん)〔志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人〕七人の一人。
可も無く不可も無し|「論語」微子第十八08
※隠居して言いたい放題に言い、身は清らかで、世を捨て去る様子は臨機応変であった。
伊尹(いいん)
殷(いん)の名宰相。名は摯(し)。湯王(とうおう)が夏(か)の桀王(けつおう)を滅ぼすのを助け、以後三代にわたって国事を取り仕切った。阿衡 (あこう)《摂政・関白の異称》。
姓は伊(い)、名は摯(し)。湯王(とうおう)の尹(いん)《宰相》となって善政を行い、以後、不仁者が遠ざかったという。湯王は夏(か)王朝の桀王(けつおう)を討って殷(いん)王朝の祖となったが、その時の立役者。古代の代表的な賢人とされる。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
燓遅仁を問う。子曰わく、人を愛す|「論語」顔淵第十二22
※「直きを挙げて諸を枉れるに錯けば、能く枉れる者をして直からしむ」の例として挙げられています。
禹(う)
衛君(えいくん、えいのきみ)
偃(えん)
王孫賈(おうそんか)
衛(えい)の国の大夫。霊公(れいこう)に仕えて軍を統率した名臣。
衛(えい)の大夫。霊公(れいこう)に仕えて軍を統率し、仲叔圉(ちゅうしゅくぎょ)・祝鮀(しゅくだ)と並称された名臣。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
罪を天に獲れば、禱る所無なきなり|「論語」八佾第三13
※孔子にある神について尋ねています。
子衛の霊公の無道なるを言う|「論語」憲問第十四20
※国防を司っていた。
か行 △ ▽
顔淵(がんえん)回(かい)
姓は顔(がん)、名は回(かい)、字は子淵(しえん)。孔子より三十歳若い。孔子よりも早く、三十歳(一説では四十歳とも)で死んだ。秀才で、門人の中で一番の学問好き。孔子の第一の弟子ともいわれる。
もの静かだが孔子の教えを充分に実践しており、一を聞いて十を知る孔子もかなわない部分を持つ秀才。
顔回は魯人。字は子淵。孔子より少きこと三十歳。年二十九にして髪白く、三十一にして早く死す。孔子曰く、吾に回有りてより、門人日々益々親しむ、と。回、徳行を以て名を著す。孔子其の仁なるを称ふ。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五二一 – 四九0)孔門の十哲。姓は顔、名は回、字は子淵。魯の人。孔子より三十歳(一説に三十七歳)若い。二十九歳で既に白髪だったと言われ、孔子より早く三十歳(一説に四十歳)で死んだ。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
一椀の飯と一椀の汁だけで、裏長屋に住みながら、一を聞いて十を知る秀才であり、門人の中でもっとも学問好きの、孔門第一の弟子。
後世「復聖顔子」と称され、曲阜には顔淵を祭った「復聖殿」がある。
吾回と言うに、終日違はざること愚なるが如し|「論語」為政第二09
※孔子の前ではもの静かだが、孔子の教えを充分に実践していると評価されている。
※この章句では、孔子から親しみを込めて名で呼ばれている。
如かざるなり。吾と女と如かざるなり|「論語」公冶長第五09
※一を聞いて十を知る。孔子もかなわない部分があると認めています。
※この章句では、孔子から親しみを込めて名で呼ばれている。
顔回なる者有り学を好めり|「論語」雍也第六02
※孔子は弟子の中で学問を好む者として哀公(あいこう)に答えているが、同時に彼の死を伝え彼以上に学問を好む者はいないと伝えている。
回や、其の心三月仁に違わず|「論語」雍也第六05
※孔子は常に「仁」の中に居ると評価している。
回や其の楽しみを改めず。賢なるかな回や|「論語」雍也第六09
※孔子は顔淵の賢明さを褒めている。
子顏淵に謂いて曰わく、之を用うれば則ち行い、之を舍つれば則ち藏る。唯我と爾と是れ有るかな|「論語」述而第七10
※任用されれば政治を正しく行い、退任すれば世の中からかくれるように静かにできると評価されている。
之れ語げて惰らざる者は、其れ回なるか|「論語」子罕第九20
※伝え知らせたことを怠らずに実践することができたのは彼だけだと評価されている。
未だ其の止まるを見ざるなり|「論語」子罕第九21
※彼の死を悼んだ孔子の言葉です。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「徳行には顔淵・閔子騫・冉伯牛・仲弓」
回や、我を助くる者に非ざるなり|「論語」先進第十一03
※孔子のことばをすぐに理解してしまうことから、孔子自身の学びにならないと評価されている。
顔回なる者あり学を好む|「論語」先進第十一06
※季康子に弟子の中で学問を好む者を尋ねられた孔子が、顔回と答えている。
才あるも才あらざるも、亦各ゝ其の子と言うなり|「論語」先進第十一07
※顔淵の父の願いを、賢いと賢くないとに関わらず親の思いは同じだと言っている。
天予を喪ぼせり|「論語」先進第十一08
※孔子が顔淵の死をただただ悼んでいます。
夫の人の為に慟するに非ずして、誰が為にかせん|「論語」先進第十一09
※慟哭する孔子の様子を伝える章句です。
予は視ること猶子のごとくするを得ず|「論語」先進第十一10
※顔淵の葬式を終えた孔子の気持ちを表した章句です。
億れば則ち屢中る|「論語」先進第十一18
※顔淵と子貢を比較した章句です。
子在す。回何ぞ敢て死せん|「論語」先進第十一22
※孔子よりも先に死ぬわけにはいかないという顔淵の深い情愛を感じます。
己に克ちて礼に復るを仁と為す|「論語」顔淵第十二01
※孔子に「仁」について尋ねています。
顏淵邦を為めんことを問う|「論語」衛霊公第十五11
※国を治めることについて尋ねています。
夏后氏(かこうし)
夏(か)王朝を尊んで「后(君)」と呼んだ。
夏(か)王朝を尊んで「后(君)」と呼んだ。
成事は説かず、遂事は諫めず、既往は咎めず|「論語」八佾第三21
※宰我が哀公の質問に答えるときに取り上げています。
桓公(かんこう)
斉(せい)の公。春秋の五覇の一人で、晋(しん)の文公(ぶんこう)とともにもっとも勢力があった。
斉(せい)の公。名は小白(しょうはく)。春秋の五覇の一人で、晋(しん)の文公(ぶんこう)とともにもっとも勢力があった。庶兄(しょhけい)(異母兄。また庶弟かともいう)の公子糾(きゅう)を殺して斉の公となり、宰相の管仲(かんちゅう)の力を借りて、即位後七年にして覇者となった。孔子は「正しくして譎らず」と評している。しかし私生児の子が多く、桓公の死後すぐ子どもたちの王位争いが始まって、桓公の遺体は六十日間も放置され、蛆がわいたという。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
斉の桓公は正しくして譎らず|「論語」憲問第十四16
※正しくて欺かないと評しています。
其の仁に如かんや|「論語」憲問第十四17
※公子糾を殺した逸話が取り上げられています。
民今に到るまで其の賜を受く|「論語」憲問第十四18
※公子糾を殺した逸話が取り上げられています。
簡公(かんこう)
斉(せい)の公。名は壬(じん)。景公の子の悼公(とうこう)の子。臣の闞止(かんし)を寵愛したため、それを怨んだ陳成子に、在位四年にして殺された。
斉(せい)の公。名は壬(じん)。景公の子の悼公(とうこう)の子。景公は非摘出子の晏儒子(あんじゅし)を太子としたので、公子たちは諸国に逃れた。魯(ろ)に逃れていた陽生(ようせい)は、帰国して晏儒子を殺して悼公となった。しかし、在位五年で殺され、子の簡公が即位した。簡公も、臣の闞止(かんし)を寵愛したため、それを怨んだ陳成子に、在位四年にして殺された。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
敢て告げずんばあらざるなり|「論語」憲問第十四22
※陳成子に殺された逸話が取り上げられています。
桓魋(かんたい)
姓は向(しょう)、名は魋(たい)。桓公の子孫なので、桓魋ともいう。
孔子が宋の国で、門人たちと大樹の下で礼を習っていた時、桓魋は孔子を殺そうとして大樹を引き倒した。
姓は向、名は魋。桓公の子孫なので、桓魋とも言い、司馬(軍隊の長官)だったので、司馬桓魋とも言う。宋の景公に重用されたが、次第にお互いに反目し、桓魋は宋から衛に逃げ、斉の陳成子に救われてその次卿となった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔子が宋の国で、門人たちと大樹の下で礼を習っていた時、桓魋は孔子を殺そうとして大樹を引き倒した。心配する門人に向かって孔子は「天から使命を授かっているこの私を、桓魋ごときがどうすることもできない」と、その信念を語った。前四九五年または前四九二年のことという。
天徳を予に生せり。桓魋其れ予を如何にせん|「論語」述而第七22
※上記、心配する門人に向かって孔子が信念を語った。
管仲(かんちゅう)
斉の大夫(臣下)として桓公(かんこう)を助けた。「管子」七十八編を記した。孔子より百七十年、百八十年以前の人。
(? – 前六五四)姓は管、名は夷吾。仲は字。贈り名は敬。斉の大夫となり、桓公を助けて覇者とした。孔子はその功績をたたえているが、「器が小さい」とも評している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
「倉廩実ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る」(史記・管晏列伝)の言葉でも有名。また鮑叔牙との交友も「管鮑の交わり」として有名である。『管子』を著したという。
管氏にして礼を知らば、孰か礼を知らざらん|「論語」八佾第三22
※器が小さく、礼を知らないと孔子は評しています。
曰わく、彼をや彼をや|「論語」憲問第十四10
※処分をした伯氏から生涯恨まれることはなかったといいます。
其の仁に如かんや|「論語」憲問第十四17
※桓公が諸侯を集めまとめる際に武力を使わなかったのは管仲の力だと評価しています。
民今に到るまで其の賜を受く|「論語」憲問第十四18
※管仲が仁者ではないという子貢に対して、孔子が答えています。
顔路(がんろ)
顔回の父。孔子の最初の弟子の一人であったらしい。
顔由は顔回の父、字は季路。孔子より少きこと六歳。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
才あるも才あらざるも、亦各ゝ其の子と言うなり|「論語」先進第十一07
※顔淵の父の願いを、賢いと賢くないとに関わらず親の思いは同じだと言っている。
季騧(きか)
季桓子(きかんし)
魯(ろ)の大夫。季孫氏の六代目。名は斯(し)、桓(かん)は贈り名。前五○五年に大夫になると、臣の陽虎(ようこ)に脅され、前四九八年には公山弗擾(こうざんふつじょう)に背かれている。
(?ー前四九二)魯(ろ)の大夫。季孫(きそん)氏の六代目。名は斯(し)、桓(かん)は贈り名。前五○五年に大夫になると、臣の陽虎(ようこ)に脅され、前四九八年には公山弗擾(こうざんふつじょう)に背かれている。政治への情熱もあり、孔子を用いたりしている。一方、斉(せい)の国からの女楽(音楽や舞踊の巧みな女性)八十人を喜び受けて、三日間朝廷の政治を怠ったので、失望した孔子は遂に魯国を去った。その時、孔子を惜しむ良心も持っていた。人間臭い人物である。
三日朝せず。孔子行る|「論語」微子第十八04
※孔子が魯の国を去るきっかけを作った様子が語られています。
季康子(きこうし)康子(こうし)
魯の大夫。季氏(季孫氏)の七代目。名は肥(ひ)、贈り名は康(こう)。孔子の門人、冉求、子貢、子路、樊遅らを任用し、冉求の求めで孔子を招いたりもした。
(? – 前四七七)魯の大夫。季孫氏の七代目。名は肥、康は贈り名。父の季桓子の跡を継いで大夫となる。孔子の門人の冉求・子貢・子路・樊遅らを任用し、また冉求の勧めで孔子を招いたりもした。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
政治に関して、孔子に四度質問している。孔子は「政は正なり」「子、善ならんと欲すれば、民、善なり」と、自己を治めることを説いている。
之に臨むに荘を以てすれば則ち敬す|「論語」為政第二20
※人民に敬意と忠誠の念をもって仕事に精を出させるにはどうすればいいかと尋ねています。
政に従うに於て何か有らん|「論語」雍也第六06
※仲由、子貢、冉有について孔子に尋ねています。
再拝して之を送る|「論語」郷党第十11
※孔子に薬を送っています。
顔回なる者あり学を好む|「論語」先進第十一06
※弟子のうち誰が学問を好むか尋ねています。
子帥いるに正しきを以てすれば|「論語」顔淵第十二17
※孔子に政治について尋ねています。
季康子盗を患えて、孔子に問う|「論語」顔淵第十二18
※盗賊に悩んで、孔子に尋ねています。
君子の徳は風なり。小人の徳は草なり|「論語」顔淵第十二19
※孔子に政事について尋ねています。
子衛の霊公の無道なるを言う|「論語」憲問第十四20
※霊公が無道であるのになぜ滅びないのでしょうと尋ねています。
季氏(きし)季孫氏(きそんし)
魯(ろ)の大夫、三桓(さんかん)(孟孫氏、叔孫氏、季孫氏)のひとつ。魯の襄公のころから大臣職を独占し、襄公を無視して権力を欲しいままにした。
三桓 … 魯(ろ)の大夫、孟孫(もうそん)子(初め仲孫氏と言った)・叔孫(しゅくそん)子・季孫(きそん)氏の三氏の家。魯の桓公(かんこう)の子孫なので、三桓と称する。また、公子(初校や貴族の子)を公孫(こうそん)と言ったので「孫」と称する。「孟(伯)・中・叔・季」は長男から順に兄弟の順序を言う。季孫氏の三代目の季文子(きぶんし)が、魯の襄公(じょうこう)のころから魯の司徒(文部大臣)・司馬(陸軍大臣)・司空(土地・人民の管理)の職を三桓氏で独占し、襄公を無視して権勢をほしいままにし始めた。四代目の季武子(きぶし)は、襄公十一年(前五四二)に魯国の土地を三分して三桓氏の所有とし、襄公二十年には国政を握った。昭公(しょうこう)七年(前五三五)に没すると、後を季平子(きへいし)が継ぎ、昭公を国外(斉)に追放した。昭公は斉で没し、季平子も定公五年(前五○五)に没した。
しかし、季武子の臣の南蒯(なんかい)が季平子の時に、季平子の臣の陽虎や公山弗擾(こうざんふつじょう)らが季平子の子の季桓子(きかんし)の時に、それぞれ反乱を起こし、三桓氏の精力も徐々に衰えていく。この間の事情を公子はこう述べている。「魯の公室から爵禄を与える権力が離れて五代(宣公・成公・襄公・昭公・定公)になる。政治が大夫の手に移ってから四代(季武子・季悼氏・季平子・季桓子)になる。だから、三桓氏の子孫も衰えたのだ。」
是をも忍ぶべくんば、孰れをか忍ぶべからざらんや|「論語」八佾第三01
※孔子が季氏の行いを批評しています。
嗚呼、曾ち泰山は林放に如かずと謂えるか|「論語」八佾第三06
※季氏の行いを冉有に止められないのかと尋ねています。
善く我が為に辞せよ|「論語」雍也第六07
※閔子騫を斉の国の費の代官にしようとしましたが、断られてしまいます。
爾の知る所を挙げよ|「論語」子路第十三02
※仲弓が任官しました。
吾季孫の憂は、顓臾に在らずして、蕭牆の内に在るを恐るるなり。|「論語」季氏第十六01
※季氏が顓臾に戦争を起こそうとすると、冉有と季路が孔子に相談します。
孔子行る|「論語」微子第十八03
※斉の景公が孔子の待遇を考える際に引き合いに出されました。
箕子(きし)
箕(き)は国名、子は子爵を表すかという。名は胥余(しょよ)。殷(いん)の紂(ちゅう)王の叔父。
箕(き)は国名、子は子爵を表すかという。名は胥余(しょよ)。殷(いん)の紂(ちゅう)王の叔父。紂王のぜいたくと暴政を諌めたが聞き入れられず、紂王の仕返しを恐れて狂人をまね、奴隷となって身を隠した。周の武(ぶ)王が紂王を滅ぼすと、武王は箕子に天下を治める策を尋ねた。また、朝鮮半島に封ぜられて、開祖となったという。孔子は、殷の三人の仁者の一人に挙げている。
殷に三仁有り|「論語」微子第十八01
※孔子は、殷にいた三人の仁者のひとりと評しています。
季子然(きしぜん)
魯の大夫、季平子の子。
魯の大夫、季平子の子。孔子の門人の子路と冉有とを時ぶうの臣とし、更に孔子に「彼らは大臣の勤まる人物か」と問うている。自信も孔子の門人かとも言われるが、確証はない。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
道を以て君に事え、不可なれば則ち止む|「論語」先進第十一23
※孔子に、子路、冉有は大臣と言うべきかと問い、孔子から皮肉られる。
季隨(きずい)|季騧(きか)
周の成王(また宣王、文王、武王ともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。
周(しゅう)の成王(せいおう・また宣王せんのう、文王ぶんのう、武王ぶおうともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。その一人で、かつ季隨と双児の末っ子だったという。
周に八士有り|「論語」微子第十八11
※周の時代の能力ある八人として紹介されています。
季文子(きぶんし)
魯(ろ)の大夫。季孫(きそん)氏の三代目。名は行父(こうほ)、文子は贈り名。魯の文公(ぶんこう)・宣公(せんこう)・成公(せいこう)・襄公(じょうこう)の四代に仕えて信頼を集めた。
(? – 前五0五)魯(ろ)の大夫。季孫(きそん)氏の三代目。名は行父(こうほ)、文子(ぶんし)は贈り名。魯の文公(ぶんこう)・宣公(せんこう)・成公(せいこう)・襄公(じょうこう)の四代に仕えて信頼を集めた。常識も才知もあり、質素な人柄だったが孔子は「熟慮に過ぎる」と評した。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
再びせば斯れ可なり|「論語」公冶長第五20
※三度も熟考して実行したことを聞いて孔子が批評しています。
季平子(きへいし)
魯(ろ)の大夫。季孫(きそん)氏の五代目。名は意如(いじょ)、平子(へいし)は贈り名。昭公(しょうこう)十年(前五三二)に卿(きょう)となり、横暴をほしいままにした。
(?ー前五○五)魯(ろ)の大夫。季孫(きそん)氏の五代目。名は意如(いじょ)、平子(へいし)は贈り名。昭公(しょうこう)十年(前五三二)に卿(きょう)となり、横暴をほしいままにした。天子だけに許された八佾(はちいつ)の舞いを自分の所で行ったのも、季平子かとも言われる。この専横などで他の大夫たちの怨みを買い、大夫たちは昭公と諮って季平子を討とうとしたが、季平子は叔孫(しゅくそん)氏の援軍を得て、逆に昭公は二十五年(前五一七)に斉(せい)国に亡命した。囲碁七年間、昭公が斉で没するまで、季平子は魯の最高権力者として君臨した。定公(ていこう)五年(前五○五)、東野を巡視した帰途に没する。
是をも忍ぶべくんば、孰れをか忍ぶべからざらんや|「論語」八佾第三01
※孔子がその行いを批評しています。
求(きゅう)
堯・舜・禹(ぎょう・しゅん・う)
伝説上の天子、帝王。舜は尭から禅譲[帝王がその位を世襲せず、有徳者に譲ること]した。禹は舜に推されて王となり、夏王朝を開いたとされる。
尭 伝説上の聖天子。姓は伊祁(いき)、名は放勛(ほうくん)。帝嚳(ていこく)の子。初め陶(とう)に住み、のち唐(とう)に移ったので、陶唐(とうとう)氏ともいう。次代の舜とともに儒家で理想と仰ぎ、尭舜と併称される。
舜 伝説上の聖天子で、姓は有虞(ゆうぐ)氏、名は重華(ちょうか)。帝尭に民間から登用され、その二人の娘、娥皇(がこう)・女英(じょえい)と結婚した。無為にして世を治め、帝尭とともに儒家で理想と仰がれ、尭舜と返照される。
禹 夏(か)王朝夷の開祖とされる。伝統的な聖王。名は文明(ぶんめい)、帝顓頊(せんぎょく)の孫。夏后(かこう)氏、また有愚(ゆうぐ)氏とも言われる。父の鯀(こん)が失敗した黄河の治水を受け継いで成功した功績で、帝舜に位を譲られた。禹はまた、天下を九州に分け、租税の制度を定めた。孔子は「禹の天子としてのやり方に、自分は一言も口をはさむ余地はない」と敬服している。禹の没後は、子の啓(けい)が跡を継ぎ、以降、子の啓が跡を継ぎ、以後、天子の世襲制度がはじまった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
何ぞ仁を事とせん。必ずや聖か。堯舜も其れ猶諸を病めり|「論語」雍也第六28
※堯舜を例に子貢に答えています。
巍巍乎たり。舜禹の天下を有てるや。|「論語」泰伯第八18
※孔子が舜禹を評価しています。
禹は吾間然すること無し|「論語」泰伯第八21
※非難することがないと言っています。
燓遅仁を問う。子曰わく、人を愛す|「論語」顔淵第十二22
※孔子の回答を理解できずに子夏に改めてその意味を聞いています。
燓遅仁を問う。子曰わく、人を愛す|「論語」顔淵第十二22
※「直きを挙げて諸を枉れるに錯けば、能く枉れる者をして直からしむ」の例として挙げられています。
君子なるかな若き人|「論語」憲問第十四06
※南容が孔子に話をする中で、取り上げています。
堯舜も其れ猶諸を病めり|「論語」憲問第十四44
※自己を修養し多くの人民を安心させることを尭舜も悩んでいたと話しています。
無為にして治むる者は、其れ舜なるか|「論語」衛霊公第十五05
※徳により国を治めたのは舜だといいます。
周に大いなる賚有り。善人是れ富めり|「論語」堯曰第二十01
※帝位を譲られた際の言葉を紹介しています。
棘子成(きょくしせい)
衛(えい)の大夫。
衛(えい)の大夫という。子貢(しこう)に「君子は質(本質の素朴さ)だけが大切で、文(学問や修養)で飾る必要はない」と語り、「文も質もともに大切だ」とたしなめられている。
文は猶質のごとく、質は猶文のごときなり|「論語」顔淵第十二08
※君子についての考えを子貢からたしなめられています。
蘧伯玉(きょはくぎょく)
衛(えい)の大夫。蘧(ぎょ)は姓。名は(えん)。伯玉(はくぎょ)は字。
衛(えい)の大夫。蘧(ぎょ)は姓。名は(えん)。伯玉(はくぎょ)は字。孔子は、その出処進退を明らかにする態度に対して「君子なるかな」と褒めたたえている。また、日々に努力を重ねる人で、「蘧伯玉は五十歳になって四十九年間の非を知る」とたたえられ、「六十歳にして六十回変化した」とも言われている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
使なるかな使なるかな|「論語」憲問第十四26
※蘧伯玉の遣いを褒めています。
君子なるかな蘧伯玉|「論語」衛霊公第十五07
※君子のようだと評されています。
季路(きろ)
牢(ろう)琴牢(きんろう)
琴牢(きんろう)、姓は琴、名は牢、字は子開また子張。
姓は琴(きん)。名は牢(ろう)、字は子開(しかい)、また子張(しちょう)。衛(えい)の人。孔子が牢に語った一章に登場するだけであり、『史記(しき)』には名が載っていない。
なお、「吾試いられず故に芸ありと|「論語」子罕第九07」この章句は「牢曰ハク」とあり、「曰の上に「牢」のように名を記した礼は他にないので荻生徂徠(おぎゅうそらい)〔江戸中期の儒学者。一六六六ー一七二八〕は『論語』の前半十章を、太齋春台(ださいしゅんだい)〔江戸中期の儒学者・経済学産。一六八○ー一七四七〕は『論語』の全編をこの牢牛が編集した、と言っている。
吾試いられず故に芸ありと|「論語」子罕第九07
※孔子の言葉を紹介しています。
虞仲(ぐちゅう)
周の文王(ぶんのう)の祖父・太王(たいおう)〔古公亶父〕の長男が泰伯(たいはく)、次が虞仲(ぐちゅう)、という。
周(しゅう)の文王(ぶんのう)の祖父・太王(たいおう)〔古公亶父・ここうたんぽ〕の長男が泰伯(たいはく)、次が虞仲(ぐちゅう)、という。王位を継ぐのを避けて刑蛮(けいばん)〔南方の楚や越の地〕に逃げた。孔子の挙げる遺逸(いいつ)の民〔志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人〕七人の一人。
可も無く不可も無し|「論語」微子第十八08
※隠居して言いたい放題に言い、身は清らかで、世を捨て去る様子は臨機応変であった。
羿(げい)
夏の時の諸侯で、有窮(ゆうきゅう)国の君。
※有窮氏(有穹氏、ゆうきゅうし)は、中国の歴史書に見える夏の時代の氏族。
姓は夷(い)。夏王朝時代の諸侯で有窮(ゆうきゅう)国の君。夏の天子・相(しょう)を殺して王位を奪ったが、羿(げい)の臣の寒浞(かんさく)に殺され、煮られてしまった。/また、弓の名人。帝尭の時に天に太陽が十個並び出たので、尭は羿に命じてその九個を射落とさせた。その妻が嫦娥(じょうが)[姮娥(こうが)とも言う。月に住む美女]。(「/」の前後は別の人ともいう。)
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
君子なるかな若き人|「論語」憲問第十四06
※南容が孔子に尋ねる時、例として取り上げています。
景公(けいこう)
斉(せい)の君。名は杵臼(しょきゅう)。
(前五四七 – 四八七)斉の君。名は杵臼(しょきゅう)。斉の大夫・崔杼(さいちょ)がその君の荘公を弑して立てた君。晏嬰(あんえい)に助けられて、在位五十八年。その間、晏嬰(あんえい)とともに魯に来て孔子に会っている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
しかし人民には苛酷で、自身は淫乱な政治を行い、その死後は内乱が起こって、公位を陳氏に奪われた。景公が死んだ時、馬四千頭を持っていたが、だれもその徳をたたえなかったという。
君君たり、臣臣たり、父父たり、子子たり|「論語」顔淵第十二11
※政治について尋ねています。
民今に到るまで之を称す|「論語」季氏第十六12
※民から徳のある人として賞賛されることはなかったといいます。
孔子行る|「論語」微子第十八03
※孔子の待遇について話しています。その様子を聞いた孔子は斉を去ります。
撃磬襄(げきけいじょう・げっけいじょう)
磬(けい)を打ち鳴らす役の襄(じょう)。
磬(けい)を打ち鳴らす役の襄(じょう)。魯(ろ)国の衰乱を見て、海のほとりに去った。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※海のほとりに移りました。
桀溺(けつでき)
隠者(いんじゃ)の名。
隠者(いんじゃ)の名。長沮(ちょうそ)とともに登場し、孔子に会ってお供お子路と問答をしている。
丘は与に易えざるなり|「論語」微子第十八06
※孔子に従うより、自分たちのように世を捨てたものに従う方がいいのでは?と子路に言います。
原思(げんし)
姓は原(げん)、名は憲(けん)、字は子思(しし)。孔子より三十六歳若い。孔子が魯の司寇(しこう・長官)になったとき執事となった。貧しかったらしい。(論語集註)
原憲は宋人。字は子思。孔子より少きこと三十六歳。清浄にして節を守る。貧にして道を楽しむ。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五二五 – ?)姓は原、名は憲、字は子思。魯の人、また宋の人、斉の人という。孔子より三十六歳若い。清廉な人で、また貧しかったらしい。孔子が司寇となった時、その執事(事務を扱う役)となった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔子の死後は、草沢の中に隠れ住んだ。子貢が肥った馬に乗り、着飾って原思を訪ねると、迎え出た原思の冠の紐は切れ、衣服から肘が出、靴からは踵がはみ出ていたという。(韓詩外伝)
原思之が宰たり。之に粟九百を与う。辞す|「論語」雍也第六03
※孔子からの俸禄が多すぎると辞退するような清廉なひとだったようだ。
憲恥を問う。子曰わく、邦道有れば穀す|「論語」憲問第十四01
※孔子に「恥」について尋ねています。
原壤(げんじょう)
原(げん)は姓、壤(じょう)は名。孔子と同郷の人で、また旧友だった。
原(げん)は姓、壤(じょう)は名。孔子と同郷の人で、また旧友だった。うずくまって頭を垂れたまま孔子を迎えたので、孔子は「礼儀知らずの、生を倫(ぬす)む者」と、杖で脛を叩いた。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
杖を以て其の脛を叩く|「論語」憲問第十四45
※孔子にその行動を批判されています。
言游(げんゆう)
奡(ごう)
夏王朝の諸侯である羿(げい)の臣の寒浞(かんさく)の子。大力の持ち主で、地上で大きな船を動かしたという。
夏王朝の諸侯である羿(げい)の臣の寒浞(かんさく)が、羿の妻と通じて生まれた子。大力の持ち主で、地上で大きな船を動かしたという。奡は夏の天子・相(しょう)を弑して位を奪い、奡の父の寒浞は羿を殺して位を奪ったが、奡も寒浞も、相の子の少康(しょうこう)に殺された。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
君子なるかな若き人|「論語」憲問第十四06
※南容が孔子に尋ねる時、例として取り上げています。
髙柴(こうさい)
公山弗擾(こうざんふつじょう)
姓は公山、名は弗擾で、不擾(ふじょう)・不狃(ふちゅう)とも書く。魯(ろ)の季氏の家臣で、季氏の領地の費(ひ)の長官を務めていた。
姓は公山、名は弗擾で、不擾(ふじょう)・不狃(ふちゅう)とも書く。字は子洩(しえい)。魯(ろ)の季氏の家臣で、季氏の領地の費(ひ)の長官を務めていたが、陽虎(ようこ)と親しく、共に反乱を起こして、孔子を招いた。孔子はその招きに応じようとした。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
吾は其れ東周を為さんか|「論語」陽貨第十七05
※孔子は公山弗擾に招かれます。
公子糾(こうしきゅう)
斉(さい)の公子(大夫)の糾(きゅう)。斉の僖公(きこう)の庶子(しょし)で、襄公(じょうこう)の異母弟、桓公の異母弟。
斉(さい)の公子(大夫)の糾(きゅう)。斉の僖公(きこう)の庶子(しょし)で、襄公(じょうこう)の異母弟、桓公の異母弟。斉の内乱の時、管仲(かんちゅう)と召忽(しょうこつ)を伴って母の生地の魯(ろ)に逃れた。斉に戻ろうとして小白(しょうはく)と戦って敗れ、小白は斉の桓公となった。桓公は魯国に糾を殺させ、召忽はこれに殉死した。しかし管仲は、友人の鮑叔牙(ほうしゅくが)の誘いを受けて桓公の臣となり、宰相として活躍し、桓公を覇者とした。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
其の仁に如かんや|「論語」憲問第十四17
※子路が孔子に仁を問う際の例として取り上げています。
民今に到るまで其の賜を受く|「論語」憲問第十四18
※子貢が孔子に仁を問う際の例として取り上げています。
公子荊(こうしけい)
名は荊(けい)、衛の公子(中国の春秋戦国時代の諸侯国の公族の子弟。)で大夫(中国の周代から春秋戦国時代にかけての身分を表す言葉で領地を持った貴族。 )だった。
衛の公子(大夫)の荊(けい)。孔子は荊は家庭のその時々の貧富に応じて満足している、と褒めている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
子衛の公子荊を謂わく。善く室に居れり|「論語」子路第十三08
※公子荊を知るを足る人物として評価している。
公叔文子(こうしゅくぶんし)文子(ぶんし)
文は贈り名。衛の大夫。
姓は公叔、名は発(はつ)、また抜(はつ)。文は贈り名。衛の大夫。人格者だったようで、家臣を自分と同列の大夫に抜擢して孔子に称賛された。しかし、衛の公明賈(こうめいか)が「君子」と評したのを、孔子は疑問視している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
信なるか、夫子の言わず、笑わず、取らざること|「論語」憲問第十四14
※孔子が公明賈に公叔文子について尋ねています。
公叔文子の臣大夫僎、文子と同じく諸を公に升す|「論語」憲問第十四19
※家臣の僎を公に推薦した。
公西華(こうせいか)赤(せき)子華(しか)
姓は公西(こうせい)、名は赤(せき)、字は子華(しか)。孔子より四十二歳若い。儀式・礼法に通じ、孔子が亡くなったときの葬儀委員長を務めたという。
公西赤は魯人。字は子華。孔子より少きこと四十二歳。束帯して朝に立ち、賓主の儀に閑ふ。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五0九 – ?)姓は公西、名は赤、字は子華。魯の人。孔子より四十二歳若い。儀式、礼法に通じ、孔子は門人たちに「賓客接待の礼は彼に学べ」と言っている〔孔子家語〕。また孔子が死んだ時には、その葬儀委員長を務めた〔礼記・檀弓〕。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
其の仁を知らざるなり|「論語」公冶長第五08
※孔子の人物評では、礼服を着て朝廷に立ち、お客様の応対を任せることができる。
以て爾が鄰里郷党に与えんか|「論語」雍也第六03
※子華が斉に行く際に、残した母に対する冉求の対応が語られています。
弟子学ぶこと能わざるなり|「論語」述而第七33
※孔子の学ぶ姿勢について、公西華が及ばないと話しています。
聞くままに斯れ諸を行わんか|「論語」先進第十一21
※兄弟子への孔子の返答の違いを素直に尋ねています。
子路・曽晳・冉有・公西華、侍坐す|「論語」先進第十一25
※孔子から抱負を聞かれ答えています。
高宗(こうそう)
殷(いん)の名君。
(前一三二四? ー 一二六六?)殷(いん)の名君。名は武丁(ぶてい)。傅説(ふえつ)という名臣を得て、殷の中興に成功した。父・定公(ていこう)の喪にあたって、三年間は政治を執らなかった。
冢宰に聴くこと三年|「論語」憲問第十四42
※子張が高宗について尋ねています。
公孫僑(こうそんきょう)子産(しさん)
鄭(てい)の国の大夫。姓は公孫(こうそん)、名は僑(きょう)、子産は字。優れた政治家。教養人とたたえられる。晋(しん)・楚(そ)の両国に挟まれた鄭の国力の充実に尽力した。
(前五八五?ー五二二)鄭(てい)の大夫。姓は公孫(こうそん)、名は僑(きょう)、また子美(しび)。子産は字。優れた政治家、教養人とたたえられる。簡公(かんこう)・定公(ていこう)・献公(けんこう)・声公(せいこう)の四代に仕え、晋(しん)・楚(そ)の両国に挟まれた鄭の国力の充実に尽力した。孔子は「君子としての四つの道を備えている人物」と、高く評価している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
君子の道四有り|「論語」公冶長第五16
※孔子が、優れた政治家として四つの道理が備わっていると評しています。
東里の子産之を潤色す|「論語」憲問第十四09
※外交文章を作成する手順について孔子が話しています。
曰わく、彼をや彼をや|「論語」憲問第十四10
※子産は恵人だと孔子が評しています。
公孫朝(こうそんちょう)
衛(えい)の大夫。
衛(えい)の大夫。他は未詳。子貢(しこう)に「孔子は、どこで誰に学んだのか」と質問している。
夫子焉にか学ばざらん|「論語」子張第十九22
※孔子がどこで誰に学んだのか、子貢に尋ねています。
公伯寮(こうはくりょう)
姓は公伯(こうはく)、名は寮(りょう)。僚・繚とも書く。字は子周(ししゅう)。魯(ろ)の人。
姓は公伯(こうはく)、名は寮(りょう)。僚・繚とも書く。字は子周(ししゅう)。魯(ろ)の人。子路が魯の大夫の季孫(きそん)氏に仕えていた時、公伯寮は子路を季孫氏に悪く告げ口した。怒った町の有力者(子服景伯・しふくけいはく)が「公伯寮を殺して町にさらしものにしましょうか」と言ったが、孔子は、「公伯寮のごとき者が、天命をどうすることもできない」と答えた。公伯寮は『論語』のこの章にしか登場せず、孔子のこの語調から見ても、孔子の門人でないとも言われる。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
公伯寮其れ命を如何せん|「論語」憲問第十四38
※公伯寮が子路のことを季孫氏に告げ口しました。
孔文子(こうぶんし)
公明賈(こうめいか)
衛の人。
姓は公明(こうめい)、名は賈(か)。衛の人。他は不詳。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
公叔文子を公明賈に問うて曰わく|「論語」憲問第十四14
※孔子が公明賈に公叔文子について尋ねています。
公冶長(こうやちょう)
姓は公冶(こうや)、名は長(ちょう)または萇(ちょう)。字は子長(しちょう)または子芝(しし)。鳥の言葉を理解したといい、それが原因で投獄された。孔子はその人柄を信じて自分の娘を嫁がせた。
公冶長は魯人。字は子長。人と為り能く恥を忍ぶ。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
姓は公冶(こうや)、名は長(ちょう)、また萇(ちょう)。字は子長(しちょう)、また子芝(しし)。斉(せい)の人、また魯(ろ)の人。鳥の言葉を理解したという。また、それが原因で投獄されたが、孔子は「無実の罪だから」とその人柄を信じて、自分の娘を嫁がせた。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
子、公冶長を謂う、妻すべきなり|「論語」公冶長第五01
※孔子が人柄を批評しています。
皐陶(こうよう)
上古(大昔。文字が存在する以前の時代。)の伝説上の政治家。舜に仕え法律・刑罰をつかさどった。
有虞(ゆうぐ)氏。字は庭堅(ていけん)。帝舜に抜擢されてから、不仁者が遠ざかった。司寇(獄官の長)として、法律を定め、また善政を行った名臣。「書経」皐陶謨などに、その施政方針の言葉が記されている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
燓遅仁を問う。子曰わく、人を愛す|「論語」顔淵第十二22
※「直きを挙げて諸を枉れるに錯けば、能く枉れる者をして直からしむ」の例として挙げられています。
鼓方叔(こほうしゅく)
鼓(つづみ)打ちの方叔(ほうしゅく)。
鼓(つづみ)打ちの方叔(ほうしゅく)。方叔は、魯(ろ)国の衰乱を見て黄河のほとりに去った。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※黄河のほとりに移りました。
呉孟子(ごもうし)
魯の昭公の夫人。魯と呉は同じく姫を姓とする。この時代、周の制度では同性同士の結婚は認められなかったが昭公は呉から妃を迎えた。そこで本来は呉姫(ごき)とすべきだが、昭公は非礼を避けて「孟子」と称した(孟は長女の意)。魯の人々は呉孟子と呼んだ。
昭公は非難され、いろいろと問題が起きた。
※「同姓」(どうせい) … 魯も呉も周室(周王朝)の出であって「姫」(き)姓であるということ。
魯(ろ)の昭公(しょうこう)の夫人。魯と呉(ご)は同じく姫(き)を姓とする。この時代は同姓どうしの結婚は認められなかった(同姓不婚)が、昭公は魯から妃を迎えた。そこで本来は「呉姫(ごき)」と称するべきだが、昭公は非礼を避けて「孟子」と称した〔孟は、長女の意味〕。魯の人々は、これを呉孟子と呼んだ。また昭公も非難され、呉孟子も妃の扱いを受けなかったという。
苟くも過有れば、人必ず之を知る|「論語」述而第七30
※昭公の逸話の中で紹介されています。
さ行 △ ▽
宰我(さいが)宰予(さいよ)予(よ)
宰我(さいが)。孔子の門人。姓は宰(さい)、名は予(よ)、字は子我(しが)。弁論にすぐれていた一方、日中に昼寝をして孔子を嘆かせた。
宰予は字は子我、魯人。口才有り。言語を持って名を著す。斉に仕へ臨淄の大夫と為る。田常と乱を為し、其の山賊を夷せらる。孔子之を恥ぢて曰く、利の病にあらずや。それ宰予に在り、と。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五二二 – 四八九。一説に四五八)孔門の十哲。姓は宰、名は予、字は子我。魯の人。弁論にすぐれていた一方、日中に昼寝をして、孔子を嘆かせる。後に斉の臨淄の大夫となり、田常(陳成子)の乱に加わって、一族が皆殺しにされたという。孔子はこのことを恥とした。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
成事は説かず、遂事は諫めず、既往は咎めず|「論語」八佾第三21
※哀公の質問に対する宰我の対応を孔子が戒めています。
今吾人に於けるや、其の言を聴きて其の行いを観る|「論語」公冶長第五10
※この章句で、昼寝をして孔子を嘆かせた。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「言語には宰我・子貢」
三年の愛其の父母に有るか|「論語」陽貨第十七21
※喪の期間が三年では長いと孔子に言います。
崔子(さいし)
姓は崔、名は杼(ちょ)。斉(せい)の丁公(ていこう)の子孫で崔武子(さいぶし)ともいう。「武」は贈り名。
(? – 前五四六)姓は崔(さい)、名は杼(ちょ)。斉(せい)の丁公(ていこう)の子孫で、崔武子(さいぶし)ともいう。「武」は贈り名。斉の恵公に仕えた大夫で、恵公の死後はねたみを恐れて衛(えい)に逃れた。跡を継いだ霊公(れいこう)は、妾腹の子の牙(が)を天子とした。しかし霊公が病気になると、本来の太子の光(こう)を迎えた。光は牙の母を殺し、崔子の尽力によって、霊公の跡を継いで荘公(そうこう)となった。しかし、その七年後(前五四八)には、崔子は荘公を殺して景公を立てた。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
史官が「崔杼、其の君を弑す」と記録すると、崔子はその史官をも殺してしまった。しかし、内紛に乗じて殺され、死体は町にさらされた。
未だ知らず、焉んぞ仁なるを得ん|「論語」公冶長第五19
※子張が仁について孔子に尋ねた際に取り上げています。
左丘明(さきゅうめい)
姓は左丘、名は明。孔子の先輩で、孔子の尊敬する人だったらしい。
姓は左丘(さきゅう)、名は明(めい)。孔子の先輩で、孔子の尊敬する人だったらしい。魯(ろ)の大夫というが未詳。『春秋左氏伝』の著者とは同名の別人とされる。
左丘明之を恥ず、丘も亦之を恥ず|「論語」公冶長第五25
※ことば巧みでいい顔ばかりしてへりくだり過ぎることを恥じ、怨みを持ったまま友だち付き合いをすることを恥じた人物。孔子も同じだと語っています。
三家者(さんかしゃ)三桓(さんかん)
魯の大夫、孟孫氏・叔孫氏・季孫氏の三氏の家。
魯(ろ)の大夫、孟孫(もうそん)氏(初め仲孫氏と言った。)・叔孫(しゅくそん)氏・季孫(きそん)氏の三氏の家。魯の桓公(かんこう)の子孫なので、三桓と称する。また、公子(諸侯や貴族の子)を公孫と言ったので「孫」と称する。「孟(伯)・仲・叔・季」は、長男から順に兄弟の順序を言う。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
季孫氏の三代目の季文子が、魯の襄公(じょうこう)のころから、魯の司徒(文部大臣)・司馬(陸軍大臣)・司空(しこう:土地・人民の管理)の職を三桓氏で独占し、襄公を無視して権勢をほしいままにし始めた。四代目の季武子は、襄公十一年(前五四二)に魯国の土地を三分して三桓氏の所有とし、襄公二十年には国政を握った。昭公(しょうこう)七年(前五三五)に没すると、後を季平子が継ぎ、昭公を国外(斉)に追放した。昭公は斉で没し、季平子も定公(ていこう)五年(前五○五)に没した。
しかし、季武子の臣の南蒯(なんかい)が季平子の時に、季平子の臣の陽虎や公山弗擾(こうざんふつじょう)らが季平子の子の季桓子の時に、それぞれ反乱を起こし、三桓氏の勢力も徐々に衰えていく。この間の事情を知る孔子はこう述べている。「魯の公室から爵禄を与える権力が離れて五代。(宣公・成公・襄公・昭公・定公)になる。政治が大夫の手に移ってから四代(季武子・季悼氏・季平子・季桓子)になる。だから、三桓氏の子孫も衰えたのだ。」
相くるに維れ辟公あり、天子穆穆たりと|「論語」八佾第三02
※行き過ぎた行為を批判しています。
故に夫の三桓の子孫は微なり|「論語」季氏第十六03
※三桓の子孫が衰えている実態を孔子が説明しています。
三飯繚(さんはんりょう)
三飯(さんはん)は楽官の名。繚(りょう)は名。
三飯(さんはん)は楽官の名。諸侯の飲食の際に、音楽を奏して興を添える役で、三飯は三度めの食を勧める役という。繚(りょう)は、魯(ろ)国の衰乱を見て、蔡(さい)の国に去った。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※蔡に至りました。
師(し)
賜(し)
摯(し)
子羽(しう)
公孫揮(こうそんき)とも言う。鄭(てい)の大夫。使者を勤めたので諸国の風習をよく知る。
春秋時代、鄭(てい)の大夫。名は遊言(ゆうげん)。公孫揮(こうそんき)とも言う。子羽は字。使者を勤めたので諸国の風習をよう知り、また外交文章の草案を添削した。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
行人子羽之を修飾し|「論語」憲問第十四09
※鄭において外交文章を作成する様子を伝える中で登場します。
子夏(しか)商(しょう)
姓は卜(ぼく)、名は商(しょう)、字(あざな)は子夏(しか)。孔子より四十四歳年下。
衛の人。つつましやかでまじめな人柄で、また消極的だったらしい。
卜商は衛人。字は子夏。孔子より少きこと四十四歳。詩に習ひ、能く其の義に通ず。文学を以て名を著す。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五0七? – 四二0?)孔門の十哲。姓は卜(ぼく)、名は商(しょう)、子夏は字。衛(えい)の人。謹厳な人柄で、また消極的だったらしく、孔子は「師(子張)や過ぎたり、商や及ばず」と評している。孔子の死後は門人を教育し、次いで魏の文候の師となって、政治の相談も受けた。我が子が死んだ時には声を挙げて号泣し、遂に失明したという。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
賢を賢として色に易え|「論語」学而第一07
※学ぶということについて語っています。
子夏孝を問う。子曰わく、色難し|「論語」為政第二08
※孝行について孔子に尋ねています。
絵の事は素より後にす。曰わく、礼は後か|「論語」八佾第三08
※詩を語り合えると孔子に言わしめました。
女君子の儒と為れ、小人の儒と為る無かれ|「論語」雍也第六11
※学問好きの子夏は志を持って学究するように孔子から伝えられた。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「文学には子游・子夏」
過ぎたるはなお及ばざるがごとし|「論語」先進第十一15
※子夏は及ばないといいました。「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」
四海の内、皆兄弟なり|「論語」顔淵第十二05
※兄弟について子夏に悩みを相談しています。
燓遅仁を問う。子曰わく、人を愛す|「論語」顔淵第十二22
※孔子に尋ねた「知」の意味が理解できずに、後日子夏に尋ねています。
小利を見れば、則ち大事成らず|「論語」子路第十三17
※莒父の宰となったとき、孔子に政治について尋ねています。
吾が聞く所に異なり|「論語」子張第十九03
※人との交際について話したことが弟子によって語られています。
遠きを致さんには泥まんことを恐る|「論語」子張第十九04
※君子は細かいことに関わることで物事が進まないことを恐れて、それをしないと言います。
学を好むと謂うべきのみ|「論語」子張第十九05
※学ぶことを好むとは?について語っています。
仁其の中に在り|「論語」子張第十九06
※「仁」について語っています。
君子学びて以て其の道を致す|「論語」子張第十九07
※君子の道について語っています。
小人の過つや、必ず文る|「論語」子張第十九08
※小人について語っています。
君子に三変有り|「論語」子張第十九09
※君子の三つの変化、様子について語っています。
君子信ぜられて而して後に其の民を労す|「論語」子張第十九10
※信頼関係について語っています。
大徳は閑を踰えず|「論語」子張第十九11
※大徳と小徳という礼を挙げて徳について語っています。
始有り卒有る者は、其れ唯聖人か|「論語」子張第十九12
※子游の言葉に対して、君子の道を説いています。
仕えて優なれば則ち学ぶ|「論語」子張第十九13
※学びと実践について語っています。
子華(しか)
史魚(しぎょ)
衛(えい)の大夫。名は鰌(しゅう)。魚は字。史は、姓とも官名(史官)とも言われ、未詳。
衛(えい)の大夫。名は鰌(しゅう)。魚は字。史は、姓とも官名(史官)とも言われ、未詳。孔子は「直言直行の、正直一途の人物」と評している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
君子なるかな蘧伯玉|「論語」衛霊公第十五07
※真っ直ぐな性格だと評されています。
子禽(しきん)陳亢(ちんこう)陳子禽(ちんしきん)
姓は陳(ちん)、名は亢(こう)、子禽は字。孔子より四十歳若く、孔子の門人とも、子貢の弟子ともいう。
(前五一一 – ?) 姓は陳(ちん)、名は亢(こう)、子禽は字。孔子より四十歳若く、子貢の門人かともいう。孔子の子の伯魚(はくぎょ)に「父上から特別に教育されていますか」と質問し、「詩を学ぶこと、礼を学ぶこと、君子は我が子には教えないこと、の三つのことを教わった」と喜んだ。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
夫子の是の邦に至るや、必ず其の政を聞く|「論語」学而第一10
※孔子が政治について聞かれることについて、子貢に尋ねています。
詩を聞き、礼を聞き、又君子の其の子を遠ざくるを聞くなり|「論語」季氏第十六13
※孔子の子、伯魚から伝えられたエピソードから学びを得て、喜んでいます。
之を如何ぞ其れ及ぶべけんや|「論語」子張第十九25
※孔子より子貢が優れていると言ったことで、子貢から孔子の評を詳しく語られます。
子貢(しこう)賜(し)
姓は端木(たんぼく)、名は賜(し)、字は子貢(しこう)。孔子より三十一歳若い。「論語」の中で孔子との問答がもっとも多い。言葉巧みな雄弁家で自信家だったが、孔子には聡明さを褒められ、言葉の多さを指摘されている。
経済面で能力が高かったと言われている。
端木賜は字は子貢、衛人。孔子より少きこと三十一歳。口才有りて名を著す。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五二0?ー四五六?)孔門の十哲。姓は端木(たんぼく)、名は賜(し)、子貢(しこう)は字。子贛(しこう)とも書く。衛の人。「論語」の中で孔子との問答がもっとも多い。聡明で、言葉巧みな雄弁家であり、また自信家だった。孔子には聡明さをほめられ、多弁をたしなめられている。一方その雄弁を生かして魯や衛に仕えている。また、木を見て商品を売るのがうまく、膨大な財産を残した。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔子の死後、三年の喪が明けると他の門人たちは故郷に帰ったが、子貢は孔子の冢の傍らに家を建てて、さらに三年仕えたという。
夫子の是の邦に至るや、必ず其の政を聞く|「論語」学而第一10
※冉有の求めに応じて、孔子に出公輒について尋ねています。
切するが如く磋するが如く、琢するが如く磨するが如しと|「論語」学而第一15
※この章句では、孔子から親しみを込めて名で呼ばれている。
先ず行う其の言は、而る後に之に従う|「論語」為政第二13
※孔子に君子について尋ねています。
我は其の礼を愛しむ|「論語」八佾第三17
※子貢が祭礼の習慣を止めようとしたことについて孔子から意見されています。
子曰わく、女は器なり|「論語」公冶長第五04
※この章句では、自分のことを名で呼んでいる。
如かざるなり。吾と女と如かざるなり|「論語」公冶長第五09
※この章句では、自分のことを名で呼んでいる。
賜や爾が及ぶ所に非ざるなり|「論語」公冶長第五12
※人に無理強いをしないようにしたいという子貢を孔子が批評しています。
夫子の文章は、得て聞くべきなり|「論語」公冶長第五13
※孔子は生まれつきや宇宙の道理原則などを語ることはなかったといいます。
孔文子は何を以て之を文と謂うや|「論語」公冶長第五15
※孔文子の贈り名について、孔子に尋ねています。
賜や達なり。政に従うに於て何か有らん|「論語」雍也第六06
※物事をよく知っている、政治を担当することに問題ないと評価されている。
能く近く譬を取る。仁の方と謂うべきのみ|「論語」雍也第六28
※孔子に仁者について尋ねています。
仁を求めて仁を得たり。又何をか怨みん|「論語」述而第七14
※冉有に求められて、孔子が出公輒を助けるかどうかを確認しています。
君子は多からんや。多からざるなり。|「論語」子罕第九06
※子貢がある人に孔子について回答したことを聞いて、孔子自身が自分を評しています。
斯に美玉有り。匵に韞めて諸を蔵せんか、善賈を求めて諸を沽らんか|「論語」子罕第九13
※孔子を美玉にたとえて問答する。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「言語には宰我・子貢」
冉有・子貢侃侃如たり|「論語」先進第十一12
※孔子が弟子に囲まれて楽しそうな様子です。
過ぎたるはなお及ばざるがごとし|「論語」先進第十一15
※子貢の問いに答えました。「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」
億れば則ち屢中る|「論語」先進第十一18
※顔淵と子貢を比較した章句です。
民信無くんば立たず|「論語」顔淵第十二07
※孔子に政事について尋ねています。
文は猶質のごとく、質は猶文のごときなり|「論語」顔淵第十二08
※衛の大夫に君子論について答えています。
自ら辱めらるること無かれ|「論語」顔淵第十二23
※「友」について孔子に尋ねています。
噫、斗筲の人、何ぞ算うるに足らんや|「論語」子路第十三20
※優れた役人について孔子に尋ねています。
未だ可ならざるなり|「論語」子路第十三24
※世間に好かれるか嫌われるか、君子の条件について孔子に尋ねています。
民今に到るまで其の賜を受く|「論語」憲問第十四18
※緩急が仁者であるかどうか、孔子に尋ねています。
君子の道なる者三つ、我能くすること無し|「論語」憲問第十四30
※君子が進む道について孔子が語ったことを聞き、子貢が話しています。
夫れ我は則ち暇あらず|「論語」憲問第十四31
※孔子からひとを比べて批評するといわれています。
我を知る者は其れ天か|「論語」憲問第十四37
※孔子の呟きに応える子貢。弟子との温かいやり取りが伝わります。
予は一以て之を貫く|「論語」衛霊公第十五03
※孔子自身が自分のことを尋ねています。
其の士の仁なる者を友とす|「論語」衛霊公第十五10
※「仁」を実行することについて尋ねています。
子曰わく、其れ恕か|「論語」衛霊公第十五24
※生涯これを行うべきものは?と孔子に尋ねています。
天何をか言うや|「論語」陽貨第十七19
※何も言わないと思うという孔子に対して、何を学び伝えればいいかと返します。
君子も亦悪むこと有りや|「論語」陽貨第十七24
※君子もにくむことがあるのかと孔子に尋ねています。
天下の悪皆焉に帰す|「論語」子張第十九20
※殷の紂王を例に、君子について語っています。
君子の過や、日月の食の如し|「論語」子張第十九21
※君子の過ちについて語っています。
夫子焉にか学ばざらん|「論語」子張第十九22
※公孫朝の質問に答えています。
子貢は仲尼より賢れり|「論語」子張第十九23
※孔子より優れているという評価を聞き、例えてこれを否定しています。
仲尼は日月なり|「論語」子張第十九24
※叔孫武叔が孔子を悪く言うので、たしなめています。
之を如何ぞ其れ及ぶべけんや|「論語」子張第十九25
※孔子より子貢が優れているという陳子禽に対して、言葉を尽くして孔子を評しています。
子羔(しこう)髙柴(こうさい)柴(さい)
姓は髙(こう)、名は柴(さい)、字は子羔(しこう)・子髙(しこう)・子皐(しこう)・季皐(きこう)。孔子より三十歳(また四十歳)若い。
(前五二一? – ?)姓は髙、名は柴、字は子羔(子高・子皐・季皐)。衛の人。また斉の人。鄭の人。孔子より三十歳(また四十歳)若い。身長が五尺(一尺は二二・五センチ)に満たず、かつ醜男だったという。篤行の人で、孔子は「愚直」と評した。子路が彼を費(杜氏、子路の仕えていた季孫氏の領地内の地)の宰(長官)としたが、孔子は「彼を損なう」と、その未熟さを案じた。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
柴や愚、参や魯、師や辟、由や喭|「論語」先進第十一17
※愚直であると言われています。
是の故に夫の佞者を悪む|「論語」先進第十一24
※子路によって費の国の官吏に任用されました。
子西(しせい)
鄭(てい)の大夫。鄭の穆公(ぼくこう)の孫。子産の従兄弟。
鄭(てい)の大夫。鄭の穆公(ぼくこう)の孫。子産の従兄弟。また、楚の令伊(れいいん)[長官]ともいう。孔子は「取るに足りない人物」と評している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
曰わく、彼をや彼をや|「論語」憲問第十四10
※孔子が批評しています。
子産(しさん)
師摯(しし)
子賤(しせん)
姓は宓(ふく)、名は不斉(ふせい)、字は子賤(しせん)。孔子より四十九歳(または三十歳)若い。
宓不斉は魯人。字は子賤。孔子より少きこと四十歳。仕へて單父の宰と為る。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五二一? – ?)姓は宓(ふく)、名は不斉(ふせい)、子賤(しせん)は字。魯(ろ)の人。孔子より四十九歳(また三十歳)若い。孔子に「君子なるかな」と評されている。魯の単父(ぜんぼ)という町の長官となり、琴を奏でてよく治めたという。
子、子賤を謂う、君子なるかな若き人|「論語」公冶長第五03
※孔子が批評しています。
子桑伯子(しそうはくし)
よく分からない人物。集注に魯の人とある。
魯(ろ)の人か。『荘子』内編・大宗師(たいそうし)に出てくる「子桑戸(しそうこ)」かともいう。「大宗師」は、老荘思想の道を体得した偉大な師の意味で、子桑戸もその一人。孔子は子桑戸の師を聞くと、子貢(しこう)を弔問に行かせている。いずれにしても隠者らしく、孔子は「簡なり〔小事にこだわらない寛大な人物〕」と評している。
子曰わく、雍の言然り|「論語」雍也第六01
※威風堂々とした人物だと評されている。
子張(しちょう)師(し)
姓は顓孫(せんそん)、名は師(し)、字は子張(しちょう)。孔子より四十八歳若い。
顓孫師は陳人、字は子張。孔子より少きこと四十八歳。人と為り容貌資質有り。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五0三? – ?)姓は顓孫(せんそん)、名は師(し)、子張(しちょう)は字。陳の人。孔子より四十八歳若い。曽子は「堂々としているが、一緒に仁を行うのは難しい」と評する。孔子は「辟」、「過ぎたり」と評している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
言に尤寡なく行いに悔寡なければ、禄其の中に在り|「論語」為政第二18
※仕官するために学ぶ方法を孔子に尋ねています。
其れ或いは周を継ぐ者は、百世と雖も知るべきなり|「論語」為政第二23
※十代以上も以前のことを知ることができるかと孔子に尋ねています。
未だ知らず、焉んぞ仁なるを得ん|「論語」公冶長第五19
※令尹子文は仁者かどうか孔子に尋ねています。
過ぎたるはなお及ばざるがごとし|「論語」先進第十一15
※子張はやり過ぎだと評価されています。「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」
柴や愚、参や魯、師や辟、由や喭|「論語」先進第十一17
※考え方が偏っていると評されています。
迹を踐まず。亦室に入らず|「論語」先進第十一19
※善人の道について尋ねています。
子張明を問う|「論語」顔淵第十二06
※「明」について尋ねています。
徳を崇くし惑を辨ぜんことを問う|「論語」顔淵第十二10
※「徳」を高くし迷いをなくするためにはどうすべきか尋ねています。
之に居りて倦むこと無く、之を行うに忠を以てす|「論語」顔淵第十二14
※「政」について尋ねています。
士何如なれば斯れ之を達と謂うべき|「論語」顔淵第十二20
※「達」志を遂げることについて尋ねています。
冢宰に聴くこと三年|「論語」憲問第十四42
※孔子に書経の記述について尋ねています。
子張諸を紳に書す|「論語」衛霊公第十五06
※孔子に道・道理が行われないことについて尋ねています。
固より師を相くるの道なり|「論語」衛霊公第十五42
※楽師に気遣う孔子に、これは作法であるかと尋ねています。
曰わく、恭寛信敏恵なり|「論語」陽貨第十七06
※孔子に「仁」について尋ねています。
其れ可ならんのみ|「論語」子張第十九01
※「士」について述べています。
徳を執ること弘からず、道を信ずること篤からずんば|「論語」子張第十九02
※「徳」「道」について述べています。
吾が聞く所に異なり|「論語」子張第十九03
※子夏の弟子から交際について尋ねられています。
然れども未だ仁ならず|「論語」子張第十九15
※子游が子張を批評しています。
与に並びて仁を為し難し|「論語」子張第十九16
※曽子が子張を批評しています。
之を有司と謂う|「論語」堯曰第二十03
※孔子に政治をうまく行うための心得を尋ねています。
漆彫開(しっちょうかい)
姓は漆彫(しっちょう)、名は開・啓、字は子開(子啓)・子若(しじゃく)。孔子より十一歳若い。孔子から能力を買われ仕官を打診されてもなお、まだ充分ではないと言って孔子をよろこばせた。
漆彫開は蔡人。字は子若。孔子より少きこと十一歳。尚書を習ふ。仕ふるを楽しまず。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五四○ – ?)姓は漆彫、名は開、また啓(けい)。字は子開(子啓)、また子若(しじゃく)。魯(ろ)の人、また蔡(さい)の人。孔子より十一歳若い。孔子が仕官を勤めた時「まだ自身がありません」と断って、孔子を喜ばせた。
吾斯を之れ未だ信ずること能わず|「論語」公冶長第五06
※孔子から能力を買われ仕官を打診されてもなお、まだ充分ではないと言って孔子をよろこばせた。
司敗(しはい)
陳の国の官名。他国では司寇(司法長官)という。陳司敗(ちんしはい)という人名とも。定説はない。
陳(ちん)の国の官名。他国では「司寇(しこう・司法長官)」という。また、陳司敗(ちんしはい)という人名で、魯(ろ)の大夫とも言い、定説がない。
苟くも過有れば、人必ず之を知る|「論語」述而第七30
※昭公は礼を知っているかと孔子に尋ねたことから始まるエピソードが紹介されます。
司馬牛(しばぎゅう)
姓は司馬(しば)、名は耕(こう)、字は子牛(しぎゅう)。
司馬耕は宋人。字は子牛。牛、性為る躁、言語を好くす。兄桓魋の行い悪しきを見て、牛常に之を憂ふ。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
仁者は其の言や訒ぶ|「論語」顔淵第十二03
※孔子に「仁」について尋ねた。
内に省みて疚しからざれば、夫れ何をか憂え何をか懼れん|「論語」顔淵第十二04
※孔子に「君子」について尋ねた。
四海の内、皆兄弟なり|「論語」顔淵第十二05
※兄弟について子夏に悩みを相談しています。
四飯缺(しはんけつ)
四飯(しはん)は、楽官の名。缺(けつ)は名。
四飯(しはん)は、楽官の名。諸侯の飲食の際に、音楽を奏して興を添える役で、四飯は、四度めの食を勧める役という。缺(けつ)は、魯(ろ)国の衰乱を見て秦(しん)に去った。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※秦に至りました。
子服景伯(しふくけいはく)
魯(ろ)の人。姓は子服(しふく)、名は何(か)。伯(はく)は字。景(けい)は贈り名。三桓(さんかん)氏の一族で、孟献子(もうけんし)の玄孫。
魯(ろ)の人。姓は子服(しふく)、名は何(か)。伯(はく)は字。景(けい)は贈り名。三桓(さんかん)氏の一族で、孟献子(もうけんし)の玄孫。孔子やその門人たちに好意を持っていた人格者らしい。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
公伯寮其れ命を如何せん|「論語」憲問第十四38
※子路のことを悪く告げ口した公伯寮の行いを孔子に話し、罪に問うこともできると言います。
子貢は仲尼より賢れり|「論語」子張第十九23
※叔孫武叔が子貢が孔子より優れていると評していることを、子貢に知らせました。
子文(しぶん)
師冕(しべん)
師は大師(音楽師の長官)で、冕が名。目の不自由な人がこの役に当たるようです。
師は大師(音楽師の長官)で、冕が名。目の不自由な人がこの役に当たるようで、孔子は、会いに来た師冕に一つ一つ教えて誘導し、それが礼であると言っている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
固より師を相くるの道なり|「論語」衛霊公第十五42
※楽師を気遣う孔子に、子張がこれは作法であるかと尋ねています。
子游(しゆう)言游(げんゆう)偃(えん)
姓は言(げん)、名は偃(えん)、字は子游。武城の町の宰(長官)となる。孔子より四十五歳若い。
言偃は魯人。字は子游。孔子より少きこと三十五歳。詩に習ひ、能く其の義に通ず。文学を以て名を著す。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
敬せずんば何を以て別たんや|「論語」為政第二07
※孝行について孔子に尋ねています。
朋友に數すれば、斯に疏んぜらる|「論語」里仁第四26
※君子と朋友について語っています。
行不由径、非公事、未嘗至於偃之室也|「論語」雍也第六12
※武城の長官になったとき、補佐役の人材登用について孔子から尋ねられている。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「文学には子游・子夏」
鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん|「論語」陽貨第十七04
※孔子が武城を訪れた際に、その能力を評価される。
始有り卒有る者は、其れ唯聖人か|「論語」子張第十九12
※子夏の弟子について、意見をしています。
喪は哀を致して止む|「論語」子張第十九14
※喪について語っています。
然れども未だ仁ならず|「論語」子張第十九15
※子張を批評しています。
周公(しゅうこう)
周公旦。名は旦(たん)。周の文王の子、武王の弟。武王の子の成王を補佐して、制度や儀式・礼楽などを定めたが自らは天子の位に即こうとしなかった。魯の国の始祖。孔子の理想とする人物。
名は旦(たん)。周の文王(ぶんおう)の子で、武王(ぶおう)の弟。武王の子の成王(せいおう)を補佐して、周王朝の道徳、文化、制度を確立した。また自身は魯(ろ)に封ぜられ、魯国の始祖となった。孔子は彼を理想と仰ぎ、晩年には「周公を夢に見なくなった、私も衰えたなあ」と慨嘆している。
久しきかな、吾復夢に周公を見ず|「論語」述而第七05
※周公の夢を見なくなったと孔子が言います。
如し周公の才の美有りとも|「論語」泰伯第八11
※周公が美しい能力があると例えとして引き合いに出しています。
周任(しゅうにん)
昔の立派な史官。史官は記録係。
昔の立派な史官。史官は記録係。
「論語 新釈漢文大系」吉田賢抗著(明治書院 刊)
季孫の憂は、顓臾に在らずして|「論語」季氏第十六01
※冉有と季路の相談に乗る際、周任を例に説明しています。
叔夏(しゅくか)
叔斉(しゅくせい)
叔孫武叔(しゅくそんぶしゅく)
魯(ろ)の大夫、叔孫(しゅくそん)氏の第八代目。名は州仇(しゅうきゅう)。武叔(ぶそん)は贈り名。
魯(ろ)の大夫、叔孫(しゅくそん)氏の第八代目。名は州仇(しゅうきゅう)。武叔(ぶそん)は贈り名。「子貢は孔子より優れている」などと発言して、子貢に戒められている。また、前四八四年に斉(せい)が攻めてきた時には、戦いに参加せず、冉有(ぜんゆう)に「小人」と批判されている。
子貢は仲尼より賢れり|「論語」子張第十九23
※朝廷で他の大夫に、子貢が孔子より優れていると語っています。
仲尼は日月なり|「論語」子張第十九24
※孔子を悪く言い、子貢にたしなめられています。
祝鮀(しゅくだ)
名は鮀。祝は宗廟の祭官の職。字は子魚。衛の大夫。口才があった。
衛(えい)の大夫。名は鮀(だ)、字は子魚(しぎょ)。祝(しゅく)は、神官の職らしく、霊公(れいこう)に仕えて宗廟の祭祀をつかさどり、王孫賈(おうそんか)、仲叔圉(ちゅうしゅくぎょ)と併称された名臣。弁説も巧みだった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
難いかな今の世に免れんこと|「論語」雍也第六14
※口才があったと伝えている。
子衛の霊公の無道なるを言う|「論語」憲問第十四20
※祭祀を治めていた。
叔夜(しゅくや)|叔夏(しゅくか)
周の成王(また宣王、文王、武王ともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。
周(しゅう)の成王(せいおう・また宣王せんのう、文王ぶんのう、武王ぶおうともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。その一人で、かつ叔夜と三番めの双児だったという。
周に八士有り|「論語」微子第十八11
※周代の才能を備えた人として紹介されています。
朱張(しゅちょう)
孔子の挙げる遺逸(いいつ)の民〔志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人〕七人の一人。
孔子の挙げる遺逸(いいつ)の民〔志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人〕七人の一人。
可も無く不可も無し|「論語」微子第十八08
※世を逃れ隠居している人で高名な人として、孔子が取り上げています。
出公輒(しゅっこうちょう)衛君(えいくん、えいのきみ)
名は輒(ちょう)。出公(しゅっこう)といい、出公輒と呼ぶ。衛の霊公の孫、蒯聵(かいがい)の子。
名は輒(ちょう)。出公(しゅっこう)と言い、出公輒と呼ぶ。衛の霊公の孫、蒯聵(かいがい)の子。蒯聵が母の南子の品行の悪いのを恥じて殺そうとしたが失敗し、宋から晋に亡命した(前四九六)。間もなく霊公が死に、輒が即位して出公と称した。しかし蒯聵はこれを認めず、以後十六年にわたる親子の争いが続き、出公輒はついに魯に逃れた(前四八0)。蒯聵が跡を継いで、荘公と称する。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
仁を求めて仁を得たり。又何をか怨みん|「論語」述而第七14
※冉有が子貢に、孔子が出公輒を助けるかと尋ねています。
故に君子は之に名づくれば、必ず言うべきなり。之を言えば、必ず行うべきなり|「論語」子路第十三03
※子路が君の下で孔子にどんな政治を行うか尋ねています。
孺悲(じゅひ)
魯(ろ)の人か。
魯(ろ)の人か。紹介もなく孔子に会いに来たので、孔子は病気だからと会わなかった。そしてすぐに琴を奏でて歌い、仮病であることを孺悲に知らせて、それとなく非礼をさとした。
孔子辞するに疾を以てす|「論語」陽貨第十七20
※孔子との面会を断られています。
舜(しゅん)
商(しょう)
襄(じょう)
昭公(しょうこう)
魯(ろ)の君主。名は稠(ちょう)。襄(じょう)公の子。大夫の李氏を討とうとして失敗し斉の国へ逃れ晋の国で死んだ。
(前五六一 – 五一○)魯(ろ)の君。名は稠(ちょう)。条項の庶子(しょし)。十九歳で即位。大夫の季平子(きへいし)を討とうとして失敗し、前五一七年に晋(しん)に亡命して五十二歳で死んだ。
苟くも過有れば、人必ず之を知る|「論語」述而第七30
※陳の司敗が昭公は礼を知っているかと孔子に尋ねています。
葉公(しょうこう)
姓は沈(ちん)、名は諸梁(しょりょう)、字は子高(しこう)。楚(そ)の国の重臣で葉(しょう)地方の長官。自分で「公」を僭称していた。賢明な政治家だったが、孔子をあまり尊敬していなかったらしい。
姓は沈(ちん)、名は諸梁(しょりょう)、字は子高(しこう)。楚(そ)の国の重臣で、またその葉(しょう)地方の長官。自分で「公」を僭称していた。賢明な政治家だったが、孔子をあまり尊敬していなかったらしい。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
葉公孔子を子路に問う。子路対えず|「論語」述而第七18
※葉公が子路に孔子について尋ねたことを知った孔子が話をしています。
近き者説べば、遠き者来る|「論語」子路第十三16
※葉公は政治について孔子に尋ねています。
吾が党に直躬なる者有り|「論語」子路第十三18
※正しい行いについて、孔子と会話しています。
召忽(しょうこつ)
斉(せい)の公子・糾(きゅう)の傅(ふ・守り役)。
斉(せい)の公子・糾(きゅう)の傅(ふ・守り役)。斉の内乱の時、管仲(かんちゅう)と共に糾を助けて魯(ろ)に逃れた。糾は、斉に戻ろうとして小白(しょうはく)と戦って敗れ、小白は斉の桓公(かんこう)となった。桓公は魯国に糾を殺させ、召忽は自殺してこれに殉死した。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
召忽之に死し、管仲は死せず|「論語」憲問第十四17
※子路が仁について尋ねています。
少師陽(しょうしよう)
少師(しょうし)は、音楽の長官である大師(たいし)の補佐役。陽(よう)は人名。
少師(しょうし)は、音楽の長官である大師(たいし)の補佐役。陽(よう)は人名。陽は、魯(ろ)国は、衰乱を見て海のほとりに去った。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※海のほとりに移りました。
少連(しょうれん)
孔子の挙げる遺逸(いいつ)の民〔志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人〕七人の一人。
孔子の挙げる遺逸(いいつ)の民〔志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人〕七人の一人。また、よく喪に服して悲哀の情を尽くしたという。
可も無く不可も無し|「論語」微子第十八08
※言うことは道徳的であり、行動は深く考えられていたと評されています。
稷(しょく)
名は棄(き)。周の開祖。后稷(こうしょく)という農業大臣の官につき、舜に仕えた。
名は棄(き)。帝嚳(ていこく)の妃が野原で巨人の足跡を踏み、身ごもって産んだ子。帝舜(ていしゅん)に認められて仕え、后稷(こうしょく・農業大臣)となって人々に農作を教えた。その子孫が文王(ぶんのう)・武王(ぶおう)で、周(しゅう)を建国した。なお「稷」は穀物の一種で高梁(こいうりゃん)。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
君子なるかな若き人|「論語」憲問第十四06
※南宮适が孔子と話す中で、稷は自分自身で種を蒔いて天下を治めたといいます。
子路(しろ)季路(きろ)由(ゆう)仲由(ちゅうゆう)
姓は仲(ちゅう)、名は由(ゆう)、字は子路(しろ)・季路(きろ)。孔子より九歳若い。孔子のボディガード役を果たした。
仲由は弁人。字は子路。一の字は季路。孔子より少きこと九歳。勇力才芸有り。政事を以て名を著す。人と為り果烈にして剛直。性、鄙にして変通に達せず。衛に仕へて大夫と為る。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五四二 – 四八0)孔門の十哲。姓は仲、名は由、字は子路また季路とも言った。魯の卞の人。孔子より九歳若く、孔子門人中の最年長者。『論語』の四十章に登場し、門人中もっとも多い回数。性は野鄙だが、正道を守って曲げない。豪傑肌の人物。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
若い時は任侠を好んで、雄鶏を頭に載せ、雄豚を腰に下げて意気揚々としていた。孔子に乱暴をはたらこうとしたこともあったが、孔子は礼儀によって少しずつ子路を導き、子路は感化されて孔子の門人となった。以後、孔子の生涯にわたってボディガードの役を果たした。
魯の大夫である季氏の宰(家老)となり、また衛の国の蒲の宰となった。ここで内覧に巻き込まれ、二人の敵に切りかかられて冠の紐を切られてしまった。子路は「君子は死んでも冠を脱がない」と、紐を結び直して死んでいった。六十四歳で、孔子より一年早い。
之を知るを之を知ると為し、知らざるを知らずと為せ。是れ知るなり|「論語」為政第二17
※この章句では、孔子から親しみを込めて名で呼ばれている。
我に従わん者は其れ由なるか|「論語」公冶長第五07
※もし孔子が逃げ出したくなったとき着いてくるのは子路くらいだと言われ喜ぶ。
其の仁を知らざるなり|「論語」公冶長第五08
※千乗の規模を誇る国の軍隊を扱わせるだけの能力があると孔子に評価された。
唯聞く有らんことを恐る|「論語」公冶長第五14
※学びをひとつひとつ実践することを心がけ、それが不十分であれば新しい学びを知ることさえ恐れる実直さを持っていた。
盍ぞ各爾の志を言わざる|「論語」公冶長第五26
※顔淵と共に孔子に付き添っていたとき、志について尋ねられています。
由や果なり。政に従うに於て何か有らん|「論語」雍也第六06
※決断力がある、政治を担当することに問題ないと評価されている。
予が否なる所の者は、天之を厭たん|「論語」雍也第六26
※孔子が南子に拝謁したことを悦んでいません。
子路曰わく、子三軍を行らば則ち誰と与にせん|「論語」述而第七10
※孔子が大軍を動かすとしたら弟子の中では子路自身に任せるだろうと質問をする場面。これに答える孔子のことばが印象的。
葉公孔子を子路に問う。子路対えず|「論語」述而第七18
※孔子の人柄について尋ねられたが、子路なりの考えがあって答えなかった。
丘の祈ること久し|「論語」述而第七34
※孔子の容態を心配して祈ることを願い出た。
無寧二三子の手に死なんか|「論語」子罕第九12
※孔子の病床において大夫の待遇を諌められるも、孔子からその配慮に感謝された。
何ぞ以て臧しとするに足らん|「論語」子罕第九27
※孔子からの褒め言葉をくり返し読む様子が描かれています。
時なるかな時なるかな|「論語」郷党第十18
※孔子と子路が登場する場面で郷党第十を締めくくります。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「政事には冉有・季路」
未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん|「論語」先進第十一11
※孔子に神に仕えることとは?死とは?と質問したが、たしなめられている。
子路行行如たり|「論語」先進第十一12
※孔子が弟子に囲まれて楽しそうな様子の中で、子路の行く末を案じています。
由や堂に升れり。未だ室に入らざるなり|「論語」先進第十一14
※大琴の技量を評価されています。
柴や愚、参や魯、師や辟、由や喭|「論語」先進第十一17
※粗野でがさつだと評されています。
聞くままに斯れ諸を行わんか|「論語」先進第十一21
※聞いたことをすぐ実行するのではなく相談して行うようにアドバイスされます。
道を以て君に事え、不可なれば則ち止む|「論語」先進第十一23
※季子然が任用した子路と冉有について孔子に尋ねています。
是の故に夫の佞者を悪む|「論語」先進第十一24
※言い訳をする子路に、孔子が口の達者なものは嫌いだと言います。
子路・曽晳・冉有・公西華、侍坐す|「論語」先進第十一25
※孔子から抱負を聞かれ答えています。
子路は諾を宿むること無し|「論語」顔淵第十二12
※孔子から引き受けたことを引き延ばさない人物であるといわれています。
子路政を問う。子曰わく、之に先んじ、之を労う|「論語」子路第十三01
※孔子に「政」について尋ねています。
子路曰わく、衛の君子を待ちて政を為さば、子将に奚をか先にせん|「論語」子路第十三03
※孔子が衛の国の君に迎えられたら、どんな政治を行うか尋ねています。
子路問うて曰わく、何如なるか斯れ之を士と謂うべき|「論語」子路第十三28
※孔子にどんな人物が「士」といえるか尋ねています。
子路成人を問う|「論語」憲問第十四13
※「成人」について尋ねています。
曰わく、未だ仁ならざるか|「論語」憲問第十四17
※管仲がまだ思いやりの心がないと孔子に伝えています。
子路君に事えんことを問う|「論語」憲問第十四23
※主君に仕えることについて尋ねています。
公伯寮其れ命を如何せん|「論語」憲問第十四38
※公伯寮が子服景伯に子路のことを告げ口しました。
是れ其の不可なるを知りて、而も之を為す者か|「論語」憲問第十四40
※子路と門番との会話で、孔子に対する当時の噂を知ることができます。
堯舜も其れ猶諸を病めり|「論語」憲問第十四44
※「君子」について尋ねています。
君子固より窮す。小人窮すれば斯に濫る|「論語」衛霊公第十五02
※「君子」が貧しくて困ることがあるかと尋ねています。
徳を知る者は鮮なし|「論語」衛霊公第十五04
※孔子と子路が悩みを共有しています。
吾季孫の憂は、顓臾に在らずして、蕭牆の内に在るを恐るるなり。|「論語」季氏第十六01
※季氏が顓臾に戦争を起こそうとすると、冉有と季路が孔子に相談します。
吾は其れ東周を為さんか|「論語」陽貨第十七05
※公山弗擾に招かれた孔子を、子路が止めています。
焉んぞ能く繫りて食われざらんや|「論語」陽貨第十七07
※仏肸に招かれ行こうとする孔子に、その理由を聞いています。
由や、女六言六蔽を聞けるか|「論語」陽貨第十七08
※孔子は、六言六蔽について子路に伝えています。
君子勇を尚ぶか|「論語」陽貨第十七23
※君子は勇敢さを尊重するか?と孔子に尋ねています。
丘は与に易えざるなり|「論語」微子第十八06
※孔子に従わずに、世を捨てた隠者に従う方がいいのではと言われます。
道の行われざるや、已に之を知れり|「論語」微子第十八07
※君子が仕えるというのは正しい事を行うためだと話します。
参(しん)
申棖(しんとう)棖(とう)
姓は申、名は棖、また党・棠・続、字は周。章句から孔子の弟子だと考えられる。剛く見える人物だったが、孔子は本当に強いひとと呼べるだろうかといった。
姓は申、名は棖、また党(とう)、棠(とう)、続(とう)ともいう。字は周(しゅう)。魯(ろ)の人か。ある人が「剛者(堅強な人)」と評したのに対して、孔子は「彼は欲が多いから剛者ではない」と答えた。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
棖や慾あり。焉んぞ剛なるを得ん|「論語」公冶長第五11
※孔子が批評しています。
晨門(しんもん)
魯(ろ)の城外の門の一つ、石門を守る番人。普通名詞を固有名詞のように使っている。
魯(ろ)の城外の門の一つ、石門を守る番人。普通名詞を固有名詞のように使っている。孔子を「世直しは不可能と知りながら、なおうろうろしている人」と評した。
是れ其の不可なるを知りて、而も之を為す者か|「論語」憲問第十四40
※孔子一行に話しかけています。
斉君(せいくん)荘公(そうこう)
斉(せい)の荘公(そうこう)。名は光(こう)。前五五四年に即位したが、自分を擁立してくれた大夫の崔杼(さいちょ)に殺された。
未だ知らず、焉んぞ仁なるを得ん|「論語」公冶長第五19
※孔子と子張の会話で取り上げられます。
世叔(せいしゅく)
鄭(てい)の大夫。簡公(かんこう)、定公(ていこう)、献公(けんこう)に仕えた。
春秋時代、鄭(てい)の大夫。姓は游(ゆう)、名は吉(きつ)、世叔は字で、また子大叔(したいしゅく)とも言う。簡公(かんこう)、定公(ていこう)、献公(けんこう)に仕えた。美貌の人で、また故事や典礼に通じ、文才があって外交文章の草案をチェックした。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
命を為るに、裨諶之を草創し|「論語」憲問第十四09
※鄭の四人の大夫が協力して外交文章を作成していることを紹介しています。
赤(せき)
接輿(せつよ)
楚(そ)の国の隠者(いんじゃ)。偽って狂人の振りをしていたので楚狂と呼ぶ、ともいう。
楚(そ)の国の隠者(いんじゃ)。姓は陸(りく)、名は通(つう)、接輿は字という。また、姓が接、名が輿ともいう。偽って狂人の振りをしていたので楚狂と呼ぶ、ともいう。「今の政事にかかわるのは危険だ」と、孔子を諌める詩を歌っている。
已みなん、已みなん|「論語」微子第十八05
※徳が衰えた楚の国の政事に従う者は危ういと、孔子を諌めています。
僎(せん)
衛(えい)の大夫。公叔文子の臣。
衛(えい)の大夫。公叔文子(こうしゅくぶんし)の臣。後に大夫となった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
以て文と為すべし|「論語」憲問第十四19
※公叔文子が主君に推薦しています。
冉求(ぜんきゅう)
冉伯牛(ぜんはくぎゅう)伯牛(はくぎゅう)
姓は冉(ぜん)、名は耕(こう)、字は伯牛(はくぎゅう)。孔子より七歳若い。
冉有は魯人。字は伯牛。徳行を以て名を著す。悪疾有り。孔子曰く、命なるかな、と。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五四四 – ?)孔門の十哲。姓は冉、名は耕(こう)、字は伯牛。魯〔ろ)の人で、孔子より七歳若いという。魯の中都(地名)の宰(家老)を勤めたという。晩年には悪病に冒されたが、ハンセン病かと言われる。
斯の人にして而も斯の疾あるや|「論語」雍也第六08
※病床を孔子が見舞っています。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「徳行には顔淵・閔子騫・冉伯牛・仲弓」
冉有(ぜんゆう)求(きゅう)冉求(ぜんきゅう)
姓は冉(ぜん)、名は求(きゅう)また有(ゆう)。字は子有(しゆう)。孔子より二十九歳若い。温和な性格だったようです。
冉求は字は子有。仲弓の宗族なり。孔子より少きこと二十九歳。才芸有り。政事を以て名を著す。仕へて季氏の宰と為る。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五二二 – 四八九?)孔門の十哲。姓は冉(ぜん)、名は求(きゅう)、また有(ゆう)。字は子有(しゆう)。魯の人。孔子より二十九歳若い。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
穏和な人柄だったようで、孔子に「退く[引っ込み思案]」と評され「画れり[自分の力を見限っている]」と注意されている。
一方、多芸で政治家向きと言われ、季氏の宰[家老]となったが、その専横をあらためさせるどころか、かえって季氏に協力し、孔子に「我々の仲間ではない。攻撃してもよいぞ」とまで言われている。これも、人の好きの災いか。
嗚呼、曾ち泰山は林放に如かずと謂えるか|「論語」八佾第三06
※季氏の非礼を正すことができるか孔子から尋ねられますができないと答えています。やや消極的な印象を受けます。
其の仁を知らざるなり|「論語」公冶長第五08
※孔子の人物評では、千戸の集落の長官や、百乗の領地を持つ大夫の家の家老なら務まる。
以て爾が鄰里郷党に与えんか|「論語」雍也第六03
※子華の留守中に、子華の母親を気遣います。
求や芸あり。政に従うに於て何か有らん|「論語」雍也第六06
※多才な人物であり、政治を担当することに問題ないと評価されている。
今女は画れり|「論語」雍也第六10
※やる前から自分に限界を作っていると孔子から指導、励まされている。
仁を求めて仁を得たり。又何をか怨みん|「論語」述而第七14
※孔子が衛君を助けるか、子貢に意見を求めています。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「政事には冉有・季路」
冉有・子貢侃侃如たり|「論語」先進第十一12
※孔子が弟子に囲まれて楽しそうな様子です。
吾が徒に非ざるなり|「論語」先進第十一16
※季氏に加担してしまったことを孔子が弟子に伝えています。
聞くままに斯れ諸を行わんか|「論語」先進第十一21
※聞いたことをすぐ実行するように言われています。
道を以て君に事え、不可なれば則ち止む|「論語」先進第十一23
※季子然が任用した子路と冉有について孔子に尋ねています。
子路・曽晳・冉有・公西華、侍坐す|「論語」先進第十一25
※孔子から抱負を聞かれ答えています。
曰わく、之を教えん|「論語」子路第十三09
※孔子の御者として衛の国に行きます。
吾其れ之を与り聞かん|「論語」子路第十三14
※遅く帰ってきた冉有に孔子が意見をする章句です。
臧武仲の知、公綽の不欲、卞莊子の勇、冉求の芸|「論語」憲問第十四13
※冉求の才知が「成人」の条件として紹介されています。
吾季孫の憂は、顓臾に在らずして、蕭牆の内に在るを恐るるなり。|「論語」季氏第十六01
※季氏が顓臾に戦争を起こそうとすると、冉有と季路が孔子に相談します。
曾子(そうし)曽子(そうし)
姓は曾、名は参(しん)、字は子輿(しよ)。孔子より四十六歳若い。
孔子の教えを伝えた第一人者と言われています。
(前五○五? – 四三五)姓は曾、名は参(しん)、字は子與(しよ)。魯(ろ)の武城の人という。孔子より四十六歳若い。孔子は「魯(のろま)」と評したが、「三省」の章で知られるとおり、内省的な人柄である。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔子は「孝」の道に通じているとして、彼に『孝経』を書かせた[史記]。(ただし、孔子が曾子に孝の道を説いたのが『孝経』であるとも言う[漢書・芸文志(げいもんし)]。また曽子の門人の作、孔子の孫の子思(しし)の作、孟子の門人の楽正子春(がくせいししゅん)の作、などとも言われる。)
孔子の道を伝えた第一人者で、『論語』には「有子(ゆうし)有若(ゆうじゃく)」などとともに「子」をつけて登場する。七十余歳まで生きたようで、孔子の孫の子思を教えている。
なお、曽子の言行を伝えるものとして、『大戴礼(だたいれい)』に載せる「曽子」十編がある。
吾日に吾が身を三省す|「論語」学而第一04
※三省堂書店の由来になった章句です。
終を慎み遠きを追えば|「論語」学而第一09
※葬式について話しています。
夫子の道は、忠恕のみ|「論語」里仁第四15
※孔子の一貫した教えについて、他の弟子に伝えています。
而今よりして後、吾免るるを知るかな|「論語」泰伯第八03
※病床で弟子たちに「孝」について伝えています。
君子道に貴ぶ所の者三|「論語」泰伯第八04
※孟敬子が危篤の曽子を見舞います。
昔者吾が友、嘗て斯に従事せり|「論語」泰伯第八05
※曽子が友人のことを高く評価しています。
君子人か、君子人なり|「論語」泰伯第八06
※君子について語っています。
仁以て己が任と為す、亦重からずや|「論語」泰伯第八07
※ひとの上に立つ者の責任について絶え間ない努力と死ぬまで実践することを求めています。
柴や愚、参や魯、師や辟、由や喭|「論語」先進第十一17
※孔子が批評しています。
君子は文を以て友を会し、友を以て仁を輔く|「論語」顔淵第十二24
※「友」について語る章句です。
君子は思うこと其の位を出でず|「論語」憲問第十四28
※君子について語っています。
与に並びて仁を為し難し|「論語」子張第十九16
※子張について批評しています。
必ずや親の喪か|「論語」子張第十九17
※孔子に聞いた話を紹介しています。
其の父の臣と父の政とを改めざる|「論語」子張第十九18
※孔子に聞いた話として、孟荘子の孝について語っています。
哀矜して喜ぶこと勿かれ|「論語」子張第十九19
※弟子の陽膚が法務長官としての心得を曽子に尋ねています。
曾晳(そうせき)曽晳(そうせき)
姓は曽、名は点(てん)または蒧(てん)・點(てん)、字は晳(せき)・子晳(しせき)。曽子の父。
姓は曾、名は点(てん)、また蒧(てん)。晳は字で、子晳(しせき)ともいう。曾子(そうし)の父。穏和な人で、孔子に志を問われて「沂に浴し、舞雩に風し、詠じて帰らん」と答え、孔子に感嘆されている。『論語』には、この一章だけに登場。
子路・曽晳・冉有・公西華、侍坐す|「論語」先進第十一
※孔子から抱負を聞かれ答えています。
宋朝(そうちょう)
宋の公子。名は朝。美男であった。
宋(そう)国の公子で、名は朝(ちょう)、たいへんな美貌の持ち主で、また、衛(えい)の霊公(れいこう)の妃である南子(なんし)が霊公に嫁ぐ前から通じており、南子が妃となると、南子は宋朝を呼び寄せては不義を重ねたという。
難いかな今の世に免れんこと|「論語」雍也第六14
※美男であったと伝えている。
臧武仲(ぞうぶちゅう)
魯(ろ)の大夫。臧文仲(ぞうぶんちゅう)の孫。
魯(ろ)の大夫。姓は臧、名は(こつ)、武仲は贈り名。臧文仲(ぞうぶんちゅう)の孫。才知があるが、季孫(きそん)氏の跡継ぎ争いに関係して(ちゅ)の国から斉(せい)に逃げた。途中、魯の襄公(じょうこう)を強迫したとして、孔子は彼を評価しない。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
臧武仲の知、公綽の不欲、卞莊子の勇、冉求の芸|「論語」憲問第十四13
※臧武仲の知識が「成人」の条件として紹介されています。
君を要せずと曰うと雖も、吾は信ぜざるなり|「論語」憲問第十四15
※臧武仲が君主に願い請うた行動を非難しています。
臧文仲(ぞうぶんちゅう)
魯(ろ)の大夫。姓は臧孫(ぞうそん)、名は辰(しん)、字は仲(ちゅう)、贈り名は文(ぶん)。荘公(そうこう)、閔公(びんこう)、僖公(きこう)、文公(ぶんこう)の四代にわたって魯の大夫でした。
(? – 前六一七)魯(ろ)の大夫。姓は臧孫(ぞうそん)、名は辰(しん)、仲(ちゅう)は字、文(ぶん)は贈り名。荘公(そうこう)、閔公(びんこう)、僖公(きこう)、文公(ぶんこう)の四代にわたって、五十年近く魯の大夫として活躍し、また知者として知られる。しかし孔子は「あの僭越な態度は、とても知者とは言えない」「地位を盗む者」と批判している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
何如ぞ其れ知ならん|「論語」公冶長第五18
※知者ではないと批判している
臧文仲は、其の位を窃む者か|「論語」衛霊公第十五14
※臧文仲は官位を独占しようとする者であるかと批判している
た行 △ ▽
大宰(たいさい)
官名、首相に相当する地位。呉の大宰か宋の大宰なのか不明。
官名で、宰相〔大臣〕の大宰は、呉(ご)の国の大宰・伯嚭(はくひ)のことかとされる。姓は伯、名は嚭、字は子余(しよ)。大宰嚭とも言う。呉王の闔閭(こうりょ・?ー前四九六)と、その子の夫差(ふさ・?ー前四七三)に仕えた。闔閭は越(えつ)王の勾践(こうせん)と戦い、敗れて死んだので、夫差は復讐戦で勾践を破り、捕らえた。しかし、伯嚭は、越から賄賂を受けて勾践を釈放した。のち勾践が呉を討った時、伯嚭を主人(すなわち夫差)を売る不忠者として、伯嚭を殺した。
君子は多からんや。多からざるなり。|「論語」子罕第九06
※子貢に孔子が聖者かと尋ねています。
大師摯(たいしし)師摯(しし)
大師(たいし)は、音楽師の長官で、摯(し)が名。
大師(たいし)は、音楽師の長官で、摯(し)が名。魯(ろ)に仕えていたが、魯の季桓子(きかんし)が斉(せい)の女楽を受け入れたため魯の音楽が乱れたとして、斉に逃れた。晩年の孔子は「師摯の演奏が今も耳に残っている」と回顧している。
洋洋乎として耳に盈てるかな|「論語」泰伯第八15
※摯が奏でる音楽は耳から溢れ出るようだったと評価しています。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※斉に至りました。
泰伯(たいはく)
太伯とも書く。殷代末期の周の太王の長子で、下に弟の虞仲(ぐちゅう)、季歴(きれき)がいた。季歴の子が昌(しょう)で、後に周の文王(ぶんのう)となる。泰伯は優秀の孫の昌に国を継がせたいという太王の意を察し、虞仲とともに南方に逃れて、季歴に、次いで昌に地位を譲った。
太伯とも書く。殷(いん)代末期の、周の太王(たいおう・古公亶父(ここうたんぽ))の長子で、下に弟の虞仲(ぐちゅう)、季歴(きれき)がいた。季歴の子が昌(しょう)で、後に周の文王(ぶんのう)となる。泰伯は優秀の孫の昌に国を継がせたいという太王の意を察し、虞仲とともに南方に逃れて、季歴に、次いで昌に地位を譲った。孔子はこの態度を「至徳」とたたえている。
泰伯は其れ至徳と謂うべきのみ|「論語」泰伯第八01
※孔子が批評しています。
澹台滅明(たんだいめつめい)
姓は澹台、名は滅明、字は子羽。魯の武城の人。孔子より三十九歳若い。外見が醜男(ぶおとこ)であったらしいが、公正な人物であった。
(前五○二 – ?)姓は澹台、名は滅明、字は子羽(しわ)。孔子より三十九歳(四十九歳)若い。魯(ろ)の武城(ぶじょう)の人。容貌が醜かったので、孔子に、才能が乏しいと思われた。しかし彼は、正道に従って孔子に就いて学び、武城の長官をしていた子游(しゆう)に「公正な人」と評されている。江南地方に旅したときには、後に随った門人が三百人あったという。
曰わく、澹台滅明なる者あり|「論語」雍也第六12
※孔子が子游に人材がいるかと尋ねた際、子游が紹介した人物です。
紂(ちゅう)
紂王(ちゅうおう)。名は辛(しん)、また受(じゅ)。紂は、呼び名、また贈り名。殷(いん)の第三十一代、最後の王。弁説に優れ、行動は敏捷、力が強かった。
名は辛(しん)、また受(じゅ)。紂は、呼び名、また贈り名。殷(いん)の第三十一代、最後の王。弁説に優れ、行動は敏捷、力が強かった。贅沢を尽くし、暴虐無道で、「酒池肉林(しゅちにくりん)」の故事で知られる。夏の桀王(けつおう)とともに暴君の代表として「桀紂(けっちゅう)」と並称される。前一○二○年ころ、周の武王(ぶおう)に滅ぼされた。
天下の悪皆焉に帰す|「論語」子張第十九20
※子貢が紂王を例に、君子について語っています。
仲弓(ちゅうきゅう)雍(よう)
姓は冉(ぜん)、名は雍(よう)、字は仲弓(ちゅうきゅう)。孔子より二十九歳若い門人。李氏の宰になった。
冉雍は字は仲弓。伯牛の宗族なり。孔子より少きこと二十九歳。不肖の父より生れ、徳行を以て名を著す。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五二二 – ?)孔門の十哲。姓は冉(ぜん)、名は雍(よう)、仲弓(ちゅうきゅう)は字。魯の人で、孔子より二十九歳若いという。季氏の宰(家老)となった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔子は、君子にしてもよい人物、と褒めている。一方「己の欲せざる所、人に施すこと勿かれ」と教えられている、徳行の人。
或ひと曰わく、雍や仁にして佞ならず。|「論語」公冶長第五05
※この章句により寡黙な様子が伝わる。
子曰わく、雍の言然り|「論語」雍也第六01
※諸侯として政治を任せてもいい人物だと孔子から評価されている。
山川其れ諸を舎てんや|「論語」雍也第六04
※孔子が批評しています。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「徳行には顔淵・閔子騫・冉伯牛・仲弓」
己の欲せざる所は、人に施すこと勿れ|「論語」顔淵第十二02
※孔子に「仁」について尋ねています。
爾の知る所を挙げよ|「論語」子路第十三02
※季氏の宰になり、孔子に「政」について尋ねています。
仲忽(ちゅうこつ)
仲叔圉(ちゅうしゅくぎょ)孔文子(こうぶんし)
姓は孔、名は圉(ぎょ)、贈り名は文。衛の国の大夫。贈り名として「文」は最上の文字。
姓は孔、名は圉(ぎょ)、贈り名は文。衛の国の大夫。贈り名として「文」は最上の文字で、子貢は孔子に「なぜ立派な贈り名を得たのですか」と質問している。衛(えい)の大夫で、霊公(れいこう)。に仕えて賓客を接待し、祝鮀(しゅくだ)・王孫賈(おうそんか)と並称された名臣。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔文子は何を以て之を文と謂うや|「論語」公冶長第五15
※子貢は彼がなぜ最上の贈り名である「文」を得たのか、孔子に尋ねている。
子衛の霊公の無道なるを言う|「論語」憲問第十四20
※外交を治めていた。
仲突(ちゅうとつ)|仲忽(ちゅうこつ)
周の成王(また宣王、文王、武王ともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。
周(しゅう)の成王(せいおう・また宣王せんのう、文王ぶんのう、武王ぶおうともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。その一人で、かつ仲突と二番めの双児だったという。
周に八士有り|「論語」微子第十八11
※周代にいた才能がある八人として紹介されています。
仲由(ちゅうゆう)
子張(しちょう)
長沮(ちょうそ)
隠者(いんじゃ)の名。
隠者(いんじゃ)の名で、その他は未詳。桀溺(けつでき)とともに登場し、孔子と会ってお供の子路と問答をしている。
丘は与に易えざるなり|「論語」微子第十八06
※子路に道を聞かれますが、孔子であれば知っているだろうと相手しません。
「直躬」(ちょっきゅう)
正直者の躬(きゅう)。また「躬(自身)を直くする者」の意味。
正直者の躬(きゅう)。また「躬(自身)を直くする者」の意味。『呂氏春秋(りょししゅんじゅう)』・『淮南子(えなんじ)』・『荘子(そうし)』・『韓非子(かんぴし)』などでは、直躬という名として出てくる。楚(そ)の人で、葉公(しょうこう)が父を訴え出た直躬を正直者だと自慢したが、孔子は「親と子でかばい合う中に正直があるのだ」と、これを批判する。
吾が党に直躬なる者有り|「論語」子路第十三18
※葉公が孔子と話をする中で紹介しています。
陳子禽(ちんしきん)
陳司敗(ちんしはい)
⇒ 司敗(しはい)
陳成子(ちんせいし)陳恒(ちんこう)
姓は陳(ちん)、名は恒(こう)、成(せい)は贈り名。陳文子の子孫。簡公(かんこう)を弑して王位を奪い、弟の平公(へいこう)を立てて自分は宰相となった。
姓は陳(ちん)、名は恒(こう)、成(せい)は贈り名。田常(でんじょう)ともいう。陳文子の子孫。前四八一年に斉の簡公(かんこう)を弑して王位を奪い、弟の平公(へいこう)を立てて自分は宰相となった。七十一歳だった孔子は、魯(ろ)の哀公(あいこう)に無道の陳成子を討つように進言したが、哀公は「三桓氏(さんかんし)に言うように」と取り合わなかった。その曾孫の太公(たいこう)は、ついに斉侯となる。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
敢て告げずんばあらざるなり|「論語」憲問第十四22
※簡公を殺した陳成子を討つように孔子が哀公に進言しています。
陳文子(ちんぶんし)
姓は陳・田(でん)、名は須無(しゅむ)。文は贈り名。斉(せい)の大夫。
姓は陳(ちん)また田(でん)。名は須無(しゅむ)。文は贈り名。斉(せい)の大夫で、崔子(さいし)が荘公(そうこう)を弑した時(前五四六)、馬四十頭もの財産を捨てて他国に去った。孔子はこれを「清らかな、潔白な人」と評した。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
未だ知らず、焉んぞ仁なるを得ん|「論語」公冶長第五19
※子張が孔子に「仁」について尋ねた際に、取り上げています。
定公(ていこう)
魯の君主。孔子が仕えた。公山弗擾
(? – 前四九五)魯(ろ)の君。名は宋(そう)。襄公(じょうこう)の子。昭公(しょうこう)の弟。在位、前五0九 – 四九五。この間、四十三歳から五十七歳だった孔子を重用した。孔子に「一言で国を興し、国を滅ぼす言葉は?」と質問し、「君たることは難しいと知ること。忠言の道を塞がないこと」と教えられている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
君は臣を使うに礼を以てし、臣は君に事うるに忠を以てす|「論語」八佾第三19
※君子が臣下に礼を以て対するとはどういう意味か孔子に尋ねています。
一言にして以て邦を興すべきこと、諸有りや|「論語」子路第十三15
※孔子に国を興す言葉と、国を滅亡させる言葉を聞いています。
點(てん)
棖(とう)
湯王(とうおう)湯(とう)履(り)
商(殷)王朝の創始者。暴虐な夏の桀王を倒し、殷王朝を開いた。
殷(いん)の始祖、湯王(とういおう)。名は履(り)。商に都したので、商湯とも言う。帝舜(ていしゅん)に仕えた契(せつ)の子孫という。名臣・伊尹の助けによって、夏(か)王朝の暴君である桀王(けつおう)を討ち、殷王朝を建てた。儒家で理想と仰ぐ天子の一人。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
燓遅仁を問う。子曰わく、人を愛す|「論語」顔淵第十二22
※「直きを挙げて諸を枉れるに錯けば、能く枉れる者をして直からしむ」の例として挙げられています。
周に大いなる賚有り。善人是れ富めり|「論語」堯曰第二十01
※伝説上の天帝から孔子の前の時代「周」の天子まで、その任に就く際の覚悟について語った章句です。
な行 △ ▽
南子(なんし)
衛の霊公の夫人。品行が悪いと評判であった。
宋の人。衛の霊公の夫人で、霊公は南子を溺愛していた。南子は、霊公に嫁ぐ前から宋の公子・宋朝と通じ、妃となると宋朝を呼び寄せて不義を重ねたという。孔子も南子に面会し、子路はこれに不満だった。当時、宋は公子の蒯聵(かいたい)と出公輒(しゅっこうちょう・衛君)とが王位を争い。孔子は当然に公子を支持すると子貢は思ったが、孔子は衛に言っても発言せず。一方、南子は出公輒を支持していたためとされている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
予が否なる所の者は、天之を厭たん|「論語」雍也第六26
※孔子が面会したところ、子路がこれを喜びませんでした。
南容(なんよう)南宮适(なんきゅうかつ)
姓は「南宮」(なんきゅう)、名は括・适(かつ)または縚・韜(とう)、字は子容(しよう)。南容は南宮子容の略。孔子の門人。
姓は南宮(なんきゅう)、名は括・适(かつ)また縚・韜(とう)。字は子容(しよう)。南容は、南宮子容の略。魯の人。孔子は「君子で、徳を尚(とおと)ぶ人」と、その人柄を褒めていいる。そして、兄の娘を嫁がせた。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
子、南容を謂う|「論語」公冶長第五02
※孔子が批評しています。
南容白圭を三復す|「論語」先進第十一05
※詩経の一節をくり返し口ずさむ人柄から、孔子の兄の娘を嫁がせたといいます。
君子なるかな若き人|「論語」憲問第十四06
※君子であり徳を尚ぶ人物だと評しています。
甯武子(ねいぶし)
衛(えい)の成公(せいこう)の時の大夫。姓は甯、名は兪(ゆ)、武は贈り名。
衛(えい)の成公(せいこう)の時の大夫。姓は甯、名は兪(ゆ)、武は贈り名。暗愚な成公を臨機応変に助けて善処し、孔子に「愚人の態度を守って国難を救った、まねのできない人物」と評価された。
其の愚は及ぶべからざるなり|「論語」公冶長第五21
※敢えて愚人の態度を取って、衛の成公を助けて国難を乗り越えたと、孔子に評価されている。
は行 △ ▽
伯夷(はくい)|叔斉(しゅくせい)
伯夷(はくい) … 名は允(いん)。
名は允(いん)。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
叔斉(しゅくせい) … 名は致(ち)。殷末、孤竹という小国の公子で、伯夷の弟。
名は致(ち)。殷末(いんまつ)周初のひと。孤竹(こちく)という小国の公子で、伯夷(はくい)の弟。父は叔斉を跡継ぎにしようとしたが、兄の伯夷と譲り合い、二人ともに文王(ぶんのう)の徳を慕って周に移った。後、文王の子の武王(ぶおう)が殷(いん)の紂王(ちゅうおう)を討とうと兵を挙げたのを伯夷とともに諌め、武王の即位後はそれを恥じ、首陽山に隠れて餓死した。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔子は「志を高く保ち、身を清く守って、辱め汚されなかった二人」と評して、清廉潔白な人の代表とされる。また二人とも、孔子の挙げる遺逸[志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人]の民七人に属している。
舊悪を念わず。怨是を用て希なり|「論語」公冶長第五23
※清廉潔白な人柄であるだけでなく、寛容な人柄を孔子が評価している。
仁を求めて仁を得たり。又何をか怨みん|「論語」述而第七14
※子貢が孔子に衛の君が出公輒を助けるかと尋ねる際に取り上げています。
民今に到るまで之を称す|「論語」季氏第十六12
※民が現在に至るまで賞賛しているといいます。
可も無く不可も無し|「論語」微子第十八08
※志を高く保って自身を辱めなかったと評されています。
伯适(はくかつ)
伯牛(はくぎゅう)
伯魚(はくぎょ)
伯氏(はくし)
斉(せい)の大夫。
斉(せい)の大夫。名は偃(えん)。罪を犯したために、宰相の管仲に裁かれて領地を奪われ、困窮した。しかし、管仲の処置は公明正大だったとして管仲に心服し、生涯恨まなかった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
曰わく、彼をや彼をや|「論語」憲問第十四10
※管仲を評する際に取り上げられています。
伯達(はくたつ)|伯适(はくかつ)
周の成王(また宣王、文王、武王ともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。
周(しゅう)の成王(せいおう・また宣王せんのう、文王ぶんのう、武王ぶおうともいう)の時、一家から八人の人材が生まれ、ために周王朝はいっそう栄えたという。その一人で、かつ伯達と長男の双児だったという。
周に八士有り|「論語」微子第十八11
※周代の能力ある八名に挙げられています。
播鼗武(はとうぶ)
鼗(ふりつづみ)〔振って鳴らす鼓〕を鳴らす武(ぶ)。
鼗(ふりつづみ)〔振って鳴らす鼓〕を鳴らす武(ぶ)。播(は)は、動かす、振るの意味。鼗(とう)は、小球を二つ下げた、柄のついた鼓。武は、魯(ろ)国の衰乱を見て漢水のほとりに去った。
大師摯は斉に適く|「論語」微子第十八09
※漢水のほとりに移りました。
樊遅(はんち)樊須(はんす)
姓は樊(はん)、名は須(す)、字は子遅(しち)。孔子より三十四歳若い。孔子が移動に使う牛車の御者(運転手)を務めた。真面目な人柄で論語にもたびたび登場する。
燓須は魯人。字は子遅。孔子より少きこと四十六歳。弱にして季氏に仕ふ。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五0五? – ?)姓は燓(はん)、名は須(す)、字は子遅(しち)。魯の人、また斉の人とも言う。孔子より三十六歳(四十六歳)若い。孔子の御者を勤めたり、孔子に五穀の植え方を質問して「小人なるかな」と評されたりしている。一方、孔子に「仁」について三回、「知」について二回質問し、それぞれ「人を愛すること」「人を知ること」等と教えられているまじめな人物。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店
孟懿子孝を問う。子曰わく、違うこと無し|「論語」為政第二05
※孔子が燓遅に「孝」について伝えています。
仁者は難きを先にして獲ることを後にす、仁と謂うべし|「論語」雍也第六20
※「知」について孔子に尋ねています。
敢て徳を崇くし、慝を修め、惑を辨せんことを問う|「論語」顔淵第十二21
孔子に、徳を高くすること、悪いところを直すこと、迷いを処理することについて尋ねています。
燓遅仁を問う。子曰わく、人を愛す|「論語」顔淵第十二22
※孔子に「仁」「知」を尋ね、理解できないので後日子夏に尋ねています。
燓遅稼を学ばんと請う|「論語」子路第十三04
※農業について質問しています。
夷狄に之くと雖も、棄べからざる|「論語」子路第十三19
※孔子に「仁」を尋ねています。
比干(ひかん)
殷(いん)の紂(ちゅう)王のおじ。箕子(きし)を継いで紂(ちゅう)王の暴政を諌めた。
殷(いん)の紂(ちゅう)王のおじ。箕子(きし)を継いで紂(ちゅう)王の暴政を諌めると、紂王は「聖人には胸に七つの穴があるという。お前にそれを見せてもらおう」と言って、比干を殺した。孔子は、殷の三人の仁者とたたえている。
殷に三仁有り|「論語」微子第十八01
※孔子は、殷にいた三人の仁者のひとりと評しています。
微子(びし)
名は啓(けい)、また開(かい)。殷(いん)の帝乙(ていいつ)の長子で、紂(ちゅう)王の義兄。
名は啓(けい)、また開(かい)。殷(いん)の帝乙(ていいつ)の長子で、紂(ちゅう)王の義兄。紂王の暴政を諌めたが聞き入れられず、微(び)の国に逃れた。周の武(ぶ)王が紂王を討つと、武王に仕えた。武王は微国を与えたので、微子と称する。また、殷の後を継いで宋に封ぜられ、殷の遺民は微子を「聖」とたたえた。孔子は、殷の三人の仁者に挙げている。
殷に三仁有り|「論語」微子第十八01
※孔子は、殷にいた三人の仁者のひとりと評しています。
裨諶(ひじん)
名は皮。鄭(てい)の大夫。
名は皮。裨は卑(ひ)。諶は堪、湛とも書く。春秋時代、鄭(てい)の大夫。天文によって星占いをする予言者だったらしい[左伝・襄公二十八年など]。しかし、大夫の子産はその予言を信じなかった。また、外交文章の草案を担当した。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
命を為るに、裨諶之を草創し|「論語」憲問第十四09
※鄭の四人の大夫が協力して外交文章を作成していることを紹介した章句です。
微生高(びせいこう)
姓は微生、名は高。
姓は微生(びせい)、名は高(こう)。魯(ろ)の人。正直者として有名。しかし、醯(す)を借りに来た人に、隣人から借りて貸してやったので、孔子は「その態度は正直者と言えない」と批判している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
諸を其の鄰に乞うて之を与う|「論語」公冶長第五24
※融通がきかないほどの正直者だと伝えられて、いますが、その人柄について孔子の評価がこの章句です。
微生畝(びせいほ)
姓は微生(びせい)、名は畝(ほ)。孔子より年上の、徳の高い隠者らしい。
姓は微生(びせい)、名は畝(ほ)。孔子より年上の、徳の高い隠者らしい。孔子を「東奔西走して、俗世に媚びようとしているのか」と批判している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
固を疾めばなり|「論語」憲問第十四34
※孔子に直接意見をしています。
仏肸(ひっきつ)
佛(胇)肸。晋(しん)の大夫である趙管子(ちょうかんし)の臣。中牟(ちゅうぼう)の町を治めていたが、反乱を起こした。
晋(しん)の大夫である趙管子(ちょうかんし)[あるいは范中行(はんちゅうこう)]の臣。中牟(ちゅうぼう)の町[今の河北省南西部]を治めていたが、反乱を起こして孔子を招いた。孔子は、その招きに応じようとしている。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
焉んぞ能く繫りて食われざらんや|「論語」陽貨第十七07
※孔子を招いたことで、孔子と子路の会話が展開されます。
閔子騫(びんしけん)
姓は閔(びん)、名は損(そん)、字は子騫(しけん)。孔子より十五歳若い。
閔損は魯人、字は子騫。孔子より少きこと十五歳。徳行を以て名を著す。孔子其の孝なるを称ふ。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五三六 – 四八七)孔門の十哲。姓は閔、名は(そん)、字は子騫。魯(ろ)の人という。孔子より十五歳若い。『孟子(もうし)』では顔淵・冉伯牛(ぜんはくぎゅう)と並んで「小聖人」とたたえられている。
善く我が為に辞せよ|「論語」雍也第六07
※斉の国の費の代官にしようとした季孫氏に答えています。
我に陳・蔡に従う者は、皆門に及ばざるなり|「論語」先進第十一02
※「四科十哲」の出典。「徳行には顔淵・閔子騫・冉伯牛・仲弓」
孝なるかな閔子騫|「論語」先進第十一04
※当時の世間で閔子騫が称賛されていた。
閔子騫側に侍す、誾誾如たり|「論語」先進第十一12
※孔子が弟子に囲まれて楽しそうな様子です。
夫の人は言わず、言えば必ず中ること有り|「論語」先進第十一13
※無口だが発言が的確だと言われている。
武(ぶ)武王(ぶおう)
周(しゅう)の文王(ぶんのう)の子。名は発(はつ)。殷(いん)の紂王(ちゅうおう)の暴虐な政治を見かね、武力によって紂王を倒して、周王朝を建てた初代の王。
周(しゅう)の文王(ぶんのう)の子。名は発(はつ)。殷(いん)の紂王(ちゅうおう)の暴虐な政治を見かね、武力によって紂王を倒して、周王朝を建てた初代の王。封建制度を定め、後世、夏(か)王朝創建の禹王(うおう)、殷王朝創建の湯王(とうおう)、及び父の文王と併せて、三王と称され、その徳をたたえられている。(文王または武王の一方、とする説もある。)〔孟氏・告子下〕。武王は「自分には名臣十人がいる」と言っている。
武を謂わく、美を尽せり、未だ善を尽さざるなり|「論語」八佾第三25
※夏王朝の舜と周王朝の武王の音楽を比較しています。
周の徳は、其れ至徳と謂うべきのみ|「論語」泰伯第八20
※周の国の徳について話しています。
巫馬期(ふばき)
姓は巫馬、名は施(し)、字は子期(しき)または子旗(しき)。孔子の弟子。孔子より三十歳若い。
(前五二一 – ?)姓は巫馬(ふば)、名は施(し)、字は子期(しき)または子旗(しき)。魯(ろ)の人、また陳(ちん)の人。孔子より三十歳若い。魯の単父(ぜんぽ)の町を治め、政務に励んだという。
苟くも過有れば、人必ず之を知る|「論語」述而第七30
※陳の司法長官が巫馬期に尋ねたことで、孔子と会話をしています。
文公(ぶんこう)
晋(しん)の公。春秋時代の五覇の一人。
(前六九七 – 六二八)晋(しん)の公。名は重耳(ちょうじ)。春秋時代の五覇の一人。四十三歳の時、内乱を避けて国外各地に亡命し、十九年後に秦(しん)の穆公(ぼくこう)の力を借りて本国に帰り、謀略を駆使して即位五年にして覇者となった。斉の桓公とともに、もっとも勢力があった。孔子は「譎(いつわ)りて正しからず」と評している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
晋の文公は譎りて正しからず|「論語」憲問第十四16
※斉の桓公と比較しています。
文子(ぶんし)
文王(ぶんのう)
名は昌(しょう)。周の王。周の道徳文化の創始者とされ、孔子がもっとも尊敬した人物。
名は昌(しょう)。殷(いん)代に周(しゅう)を建国した古公亶父(ここうたんぽ・贈り名は太王)の孫で、周の王。在位五十年、その仁政に諸侯も感化され、西伯(さいはく・西方の覇者)と称された。周の道徳文化の創始者とされる。孔子がもっとも尊敬した人物で、孔子自身、文王の残した「道」の継承者を自認している。
匡人其れ予を如何にせん|「論語」子罕第九05
※天の意思で孔子自身が生かされているのであれば、生き抜けるはずだという孔子の強い意志が伝わります。
卞莊子(べんしょうし)
魯(ろ)の卞(べん)地方の大夫。勇気があり、虎を刺し殺したという。
魯(ろ)の卞(べん)地方の大夫。勇気があり、虎を刺し殺したという。また、親孝行でも有名で、母の生存中は戦場に出れば逃げ帰っていたが、母の死後は敢然と戦い、数十人を殺して、自身も戦死した[韓詩外伝]という。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
臧武仲の知、公綽の不欲、卞莊子の勇、冉求の芸|「論語」憲問第十四13
※卞莊子の勇が「成人」の条件として紹介されています。
方叔(ほうしゅく)
ま行 △ ▽
孟氏(もうし)
孟孫(もうそん)氏。魯(ろ)の大夫。
⇒ 三家者(さんかしゃ)三桓(さんかん)
哀矜して喜ぶこと勿かれ|「論語」子張第十九19
※孟氏の元で士師として働く陽膚(ようふ)が、曽子に心得を尋ねています。
孟懿子(もういし)
仲孫(孟孫)氏の第五世、第九代目。名は何忌。懿は贈り名。魯(ろ)の大夫。魯は孔子が生まれ育った国。大夫は周代から春秋戦国時代にかけて領地を持った貴族(王族、公族を含む)のことを呼んだ。彼らは国政に参加していた。論語によく登場する孟武伯(もうぶはく)の父。
(前五三一? – 四八一)魯(ろ)の大夫。仲孫氏の第五世。第九代目。名は何忌(かき)。懿は贈り名。孟僖子(もうきし)の子、孟武伯(もうぶはく)の父。弟の南宮敬叔(なんきゅうけいしゅく)とともに孔子に礼を学んだという。
孟懿子孝を問う。子曰わく、違うこと無し|「論語」為政第二05
※「孝」について尋ねています。
孟敬子(もうけいし)
魯の大夫。名は捷(しょう)、字は儀(ぎ)。敬子(けいし)は贈り名。孟武伯(もうぶはく)の子。
魯(ろ)の大夫・仲孫(ちゅうそん)氏の第八世、第十一代目。名は捷(しょう)、字は儀(ぎ)。敬子は贈り名。孟武伯(もうぶはく)の子。曾子(そうし)の病気を見舞い、為政者の重んじるべき三つの道を教えられている。
君子道に貴ぶ所の者三|「論語」泰伯第八04
※曽子を見舞いました。
孟公綽(もうこうしゃく)公綽(こうしゃく)
魯(ろ)の大夫。
魯の大夫。孔子は、人格者として敬意を払っていたが、また「精錬寡欲の人だが、行政的な才能に欠ける」と評している。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孟公綽、趙魏の老と為れば則ち優なり|「論語」憲問第十四12
※諸侯の国の大夫になるには能力が足りないと評されています。
臧武仲の知、公綽の不欲、卞莊子の勇、冉求の芸|「論語」憲問第十四13
※孟公綽の無欲が「成人」の条件として紹介されています。
孟之反(もうしはん)
姓は孟、名は子側(しそく)、字は之反。
魯(ろ)の大夫か。名は側(そく)、また子側(しそく)。之反(また、反)は字。孟之反とも書かれる。孔子は「功を誇らない人」と評している。
孟之反伐らず|「論語」雍也第六13
※公正な人物だと孔子は語っている。
孟荘子(もうそうし)
魯(ろ)の大夫。名は速(そく)。荘子は贈り名。仲孫(ちゅうそん)氏の第五世、第六代目。孟懿子(もういし)の伯父。
魯(ろ)の大夫。名は速(そく)。荘子は贈り名。仲孫(ちゅうそん)氏の第五世、第六代目。孟懿子(もういし)の伯父。賢大夫で知られた父の孟献子(もうけんし)の後を継いだ(前五五四)が、わずか五年後、四十余歳で死んだ。孔子はその孝行ぶりを褒めている。
其の父の臣と父の政とを改めざる|「論語」子張第十九18
⇒ 孔子が彼の孝行ぶりを評価しています。
孟孫(もうそん)
⇒ 孟懿子(もういし)
⇒ 三家者(さんかしゃ)三桓(さんかん)
孟武伯(もうぶはく)
孟懿子(もういし)の子。名は彘(てい)。武は贈り名。伯は字で長子(第一子)のこと。魯(ろ)の大夫。魯は孔子が生まれ育った国。大夫は周代から春秋戦国時代にかけて領地を持った貴族(王族、公族を含む)のことを呼んだ。彼らは国政に参加していた。ぜいたく、わがままな振る舞いが多く、健康には恵まれなかった。
魯(ろ)の大夫。孟懿子(もういし)の子。名は彘(てい)。武は贈り名。伯は字で、また長子のこと。哀公(あいこう)十五年(前四八○)に父の後を継いだ。ぜいたくで、わがままな振る舞いが多く、また献公には恵まれなかった。季康子(きこうし)とともに哀公を亡きものにしようとねらい、それを知った哀公も孟武伯を滅ぼそうとしたが果たさず、哀公は亡命する。一方では、孔子に「孝」を問うたりしている。
父母は唯だ其の疾を之れ憂う|「論語」為政第二06
※「孝」について尋ねています。
其の仁を知らざるなり|「論語」公冶長第五08
※弟子たちが仁者であるか尋ねています。
や行 △ ▽
由(ゆう)
有子(ゆうし)有若(ゆうじゃく)
姓は有(ゆう)、名は若(じゃく)、字は子有(しゆう)。孔子より十三歳(一説に三十三歳、また三十六歳)若い。
有若は魯人。字は子有。孔子より少きこと三十六歳。人と為り強識にして古道を好む。
「孔子家語 新釈漢文大系」宇野精一 著(明治書院 刊)
(前五一五? – ?)姓は有、名は若、字は子有。魯の人。孔子より十三歳(一説に三十三歳、また三十六歳)若い。「有子の発言は孔子にそっくりだ」(礼記・檀弓)と門人の信頼もあり、容貌が孔子に似ていたこともあって、孔子の死後数年経って、門人の子夏・子張・子游たちは、孔子に対したように有若を師と仰ごうとした。しかし曽子が反対して、話は立ち消えになった(孟子、滕文公上)。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
なお『論語』の門人の中で「子」をつけて呼ばれるのは、この有子と、曽子・冉子・閔氏の四人だけなので『論語』は有子や曽子の門人によって編集されたのではないかという説もある。
其の人と為りや孝弟にして|「論語」学而第一02
※家庭で礼儀を守ることは「仁」に通じるのではないかと言います。
礼の用は和を貴しと為す|「論語」学而第一12
※秩序をもって調和(和)を大切にすることが大事だと説いています。
信義に近きときは、言復むべきなり|「論語」学而第一13
※「信」「義」「礼」について述べています。
百姓足らば、君孰と与にか足らざらん|「論語」顔淵第十二09
※哀公から財政について相談され、人民が充分で無くて君主が充分であるとはどういうことかと意見しています。
予(よ)
陽(よう)
雍(よう)
陽貨(ようか)
魯(ろ)の大夫(たいふ)か。名は貨(か)。
魯(ろ)の大夫(たいふ)か。名は貨(か)、字は虎(こ)。季氏の臣の陽虎(ようこ)と同一人かとも言われるが、未詳。孔子に面会できる機会を無理に作って、仕官を勧めた。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
諾、吾将に仕えんとす|「論語」陽貨第十七01
※孔子に「仁」「知」の例を示して、任官を促しています。
陽虎(ようこ)
魯(ろ)の大夫。権勢が強く、三桓を滅ぼそうとしたが、逆に孟懿子(もういし)に攻められて、斉(さい)から宋(そう)、晋(しん)に逃げた。
魯(ろ)の大夫。権勢が強く、三桓を滅ぼそうとしたが、逆に孟懿子(もういし)に攻められて、斉(さい)から宋(そう)、晋(しん)に逃げた。容貌が孔子に似ていたため、孔子は匡(きょう)の地で監禁された。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
匡人其れ予を如何にせん|「論語」子罕第九05
※章句内では登場しません。解説を参照してください。
陽膚(ようふ)
曽子(そうし)の門人。
曽子(そうし)の門人。孟武伯(もうぶはく・あるいは孟敬子もうけいし)の士師(獄官の長)となり、曽子にその心得を教わった。
哀矜して喜ぶこと勿かれ|「論語」子張第十九19
※曽子に士師としての心得について尋ねています。
ら行 △
履(り)
鯉(り)、伯魚(はくぎょ)
孔子の一人息子。名は鯉(り)、字は伯魚(はくぎょ)。
孔子の一人っ子。姓は孔、名は鯉(り)。伯魚(はくぎょ)は字。孔子の結婚の翌年(前五三二)、孔子二十歳の時に生まれ、魯(ろ)の昭公(しょうこう)からお祝いに鯉をもらったので、それを名としたという。孔子に先立って、五十歳で死んだ。伯魚の子(孔子の孫)の孔伋は、その少し前に生まれたとされる。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
才あるも才あらざるも、亦各ゝ其の子と言うなり|「論語」先進第十一07
※顔淵の死に際して、孔子の子、鯉が死んだ時のことを引き合いに出しています。
詩を聞き、礼を聞き、又君子の其の子を遠ざくるを聞くなり|「論語」季氏第十六13
※陳亢に尋ねられて、孔子との会話を紹介しています。
柳下恵(りゅうかけい)
魯(ろ)の大夫。姓は展(てん)、名は獲(かく)、字は禽(きん)。恵(けい)は贈り名。柳下は、号とも封ぜられた土地の称とも言い、未詳。賢者で知られる。
魯(ろ)の大夫。姓は展(てん)、名は獲(かく)、字は禽(きん)。恵(けい)は贈り名。柳下は、号とも封ぜられた土地の称とも言い、未詳。賢者で知られる。臧文仲(ぞうぶんちゅう)に用いられず、魯の士師(獄官の長)を三度勤めたが、そのたびに免職になった。孟子(もうし)は「百世の後まで人の師となる聖人である」〔尽心下〕が、また「不恭(うやうやしさに欠ける)」〔公孫丑上〕とも評している。また、孔子の挙げる遺逸の民〔志が高く地位がなく、世を逃れ隠れている賢人〕七人の一人。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
臧文仲は、其の位を窃む者か|「論語」衛霊公第十五14
※賢者であると評しています。
柳下恵士師と為り、三たび黜けらる|「論語」微子第十八02
※正しい政事を行うためには、三度くらいの免職は覚悟すると言っています。
可も無く不可も無し|「論語」微子第十八08
※言うことは道徳的であり、行動は深く考えられていたと評されています。
繚(りょう)
林放(りんぽう)
魯の人。おそらく孔子の弟子だが、司馬遷の史記には記述がないそうです。
魯(ろ)の人か。孔子に「礼の根本」について質問しているが、『史記』弟子列伝には載っていない。礼に詳しい人らしい。
礼は其の奢らんよりは寧ろ倹なれ|「論語」八佾第三04
※礼の根本について尋ねています。
嗚呼、曾ち泰山は林放に如かずと謂えるか|「論語」八佾第三06
※林放を例に、弟子の冉有に意見しています。
令尹子文(れいいんしぶん)
姓は闘(とう)、名は穀於菟(とうおと)。字は子文。春秋時代の初め、楚の令尹(宰相)を三度務め、三度辞めさせられたという。
姓は闘(とう)、名は穀於菟(とうおと)。字は子文(しぶん)。春秋時代の初め、楚(そ)の令尹(宰相)を三度務め、三度辞めさせられたという。孔子は「職務に忠実な人」と評した。
未だ知らず、焉んぞ仁なるを得ん|「論語」公冶長第五19
※子張が令尹子文の行動について、仁者であるかと尋ねています。
霊公(れいこう)
衛(えい)の公。襄公(じょうこう)の庶子。夫人の南子に溺れて政治を顧みず、その死後は内乱が起こった。
衛(えい)の公。襄公(じょうこう)の庶子。名は元(げん)。七歳で即位し、無道の政治を行ったが、仲叔圉(ちゅうしゅくぎょ)、祝鮀(しゅくだ)、王孫賈(おうそんか)らの賢臣に助けられて、在位四十二年、前四九三に没した。夫人の南子に溺れて政治を顧みず、その死後は内乱が起こった。
「論語と孔子の事典」江連 隆 著(大修館書店)
孔子は、五十五歳の時に衛に行き、魯の時と同様の待遇を受けたが、結局は一年たらずで去る。その後も衛を訪れたが、軍の陣立てのことを問われて去っている。
子衛の霊公の無道なるを言う|「論語」憲問第十四20
※孔子が霊公の道に外れた行いについて話をしています。
明日遂に行る|「論語」衛霊公第十五01
※戦陣について尋ねています。
牢(ろう)
老彭(ろうほう)
殷(いん)の賢大夫。好んで古辞(こじ・昔の言葉)を述べた。
殷(いん)の賢大夫という。孔子は「述べて作らず、古道を信じて好む」自分を、老彭になぞらえている。『荘子』(逍遙遊・しょうようゆう)に出てくる、帝尭(ていぎょう)の臣で帝顓頊(せんぎょく)の玄孫である、七百年を生きた彭祖(ほうそ・姓は籛せん、名は鏗こう)をさす、という説もある。また、彭祖は老子のこと、従って老子をさすという説など、さまざまである。
述べて作らず。信じて古を好む|「論語」述而第七01
※孔子がなりたい人物と述べています。
魯公(ろこう)
周公旦(しゅうこうたん)の長子の伯禽(はくきん)。はじめ周公(しゅうこう・周公旦)が魯(ろ)の国に封ぜられたが、周室の政務に追われていたので、代わって伯禽に魯を治めさせ、魯の祖となった。
周公旦(しゅうこうたん)の長子の伯禽(はくきん)。はじめ周公(しゅうこう・周公旦)が魯(ろ)の国に封ぜられたが、周室の政務に追われていたので、代わって伯禽に魯を治めさせ、魯の祖となった。その折に周公が伯禽に与えた言葉が第十八10(微子第十八の十章句目)に載っている。
周公魯公に謂いて曰わく|「論語」微子第十八10
※周公旦が、君子の心得について話しています。