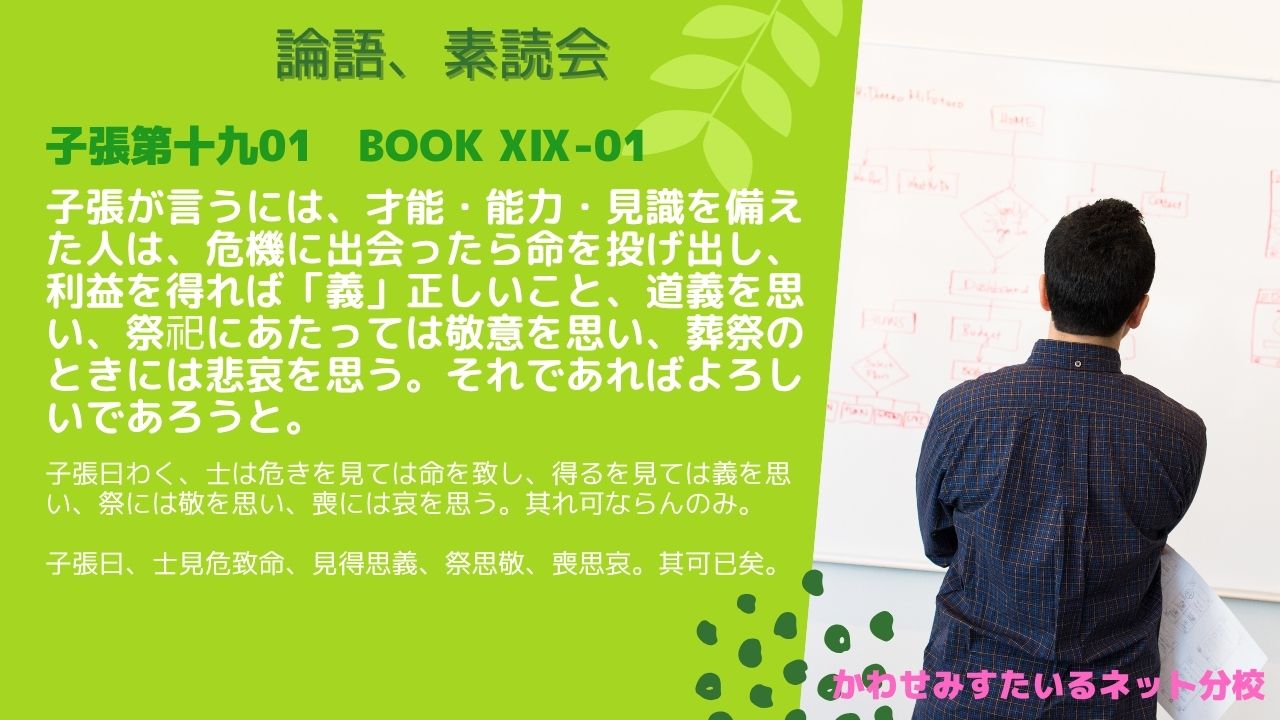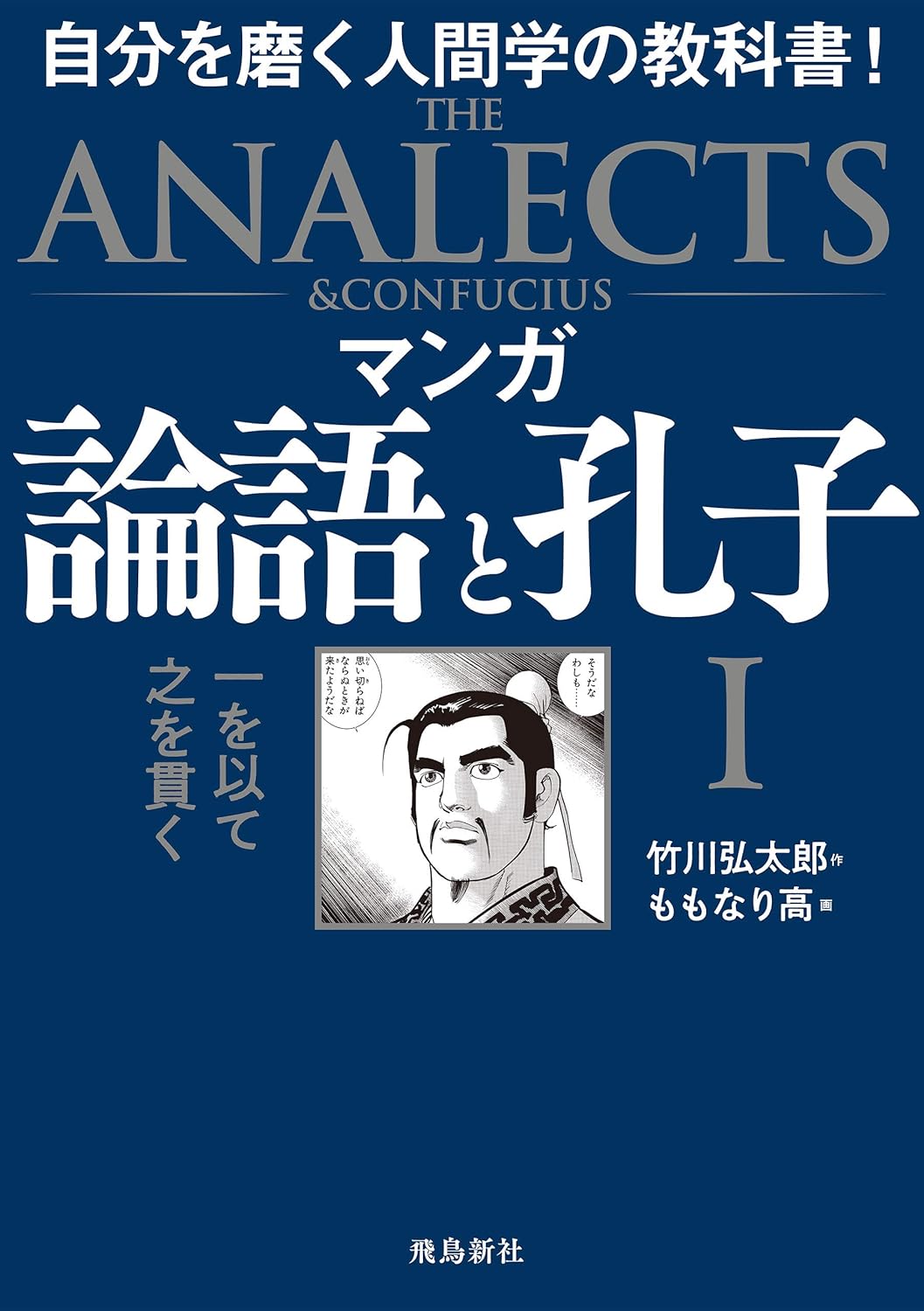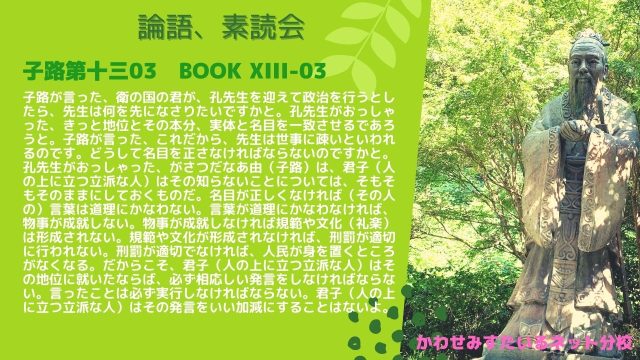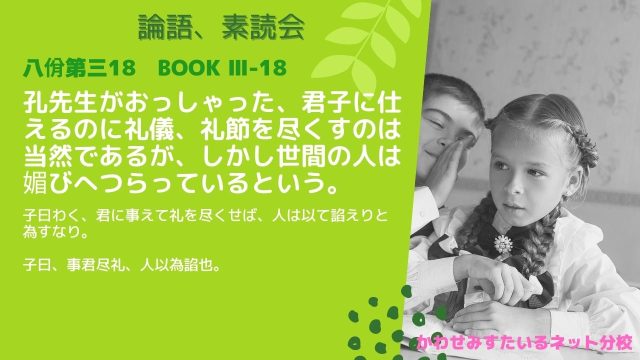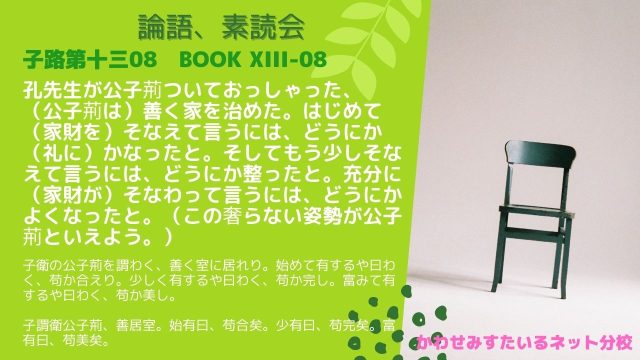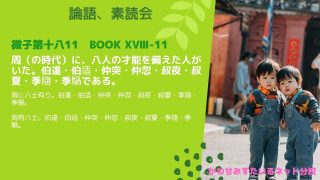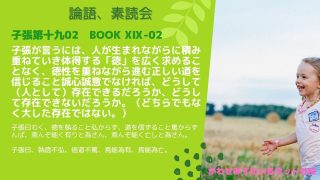子張が言うには、才能・能力・見識を備えた人は、危機に出会ったら命を投げ出し、利益を得れば「義」正しいこと、道義を思い、祭祀にあたっては敬意を思い、葬祭のときには悲哀を思う。それであればよろしいであろうと。|「論語」子張第十九01
【現代に活かす論語】
危機になったら命を投げ出す覚悟をし、利益があればそれが正しいのかと思う、先祖に敬意を払い、葬祭の際はきちんと悲しむ。
【解釈】
子張(しちょう) … 姓は顓孫(せんそん)、名は師(し)、字は子張(しちょう)。孔子より四十八歳若い。「論語」の登場人物|論語、素読会
子張曰わく、士は危きを見ては命を致し、得るを見ては義を思い、祭には敬を思い、喪には哀を思う。其れ可ならんのみ。|「論語」子張第十九01
子張曰、士見危致命、見得思義、祭思敬、喪思哀。其可已矣。
「士」(し)は才能・能力・識見を備えた人。「危」(あやうし)はあぶない。「命」(めい)はいのち。「致」(いたす)は送りとどける。「得」(うる)は収穫、手に入れられる者、利益、もうけ。「義」(ぎ)は正しいこと。道義。『義』とは?|論語、素読会 「祭」(まつり)は神仏や先祖を慰める儀式、まつり。「敬」(けい)は敬意。「喪」(も)は死者を悼み葬る儀礼、またその期間、葬式。「哀」(あい)はあわれな、いたましい。「可」(か)はよろしい、十分ではないが同意できるさま。
子張が言うには、才能・能力・見識を備えた人は、危機に出会ったら命を投げ出し、利益を得れば「義」正しいこと、道義を思い、祭祀にあたっては敬意を思い、葬祭のときには悲哀を思う。それであればよろしいであろうと。
【解説】
子張の言葉ですが、彼の言葉を通して、孔子の学びを受け取ることがこの章句の主眼です。以下の章句で孔子は、子路の問いに対して、ほぼ同様に回答しています。子路と子張は三十歳近く離れていますので、このやり取りを直接目にしていたとは考えづらいですが、その学びは綿々と受け継がれていることが分かります。
「子路が「成人」学問・道徳をかねそなえた完璧な人物について尋ねた。孔先生がおっしゃった、臧武仲の知恵、孟公綽の無欲、卞莊子の勇気、冉求の才知を備えて、「礼楽」規範と文化を以てこれを美しく飾れば、「成人」と言っていいだろうと。(さらに)孔先生がおっしゃった、今の「成人」は必ずしもその通りでなくてもいいだろう。利益を得るときには「義」正しいこと、道義を思い、危機に際しては一命を掛け、古い約束や普段の発言であっても忘れなければ、「成人」と言っていいだろうと。|「論語」憲問第十四13」
また、前述の二つの章句に共通して、「利益を得るときこそ道義を思う。」という一節があります。孔子は、以下の章句でも述べていますので、大変重要な考え方だということが分かります。「孔先生がおっしゃった、人の上に立つ立派なリーダーには、九つの心の働きがある。… 中略 … 利益を目の前にしたときには道義を思う。|「論語」季氏第十六10」
利益を得ることは問題ないが、それが正しい行いで得たものなのか自分自身に問いかけるということです。
「論語」参考文献|論語、素読会
微子第十八11< | >子張第十九02
【原文・白文】
子張曰、士見危致命、見得思義、祭思敬、喪思哀。其可已矣。
(子張曰わく、士は危きを見ては命を致し、得るを見ては義を思い、祭には敬を思い、喪には哀を思う。其れ可ならんのみ。)
【読み下し文】
子張(しちょう)曰(い)わく、士(し)は危(あやう)きを見(み)ては命(めい)を致(いた)し、得(う)るを見(み)ては義(ぎ)を思(おも)い、祭(まつり)には敬(けい)を思(おも)い、喪(も)には哀(あい)を思(おも)う。其(そ)れ可(か)ならんのみ。
「論語」参考文献|論語、素読会
微子第十八11< | >子張第十九02