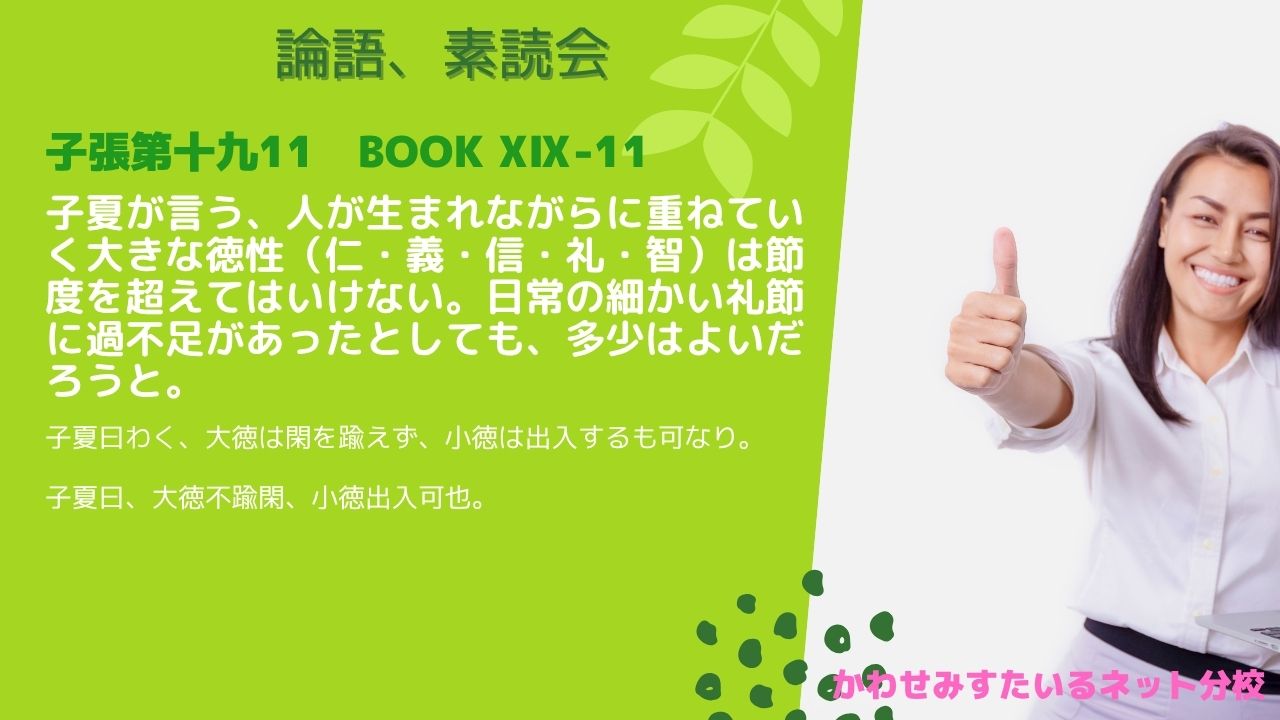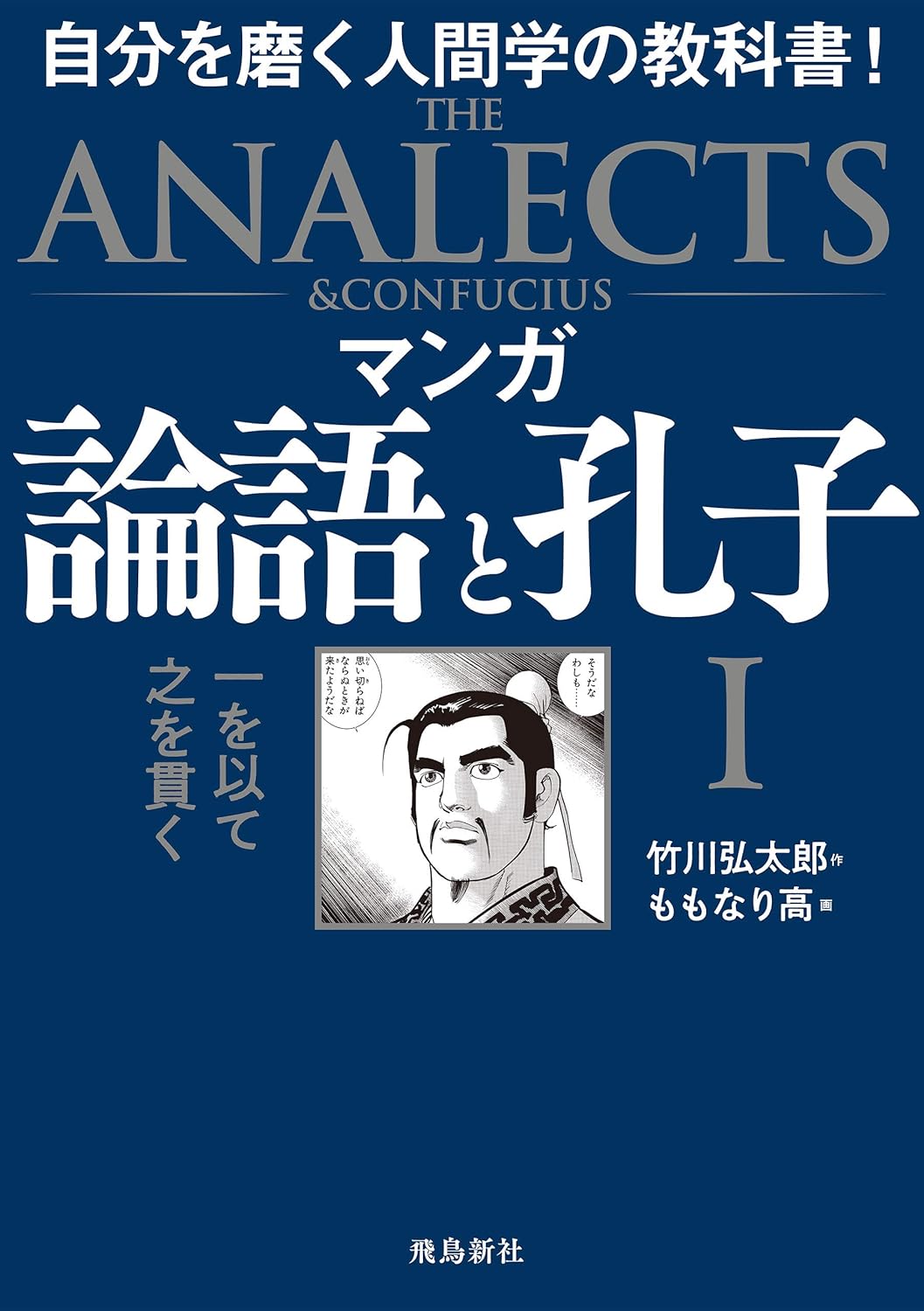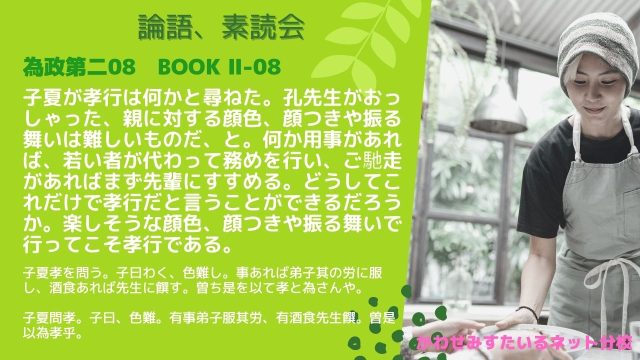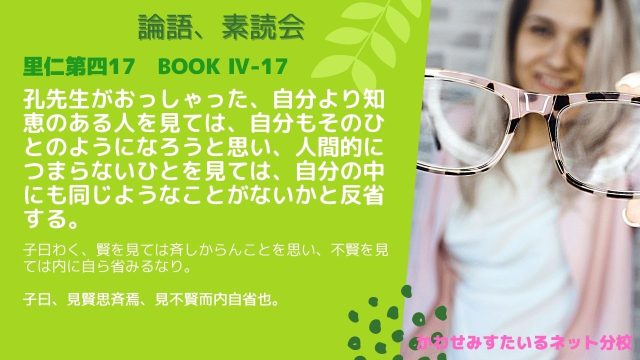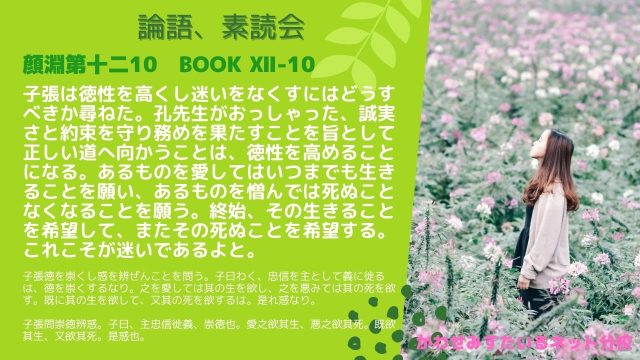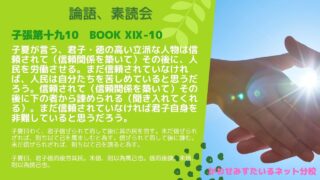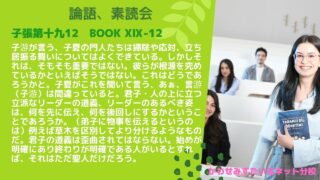子夏が言う、人が生まれながらに重ねていく大きな徳性(仁・義・信・礼・智)は節度を超えてはいけない。日常の細かい礼節に過不足があったとしても、多少はよいだろうと。|「論語」子張第十九11
【現代に活かす論語】
人が生まれながらに重ねていくよい行いは度を超してはいけません。日常の礼節に過不足があったとしても多少はいいでしょう。
【解釈】
子夏(しか) … 商(しょう)。姓は卜(ぼく)、名は「商」、字(あざな)は「子夏」。孔子より四十四歳年下。衛の人。つつましやかでまじめな人柄で、また消極的だったらしい。「論語」の登場人物|論語、素読会
子夏曰わく、大徳は閑を踰えず、小徳は出入するも可なり。|「論語」子張第十九11
子夏曰、大徳不踰閑、小徳出入可也。
「徳」(とく)はひとが生まれながらに重ねていく善い行い。『徳』とは?|論語、素読会 「大徳」(だいとく)は大きな節義。「閑」(のり)は範囲、規則、のり。「踰」(こえる)は度をすごす、違反する。「出入」(しゅつにゅう)は出たり入ったり、出し入れ。
子夏が言う、人が生まれながらに重ねていく大きな徳性(仁・義・信・礼・智)は節度を超えてはいけない。日常の細かい礼節に過不足があったとしても、多少はよいだろうと。
【解説】
大徳、小徳をどのように解釈するかです。まず、「閑を踰えず」と「出入するも可なり」に注目します。「閑を踰えず」とは節度を守る、度を超さないという意味ですので、生まれながらに重ねていく善行のうち大きなもの、全体的なものを「大徳」というのではないかと解釈します。先人の解釈ではそれを「孝弟」「大節」と表現しています。これに対して、「出入するも可なり」とは出入り、過不足があってもまあよいという意味に解釈できますので、日常生活の中で繰り返される礼節(所作・行動)に過不足があったとしても、多少はよいだろうと解釈します。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九10< | >子張第十九12
【原文・白文】
子夏曰、大徳不踰閑、小徳出入可也。
<子夏曰、大德不踰閑、小德出入可也。>
(子夏曰わく、大徳は閑を踰えず、小徳は出入するも可なり。)
【読み下し文】
子夏(しか)曰(い)わく、大徳(だいとく)は閑(のり)を踰(こ)えず、小徳(しょうとく)は出入(しゅつにゅう)するも可(か)なり。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九10< | >子張第十九12