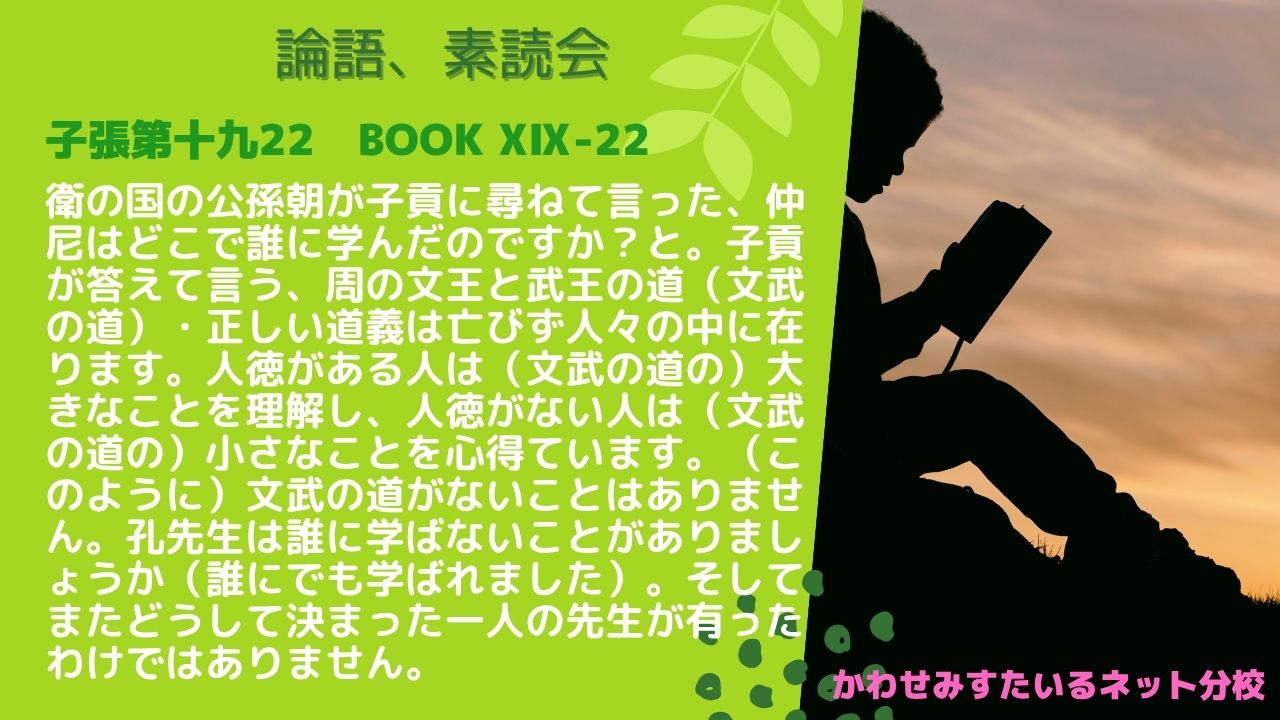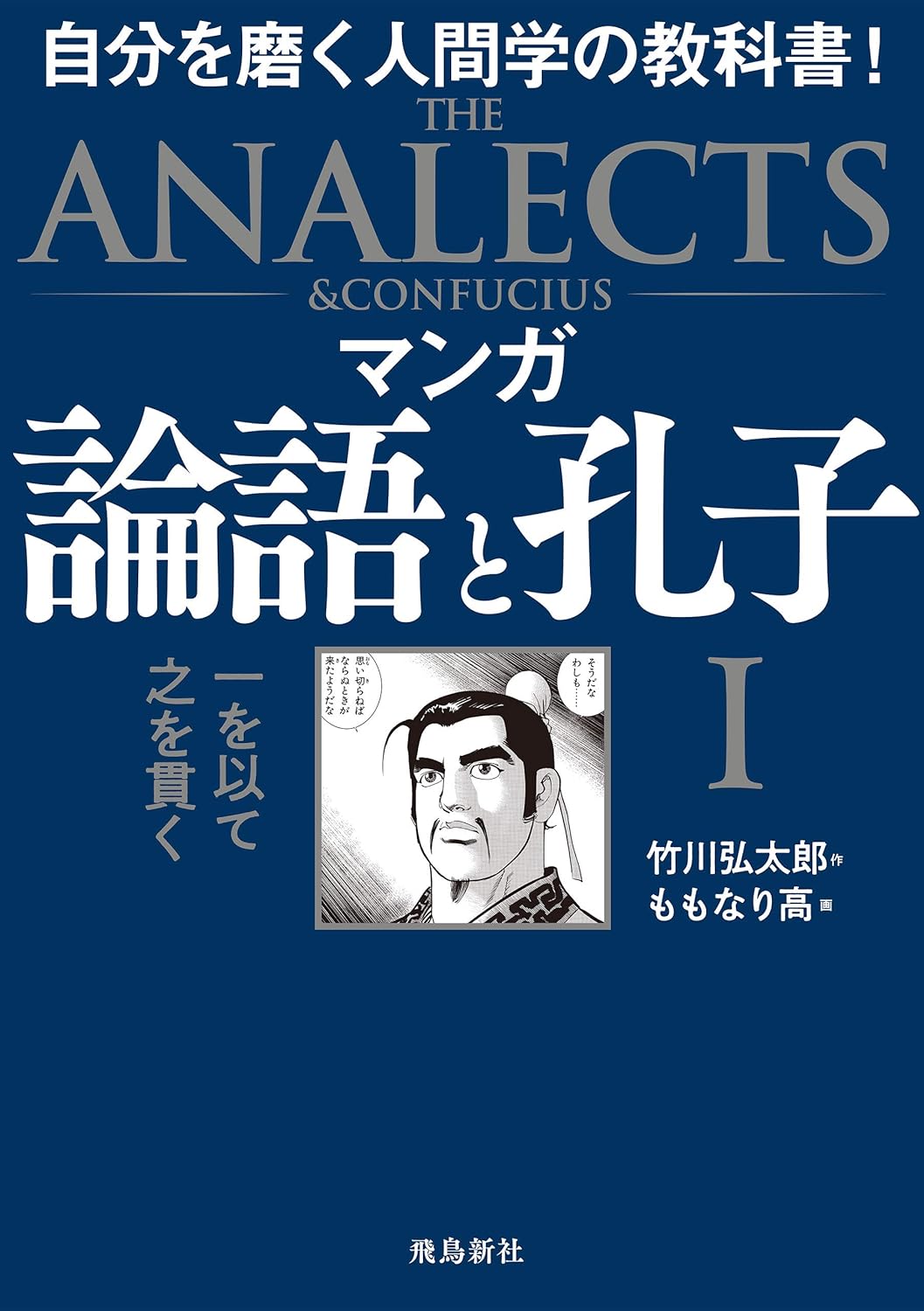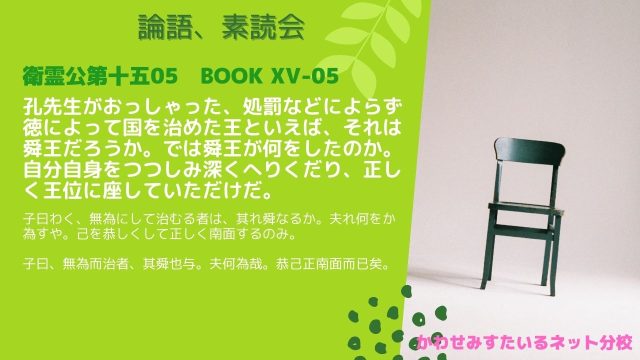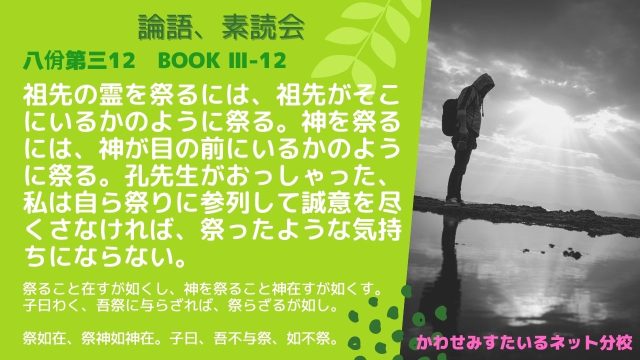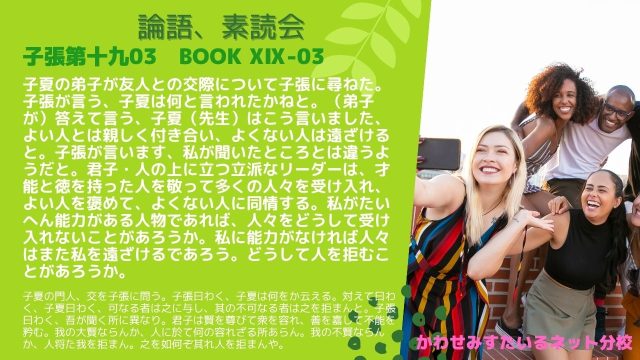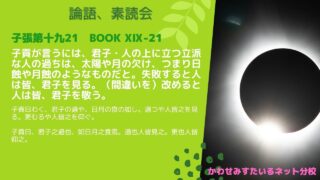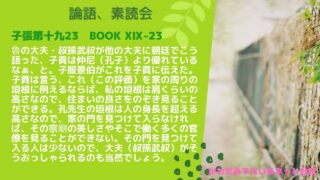衛の国の公孫朝が子貢に尋ねて言った、仲尼(孔子)はどこで誰に学んだのですか?と。子貢が答えて言う、周の文王と武王の道(文武の道)・正しい道義は亡びず人々の中に在ります。人徳がある人は(文武の道の)大きなことを理解し、人徳がない人は(文武の道の)小さなことを心得ています。(このように)文武の道がないことはありません。孔先生は誰に学ばないことがありましょうか(誰にでも学ばれました)。そしてまたどうして決まった一人の先生が有ったわけではありません。|「論語」子張第十九22
【現代に活かす論語】
正しい道徳が人の心の中にあるので、どこでも誰からでも学ぶことがあります。
【解釈】
公孫朝(こうそんちょう) … 衛(えい)の大夫。「論語」の登場人物|論語、素読会
子貢(しこう) … 姓は端木、名は賜、字は子貢。孔子より三十一歳若い。「論語」の中で孔子との問答がもっとも多い。言葉巧みな雄弁家で自信家だったが、孔子には聡明さを褒められ、言葉の多さを指摘されている。
経済面で能力が高かったと言われている。「論語」の登場人物|論語、素読会
仲尼(ちゅうじ) … 孔子(こうし)。姓は孔、名は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。仲は次男のこと。「論語」の登場人物|論語、素読会
衞の公孫朝、子貢に問うて曰わく、仲尼焉にか学べる。子貢曰わく、文武の道、未だ地に墜ちずして、人に在り。賢者は其の大なる者を識り、不賢者は其の小なる者を識る。文武の道有らざること莫し。夫子焉にか学ばざらん。而して亦何の常師か之れ有らん。|「論語」子張第十九22
衞公孫朝、問於子貢曰、仲尼焉学。子貢曰、文武之道、未墜於地、在人。賢者識其大者、不賢者識其小者。莫不有文武之道焉。夫子焉不学。而亦何常師之有。
「焉」(いずくに)はどこに…か。「文武」(ぶんぶ)は周の文王と武王。「道」(みち)は道義。正しい政治。『道』とは?|論語、素読会 「墜」(おちる)は上から下に落とす。廃する、やめる。「未墜於地」(いまだちにおちず)は地に落ちない、亡びない。「在」(ある)は存在する、生きている。「賢者」(けんじゃ)は才能に優れ、人徳がある人、賢人。「大」(だいなり)はおおきい。「者」(もの)はもの、こと。「識」(しる)はわかる、見知っている。「小」(しょう)はわずかの、少ない。「莫」(ない)は…でないもの(人・こと)はない。と訳す。「而」(しこうして)はそして、また。「夫子」(ふうし)は先生に対する尊称。「常師」(じょうし)は決まった一人の先生。
衛の国の公孫朝が子貢に尋ねて言った、仲尼(孔子)はどこで誰に学んだのですか?と。子貢が答えて言う、周の文王と武王の道(文武の道)・正しい道義は亡びず人々の中に在ります。人徳がある人は(文武の道の)大きなことを理解し、人徳がない人は(文武の道の)小さなことを心得ています。(このように)文武の道がないことはありません。孔先生は誰に学ばないことがありましょうか(誰にでも学ばれました)。そしてまたどうして決まった一人の先生が有ったわけではありません。
【解説】
公孫朝は衛の大夫である以外、情報がないようです。孔子を字の仲尼で呼びますが、近しい間柄というより、立場が上の人間の物言いに、子貢の回答も淡々としているように感じます。「文武」は文献によると、周の文王と武王を指しています。孔子の時代のひとつ前の時代で、孔子が手本としている周代の道徳が人々の中にまだ残っているということ。そしてそういう世の中であれば、様々な人からの学びが常に周りにあるという考え方が伝わってきます。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九21< | >子張第十九23
【原文・白文】
衞公孫朝、問於子貢曰、仲尼焉学。子貢曰、文武之道、未墜於地、在人。賢者識其大者、不賢者識其小者。莫不有文武之道焉。夫子焉不学。而亦何常師之有。
<衞公孫朝、問於子貢曰、仲尼焉學。子貢曰、文武之道、未墜於地、在人。賢者識其大者、不賢者識其小者。莫不有文武之道焉。夫子焉不學。而亦何常師之有。>
(衞の公孫朝、子貢に問うて曰わく、仲尼焉にか学べる。子貢曰わく、文武の道、未だ地に墜ちずして、人に在り。賢者は其の大なる者を識り、不賢者は其の小なる者を識る。文武の道有らざること莫し。夫子焉にか学ばざらん。而して亦何の常師か之れ有らん。)
【読み下し文】
衞(えい)の公孫朝(こうそんちょう)、子貢(しこう)に問(と)うて曰(い)わく、仲尼(ちゅうじ)焉(いずく)にか学(まな)べる。子貢(しこう)曰(い)わく、文武(ぶんぶ)の道(みち)、未(いま)だ地(ち)に墜(お)ちずして、人(ひと)に在(あ)り。賢者(けんじゃ)は其(そ)の大(だい)なる者(もの)を識(し)り、不賢者(ふけんじゃ)は其(そ)の小(しょう)なる者(もの)を識(し)る。文武(ぶんぶ)の道(みち)有(あ)らざること莫(な)し。夫子(ふうし)焉(いずく)にか学(まな)ばざらん。而(しこう)して亦(また)何(なん)の常師(じょうし)か之(こ)れ有(あ)らん。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九21< | >子張第十九23