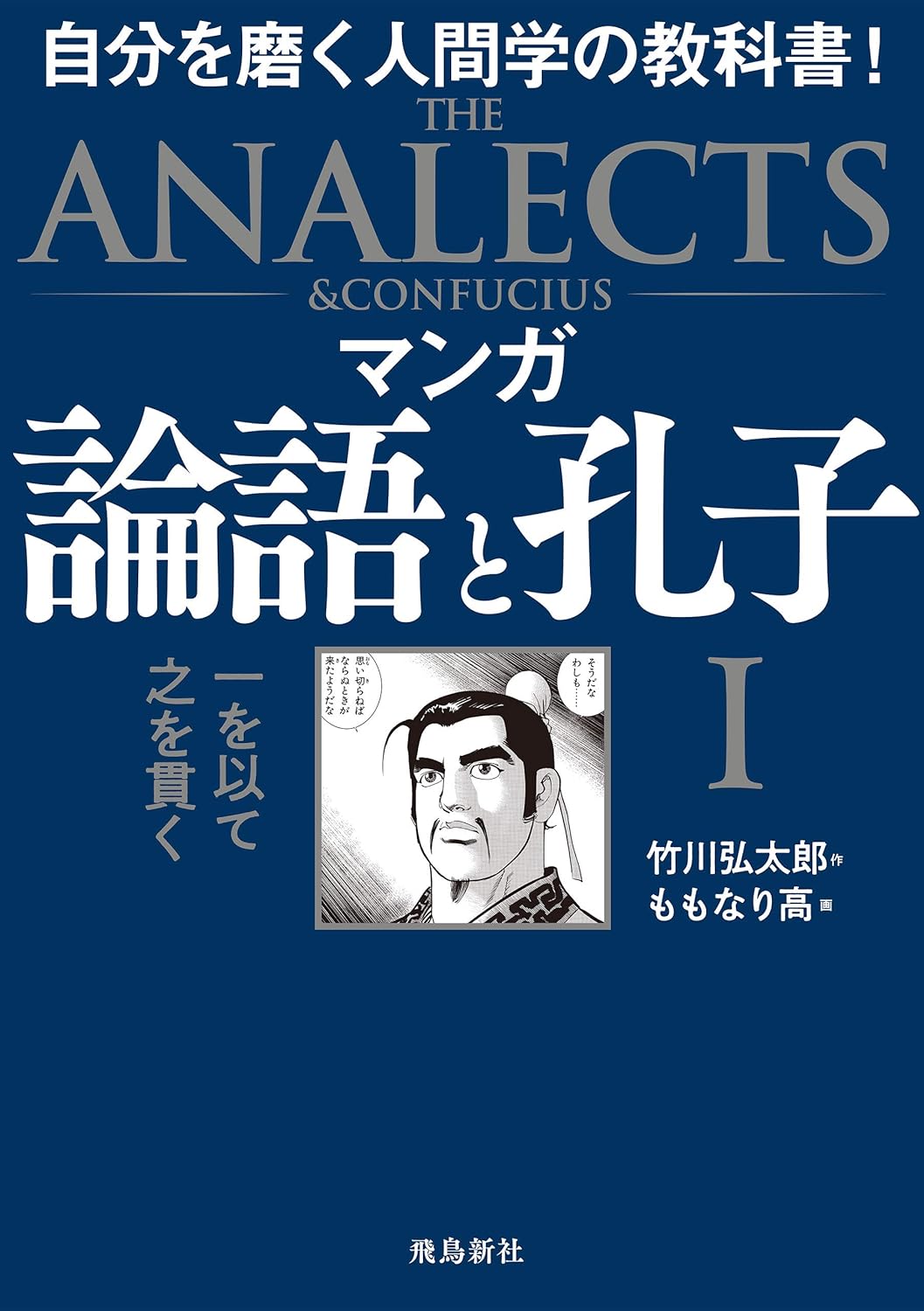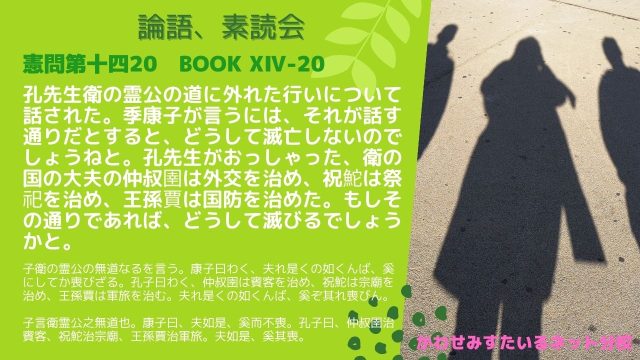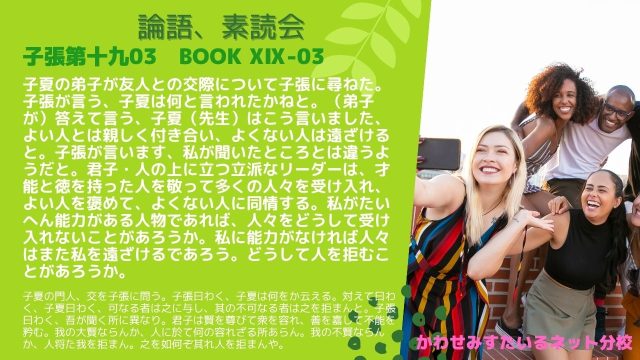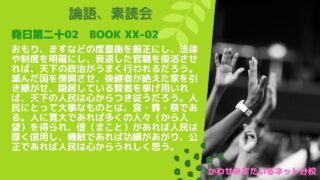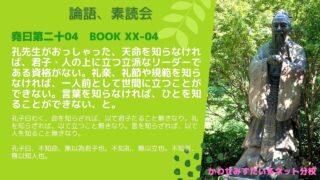子張が孔先生に尋ねて言うには、どうしたら政治に(上手く)たずさわることができましょうかと。孔先生がおっしゃった、「五美」を尊び「四悪」を排除すれば、そのことによって政治にたずさわることができるだろう、と。子張が尋ねた、何を「五美」と言うのですかと。孔先生がおっしゃった、君子・人の上に立つ立派なリーダーは、人民に希望(自主性)を与えることによって無駄な消費をしない、苦労はするが不満を言わない、欲しいと思うが欲張らない、泰然として落ちついているがおごらない、威厳はあるが猛々しくはない、と。子張は尋ねた、どういうことを恵して費やさずというのでしょうかと。孔先生がおっしゃった、人民が(自ら)利益とするところによってこれを(人民の)利益とする。これこそ与え恵んで(余計なものを)消費しないということではないだろうか。その人民が労働することを選んで自ら働く、そうすれば誰を怨むというのだろう。心の徳を重ねる・仁を求めて、ひとを思いやる心・仁を得ることができるのである、何を欲張ることがあるのか、と。君子・人の上に立つ立派なリーダーは、多寡や大きい小さいに関係なく、あえて軽んじることがない、これこそ泰然として驕らないということではないだろうか。君子はその衣服や冠を正し、眼差しを重々しくする、おごそかで人から慕われて敬服される、これが威厳はあれど猛々しくないということではないか、と。子張は尋ねる、どんなことを「四悪」というのでしょうか、と。孔先生がおっしゃった、教え導かずに黙殺してしまう、これをむごいという。注意をせずに成果を望む、これを乱暴という。命令をゆるくして期日を厳しくする、これを害という。人民に与えるべきものを与えずに出し渋る、これを官吏(役人根性)という、と。|「論語」堯曰第二十03
【現代に活かす論語】
人の上に立つ立派なリーダーは、五つの美しい行動を心がけるといいでしょう。自主性を与えることで労力を消費しない。苦労はするが不満を言わない。欲しいと思うが欲張らない。落ちついているが驕らない。威厳はあるが猛々しくはない。そして、四つの悪い行動を戒めます。教えずに黙殺する。注意をせずに成果を望む。命令を緩くして期日を厳しくする。部下への対応に差を付ける。
【解釈】
子張(しちょう) … 姓は顓孫(せんそん)、名は師(し)、字は子張(しちょう)。孔子より四十八歳若い。
子張孔子に問うて曰わく、何如なれば斯れ以て政に従うべき。子曰わく、五美を尊び、四悪を屛くれば、斯れ以て政に従うべし。子張曰わく、何をか五美と謂う。子曰わく、君子は恵して費さず、労して怨みず、欲して貪らず、泰にして驕らず、威にして猛からず。子張曰わく、何をか恵して費さずと謂う。子曰わく、民の利とする所に因りて之を利す。斯れ亦恵して費さざるにあらずや。労すべきを択びて之を労す。又誰をか怨みん。仁を欲して仁を得たり。又焉をか貧らん。君子は衆寡と無く、小大と無く、敢て慢ること無し。斯れ亦泰にして驕らざるにあらずや。君子は其の衣冠を正しくし、其の瞻視を尊くす。厳然として人望みて之を畏る。斯れ亦威にして猛からざるにあらずや。子張曰わく、何をか四悪と謂う。子曰わく、教えずして殺す、之を虐と謂う。戒めずして成るを視る、之を暴と謂う。令を慢くして期を致す、之を賊と謂う。之を猶しく人に与うるに、出納の吝なる、之を有司と謂う。|「論語」堯曰第二十03
子張問於孔子曰、何如斯可以従政矣。子曰、尊五美、屛四悪、斯可以従政矣。子張曰、何謂五美。子曰、君子恵而不費、労而不怨、欲而不貪、泰而不驕、威而不猛。子張曰、何謂恵而不費。子曰、因民之所利而利之。斯不亦恵而不費乎。択可労而労之。又誰怨。欲仁而得仁。又焉貧。君子無衆寡、無小大、無敢慢。斯不亦泰而不驕乎。君子正其衣冠、尊其瞻視。厳然人望而畏之。斯不亦威而不猛乎。子張曰、何謂四悪。子曰、不教而殺、謂之虐。不戒視成、謂之暴。慢令致期、謂之賊。猶之与人也、出納之吝、謂之有司。
「政」(まつりごと)は政治。「従」(したがう)は加わる、たずさわる。「屛」(しりぞく)は排除する、除く。「謂」(いう)は人や事物を評論する。「君子」(くんし)は徳の高いりっぱな人物、人の上に立つ立派な人、リーダー。「恵」(けい)は人に与えたり、人から受ける好意。「費」(ひ)は散財する、消耗する。「労」(ろう)はまじめに努めるさま、苦しむさま。「怨」(うらむ)は不満の思いを抱く、とがめる。「欲」(よく)は〔事物を〕ほしがる、手に入れたいと思う。「貪」(むさぼる)は欲張る、満足することを知らずに追求する。「泰」(ゆたか)は順調さ、幸運。「驕」(おごる)はわがままにふるまう。「威」(い)は震撼させる、驚かす。「猛」(たけし)は凶暴なさま、あらあらしい。「択」(えらぶ)は選び取る。「仁」(じん)は心の徳を重ね徳性を高めること。『仁』とは?|論語、素読会 「仁」(じん)はひとを思いやる心、情愛の心。『仁』とは?|論語、素読会 「焉」(なにをか)は事柄をたずねる。「衆寡」(しゅうか)は多数と少数、多数と少数、多寡。「慢」(あなどる)は軽んじる、あなどる。「衣冠」(いかん)は衣服とかんむり、正装。「瞻視」(せんし)はあたりを見る、外見。「尊」(たっとい)は身分が高い。「厳然」(げんぜん)はおごそかなさま。「望」(のぞむ)はあがめる、敬う、慕う。「畏」(おそる)は敬服する。「虐」(ぎゃく)は残虐、むごいしうち。「戒」(いましめる)はそなえる、用心する。「成」(なる)は成功、成果、成就、できあがり。「視」(みる)はつまびらかに見る、職務を行う、治める。「暴」(ぼう)は手荒さ、乱暴。「令」(れい)は命令。「期」(き)は決まった、あるいは約束した時間、機会。「致」(いたす)は到達する、極める。「賊」(ぞく)は害、災難、わざわい。「猶」AはBと同じである。「出納・出内」(すいとう)は帝の命を下達し、下部の意見を帝にとどける、出し入れ。「吝」(やぶさかなり)はおしむ、けちけちする。「有司」(ゆうし)は官吏、役人。
子張が孔先生に尋ねて言うには、どうしたら政治に(上手く)たずさわることができましょうかと。孔先生がおっしゃった、「五美」を尊び「四悪」を排除すれば、そのことによって政治にたずさわることができるだろう、と。子張が尋ねた、何を「五美」と言うのですかと。孔先生がおっしゃった、君子・人の上に立つ立派なリーダーは、人民に希望(自主性)を与えることによって無駄な消費をしない、苦労はするが不満を言わない、欲しいと思うが欲張らない、泰然として落ちついているがおごらない、威厳はあるが猛々しくはない、と。子張は尋ねた、どういうことを恵して費やさずというのでしょうかと。孔先生がおっしゃった、人民が(自ら)利益とするところによってこれを(人民の)利益とする。これこそ与え恵んで(余計なものを)消費しないということではないだろうか。その人民が労働することを選んで自ら働く、そうすれば誰を怨むというのだろう。心の徳を重ねる・仁を求めて、ひとを思いやる心・仁を得ることができるのである、何を欲張ることがあるのか、と。君子・人の上に立つ立派なリーダーは、多寡や大きい小さいに関係なく、あえて軽んじることがない、これこそ泰然として驕らないということではないだろうか。君子はその衣服や冠を正し、眼差しを重々しくする、おごそかで人から慕われて敬服される、これが威厳はあれど猛々しくないということではないか、と。子張は尋ねる、どんなことを「四悪」というのでしょうか、と。孔先生がおっしゃった、教え導かずに黙殺してしまう、これをむごいという。注意をせずに成果を望む、これを乱暴という。命令をゆるくして期日を厳しくする、これを害という。人民に与えるべきものを与えずに出し渋る、これを官吏(役人根性)という、と。
【解説】
孔子の学び、特に官職に就く心構えを「五美」「四悪」で解説した章句です。これを前提としてこちら「猶之与人也、出納之吝、謂之有司。」を解釈するにあたり、文献を参考にします。「吝」けちけちする、惜しむのは「出納」です。官吏が帝と下の者の意見を仲介するという意味と物の出し入れの意味どちらを採用するかという判断は、等しく人民に与える場面を想像して決定します。官吏が人民に与える物・ことをけちる、出し惜しみするというのはどんな場面でしょう。文献では、官吏がその権限を利用して本来条件なしで与えることができる物の出し入れを勝手に判断している場面、横流し、贈収賄という、官吏にあるまじき行動、「悪」を想像し、解釈しています。そして、この行動こそ役人であると表現しているので、ここはあえて「役人根性」という表現を使いました。
この時代でもこのような役人を揶揄するような表現があることに驚かされます。
「論語」参考文献|論語、素読会
堯曰第二十02< | >堯曰第二十04
【原文・白文】
子張問於孔子曰、何如斯可以従政矣。子曰、尊五美、屛四悪、斯可以従政矣。子張曰、何謂五美。子曰、君子恵而不費、労而不怨、欲而不貪、泰而不驕、威而不猛。子張曰、何謂恵而不費。子曰、因民之所利而利之。斯不亦恵而不費乎。択可労而労之。又誰怨。欲仁而得仁。又焉貧。君子無衆寡、無小大、無敢慢。斯不亦泰而不驕乎。君子正其衣冠、尊其瞻視。厳然人望而畏之。斯不亦威而不猛乎。子張曰、何謂四悪。子曰、不教而殺、謂之虐。不戒視成、謂之暴。慢令致期、謂之賊。猶之与人也、出納之吝、謂之有司。
<子張問於孔子曰、何如斯可以從政矣。子曰、尊五美、屛四惡、斯可以從政矣。子張曰、何謂五美。子曰、君子惠而不費、勞而不怨、欲而不貪、泰而不驕、威而不猛。子張曰、何謂惠而不費。子曰、因民之所利而利之。斯不亦惠而不費乎。擇可勞而勞之。又誰怨。欲仁而得仁。又焉貧。君子無衆寡、無小大、無敢慢。斯不亦泰而不驕乎。君子正其衣冠、尊其瞻視。儼然人望而畏之。斯不亦威而不猛乎。子張曰、何謂四惡。子曰、不教而殺、謂之虐。不戒視成、謂之暴。慢令致期、謂之賊。猶之與人也、出納之吝、謂之有司。>
(子張孔子に問うて曰わく、何如なれば斯れ以て政に従うべき。子曰わく、五美を尊び、四悪を屛くれば、斯れ以て政に従うべし。子張曰わく、何をか五美と謂う。子曰わく、君子は恵して費さず、労して怨みず、欲して貪らず、泰にして驕らず、威にして猛からず。子張曰わく、何をか恵して費さずと謂う。子曰わく、民の利とする所に因りて之を利す。斯れ亦恵して費さざるにあらずや。労すべきを択びて之を労す。又誰をか怨みん。仁を欲して仁を得たり。又焉をか貧らん。君子は衆寡と無く、小大と無く、敢て慢ること無し。斯れ亦泰にして驕らざるにあらずや。君子は其の衣冠を正しくし、其の瞻視を尊くす。厳然として人望みて之を畏る。斯れ亦威にして猛からざるにあらずや。子張曰わく、何をか四悪と謂う。子曰わく、教えずして殺す、之を虐と謂う。戒めずして成るを視る、之を暴と謂う。令を慢くして期を致す、之を賊と謂う。之を猶しく人に与うるに、出納の吝なる、之を有司と謂う。)
【読み下し文】
子張(しちょう)孔子(こうし)に問(と)うて曰(い)わく、何如(いか)なれば斯(こ)れ以(もっ)て政(まつりごと)に従(したが)うべき。子(し)曰(のたま)わく、五美(ごび)を尊(たっと)び、四悪(しあく)を屛(しりぞ)くれば、斯(こ)れ以(もっ)て政(まつりごと)に従(したが)うべし。子張(しちょう)曰(い)わく、何(なに)をか五美(ごび)と謂(い)う。子(し)曰(のたま)わく、君子(くんし)は恵(けい)して費(ついや)さず、労(ろう)して怨(うら)みず、欲(ほっ)して貪(むさぼ)らず、泰(ゆたか)にして驕(おご)らず、威(い)にして猛(たけ)からず。子張(しhちょう)曰(い)わく、何(なに)をか恵(けい)して費(ついや)さずと謂(い)う。子(し)曰(のたま)わく、民(たみ)の利(り)とする所(ところ)に因(よ)りて之(これ)を利(り)す。斯(こ)れ亦(また)恵(けい)して費(ついや)さざるにあらずや。労(ろう)すべきを択(えら)びて之(これ)を労(ろう)す。又(また)誰(だれ)をか怨(うら)みん。仁(じん)を欲(ほっ)して仁(じん)を得(え)たり。又(また)焉(なに)をか貧(むさぼ)らん。君子(くんし)は衆寡(しゅうか)と無(な)く、小大(しょうだい)と無(な)く、敢(あえ)て慢(あなど)ること無(な)し。斯(こ)れ亦(また)泰(ゆたか)にして驕(おご)らざるにあらずや。君子(くんし)は其(そ)の衣冠(いかん)を正(ただ)しくし、其(そ)の瞻視(せんし)を尊(たっと)くす。厳然(げんぜん)として人(ひと)望(のぞ)みて之(これ)を畏(おそ)る。斯(こ)れ亦(また)威(い)にして猛(たけ)からざるにあらずや。子張(しちょう)曰(い)わく、何(なに)をか四悪(しあく)と謂(い)う。子(し)曰(のたま)わく、教(おし)えずして殺(ころ)す、之(これ)を虐(ぎゃく)と謂(い)う。戒(いまし)めずして成(な)るを視(み)る、之(これ)を暴(ぼう)と謂(い)う。令(れい)を慢(ゆる)くして期(き)を致(いた)す、之(これ)を賊(ぞく)と謂(い)う。之(これ)を猶(ひと)しく人(ひと)に与(あた)うるに、出納(すいとう)の吝(やぶさか)なる、之(これ)を有司(ゆうし)と謂(い)う。
「論語」参考文献|論語、素読会
堯曰第二十02< | >堯曰第二十04