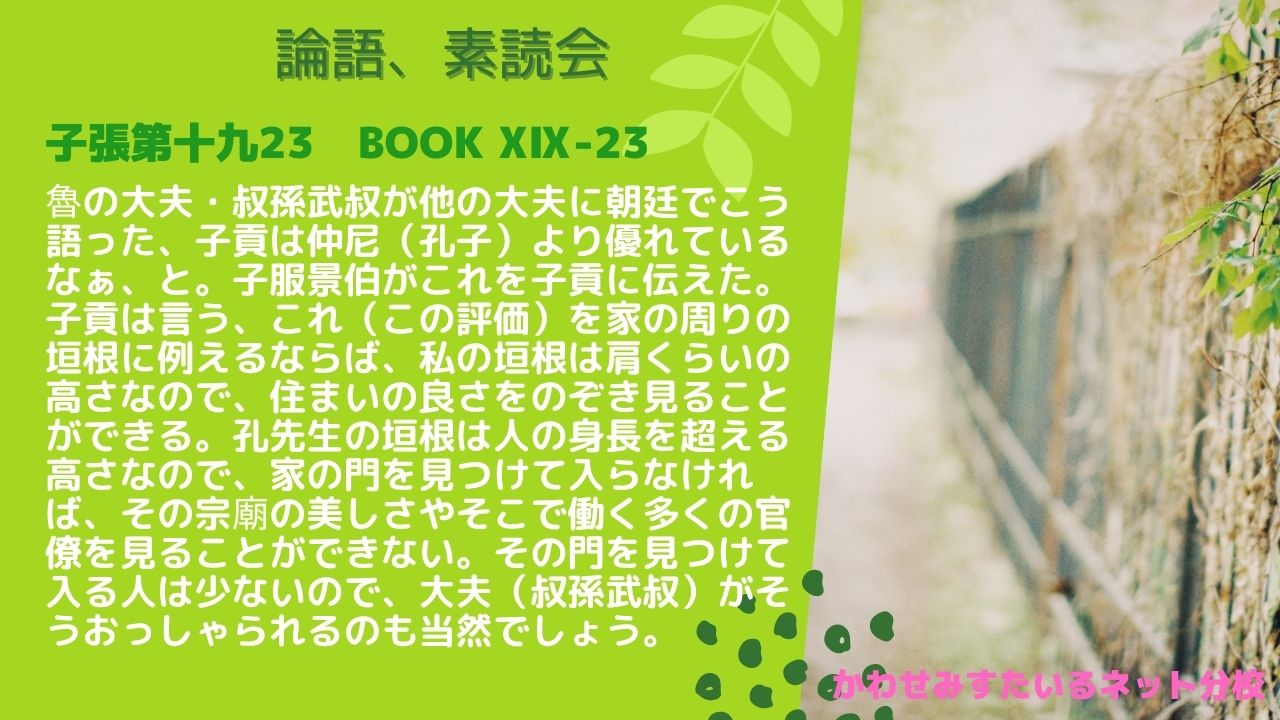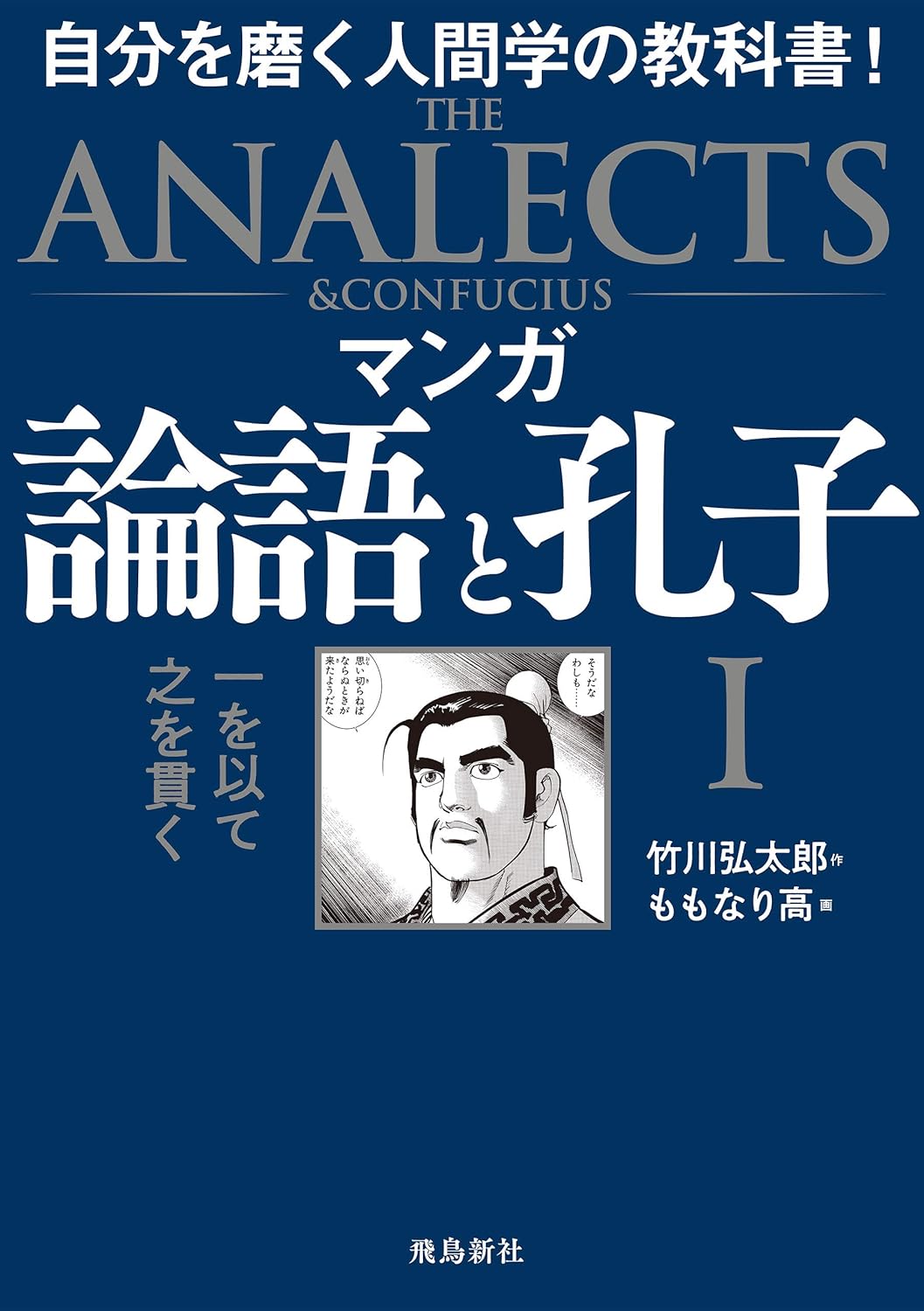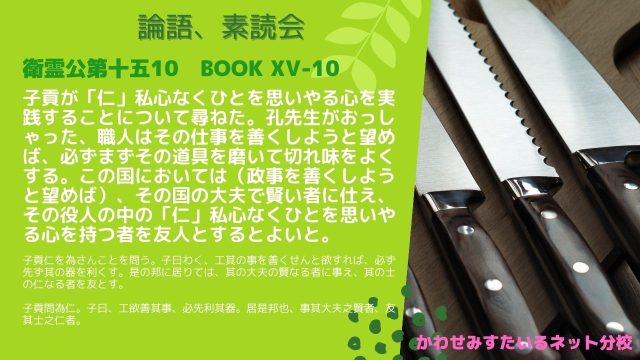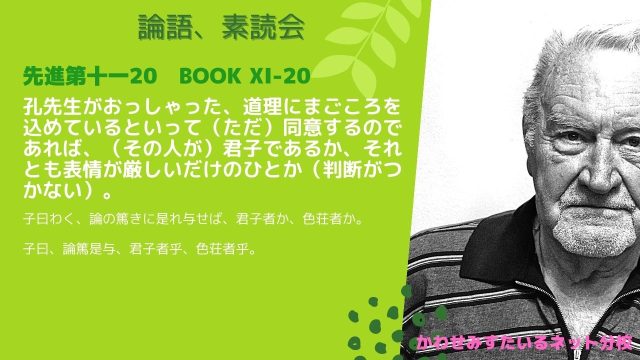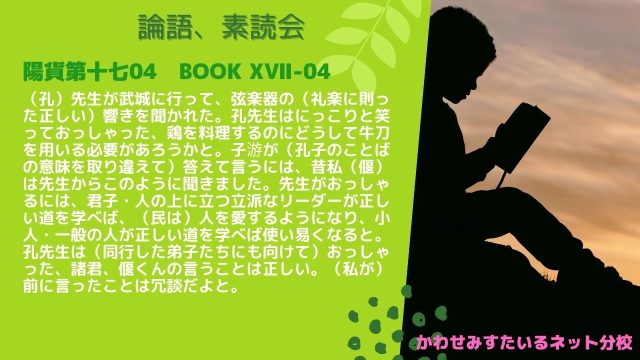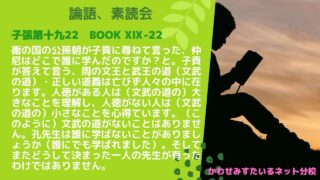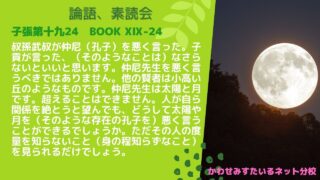魯の大夫・叔孫武叔が他の大夫に朝廷でこう語った、子貢は仲尼(孔子)より優れているなぁ、と。子服景伯がこれを子貢に伝えた。子貢は言う、それ(私と孔先生の能力)を家の周りの垣根に例えるならば、私の垣根は肩くらいの高さなので、住まいの良さをのぞき見ることができる。孔先生の垣根は人の身長を超える高さなので、家の門を見つけて入らなければ、その宗廟の美しさやそこで働く多くの官僚を見ることができない。その門を見つけて入る人は少ないので、大夫(叔孫武叔)がそうおっしゃられるのも当然でしょう。|「論語」子張第十九23
【現代に活かす論語】
師匠や先達のすばらしい能力は、垣根の外からのぞき見ることはできないので、門を探して中に入りらなければ、深く知ることはできない。
【解釈】
叔孫武叔(しゅくそんぶしゅく) … 魯(ろ)の大夫、叔孫(しゅくそん)氏の第八代目。名は州仇(しゅうきゅう)。武叔(ぶそん)は贈り名。「論語」の登場人物|論語、素読会
子貢(しこう)賜(し) … 姓は端木、名は賜、字は子貢。孔子より三十一歳若い。「論語」の中で孔子との問答がもっとも多い。言葉巧みな雄弁家で自信家だったが、孔子には聡明さを褒められ、言葉の多さを指摘されている。
経済面で能力が高かったと言われている。「論語」の登場人物|論語、素読会
仲尼(ちゅうじ) … 孔子(こうし)。姓は孔、名は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。仲は次男のこと。「論語」の登場人物|論語、素読会
子服景伯(しふくけいはく) … 魯(ろ)の人。姓は子服(しふく)、名は何(か)。伯(はく)は字。景(けい)は贈り名。三桓(さんかん)氏の一族で、孟献子(もうけんし)の玄孫。「論語」の登場人物|論語、素読会
叔孫武叔、大夫に朝に語りて曰わく、子貢は仲尼より賢れり。子服景伯、以て子貢に告ぐ。子貢曰わく、之を宮牆に譬うれば、賜の牆や肩に及べり。室家の好きを窺い見ん。夫子の牆や数仞。其の門を得て入らざれば、宗廟の美、百官の富を見ず。其の門を得る者或は寡なし。夫子の云うこと、亦宜ならずや。|「論語」子張第十九23
叔孫武叔、語大夫於朝曰、子貢賢於仲尼。子服景伯、以告子貢。子貢曰、譬之宮牆、賜之牆也及肩。窺見室家之好。夫子之牆数仞。不得其門而入、不見宗廟之美、百官之富。得其門者或寡矣。夫子之云、不亦宜乎。
「大夫」(たいふ)は官吏の身分の一つ、中央の要職や顧問など、重要な地位をしめる場合が多い。「朝」(ちょう)は君主や高級官僚が政務を処理した場所、朝廷。「賢」(まさる)は[能力などが]超過する、優れる。「宮牆」(きゅうしょう)は家屋の周囲のかきね、師の門。「譬」(たとえる)はひきあいに出して説明する、なぞらえる。「牆」(かき)はれんがや石で造成した障壁や囲い、へい、かき。「室家」(しっか)はいえ、すまい。「好」(すく)はこのましい、優れているさま。「窺」(うかがう)は小さい穴や透き間からのぞく。「夫子」(ふうし)は男子の尊称、先生に対する尊称、孔子の尊称。「仞」(じん)は長さの単位、周では八尺、漢では七尺。ひろ。「数仞」(すうじん)は数尋(すうひろ)。「宗廟」(そうびょう)は天子や諸侯が祖先を祭った建物、みたまや。「百官」(ひゃっかん)は公卿以下の多くの官僚。「或」(あるいは)はだれ[でも]、いかなる人[でも]。「宜」(むべ)は当然であるさま、本当であるさま、むべ。
魯の大夫・叔孫武叔が他の大夫に朝廷でこう語った、子貢は仲尼(孔子)より優れているなぁ、と。子服景伯がこれを子貢に伝えた。子貢は言う、これ(この評価)を家の周りの垣根に例えるならば、私の垣根は肩くらいの高さなので、住まいの良さをのぞき見ることができる。孔先生の垣根は人の身長を超える高さなので、家の門を見つけて入らなければ、その宗廟の美しさやそこで働く多くの官僚を見ることができない。その門を見つけて入る人は少ないので、大夫(叔孫武叔)がそうおっしゃられるのも当然でしょう。
【解説】
孔子の能力を侮るなかれ。叔孫武叔は孔子の一体どの部分を見て、私(子貢)と比べ、私が優れているとおっしゃるのでしょう。という子貢の気持ちが前面に出ている章句です。しかし、その表現は冷静で秀逸です。まさに子貢が学んだのは孔子の教えだけでなく、後年に語り継がれる表現のエッセンスだと思います。
「仞」尋は現代では六尺(一.八メートル)。孔子の家の垣根は数尋ですが、一尋を少し超える高さと考えるのが妥当かと思います。「夫子」は最初のものが孔先生、次のものが叔孫武叔を指します。
さらに深読みすると、「宗廟の美」とはその美しさや荘厳さを指しているのだと思いますが、孔子の「礼楽」の知識と大切に思う考え方を指し、「百官の富」は才気ある多くの官僚が淀みなく働くさまを、孔子の「仁」「義」「信」「智」などを発する姿に重ね合わせていると思います。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九22< | >子張第十九24
【原文・白文】
叔孫武叔、語大夫於朝曰、子貢賢於仲尼。子服景伯、以告子貢。子貢曰、譬之宮牆、賜之牆也及肩。窺見室家之好。夫子之牆数仞。不得其門而入、不見宗廟之美、百官之富。得其門者或寡矣。夫子之云、不亦宜乎。
<叔孫武叔、語大夫於朝曰、子貢賢於仲尼。子服景伯、以告子貢。子貢曰、譬之宮牆、賜之牆也及肩。闚見室家之好。夫子之牆數仞。不得其門而入、不見宗廟之美、百官之富。得其門者或寡矣。夫子之云、不亦宜乎。>
(叔孫武叔、大夫に朝に語りて曰わく、子貢は仲尼より賢れり。子服景伯、以て子貢に告ぐ。子貢曰わく、之を宮牆に譬うれば、賜の牆や肩に及べり。室家の好きを窺い見ん。夫子の牆や数仞。其の門を得て入らざれば、宗廟の美、百官の富を見ず。其の門を得る者或は寡なし。夫子の云うこと、亦宜ならずや。)
【読み下し文】
叔孫武叔(こうそんぶしゅく)、大夫(たいふ)に朝(ちょう)に語(かた)りて曰(い)わく、子貢(しこう)は仲尼(ちゅうじ)より賢(まさ)れり。子服景伯(しふくけいはく)、以(もっ)て子貢(しこう)に告(つ)ぐ。子貢(しこう)曰(い)わく、之(これ)を宮牆(きゅうしょう)に譬(たと)うれば、賜(し)の牆(かき)や肩(かた)に及(およ)べり。室家(しっか)の好(す)きを窺(うかが)い見(み)ん。夫子(ふうし)の牆(かき)や数仞(すうじん)。其(そ)の門(もん)を得(え)て入(い)らざれば、宗廟(そうびょう)の美(び)、百官(ひゃっかん)の富(とみ)を見(み)ず。其(そ)の門(もん)を得(え)る者(もの)或(あうい)は寡(すく)なし。夫子(ふうし)の云(い)うこと、亦(また)宜(むべ)ならずや。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九22< | >子張第十九24