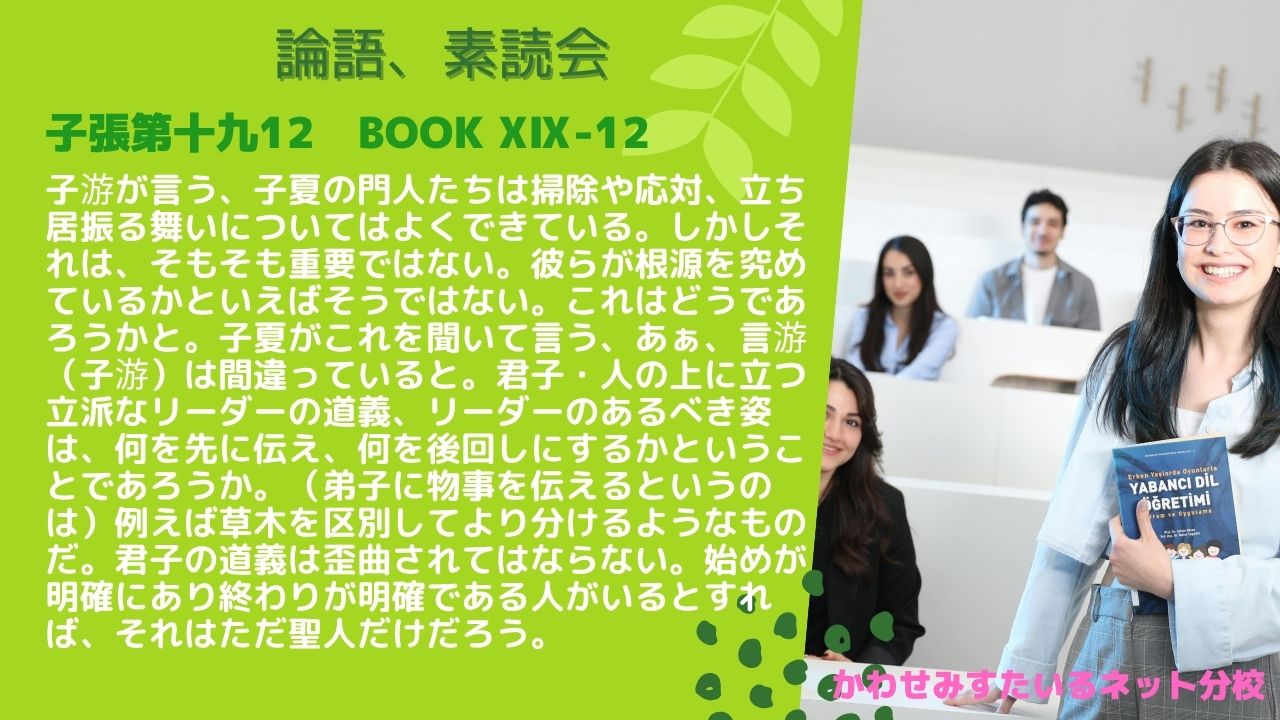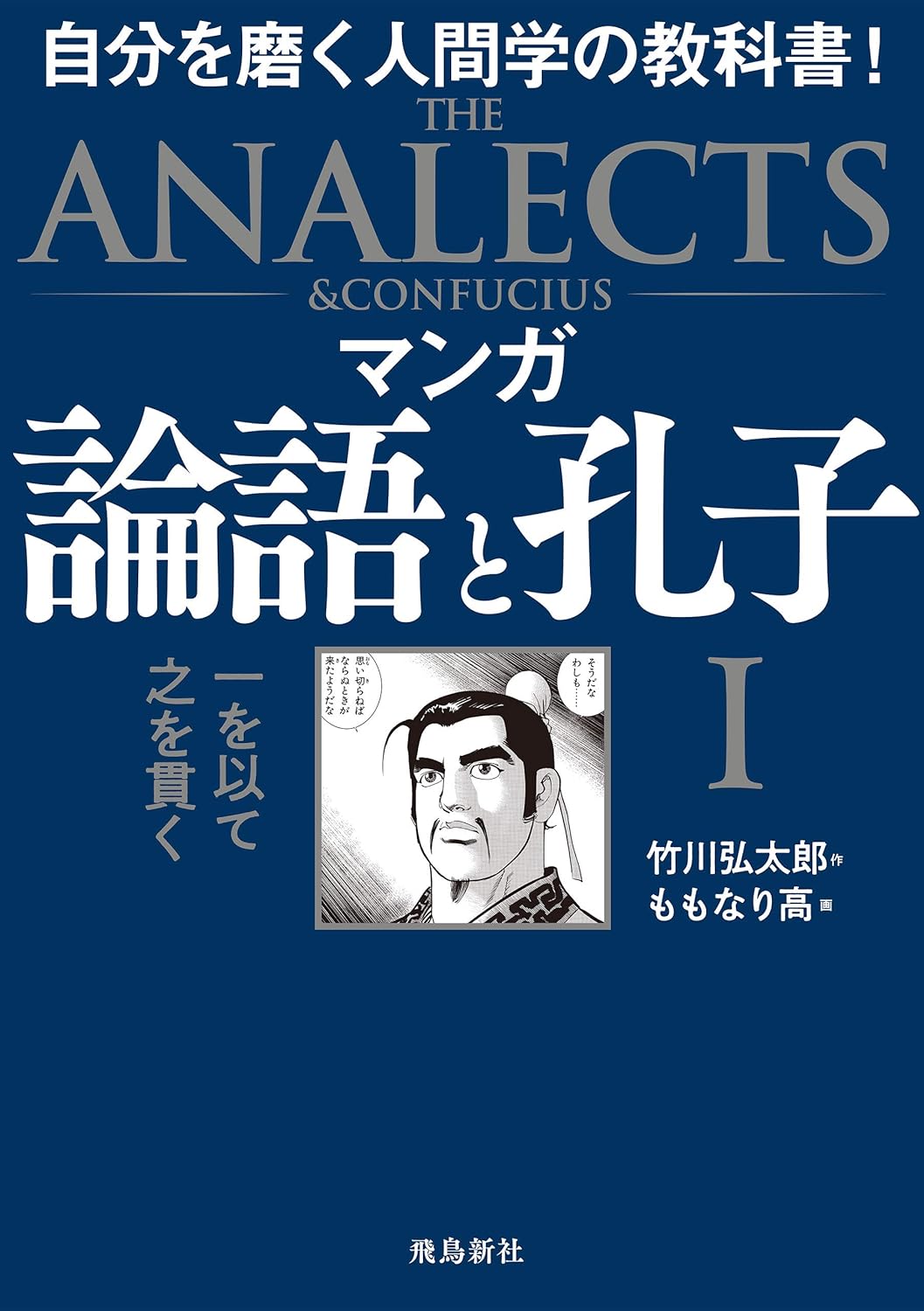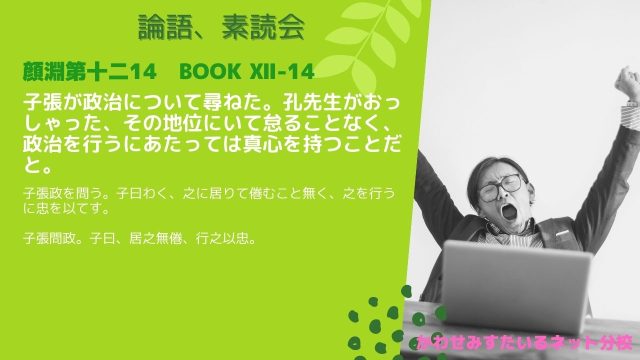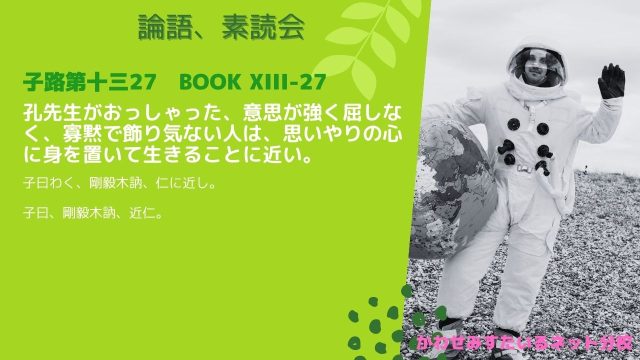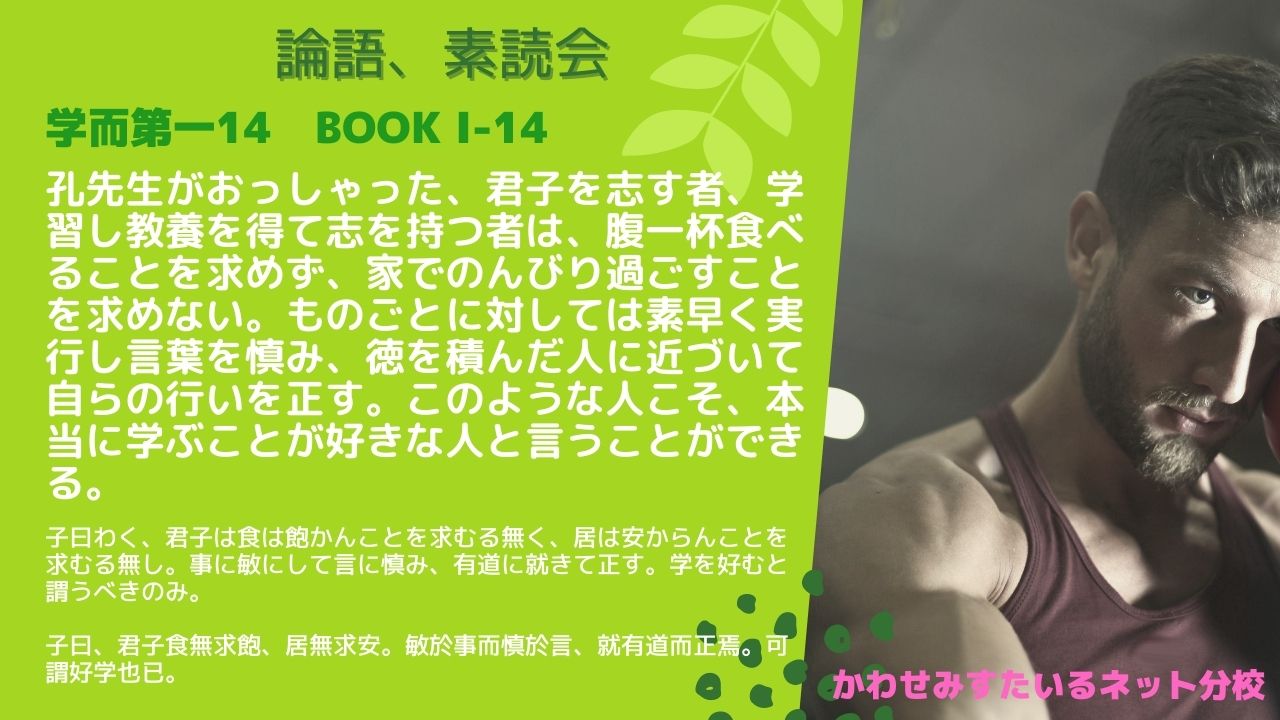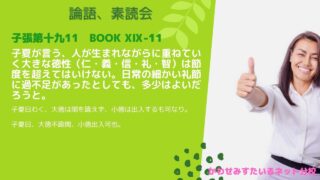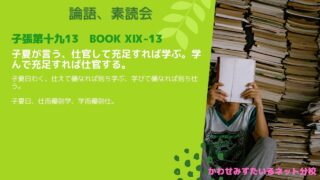子游が言う、子夏の門人たちは掃除や応対、立ち居振る舞いについてはよくできている。しかしそれは、そもそも重要ではない。彼らが根源を究めているかといえばそうではない。これはどうであろうかと。子夏がこれを聞いて言う、あぁ、言游(子游)は間違っていると。君子・人の上に立つ立派なリーダーの道義、リーダーのあるべき姿は、何を先に伝え、何を後回しにするかということであろうか。(弟子に物事を伝えるというのは)例えば草木を区別してより分けるようなものだ。君子の道義は歪曲されてはならない。始めが明確にあり終わりが明確である人がいるとすれば、それはただ聖人だけだろう。|「論語」子張第十九12
【現代に活かす論語】
人の上に立つ立派なリーダーが心がけるべき筋道とは、それぞれの部下に合わせて伝える順序を変えることです。
【解釈】
子游(しゆう)言游(げんゆう) … 姓は言(げん)、名は偃(えん)、字は子游。武城の町の宰(長官)となる。孔子より四十五歳若い。「論語」の登場人物|論語、素読会
子夏(しか) … 商(しょう)。姓は卜(ぼく)、名は「商」、字(あざな)は「子夏」。孔子より四十四歳年下。衛の人。つつましやかでまじめな人柄で、また消極的だったらしい。「論語」の登場人物|論語、素読会
子游曰わく、子夏の門人小子、洒掃応対進退に当りては、則ち可なり。抑末なり。之に本づくれば則ち無し。之を如何。子夏之を聞きて曰わく、噫、言游過てり。君子の道、孰れをか先に伝え、孰れをか後に倦まん。諸を草木の区して以て別つに譬う。君子の道は、焉んぞ誣うべけんや。始有り卒有る者は、其れ唯聖人か。|「論語」子張第十九12
子游曰、子夏之門人小子、当洒掃応対進退、則可矣。抑末也。本之則無。如之何。子夏聞之曰、噫、言游過矣。君子之道、孰先伝焉、孰後倦焉。譬諸草木区以別矣。君子之道、焉可誣也。有始有卒者、其唯聖人乎。
「小子」(しょうし)は目上の者や師が、後輩を呼ぶ語。「洒掃」(さいそう)は水をまき、ほうきではき清める。「進退」(しんたい)は立ち居振る舞い、挙措動作。「可」(か)は…できる、…しうる。「則」(すなわち)は…は(〜なのである)と判断の強調として訳す。「末」(すえ)は物事の重要で無い部分。「本」(もとづく)は根源を究める、追求する。「如何」(いかん)はどのようにしようか、いかにすればよいか。「君子」(くんし)は徳の高いりっぱな人物、人の上に立つ立派な人、リーダー。「道」(みち)は道理、道義、あるべき姿。『道』とは?|論語、素読会 「倦」(うむ)は飽きる、おこたる(懈)、うむ。「区」(くす)は分別する、より分ける。「譬」(たとえる)はひきあいに出して説明する、なぞらえる。「焉」(いずくんぞ)はどうして…であろうか(いや…ではない)。「誣」(しいる)は歪曲する、ゆがめる。「卒」(おわる)は終了する、尽きはてる。「聖人」(せいじん)は高い知徳を身につけた理想的な人物。
子游が言う、子夏の門人たちは掃除や応対、立ち居振る舞いについてはよくできている。しかしそれは、そもそも重要ではない。彼らが根源を究めているかといえばそうではない。これはどうであろうかと。子夏がこれを聞いて言う、あぁ、言游(子游)は間違っていると。君子・人の上に立つ立派なリーダーの道義、リーダーのあるべき姿は、何を先に伝え、何を後回しにするかということであろうか。(弟子に物事を伝えるというのは)例えば草木を区別してより分けるようなものだ。君子の道義は歪曲されてはならない。始めが明確にあり終わりが明確である人がいるとすれば、それはただ聖人だけだろう。
【解説】
子游は子夏とほぼ同じ歳ですが、子夏の弟子についてこのようなことを言ったのはどういう経緯だったのでしょう。当人の前で言ったのではないと想像できますが、子游の本意は伝わってきません。伝聞であるという点、伝えた人の意図も気になります。
これを聞いた子夏は、それを伝えてきた者、周りに居る者に聞こえるように話します。「君子之道」は君子の道義、君子のあるべき姿と解釈しました。掃除や応対、立ち居振る舞いと、学びの本質を教えるのに順序など無い。とすることで次の草木を区別するようなものだという例えに繋げます。草木を区別して分けるというのは、それぞれの弟子によって教える順序を変えると捉えられます。このような君子の道義を歪曲すべきではないと子夏は言っているのだと思います。もし、子游が言うように順序立てて教えられるとすれば、それは相手が聖人である場合だけだろうと締めているのです。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九11< | >子張第十九13
【原文・白文】
子游曰、子夏之門人小子、当洒掃応対進退、則可矣。抑末也。本之則無。如之何。子夏聞之曰、噫、言游過矣。君子之道、孰先伝焉、孰後倦焉。譬諸草木区以別矣。君子之道、焉可誣也。有始有卒者、其唯聖人乎。
<子游曰、子夏之門人小子、當洒掃應對進退、則可矣。抑末也。本之則無。如之何。子夏聞之曰、噫、言游過矣。君子之道、孰先傳焉、孰後倦焉。譬諸草木區以別矣。君子之道、焉可誣也。有始有卒者、其唯聖人乎。>
(子游曰わく、子夏の門人小子、洒掃応対進退に当りては、則ち可なり。抑末なり。之に本づくれば則ち無し。之を如何。子夏之を聞きて曰わく、噫、言游過てり。君子の道、孰れをか先に伝え、孰れをか後に倦まん。諸を草木の区して以て別つに譬う。君子の道は、焉んぞ誣うべけんや。始有り卒有る者は、其れ唯聖人か。)
【読み下し文】
子游(しゆう)曰(い)わく、子夏(しか)の門人(もんじん)小子(しょうし)、洒掃(さいそう)応対(おうたい)進退(しんたい)に当(あた)りては、則(すなわ)ち可(か)なり。抑(そもそも)末(すえ)なり。之(これ)に本(もと)づくれば則(すなわ)ち無(な)し。之(これ)を如何(いかん)。子夏(しか)之(これ)を聞(き)きて曰(い)わく、噫(ああ)、言游(げんゆう)過(あやま)てり。君子(くんし)の道(みち)は、孰(いず)れをか先(さき)に伝(つた)え、孰(いず)れをか後(のち)に倦(う)まん。諸(これ)を草木(そうもく)の区(く)して以(もっ)て別(わか)つに譬(たと)う。君子(くんし)の道(みち)は、焉(いずく)んぞ誣(し)うべけんや。始(はじめ)有(あ)り卒(おわり)有(あ)る者(もの)は、其(そ)れ唯(ただ)聖人(せいじん)か。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九11< | >子張第十九13