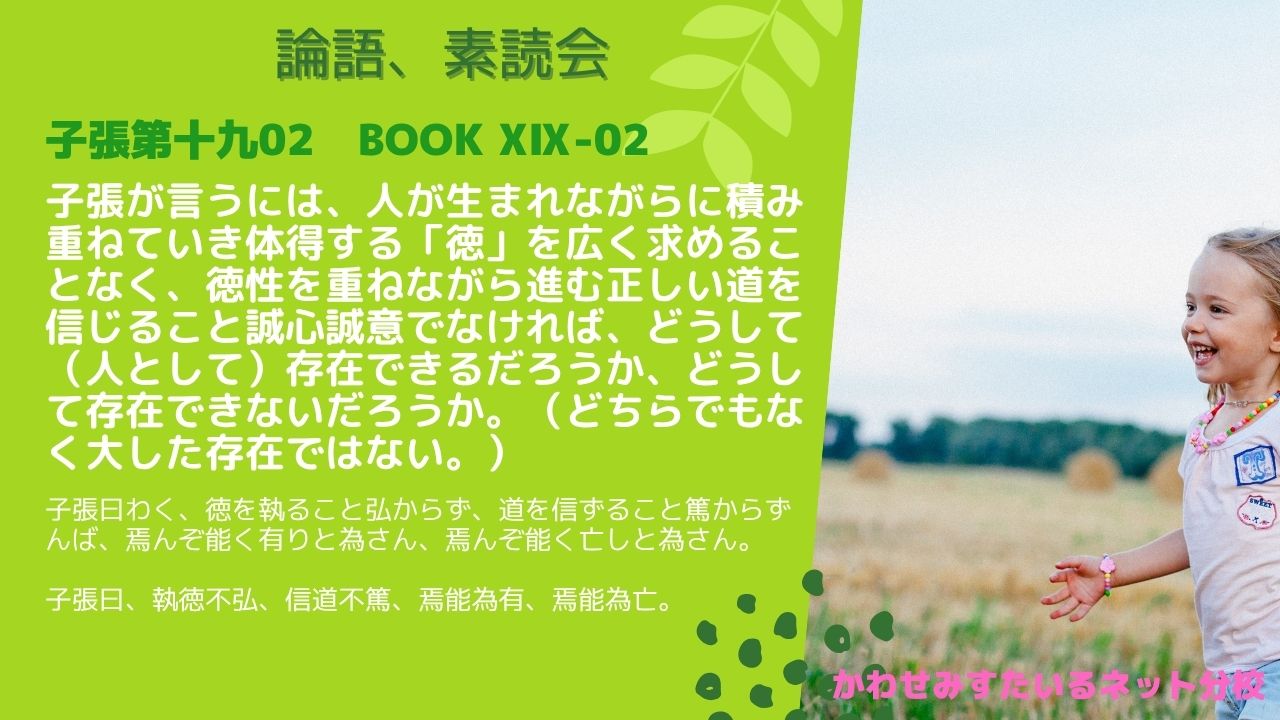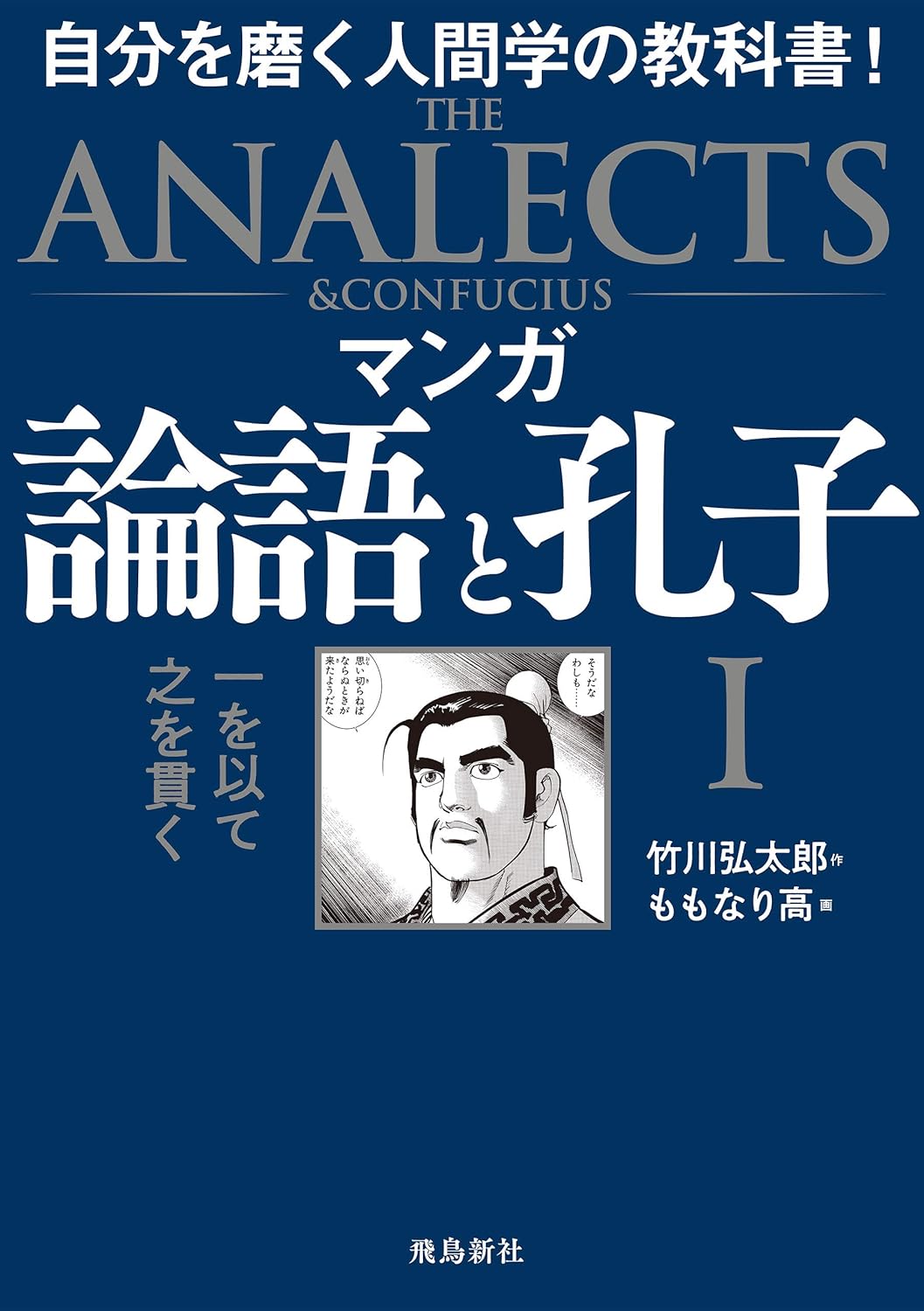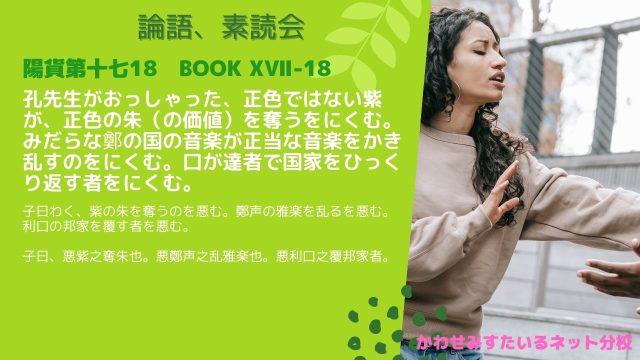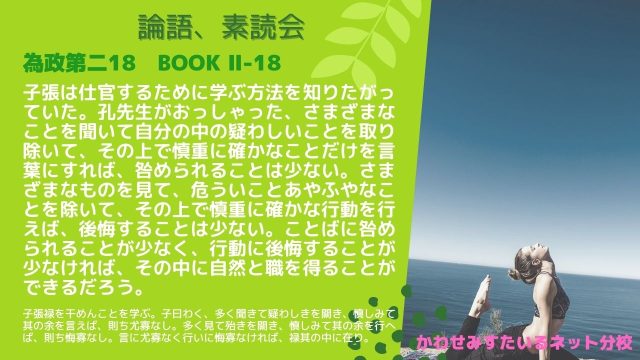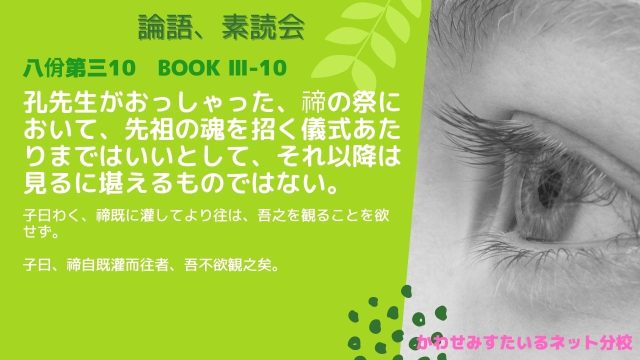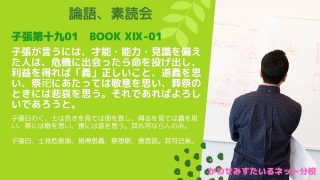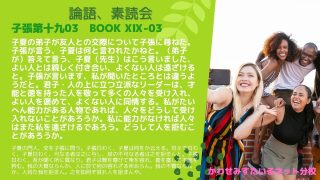子張が言うには、人が生まれながらに積み重ねていき体得する「徳」を広く求めることなく、徳性を重ねながら進む正しい道を信じること誠心誠意でなければ、どうして(人として)存在できるだろうか、どうして存在できないだろうか。(どちらでもなく大した存在ではない。)|「論語」子張第十九02
【現代に活かす論語】
人が生まれながら重ねていく徳性を広く求め、人が進む正しい道を心から信じるべきである。
【解釈】
子張(しちょう) … 姓は顓孫(せんそん)、名は師(し)、字は子張(しちょう)。孔子より四十八歳若い。「論語」の登場人物|論語、素読会
子張曰わく、徳を執ること弘からず、道を信ずること篤からずんば、焉んぞ能く有りと為さん、焉んぞ能く亡しと為さん。|「論語」子張第十九02
子張曰、執徳不弘、信道不篤、焉能為有、焉能為亡。
「執」(とる)は選びとる。「徳」(とく)は人が生まれながらに積み重ねていき体得したもの、人の道理など。『徳』とは?|論語、素読会 「弘」(ひろい)は広大なさま、おおきい。道」(みち)はひとが生まれながらにして徳性を重ねながら進む道。正しい道。『道』とは?|論語、素読会 「篤」(おつい)は誠を尽くす、まごころをこめる。「焉」(いずくんぞ)はどうして…であろうか。「能」(よく)は…できる、…しうる、…られる。「亡」(なし)は存在しない。
子張が言うには、人が生まれながらに積み重ねていき体得する「徳」を広く求めることなく、徳性を重ねながら進む正しい道を信じること誠心誠意でなければ、どうして(人として)存在できるだろうか、どうして存在できないだろうか。(どちらでもなく大した存在ではない。)
【解説】
「焉んぞ能く有りと為さん、焉んぞ能く亡しと為さん。」こちらの解釈は、文献の解釈に頼ります。有と亡の対比なので、人としての存在と解釈しました。有りと為さん、亡しと為さん。で締めていますので、大した存在ではないという解釈です。
「徳」は範囲を狭めることなく、「道」は心から信じるとよい。これが子張が伝えたかったことです。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九01< | >子張第十九03
【原文・白文】
子張曰、執徳不弘、信道不篤、焉能為有、焉能為亡。
<子張曰、執德不弘、信道不篤、焉能爲有、焉能爲亡。>
(子張曰わく、徳を執ること弘からず、道を信ずること篤からずんば、焉んぞ能く有りと為さん、焉んぞ能く亡しと為さん。)
【読み下し文】
子張(しちょう)曰(い)わく、徳(とく)を執(と)ること弘(ひろ)からず、道(みち)を信(しん)ずること篤(あす)からずんば、焉(いずく)んぞ能(よ)く有(あ)りと為(な)さん、焉(いずく)んぞ能(よ)く亡(な)しと為(な)さん。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九01< | >子張第十九03