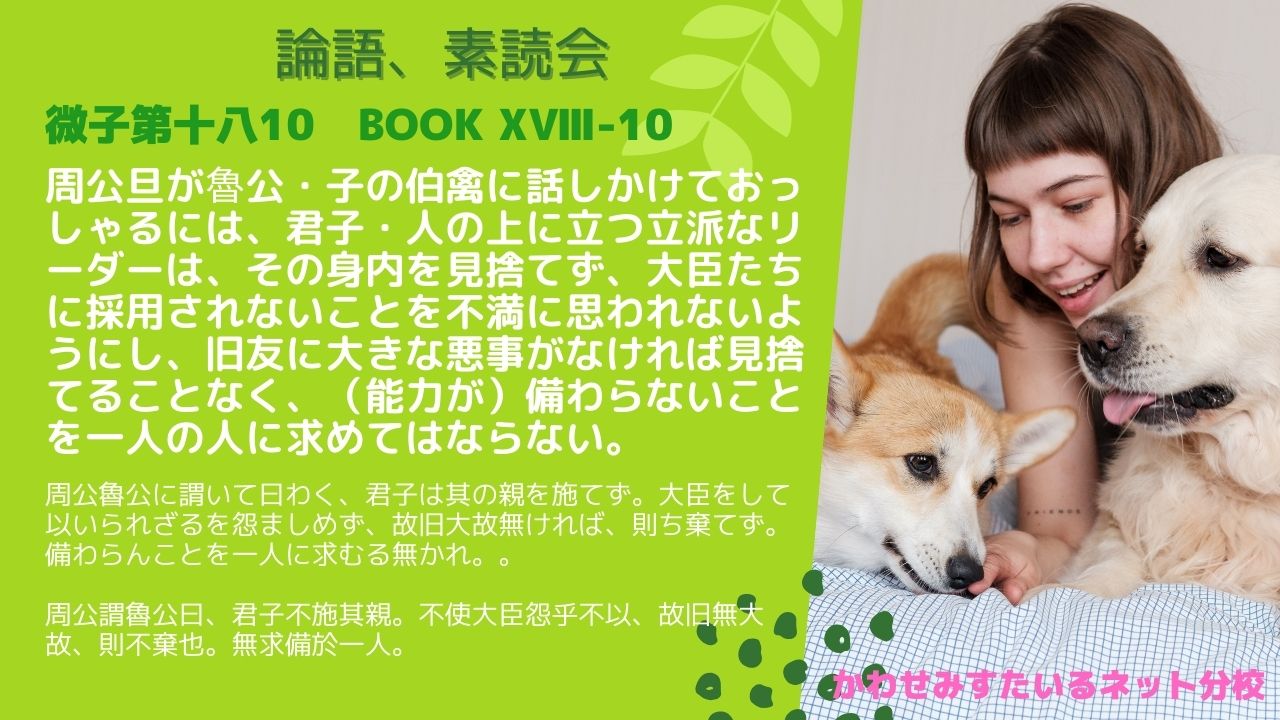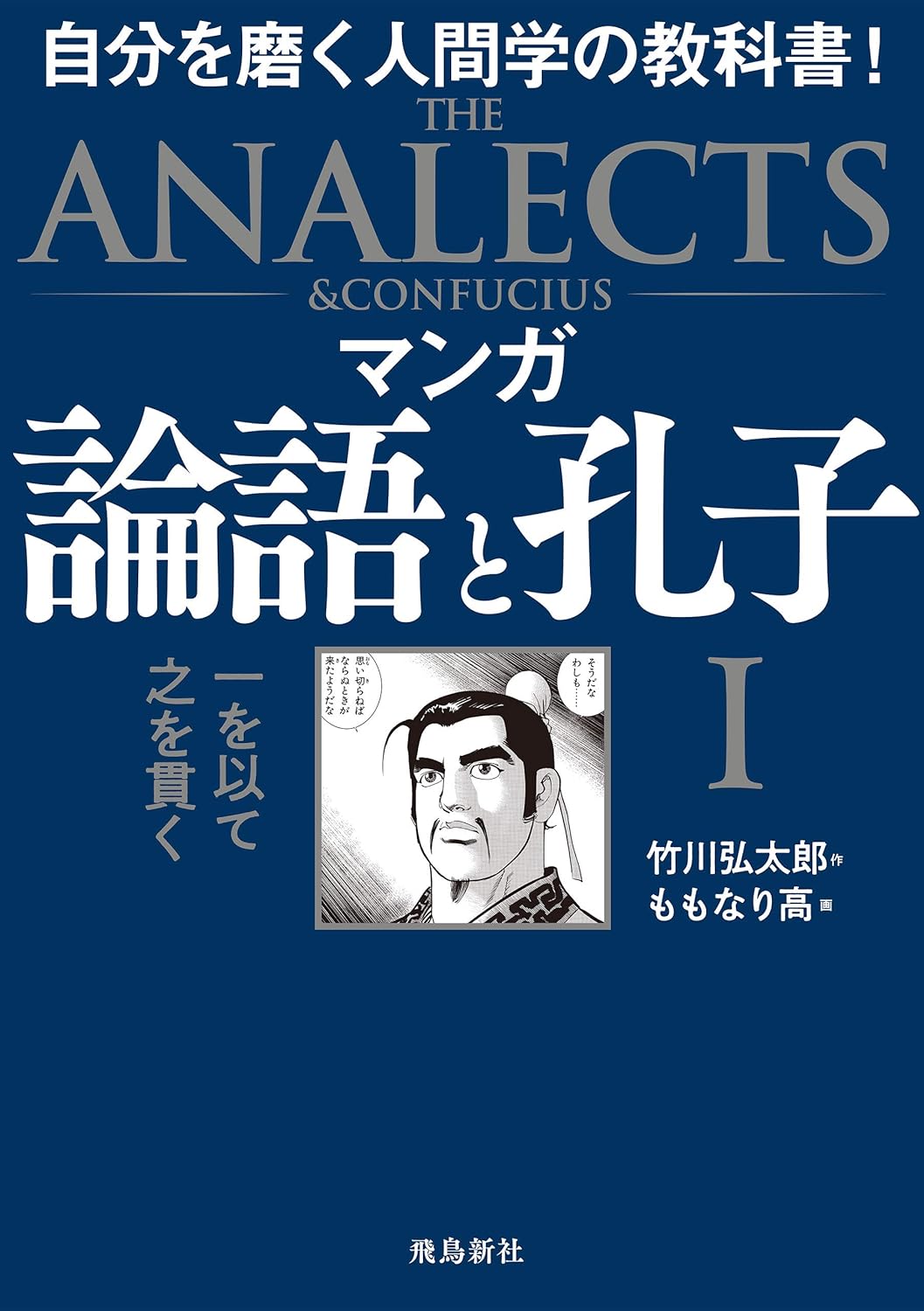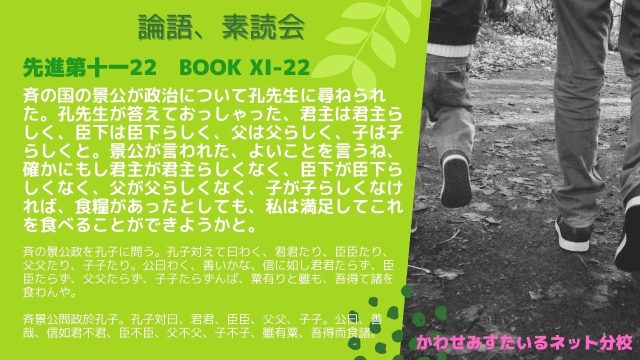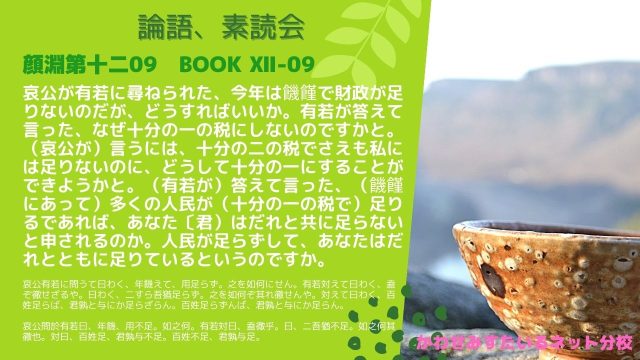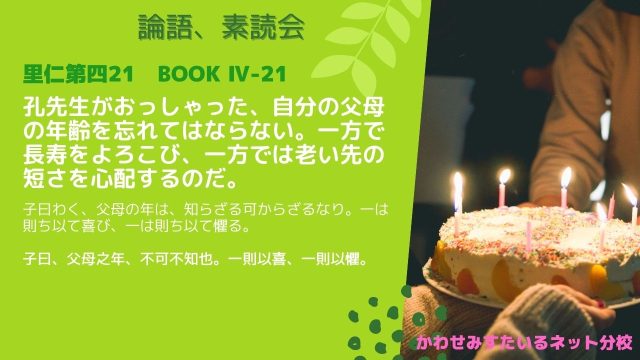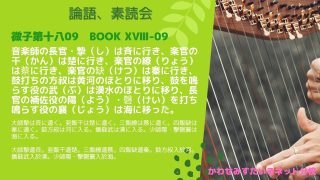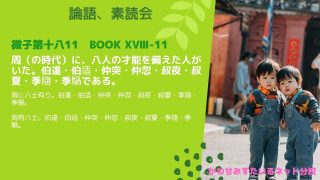周公旦が魯公・子の伯禽に話しかけておっしゃるには、君子・人の上に立つ立派なリーダーは、その身内を見捨てず、大臣たちに採用されないことを不満に思われないようにし、旧友に大きな悪事がなければ見捨てることなく、(能力が)備わらないことを一人の人に求めてはならない。|「論語」微子第十八10
【現代に活かす論語】
人の上に立つ立派なりーダーは、身内を見捨てず、採用不採用で不満が出ないようにし、大きな悪事がなければ旧友を見捨てず、人の納涼句以上のことを求めてはならない。
【解釈】
周公(しゅうこう) … 周公旦。名は旦(たん)。周の文王の子、武王の弟。武王の子の成王を補佐して、制度や儀式・礼楽などを定めたが自らは天子の位に即こうとしなかった。魯の国の始祖。孔子の理想とする人物。「論語」の登場人物|論語、素読会
魯公(ろこう) … 周公旦(しゅうこうたん)の長子の伯禽(はくきん)。はじめ周公(しゅうこう・周公旦)が魯(ろ)の国に封ぜられたが、周室の政務に追われていたので、代わって伯禽に魯を治めさせ、魯の祖となった。「論語」の登場人物|論語、素読会
周公魯公に謂いて曰わく、君子は其の親を施てず。大臣をして以いられざるを怨ましめず、故旧大故無ければ、則ち棄てず。備わらんことを一人に求むる無かれ。|「論語」微子第十八10
周公謂魯公曰、君子不施其親。不使大臣怨乎不以、故旧無大故、則不棄也。無求備於一人。
「謂」(いう)はつげる、話しかける。「君子」(くんし)は徳の高いりっぱな人物、人の上に立つ立派な人、リーダー。「親」(しん)は身内、親類。「施」(すてる)は見捨てる、忘れさる。「大臣」(だいじん)は高い官職についている臣下。「以」(もちいる)は使用する、採用する。「怨」(うらむ)は不満の思いを抱く、とがめる。「故旧」(こきゅう)は以前からの知人、旧友。「大故」(たいこ)は大きな悪事、大罪。「棄」(すてる)はうちすてる。「備」(そなわる)はととのう、十分となる。
周公旦が魯公・子の伯禽に話しかけておっしゃるには、君子・人の上に立つ立派なリーダーは、その身内を見捨てず、大臣たちに採用されないことを不満に思われないようにし、旧友に大きな悪事がなければ見捨てることなく、(能力が)備わらないことを一人の人に求めてはならない。
【解説】
文献によれば、周公旦が子の伯禽に魯の国を治めさせた際に伝えた言葉です。この前後数章句は主語がなく、孔子が話した言葉かどうかは定かではありませんが、史実を伝えていると考えられます。
「論語」参考文献|論語、素読会
微子第十八09< | >微子第十八11
【原文・白文】
周公謂魯公曰、君子不施其親。不使大臣怨乎不以、故旧無大故、則不棄也。無求備於一人。
<周公謂魯公曰、君子不施其親。不使大臣怨乎不以、故舊無大故、則不棄也。無求備於一人。>
(周公魯公に謂いて曰わく、君子は其の親を施てず。大臣をして以いられざるを怨ましめず、故旧大故無ければ、則ち棄てず。備わらんことを一人に求むる無かれ。)
【読み下し文】
周公(しゅうこう)魯公(ろこう)に謂(い)いて曰(のたま)わく、君子(くんし)は其(そ)の親(しん)を施(す)てず。大臣(だいじん)をして以(もち)いられざるを怨(うら)ましめず、故旧(こきゅう)大故(たいこ)無(な)ければ、則(すなわ)ち棄(す)てず。備(そな)わらんことを一人(いちにん)に求(もと)むる無(な)かれ。
「論語」参考文献|論語、素読会
微子第十八09< | >微子第十八11