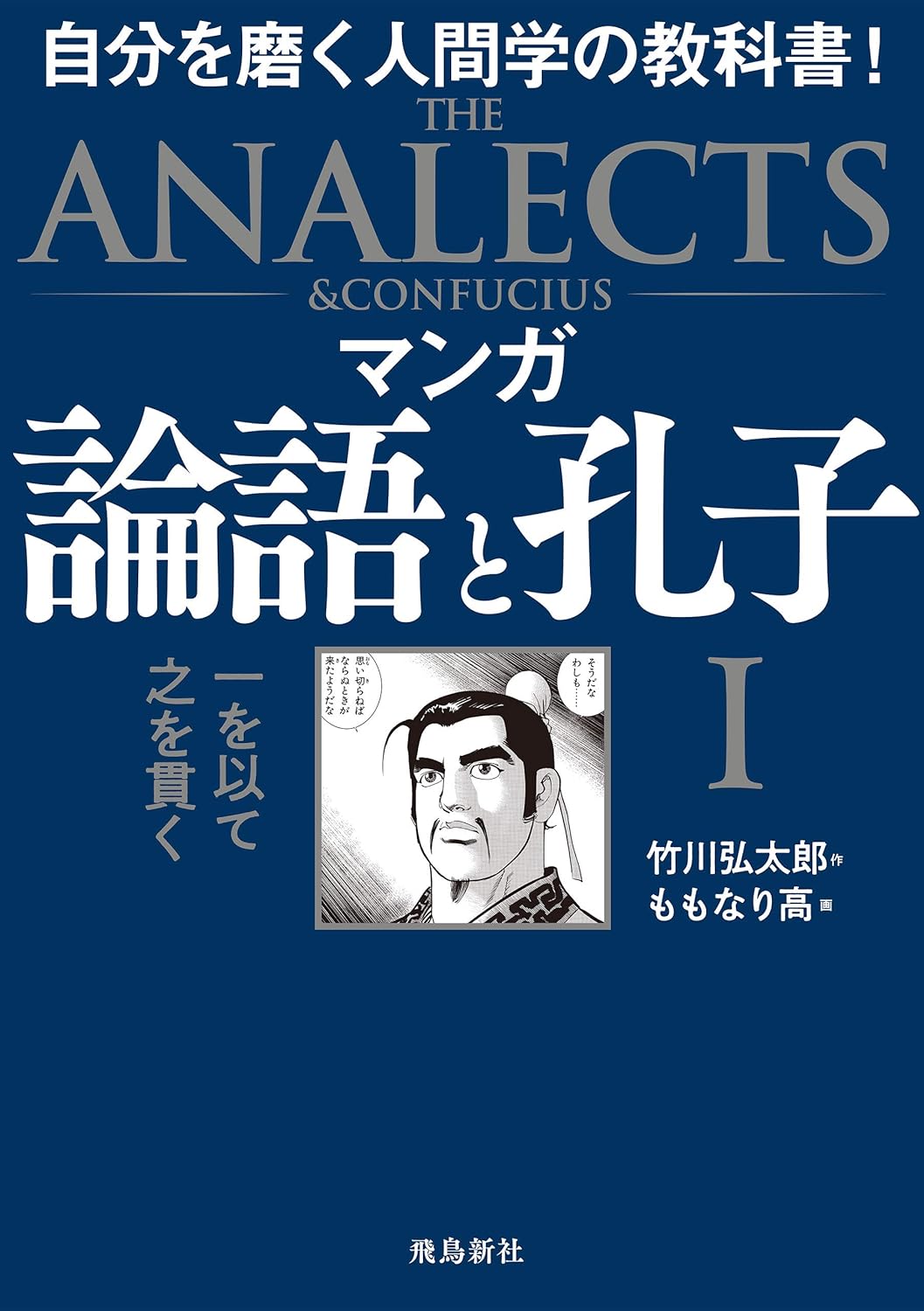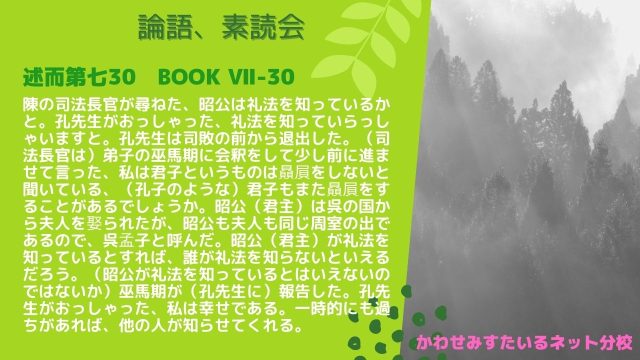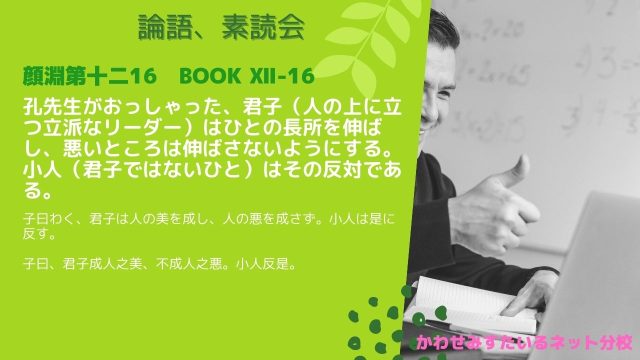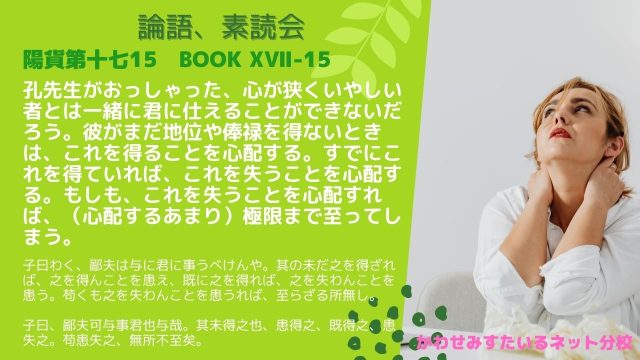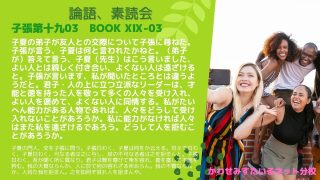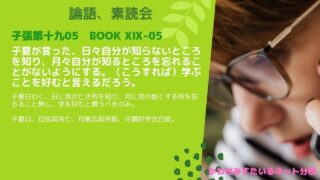子夏が言うには、技芸といえども必ず見るべきものはある。遠大なこと(志)を達成するには、(細かいことが)支障となって進まないのを恐れる。このことを以て、君子・人の上に立つ立派なリーダーは(技芸などの小さなことを見ることを)しないのである。|「論語」子張第十九04
【現代に活かす論語】
人の上に立つ立派なリーダーは、自分自身が細かいことに携わることが支障となって物事が進まないのを恐れるので、細かいことはしないのです。
【解釈】
子夏(しか) … 商(しょう)。姓は卜(ぼく)、名は「商」、字(あざな)は「子夏」。孔子より四十四歳年下。衛の人。つつましやかでまじめな人柄で、また消極的だったらしい。「論語」の登場人物|論語、素読会
子夏曰わく、小道と雖も、必ず観るべき者有り。遠きを致さんには泥まんことを恐る。是を以て君子は為さざるなり。|「論語」子張第十九04
子夏曰、雖小道、必有可観者焉。致遠恐泥。是以君子不為也。
「小道」(しょうどう)は儒家から見て儒家以外の学説や技芸をさげすんで言う言葉。〔漢辞海〕「小道」(しょうどう)は各種の技芸ごとをいう。朱注に農・圃・医・卜の属とある。茶道・華道・碁・将棋などの技芸ごと。〔新釈漢文大系〕「道」(みち)は技芸、わざ。「者」(もの)は人・事・物などを表す。「もの」「こと」と訓読する。「遠」(とおい)は長期の、遠大な。「泥」(なずまん)は支障となって進まない。「君子」(くんし)は徳の高いりっぱな人物、人の上に立つ立派な人、リーダー。
子夏が言うには、技芸といえども必ず見るべきものはある。遠大なこと(志)を達成するには、(細かいことが)支障となって進まないのを恐れる。このことを以て、君子・人の上に立つ立派なリーダーは(技芸などの小さなことを見ることを)しないのである。
【解説】
子夏が伝えようとしているのは、孔子の教えです。
『漢辞海』では「小道」の意味の中に「蔑み(さげすみ)」が含まれると説明します。この章句を解釈した過去の文献を参考に判断されたのだと推察しますが、この章句を丁寧に解釈すると、蔑みとは違った感情を受け取ることもできます。
まず、「君子は器ならず|「論語」為政第二12」という章句にあるように、君子は特定の用途に限られるような器(器量)であってはならない、様々な能力を兼ね備えるべき、もしくは、細かい能力に拘らないという孔子の教えがあります。
その上で、孔子が目指す君子の「道」、周代から伝わる「道」に対して、「小道」とはどんなものでしょうか。遠大なことを為すためには、細かいことが支障となって進まないのを恐れるという言葉から、「小道」は関わると支障になる細かいことだと分かります。
この「小道」において、「道」を〔道義〕と解釈すると孔子が目指す王道ではなく、些細な道義を指すことになります。「道」を〔技芸〕とすると、君子には敢えて必要のない、様々な技芸を指します。文献によれば、この技芸は、農・圃・医・卜あるいは茶道・華道・碁・将棋などを指すそうです。
「燓遅稼を学ばんと請う|「論語」子路第十三04」こちらの章句では、君子を目指す者が、礼・儀・信を学べば、人材や労働力となる人民が集まり国が豊かになるので、君子自らが農業を学ぶ必要はない、農家や農夫には敵わないと言っています。農に対する尊敬の念を感じます。
以上の点から、私は小道を技芸と捉え、そこに蔑みの感情よりむしろ尊敬の気持ちを含むと解釈します。みなさんは、いかがでしょうか。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九03< | >子張第十九05
【原文・白文】
子夏曰、雖小道、必有可観者焉。致遠恐泥。是以君子不為也。
<子夏曰、雖小道、必有可觀者焉。致遠恐泥。是以君子不爲也。>
(子夏曰わく、小道と雖も、必ず観るべき者有り。遠きを致さんには泥まんことを恐る。是を以て君子は為さざるなり。)
【読み下し文】
子夏(しか)曰(い)わく、小道(しょうどう)と雖(いえど)も、必(かなら)ず観(み)るべき者(もの)有(あ)り。遠(とお)きを致(いた)さんには泥(なず)まんことを恐(おそ)る。是(ここ)を以(もっ)て君子(くんし)は為(な)さざるなり。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九03< | >子張第十九05