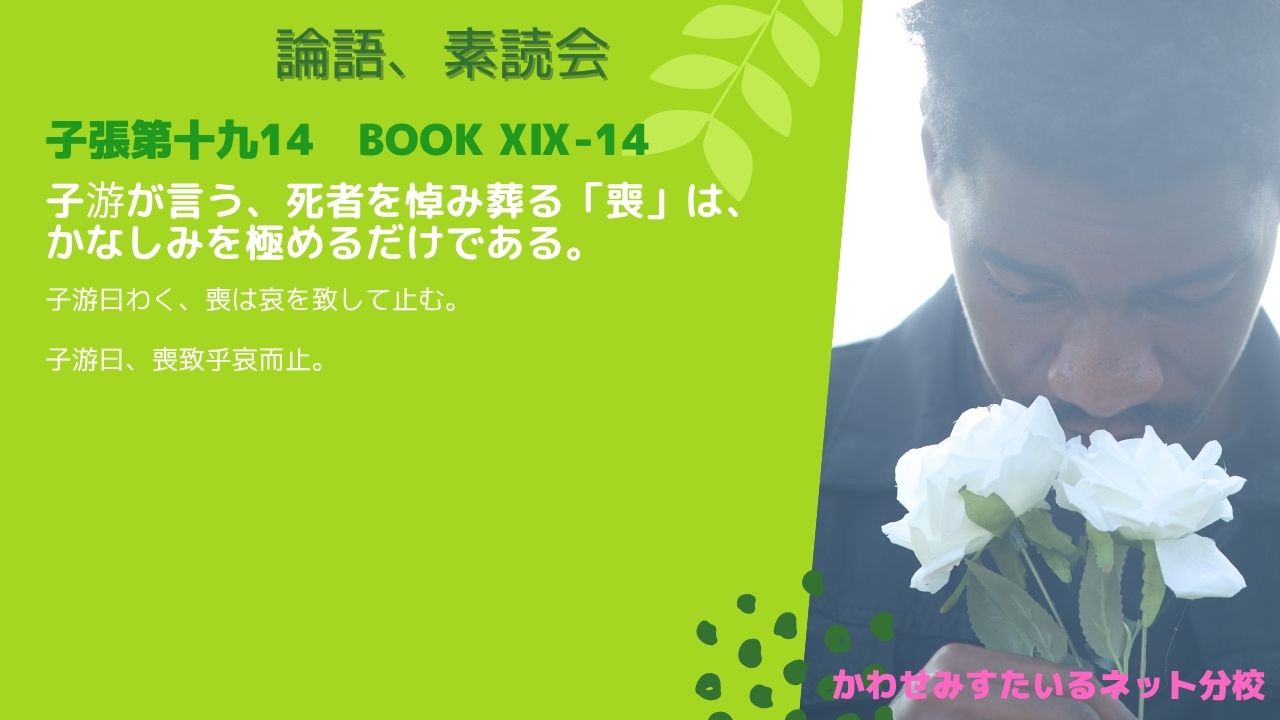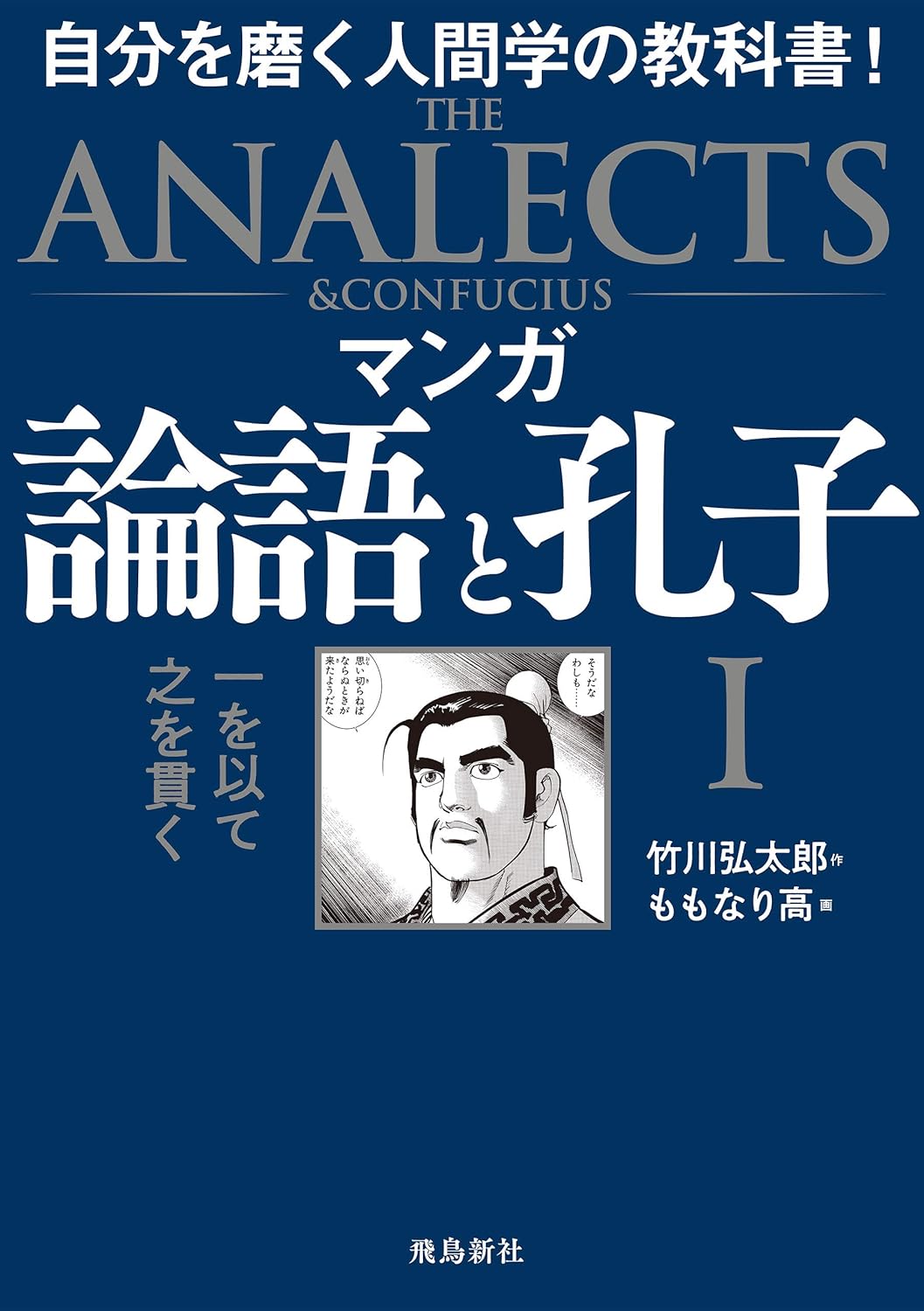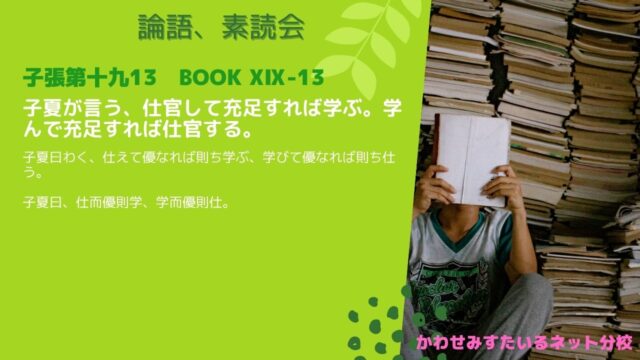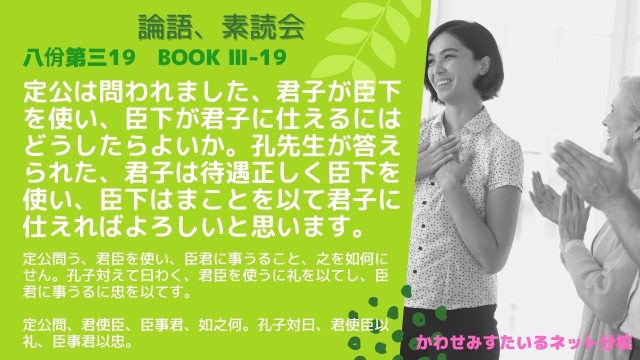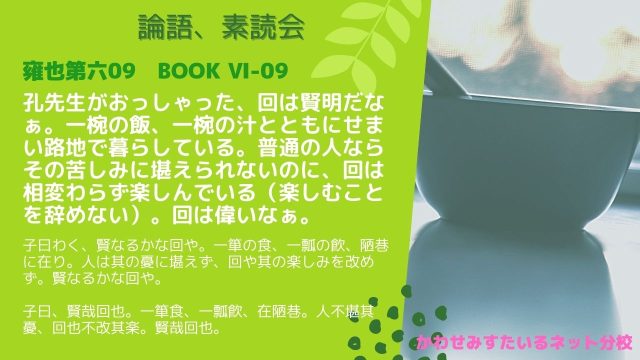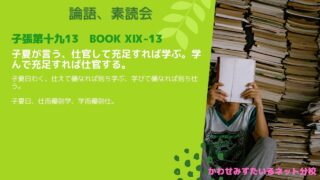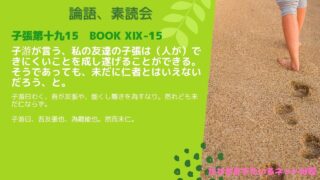子游が言う、死者を悼み葬る「喪」は、かなしみを極めるだけである。|「論語」子張第十九14
【現代に活かす論語】
家族、親戚の死にあたっては、ただ悲しみを深めるだけです。形式にとらわれることはありません。
【解釈】
子游(しゆう) … 言游(げんゆう)。姓は言(げん)、名は偃(えん)、字は子游。武城の町の宰(長官)となる。孔子より四十五歳若い。「論語」の登場人物|論語、素読会
子游曰わく、喪は哀を致して止む。|「論語」子張第十九14
子游曰、喪致乎哀而止。
「喪」(も)は死者を悼み葬る儀式、またその期間、葬式。「哀」(あい)はかなしみ嘆く。「致」(いたす)は到達する、極める。「止」(やむ)は文末に置き、確定・決意を表すことば。
子游が言う、死者を悼み葬る「喪」は、かなしみを極めるだけである。
【解説】
「礼は其の奢らんよりは寧ろ倹なれ|「論語」八佾第三04」では、孔子は、「お葬式は形式が整うよりむしろ心から悲しむようにしなさい。」と林放という人物に伝えています。この章句も同じでしょう。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九13< | >子張第十九15
【原文・白文】
子游曰、喪致乎哀而止。
(子游曰わく、喪は哀を致して止む。)
【読み下し文】
子游(しゆう)曰(い)わく、喪(も)は哀(あい)を致(いた)して止(や)む。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九13< | >子張第十九15