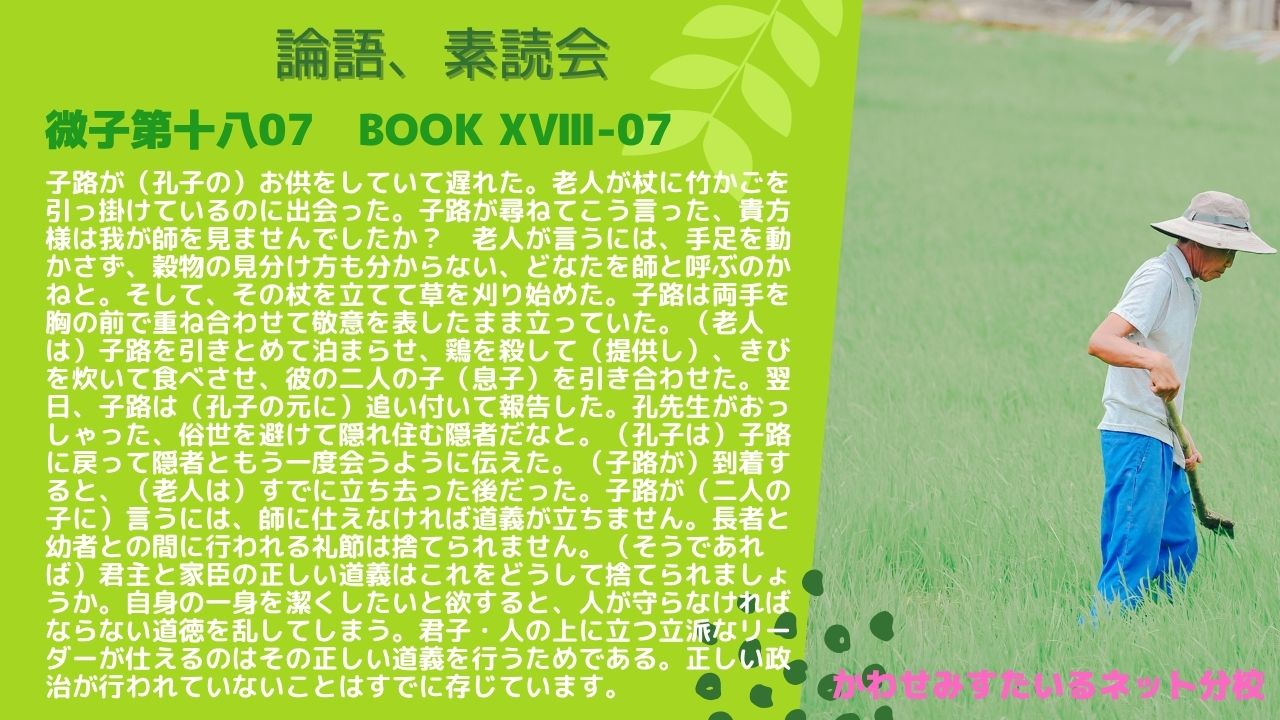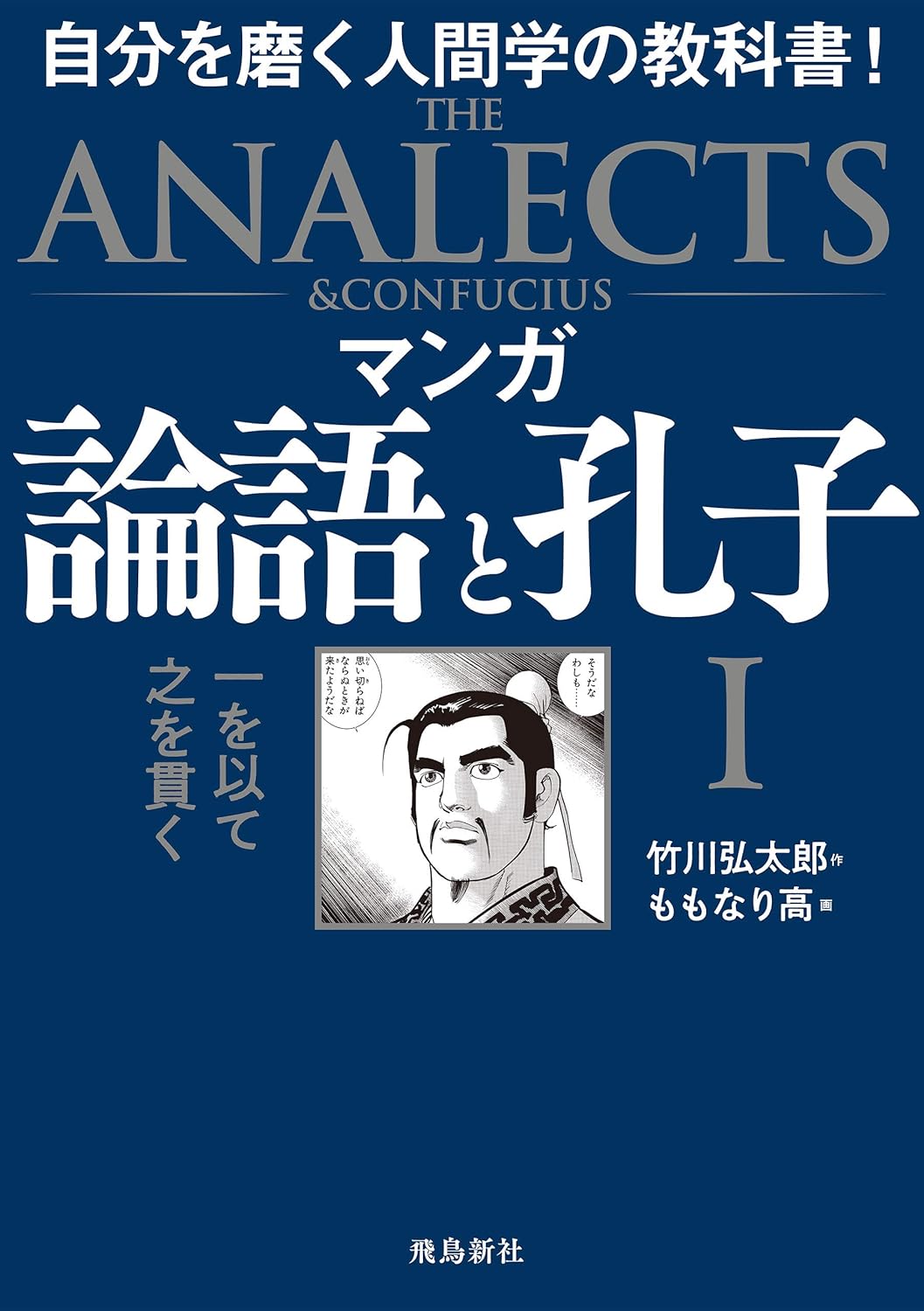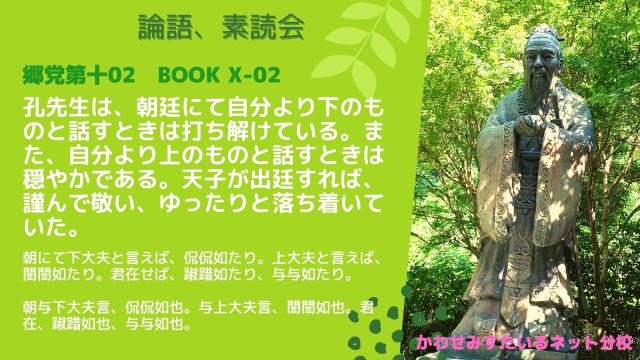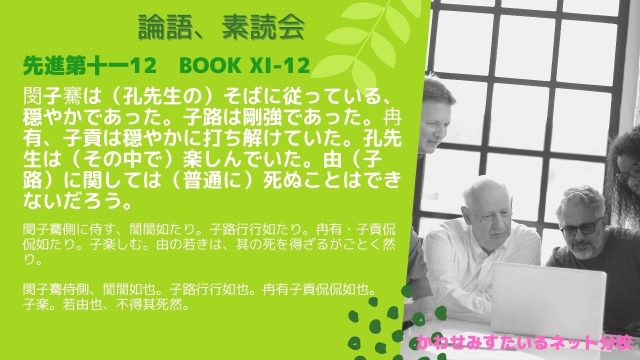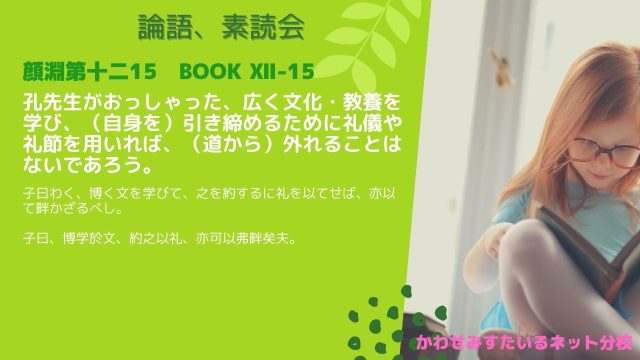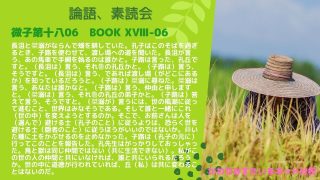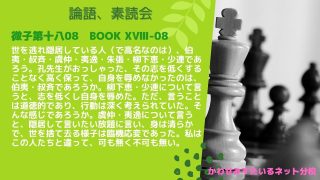子路が(孔子の)お供をしていて遅れた。老人が杖に竹かごを引っ掛けているのに出会った。子路が尋ねてこう言った、貴方様は我が師を見ませんでしたか? 老人が言うには、手足を動かさず、穀物の見分け方も分からない、どなたを師と呼ぶのかねと。そして、その杖を立てて草を刈り始めた。子路は両手を胸の前で重ね合わせて敬意を表したまま立っていた。(老人は)子路を引きとめて泊まらせ、鶏を殺して(提供し)、きびを炊いて食べさせ、彼の二人の子(息子)を引き合わせた。翌日、子路は(孔子の元に)追い付いて報告した。孔先生がおっしゃった、俗世を避けて隠れ住む隠者だなと。(孔子は)子路に戻って隠者ともう一度会うように伝えた。(子路が)到着すると、(老人は)すでに立ち去った後だった。子路が(二人の子に)言うには、師に仕えなければ道義が立ちません。長者と幼者との間に行われる礼節は捨てられません。(そうであれば)君主と家臣の正しい道義はこれをどうして捨てられましょうか。自身の一身を潔くしたいと欲すると、人が守らなければならない道徳を乱してしまう。君子・人の上に立つ立派なリーダーが仕えるのはその正しい道義を行うためである。正しい政治が行われていないことはすでに存じています。|「論語」微子第十八07
【現代に活かす論語】
人の上に立つ立派なリーダーが組織に使えるのは、正しいことを行うためです。
【解釈】
子路(しろ) … 姓は仲(ちゅう)、名は由(ゆう)、字は子路(しろ)・季路(きろ)。孔子より九歳若い。孔子のボディガード役を果たした。「論語」の登場人物|論語、素読会
子路従いて後れたり。丈人の杖を以て蓧を荷うに遇う。子路問うて曰わく、子夫子を見たるか。丈人の曰わく、四体勤めず、五穀分たず。孰をか夫子と為す。其の杖を植てて芸る。子路拱して立つ。子路を止めて宿らしめ、鶏を殺し黍を為りて之を食わしめ、其の二子を見えしむ。明日子路行きて以て告ぐ。子曰わく、隠者なり。子路をして反りて之を見しむ。至れば則ち行れり。子路曰わく、仕えざれば義無し。長幼の節は、廃すべかあざるなり。君臣の義は、之を如何ぞ其れ廃せん。其の身を潔くせんと欲して大倫を乱る。君子の仕うるや、其の義を行わんとなり。道の行われざるや、已に之を知れり。|「論語」微子第十八07
子路従而後。遇丈人以杖荷蓧。子路問曰、子見夫子乎。丈人曰、四体不勤、五穀不分。孰為夫子。植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿、殺鶏為黍而食之、見其二子焉。明日子路行以告。子曰、隠者也。使子路反見之。至則行矣。子路曰、不仕無義。長幼之節、不可廃也。君臣之義、如之何其可廃之。欲潔其身而乱大倫。君子之仕也、行其義也。道之不行、已知之矣。
「従」(したがう)は人のあとにつき従う。「丈人」(じょうじん)は老人への敬称。「蓧」(あじか)は遅くて矢がらを作るのに適した竹。「荷」(になう)は背負う、肩にかつぐ。「子」(し)は男子の尊称。「夫子」(ふうし)は先生に対する尊称、孔子の尊称。「四体」(したい)は両手と両足、またからだ。四肢、四支。「勤」(つとめる)は働く、力を尽くす、いそしむ。「五穀」(ごこく)は五種の穀物。「分」(わかつ)は見分ける、判別する。「芸」(くさぎる)は除草する、くさぎる。「供」(きょうする)は両手を胸の前でかさね合わせ、敬意を表す。「止」(とどめる)は引きとめる。「宿」(やどる)は夜を過ごす、泊まる、泊める。「黍」(きび)はきび、イネ科の一年草の穀物。「二子」(にし)は二人の子。「見」(まみえる)は拝謁する。「隠者」(いんじゃ)は俗世を避けて隠れ住む人。世を避けて仕官しない人。「反」(かえる)は戻る。「義」(ぎ)は正しいこと。道義。『義』とは?|論語、素読会 「長幼」(ちょうよう)は年長者と年少者、「長幼之節」(ちょうようのせつ)は長者と幼者との間に行われる道徳で礼節のこと、序ともいう。「廃」(はいす)は捨てさる。「潔」(いさぎよい)は清く正しくする。「大倫」(たいりん)は人が守らなければならない基本的な道徳。「君子」(くんし)は徳の高いりっぱな人物、人の上に立つ立派な人、リーダー。「道」(みち)は道義。正しい政治。『道』とは?|論語、素読会
子路が(孔子の)お供をしていて遅れた。老人が杖に竹かごを引っ掛けているのに出会った。子路が尋ねてこう言った、貴方様は我が師を見ませんでしたか? 老人が言うには、手足を動かさず、穀物の見分け方も分からない、どなたを師と呼ぶのかねと。そして、その杖を立てて草を刈り始めた。子路は両手を胸の前で重ね合わせて敬意を表したまま立っていた。(老人は)子路を引きとめて泊まらせ、鶏を殺して(提供し)、きびを炊いて食べさせ、彼の二人の子(息子)を引き合わせた。翌日、子路は(孔子の元に)追い付いて報告した。孔先生がおっしゃった、俗世を避けて隠れ住む隠者だなと。(孔子は)子路に戻って隠者ともう一度会うように伝えた。(子路が)到着すると、(老人は)すでに立ち去った後だった。子路が(二人の子に)言うには、師に仕えなければ道義が立ちません。長者と幼者との間に行われる礼節は捨てられません。(そうであれば)君主と家臣の正しい道義はこれをどうして捨てられましょうか。自身の一身を潔くしたいと欲すると、人が守らなければならない道徳を乱してしまう。君子・人の上に立つ立派なリーダーが仕えるのはその正しい道義を行うためである。正しい政治が行われていないことはすでに存じています。
【解説】
この老人は、孔子とその弟子、子路のことを知っていると思います。子路もこの老人にただならぬ雰囲気を感じて敬意を以て老人の言葉を待ちます。子路の人間性を認めた老人は子路を歓待し、子ども(恐らく息子)を紹介したのでしょう。これを聞いた孔子が子路を再び老人の元に走らせたのですが、老人は不在でした。老人は隠れたのかも知れません。子路はそれを感じたのか、老人を待つのではなく、残っていた二人の子に対して、過日の老人の問い「どうして孔子を師とするのか」に答えます。長幼の節はまさに子路がこの老人に敬意を払い、老人が子路に子を紹介したことです。これを引き合いに出して、みだれた政界の道義を正すことも同じであると考えると伝えているのです。
この章句の特長は、「なぜ孔子は乱れた政治に立ち向かうのか」という問いに回答していると考えていいのではないでしょうか。またそれを、子路の言葉を通して表現しているところが大変おもしろいです。前の章句でも子路が隠者の言葉を孔子に伝えることで、孔子の心情を表現しています。隠者は世間に蔓延する諦めの雰囲気。対して孔子の志は揺るぎないことが伝わってきます。
「論語」参考文献|論語、素読会
微子第十八06< | >微子第十八08
【原文・白文】
子路従而後。遇丈人以杖荷蓧。子路問曰、子見夫子乎。丈人曰、四体不勤、五穀不分。孰為夫子。植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿、殺鶏為黍而食之、見其二子焉。明日子路行以告。子曰、隠者也。使子路反見之。至則行矣。子路曰、不仕無義。長幼之節、不可廃也。君臣之義、如之何其可廃之。欲潔其身而乱大倫。君子之仕也、行其義也。道之不行、已知之矣。
<子路從而後。遇丈人以杖荷蓧。子路問曰、子見夫子乎。丈人曰、四體不勤、五穀不分。孰爲夫子。植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿、殺雞爲黍而食之、見其二子焉。明日子路行以告。子曰、隱者也。使子路反見之。至則行矣。子路曰、不仕無義。長幼之節、不可廢也。君臣之義、如之何其可廢之。欲潔其身而亂大倫。君子之仕也、行其義也。道之不行、已知之矣。>
(子路従いて後れたり。丈人の杖を以て蓧を荷うに遇う。子路問うて曰わく、子夫子を見たるか。丈人の曰わく、四体勤めず、五穀分たず。孰をか夫子と為す。其の杖を植てて芸る。子路拱して立つ。子路を止めて宿らしめ、鶏を殺し黍を為りて之を食わしめ、其の二子を見えしむ。明日子路行きて以て告ぐ。子曰わく、隠者なり。子路をして反りて之を見しむ。至れば則ち行れり。子路曰わく、仕えざれば義無し。長幼の節は、廃すべかあざるなり。君臣の義は、之を如何ぞ其れ廃せん。其の身を潔くせんと欲して大倫を乱る。君子の仕うるや、其の義を行わんとなり。道の行われざるや、已に之を知れり。)
【読み下し文】
子路(しろ)従(したが)いて後(おく)れたり。丈人(じょうじん)の杖(つえ)を以(もっ)て蓧(あじか)を荷(にな)うに遇(あ)う。子路(しろ)問(と)うて曰(い)わく、子(し)夫子(ふうし)を見(み)たるか。丈人(じょうじん)の曰(い)わく、四体(したい)勤(つと)めず、五穀(ごこく)分(わか)たず。孰(たれ)をか夫子(ふうし)と為(な)す。其(そ)の杖(つえ)を植(た)てて芸(くさぎ)る。子路(しろ)拱(きょう)して立(た)つ。子路(しろ)を止(とど)めて宿(やど)らしめ、鶏(とり)を殺(ころ)し黍(きび)を為(つく)りて之(これ)を食(くら)わしめ、其(そ)の二子(にし)を見(まみ)えしむ。明日(みょうにち)子路(しろ)行(い)きて以(もっ)て告(つ)ぐ。子(し)曰(のたま)わく、隠者(いんじゃ)なり。子路(しろ)をして反(かえ)りて之(これ)を見(み)しむ。至(いた)れば則(すなわ)ち行(さ)れり。子路(しろ)曰(い)わく、仕(つか)えざれば義(ぎ)無(な)し。長幼(ちょうよう)の節(せつ)は、廃(はい)すべかあざるなり。君臣(くんしん)の義(ぎ)は、之(これ)を如何(いかん)ぞ其(そ)れ廃(はい)せん。其(そ)の身(み)を潔(いさぎよ)くせんと欲(ほっ)して大倫(たいりん)を乱(みだ)る。君子(くんし)の仕(つか)うるや、其(そ)の義(ぎ)を行(おこな)わんとなり。道(みち)の行(おこな)われざるや、已(すで)に之(これ)を知(し)れり。
「論語」参考文献|論語、素読会
微子第十八06< | >微子第十八08