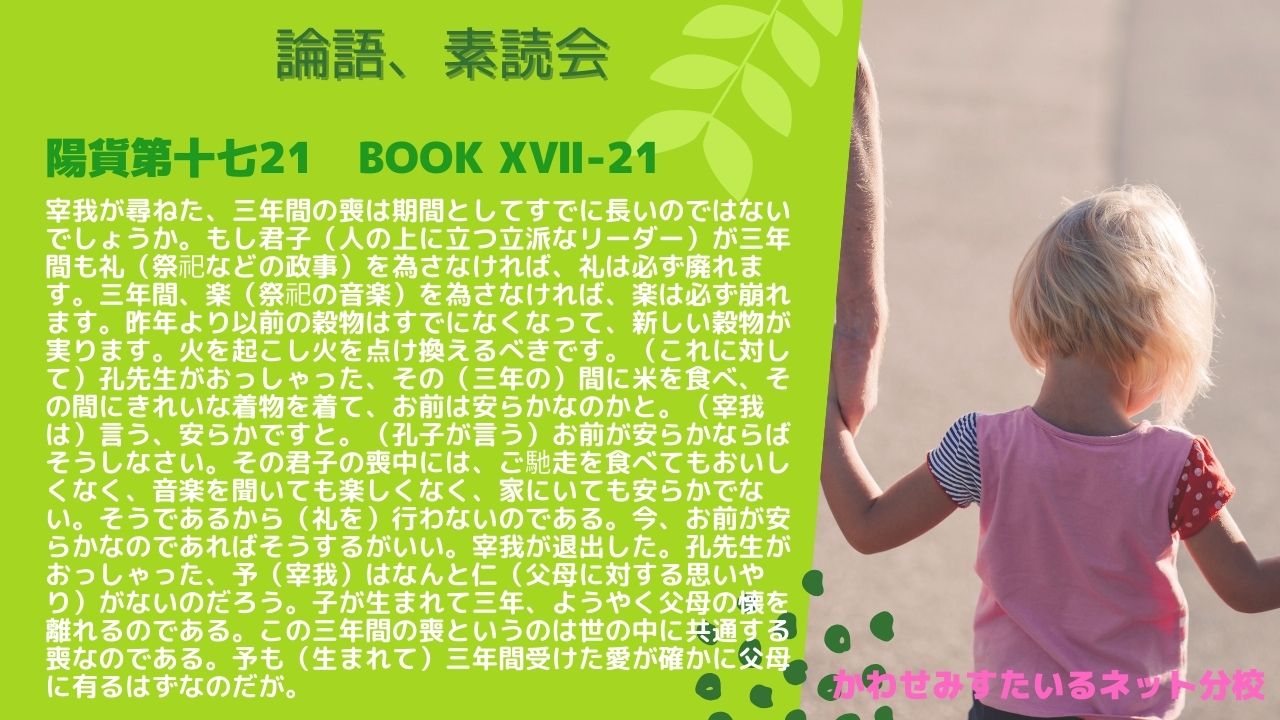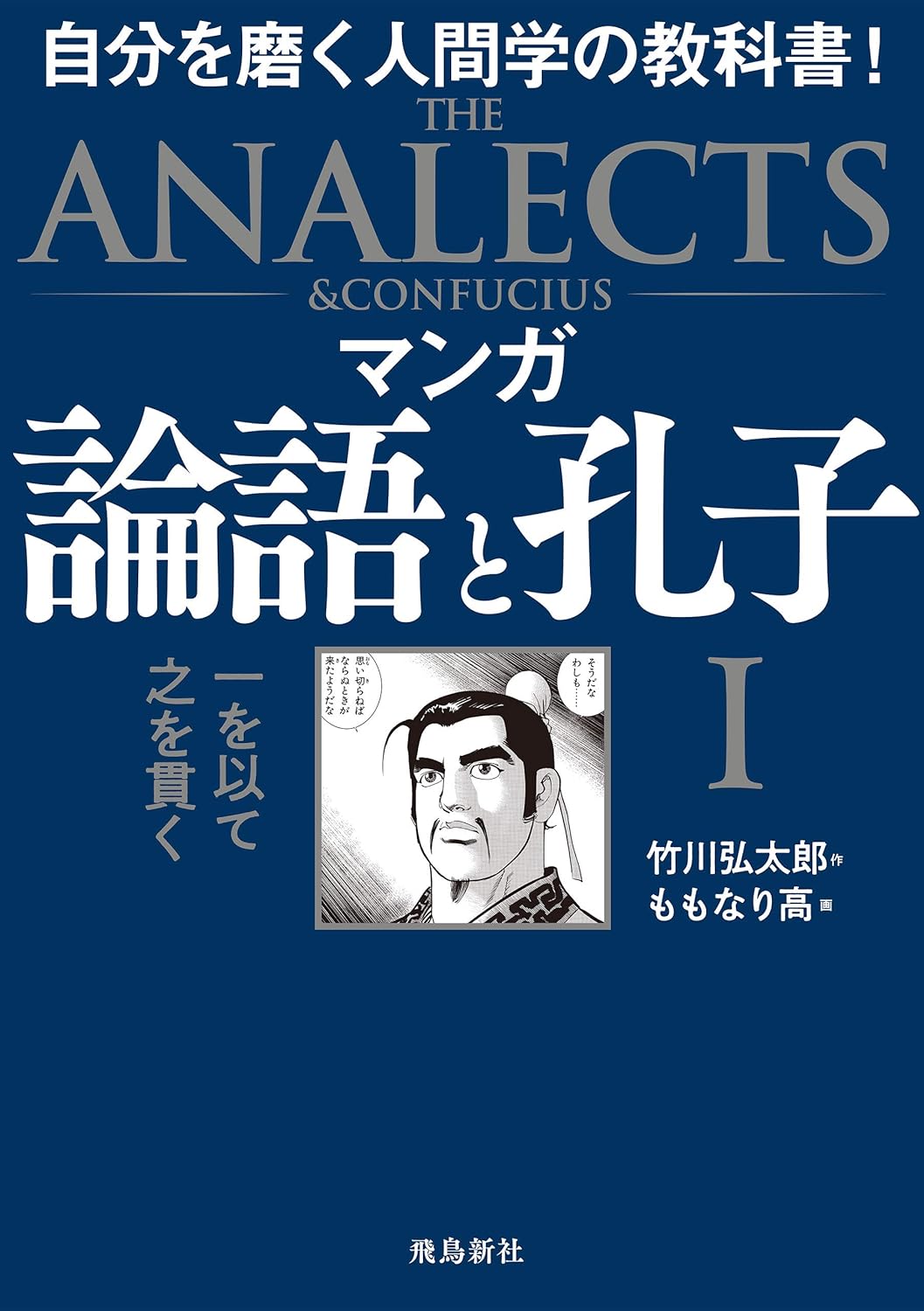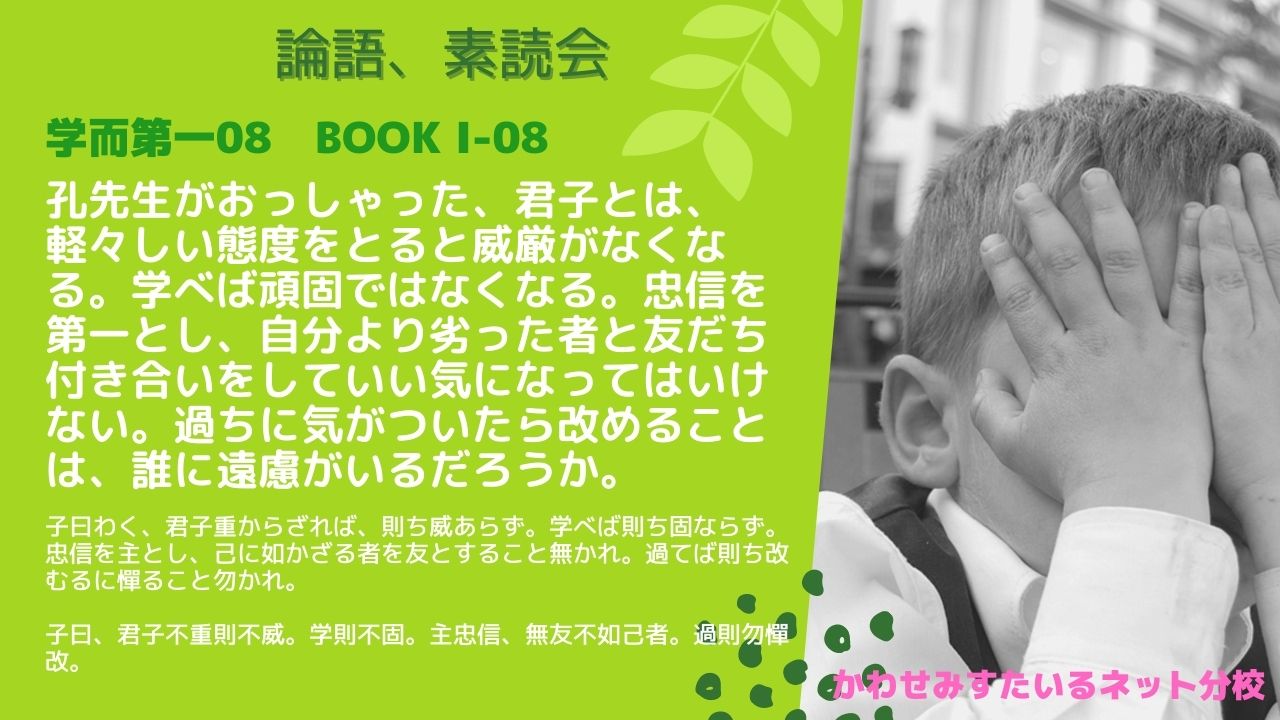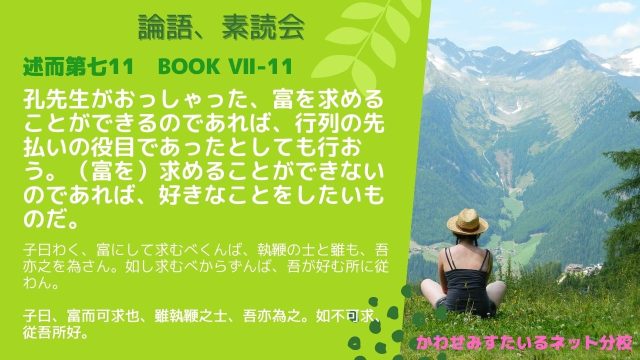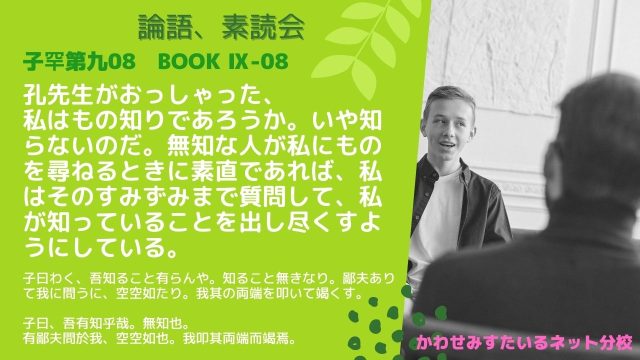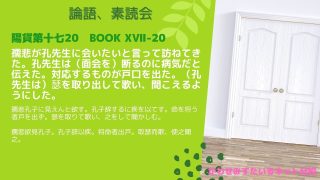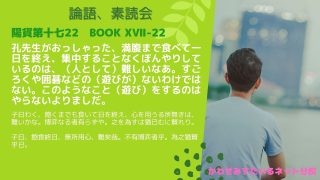宰我が尋ねた、三年間の喪は期間としてすでに長いのではないでしょうか。もし君子(人の上に立つ立派なリーダー)が三年間も礼(祭祀などの政事)を為さなければ、礼は必ず廃れます。三年間、楽(祭祀の音楽)を為さなければ、楽は必ず崩れます。昨年より以前の穀物はすでになくなって、新しい穀物が実ります。火起こしで火を点け換えるべきです。(これに対して)孔先生がおっしゃった、その(三年の)間に米を食べ、その間にきれいな着物を着て、お前は安らかなのかと。(宰我は)言う、安らかですと。(孔子が言う)お前が安らかならばそうしなさい。その君子の喪中には、ご馳走を食べてもおいしくなく、音楽を聞いても楽しくなく、家にいても安らかでない。そうであるから(礼を)行わないのである。今、お前が安らかなのであればそうするがいい。宰我が退出した。孔先生がおっしゃった、予(宰我)はなんと仁(父母に対する思いやり)がないのだろう。子が生まれて三年、ようやく父母の懐を離れるのである。この三年間の喪というのは世の中に共通する喪なのである。予も(生まれて)三年間受けた愛が確かに父母に有るはずなのだが。|「論語」陽貨第十七21
【現代に活かす論語】
子が生まれて三年、ようやく父母の懐を離れます。父母が亡くなった後、慎み深く過ごす期間が三年間というのは先人から伝わる共通の喪の期間なのです。
【解釈】
宰我(さいが)予(よ) … 孔子の門人。姓は宰(さい)、名は予(よ)、字は子我(しが)。弁論にすぐれていた一方、日中に昼寝をして孔子を嘆かせた。「論語」の登場人物|論語、素読会
宰我問う。三年の喪は、期にして已に久し。君子三年礼を為さずんば、礼必ず壊れん。三年楽を為さずんば、楽必ず崩れん。旧穀既に沒きて、新穀既に升る。燧を鑽りて火を改む。期にして已むべし。子曰わく、夫の稲を食い、夫の錦を衣て。女に於て安きか。曰わく、安し。女安くんば則ち之を為せ。夫れ君子の喪に居る、旨きを食うも甘からず、楽を聞くも楽からず、居処安からず。故に為さざるなり。今女安くんば、則ち之を為せ。宰我出ず。子曰わく、予の不仁なるや。子生まれて三年、然る後に父母の懐を免る。夫れ三年の喪は、天下の通喪なり。予や三年の愛其の父母に有るか。|「論語」陽貨第十七21
宰我問。三年之喪、期已久矣。君子三年不為礼、礼必壊。三年不為楽、楽必崩。旧穀既沒、新穀既升。鑽燧改火。期可已矣。子曰、食夫稲、衣夫錦。於女安乎。曰、安。女安則為之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞楽不楽、居処不安。故不為也。今女安、則為之。宰我出。子曰、予之不仁也。子生三年、然後免於父母之懐。夫三年之喪、天下之通喪也。予也有三年之愛於其父母乎。
「期」(き)は期間。一か年、また1か月など周期的な時間。「久」(ひさしい)は時間が長い。「君子」(くんし)は徳の高いりっぱな人物、人の上に立つ立派な人、リーダー。「礼」(れい)は楽と併せて用いられた場合、祭祀などを通じて行われる政事など受け継がれている大切なこと。『礼』とは?|論語、素読会 「楽」(がく)は祭祀に不可欠な音楽。「壊」(やぶれる)はある状態を悪くする、悪くなる、衰える。「旧穀」(きゅうこく)は昨年以前に収穫した穀物。「沒」(つきる)はほろびる、なくなる。「升」(のぼる)は成熟する、みのる。「燧」(すい)はきりもみして摩擦で火を取る木。「鑽」(きる)は穴をあける、きりもみしてこする。「鑽燧」(さんすい)は木の棒をきりもみして火をおこす。「改」(あらたむ)は新しくする、作り直す。「已」(やむ)は停止する、終わる。「安」(やすい)は気楽にのんびりしたさま。「不仁」(ふじん)は仁がないこと。父母に対する思いやりや先人の教えを学ばないこと。『仁』とは?|論語、素読会 「免」(まぬがれる)は離れる。「通」(つう)は共通の、普遍的な、いかなる時も変わることことないさま。
宰我が尋ねた、三年間の喪は期間としてすでに長いのではないでしょうか。もし君子(人の上に立つ立派なリーダー)が三年間も礼(祭祀などの政事)を為さなければ、礼は必ず廃れます。三年間、楽(祭祀の音楽)を為さなければ、楽は必ず崩れます。昨年より以前の穀物はすでになくなって、新しい穀物が実ります。火起こしで火を点け換えるべきです。(これに対して)孔先生がおっしゃった、その(三年の)間に米を食べ、その間にきれいな着物を着て、お前は安らかなのかと。(宰我は)言う、安らかですと。(孔子が言う)お前が安らかならばそうしなさい。その君子の喪中には、ご馳走を食べてもおいしくなく、音楽を聞いても楽しくなく、家にいても安らかでない。そうであるから(礼を)行わないのである。今、お前が安らかなのであればそうするがいい。宰我が退出した。孔先生がおっしゃった、予(宰我)はなんと仁(父母に対する思いやり)がないのだろう。子が生まれて三年、ようやく父母の懐を離れるのである。この三年間の喪というのは世の中に共通する喪なのである。予も(生まれて)三年間受けた愛が確かに父母に有るはずなのだが。
【解説】
孔子の時代、喪中の期間は三年でした。この喪の三年間については「論語」に度々登場します。
・三年の間は父親が行ってきたやり方や意志をあらためない。
「三年父の道を改むる無きは、孝と謂う可し|「論語」里仁第四20」
・昔の君主は喪の三年間、ことばを発する必要がない。
「冢宰に聴くこと三年|「論語」憲問第十四42」
宰我はこの三年という期間が長いと言います。宰我の個人的な意見だけではなく、世の中でそのような考え方が主流になりつつあり、恐らくそれを代弁したのだと思います。宰我がその理由として挙げた政事の停滞については、上記「憲問第十四42」にあるように補佐によって解決できると孔子は考えています。しかし、宰我が喪の期間を短くしても安らかなのであればそうすればいいと伝えます。孔子の考えに対して宰我のこの物言いに対して、叱責したり説得したりする、師と弟子の関係もあるでしょう。しかし孔子がこの章句のような対応を選んだのには2つの理由が考えられます。
まず、第一は「朋友に數すれば、斯に疏んぜらる|「論語」里仁第四26」親しい友人にしつこく忠告すれば嫌われ疎んぜられるという、孔子の考えがあります。ある程度伝えたらあとは相手に委ねるという考え方で、伝えるのを止めたからといって、自分の考えや行いが否定されるということではありません。第二に、宰我の人間性に関係しています。「今吾人に於けるや、其の言を聴きて其の行いを観る|「論語」公冶長第五10」こちらの章句では、昼寝をした宰我に対して責めたところで仕方ないと(宰我本人以外の人物に)伝えます。宰我が登場する他の章句を併せて考えると、本章句の宰我への対応にもうなずけます。
さらに、「人にして仁あらずんば、礼を如何にせん。人にして仁ならずんば、楽を如何にせん。|「論語」八佾第三03」こちらにあるように、礼や楽より「仁」が勝っているので、宰我の言う礼楽よりも、喪の期間を大切にする「仁」の方が優先されるべきというのが孔子の考え方なのです。宰我はまだその考えまでは至っていないということになります。
「論語」参考文献|論語、素読会
陽貨第十七20< | >陽貨第十七22
【原文・白文】
宰我問。三年之喪、期已久矣。君子三年不為礼、礼必壊。三年不為楽、楽必崩。旧穀既沒、新穀既升。鑽燧改火。期可已矣。子曰、食夫稲、衣夫錦。於女安乎。曰、安。女安則為之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞楽不楽、居処不安。故不為也。今女安、則為之。宰我出。子曰、予之不仁也。子生三年、然後免於父母之懐。夫三年之喪、天下之通喪也。予也有三年之愛於其父母乎。
<宰我問。三年之喪、期已久矣。君子三年不爲禮、禮必壊。三年不爲樂、樂必崩。舊穀既沒、新穀既升。鑽燧改火。期可已矣。子曰、食夫稻、衣夫錦。於女安乎。曰、安。女安則爲之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞樂不樂、居處不安。故不爲也。今女安、則爲之。宰我出。子曰、予之不仁也。子生三年、然後免於父母之懷。夫三年之喪、天下之通喪也。予也有三年之愛於其父母乎。>
(宰我問う。三年の喪は、期にして已に久し。君子三年礼を為さずんば、礼必ず壊れん。三年楽を為さずんば、楽必ず崩れん。旧穀既に沒きて、新穀既に升る。燧を鑽りて火を改む。期にして已むべし。子曰わく、夫の稲を食い、夫の錦を衣て。女に於て安きか。曰わく、安し。女安くんば則ち之を為せ。夫れ君子の喪に居る、旨きを食うも甘からず、楽を聞くも楽からず、居処安からず。故に為さざるなり。今女安くんば、則ち之を為せ。宰我出ず。子曰わく、予の不仁なるや。子生まれて三年、然る後に父母の懐を免る。夫れ三年の喪は、天下の通喪なり。予や三年の愛其の父母に有るか。)
【読み下し文】
宰我(さいが)問(と)う。三年(さんねん)の喪(も)は、期(き)にして已(すで)に久(ひさ)し。君子(くんし)三年(さんねん)礼(れい)を為(な)さずんば、礼(れい)必(かなら)ず壊(やぶ)れん。三年(さんねん)楽(がく)を為(な)さずんば、楽(がく)必(かなら)ず崩(くず)れん。旧穀(きゅうこく)既(すで)に沒(つ)きて、新穀(しんこく)既(すで)に升(のぼ)る。燧(すい)を鑽(き)りて火(ひ)を改(あらた)む。期(き)にして已(や)むべし。子(し)曰(のたま)わく、夫(か)の稲(いね)を食(くら)い、夫(か)の錦(にしき)を衣(き)て。女(なんじ)に於(おい)て安(やす)きか。曰(い)わく、安(やす)し。女(なんじ)安(やす)くんば則(すなわ)ち之(これ)を為(な)せ。夫(そ)れ君子(くんし)の喪(も)に居(お)る、旨(うま)きを食(くら)うも甘(あま)からず、楽(がく)を聞(き)くも楽(たのし)からず、居処(きょしょ)安(やす)からず。故(ゆえ)に為(な)さざるなり。今(いま)女(なんじ)安(やす)くんば、則(すなわ)ち之(これ)を為(な)せ。宰我(さいが)出(い)ず。子(し)曰(のたま)わく、予(よ)の不仁(ふじん)なるや。子(こ)生(う)まれて三年(さんねん)、然(しか)る後(のち)に父母(ふぼ)の懐(ふところ)を免(のが)る。夫(そ)れ三年(さんねん)の喪(も)は、天下(てんか)の通喪(つうも)なり。予(よ)や三年(さんねん)の愛(あい)其(そ)の父母(ふぼ)に有(あ)るか。
「論語」参考文献|論語、素読会
陽貨第十七20< | >陽貨第十七22