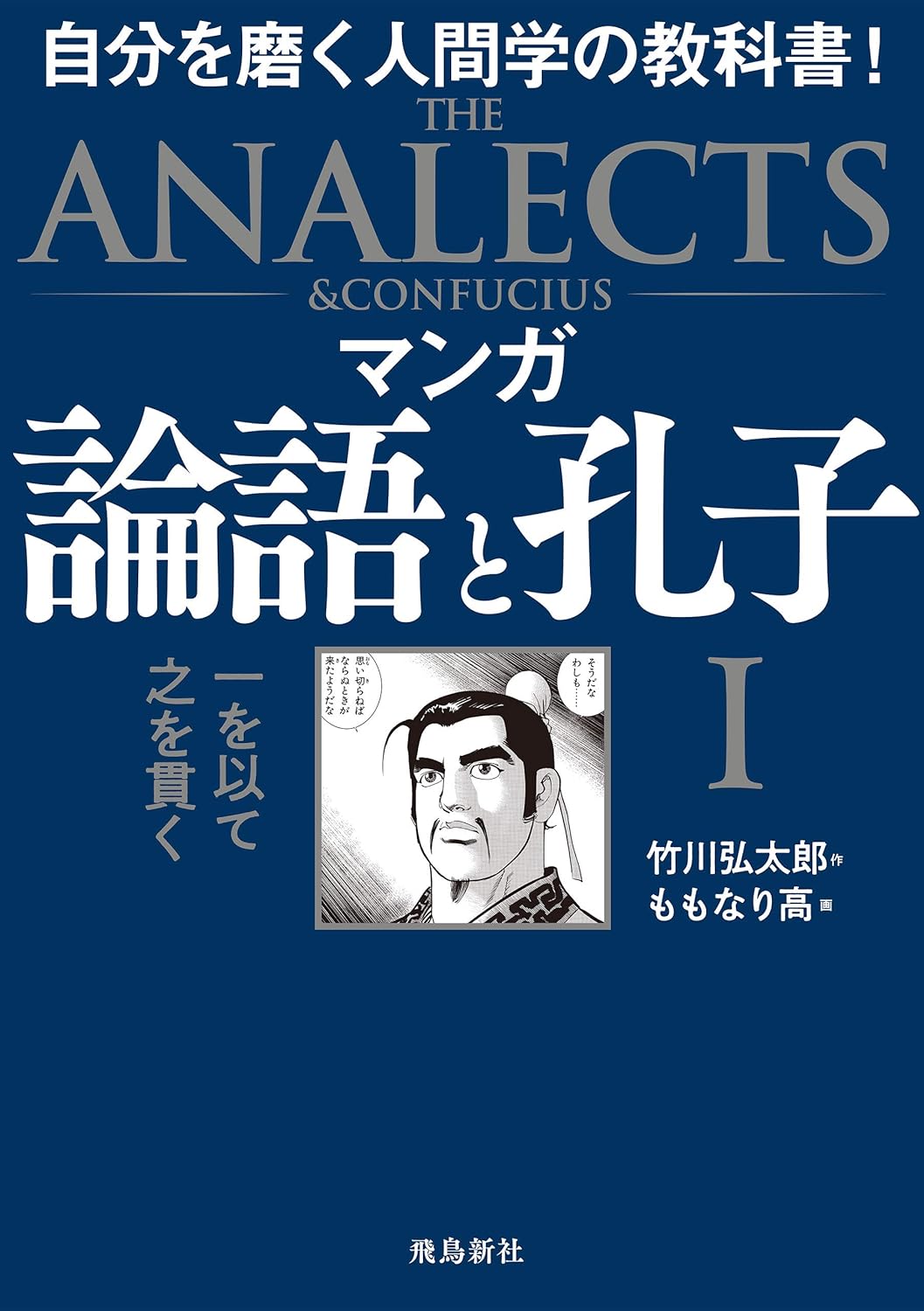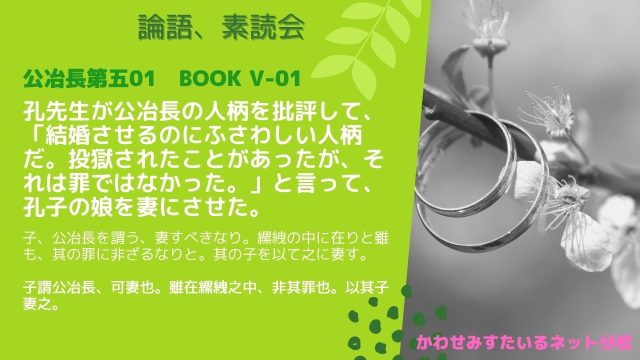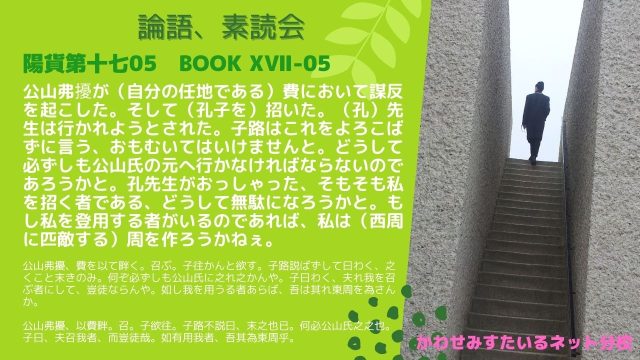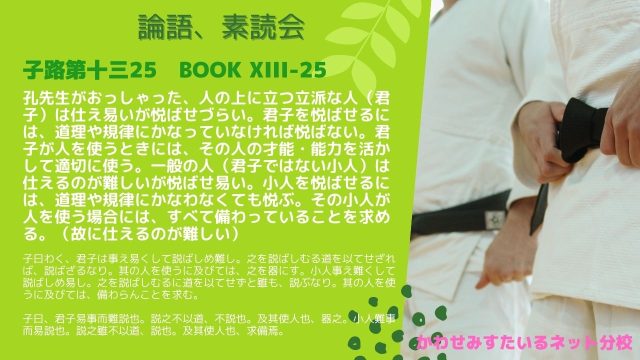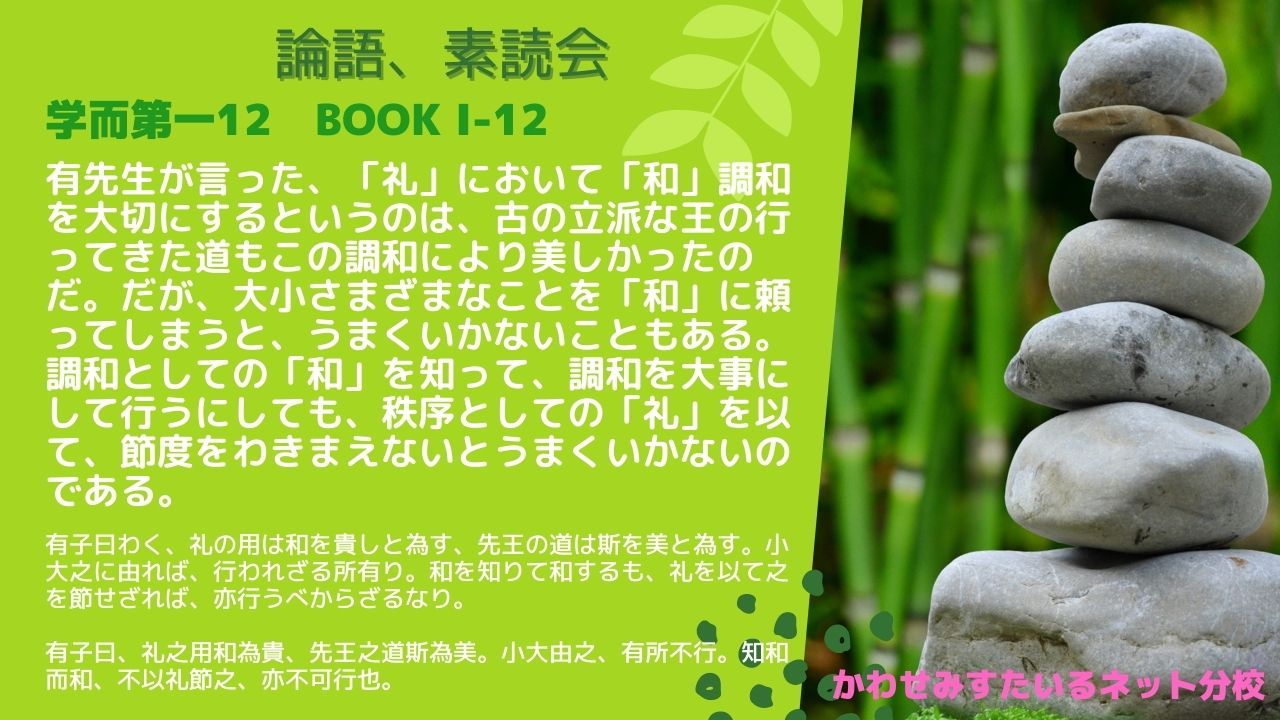「道」(みち)はみち。
道聴而塗説、
道を歩いているときに聴いて、そのまま出会った人に話してしまうことは、
道に聴きて塗に説くは、|「論語」陽貨第十七14
君子学以致其道。
君子・人の上に立つ立派なリーダーは学ぶことでその道を究める。
君子学びて以て其の道を致す|「論語」子張第十九07
「道」は道く(みちびくに)とも、道むる(おさむるには)とも読み下す。
道千乗之国、
千乗の兵車を出しうる国を治めるには、
千乗の國を導くに|「論語」学而第一05
「道」とは父の行い足跡のこと。
三年無改於父之道、可謂孝矣。
三年間、父の習慣を変えずに喪に服すなら、親孝行な人と言えるだろう。
三年父の道を改むるる無きは、孝と謂う可し|「論語」学而第一11
「道」(みち)は人が生まれながらにして徳性を重ねながら進む道
先王之道斯為美。
古の立派な王の行ってきた道もこの調和により美しかったのだ。
先王の道は斯を美と為す|「論語」学而第一12
君子道者三、我無能焉。仁者不憂、知者不惑、勇者不懼。
君子の道なる者三つ、我能くすること無し。仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず。
君子の道なる者三つ、我能くすること無し|「論語」憲問第十四30
「道」(みち)はひとが生まれながらにして徳性を重ねながら進む道。正しい道。
志於道、
ひととして正しい道を志し、
道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に游ぶ|「論語」述而第七06
是道也、何足以臧。
このくらいの徳を重ねることで、どうして充分に足るといえようか。
是の道や、何ぞ以て臧しとするに足らん|「論語」子罕第九27
可与共学、未可与適道。可与適道、未可与立。
一緒に学ぶことはできるが、未だに一緒に徳性を重ねながら正しい道へ向かう人はいない。一緒に徳性を重ねながら正しい道へ向かう人はいるが、未だに一緒に成し遂げる人はいない。
未だ与に道に適くべからず。与に道に適くべし|「論語」子罕第九30
道之将行也与、命也。道之将廃也与、命也。
正しい道が行われようとするのも天命です。正しい道が崩れるのも天命です。
道の将に行われんとするや、命なり。道の将に廃れんとするや、命なり|「論語」憲問第十四38
執徳不弘、信道不篤。
人が生まれながらに積み重ねていき体得する「徳」を広く求めることなく、徳性を重ねながら進む正しい道を信じること誠心誠意でなければ、
徳を執ること弘からず、道を信ずること篤からずんば|「論語」子張第十九02
「有道」とはまず「道」は人が生まれながらにして徳を重ねる道。その道が有るとはそのような行いができる人またはその行い。
就有道而正焉。
徳を積んだ人に近づいて自らの行いを正す。
有道に就きて正す|「論語」学而第一14
「道」は人が生まれながらにして徳性を高めること
未若貧而楽道、
しかしまだ、貧しくても人の道を高めることを楽しみ、
未だ貧しくして道を楽しみ|「論語」学而第一15
「道」は導く。「政」は政治、国を治めること。法律や制度、命令や禁止などの規制を指している。
道之以政、斉之以刑、民免而無恥。
国を法律や制度をもって導き、刑罰で統制しようとするならば、国民はただその刑を逃れるだけで何も恥じなくなる。
之を道くに政を以し、之を斉うるに刑を以てすれば|「論語」為政第二03
道之以徳、斉之以礼、有恥且格。
道徳によって導き、礼儀や儀礼を伝えて統制していくと、人民は自分を恥じて自らを省みて、自ずと正して善に向かっていくようになる。
之を道くに徳を以てし、之を斉うるに礼を以てすれば|「論語」為政第二03
道之斯行
これを導けばここに行われ
之を道びけば斯に行われ|「論語」子張第十九25
「父之道」(ちちのみち)は父のやってきたこと。
三年無改於父之道、可謂孝矣。
喪中の三年の間は亡くなった父のやり方や意思を変えないのが親孝行というものだ。
三年父の道を改むる無きは、孝と謂う可し|「論語」里仁第四20
「道」(みち)は道理。
邦有道不廃、邦無道免於刑戮。
国の政治が道理の上に行われれば必要となり任用され、国の政治が道理の上に行われないときでも刑罰を免れるだろう。
邦に道有れば廃てられず、邦に道無ければ刑戮より免れん|「論語」公冶長第五02
有君子之道四焉。其行己也恭、其事上也敬、其養民也恵、其使民也義。
彼には優れた政治家としての4つの道理が備わっている。その振る舞いはうやうやしい。君主に仕えては敬いまじめに勤める。人民を養うのに恵み深い。人民を公役に使うのに正しく公正に行う。
君子の道四有り。其の己を行うや恭、其の上に事うるや敬、其の民を養うや恵、其の民を使うや義|「論語」公冶長第五16
君子所貴乎道者三。
人の上に立つ立派な人が重視する道理が3つある。
君子道に貴ぶ所の者三|「論語」泰伯第八04
「道」(みち)は道理、道義、あるべき姿。
道不行、乗桴浮于海。
国で正しい政治が行われないので、いかだに乗って海にでも逃げ出したい想いだ。
道行なわれず、桴に乗りて海に浮ばん|「論語」公冶長第五07
隠居以求其志、行義以達其道。
世を避けて仕官しないでいてもその志を追い求め、正しいことを行うことによってあるべき姿に達しようとする。
隠居して以て其の志を求め、義を行いて以て其の道を達す|「論語」季氏第十六11
君子之道、孰先伝焉、孰後倦焉。譬諸草木区以別矣。君子之道、焉可誣也。
君子・人の上に立つ立派なリーダーの道義、リーダーのあるべき姿は、何を先に伝え、何を後回しにするかということであろうか。(弟子に物事を伝えるというのは)例えば草木を区別してより分けるようなものだ。君子の道義は歪曲されてはならない。
君子の道、孰れをか先に伝え、孰れをか後に倦まん。諸を草木の区して以て別つに譬う。君子の道は、焉んぞ誣うべけんや|「論語」子張第十九12
「道」(みち)は道義。正しい政治。
甯武子、邦有道則知。邦無道則愚。
甯武子は国で正しい政治が行われているときは知者として(能力を発揮したが)、国で正しい政治が行われなければ控えめにして愚者のように振る舞った。
甯武子、邦に道有るときは則ち知なり。邦に道無きときは則ち愚なり|「論語」公冶長第五21
邦有道穀。邦無道穀、恥也。
国家で正しい政治が行われていれば俸禄を受ける。国家で正しい政治が行われていないのに俸禄を受けるのは、「恥」である。
邦道有れば穀す。邦道無くして穀するは、恥なり|「論語」憲問第十四01
邦有道、危言危行。邦無道、危行言孫。
国に正しい政治が行われていれば、言葉を正しく行動を正しくする。国に正しい政治が行われてなければ、行動を正しくし、言葉は控えめにする。
邦道有れば、言を危くし行を危くす。邦道無ければ、行を危くし言は孫う|「論語」憲問第十四04
立則見其参於前也、在輿則見其倚於衡也。夫然後行。
立っているときには目の前に拝謁するかのように見え、馬車に乗ったときには馬車を牽く馬の横木によりかかっているかのように見えて、そうした後に(道理が)行われるのだと。
立ちては則ち其の前に参するを見、輿に在りては則ち其の衡に倚るを見るなり。夫れ然る後に行われん|「論語」衛霊公第十五06
※この章句では明確な「道」の表記はありません。
直哉史魚。邦有道如矢、邦無道如矢。君子哉蘧伯玉、邦有道則仕、邦無道則可巻而懐之。
真っ直ぐだな衛の大夫・史魚は。国の政事が正しく行われているときには射られた矢のようであり、国の政事が行われていないときにも矢のようである。立派なリーダーだな衛の大夫・蘧伯玉は、国の政事が正しく行われているときには国に仕え、国の政事が行われていないときには、(能力を)まとめて懐にしまってしまう。
直なるかな史魚。邦に道有るにも矢の如く、邦に道無きにも矢の如し。君子なるかな蘧伯玉、邦に道有れば則ち仕え、邦に道無ければ則ち巻いて之を懐にすべし|「論語」衛霊公第十五07
天下有道、則礼楽征伐自天子出。天下無道、則礼楽征伐自諸侯出。
天下に正しい政事があれば、政策や征伐が君主から発せられる。天下に正しい政事が無ければ政策や征伐が諸侯から発せられる。
天下道有れば、則ち礼楽征伐天子より出ず。天下道無ければ、則ち礼楽征伐諸侯より出いず。|「論語」季氏第十六02
直道而事人、焉往而不三黜。枉道而事人、何必去父母之邦。
正しい政事を行って人に仕えれば、どこに行ったとしても三度(くらいは)免職されるでしょう。道理を曲げて人に仕えるのであれば、どうして母国を去る必要があるのだろう。
道を直くして人に事うれば、焉くに往くとして三たび黜けられざらん。道を枉げて人に事うれば、何ぞ必ずしも父母の邦を去らん|「論語」微子第十八02
天下有道、丘不与易也。
世の中に道徳が行われていれば、丘(私)は一緒に変わることはないのだ。
天下道有らば、丘は与に易えざるなり。|「論語」微子第十八06
不仕無義。長幼之節、不可廃也。君臣之義、如之何其可廃之。
師に仕えなければ道義が立ちません。長者と幼者との間に行われる礼節は捨てられません。(そうであれば)君主と家臣の正しい道義はこれをどうして捨てられましょうか。
仕えざれば義無し。長幼の節は、廃すべかあざるなり。君臣の義は、之を如何ぞ其れ廃せん。|「論語」微子第十八07
上失其道、民散久矣。
上の者が正しい政治を失い、人民(の心)が離散して久しい。
上其の道を失いて、民散ずること久し。|「論語」子張第十九19
文武之道、未墜於地、在人。
周の文王と武王の道(文武の道)・正しい道義は亡びず人々の中に在ります。
文武の道、未だ地に墜ちずして、人に在り。|「論語」子張第十九22
「道」(みち)は道理。規律。
所謂大臣者、以道事君、不可則止。
いわゆる大臣という者は、道理を以て君主に仕え、それが許されなければすぐに(職を)辞める。
道を以て君に事え、不可なれば則ち止む|「論語」先進第十一23
君子易事而難説也。説之不以道、不説也。
人の上に立つ立派な人(君子)は仕え易いが悦ばせづらい。君子を悦ばせるには、道理や規律にかなっていなければ悦ばない。
君子は事え易くして説ばしめ難し。之を説ばしむる道を以てせざれば、説ばざるなり|「論語」子路第十三25
人能弘道。非道弘人。
ひとが「道」道理や規律を広めるのであって、「道」道理や規律がひとを広める(人間性を豊かにする)のではない。
人能く道を弘む。道人を弘むるに非らず|「論語」衛霊公第十五29
「子之道」(しのみち)は孔子が説く道、道理。
非不説子之道、力不足也。
孔先生の説く道を悦ばないわけではありませんが、私の力が足りません。
子の道を説ばざるに非ず、力足らざればなり|「論語」雍也第六10
「斯道」(このみち)は人の道、人として大切な道。
何莫由斯道也。
なぜ人として大切な道を通ろうとしないのだろう。
何ぞ斯の道に由ること莫きや|「論語」雍也第六15
「道」(みち)は道義のある道徳のある政治。ここではその政治が行われる国。
斉一変至於魯。魯一変、至於道。
斉の国が少し変わって進歩すれば魯の国のようになるだろう。魯の国が少し変わって進歩すれば道義のある政治が行われる国になるだろう。
斉一変せば魯に至らん。魯一変せば、道に至らん|「論語」雍也第六22
「道」(みち)は、道理、規律、意向、行き先。
道不同、不相為謀。
歩む道が同じでなければ、お互いに力を合わせて相談することはない。
道同じからざれば、相為に謀らず。|「論語」衛霊公第十五40
「道」(みち)は、方法、やり方、手段。
子張問曰、与師言之道与。子曰、然。固相師之道也。
子張問うて曰わく、師と言うの道か。子曰わく、然り。固より師を相くるの道なり。
子張が孔子に尋ねて言った、楽師と話をするときの作法ですかと。孔先生がおっしゃった、その通りだよ。本来の楽師を補佐する作法だよと。|「論語」衛霊公第十五42
私にとって「道徳」についての最大の出会いは、安岡正篤先生の人間学講話「人物を創る」の巻頭の言葉です。この普遍的な考え方に感銘を受けて、人間学・中国古典を習い始めるきっかけになりました。
宇宙の本体は、絶えざる創造変化活動であり、進行である。その宇宙生命より人間が得たるものを「徳」という。この「徳」の発生する本源が「道」である。「道」とは、これなくして宇宙も人生も存在し得ない、その本質的なものであり、これが人間に発して「徳」となる。
安岡正篤「人物を創る」プレジデント社
これを結んで「道徳」という。よって「道徳」の中には宗教も狭義の道徳も政治もみな含まれている。しかもその本質は「常に自己を新しくする」ことである。殷の湯王の盤銘にいう「苟に日に新たに、日日に新たに、又日に新たなり」という言葉は、宇宙万物運行の原則であり、したがって人間世界を律する大原則でもある。
人はこの「道徳」の因果関係を探求し、その本質に則ることによって自己の徳(能力)を無限大に発揮することができるのである。