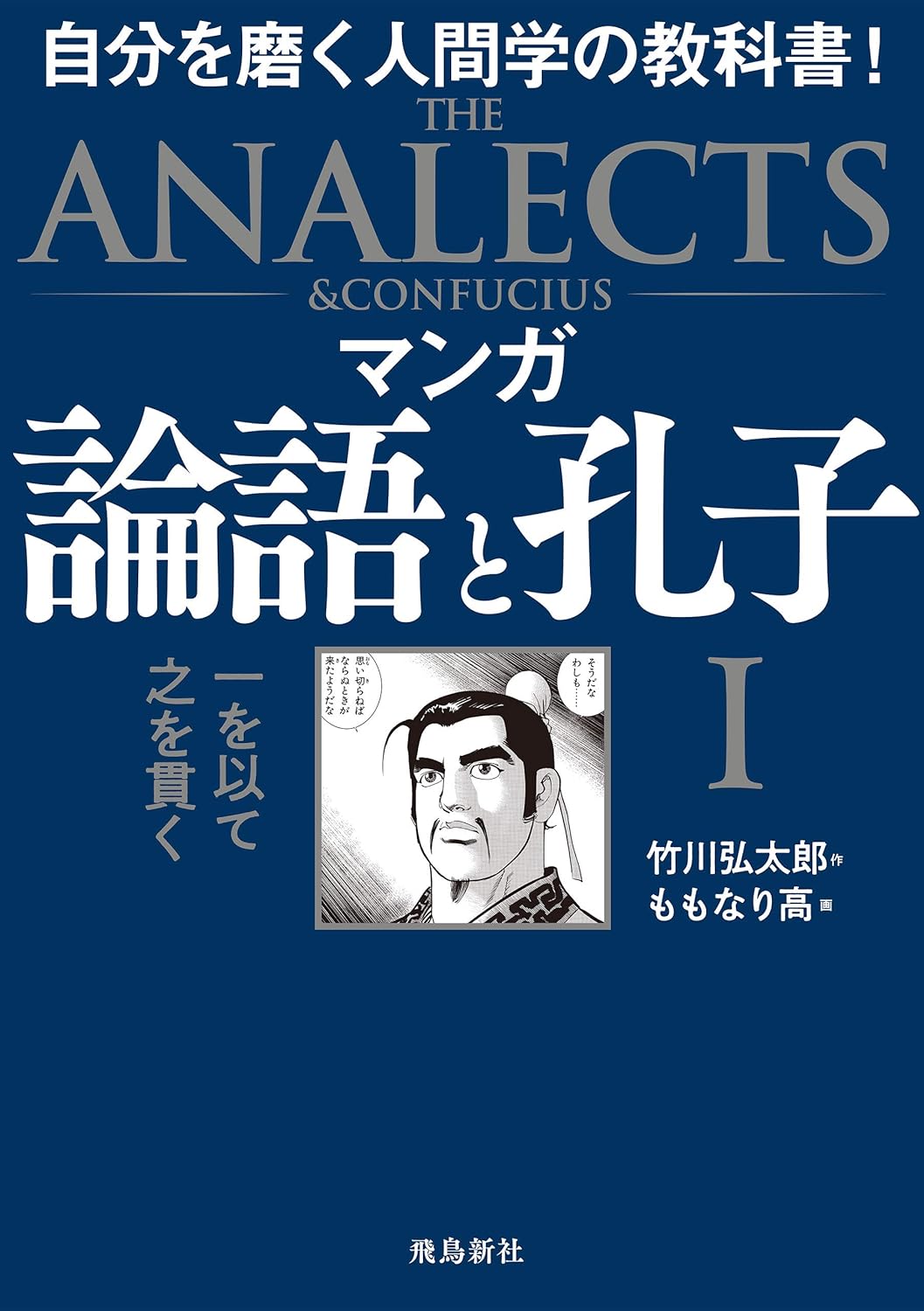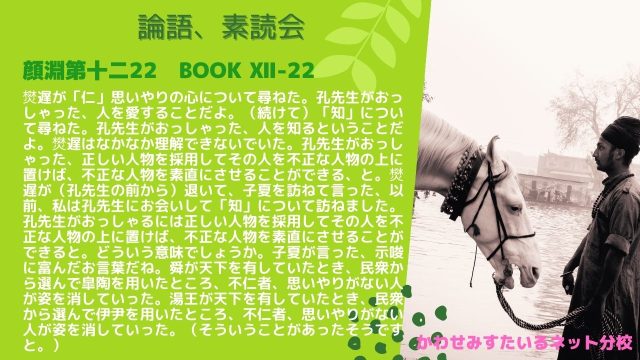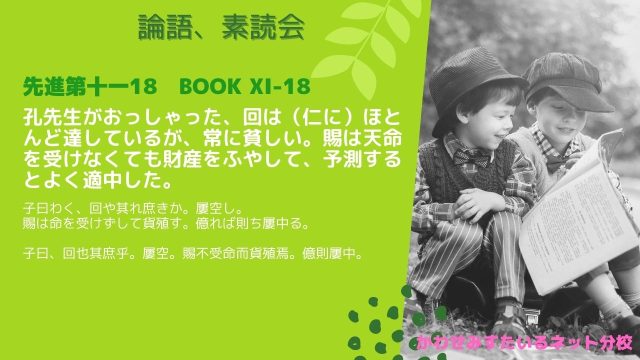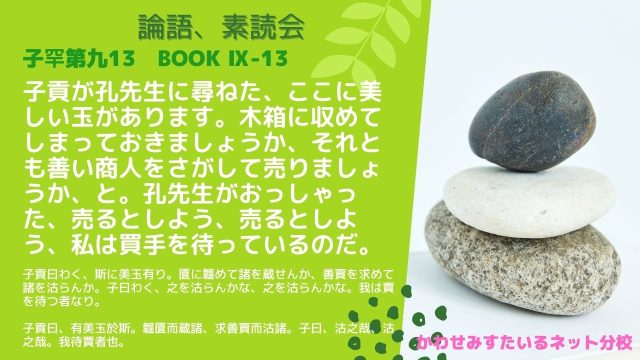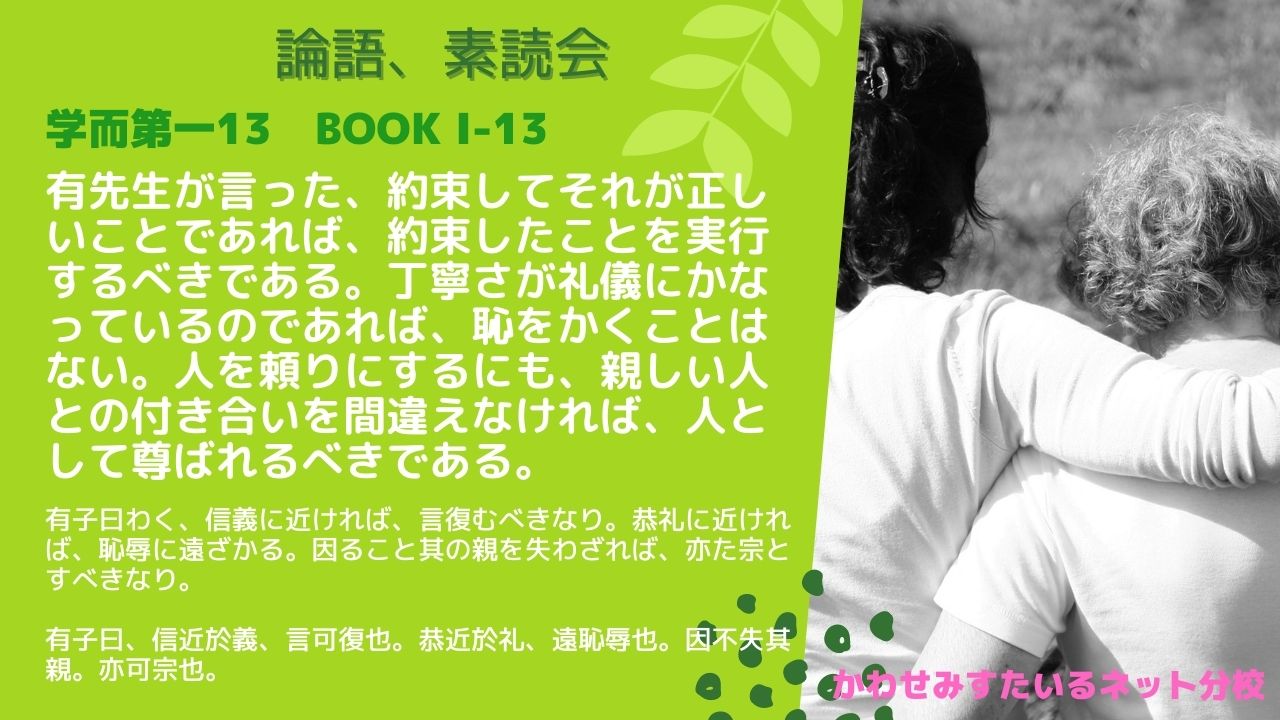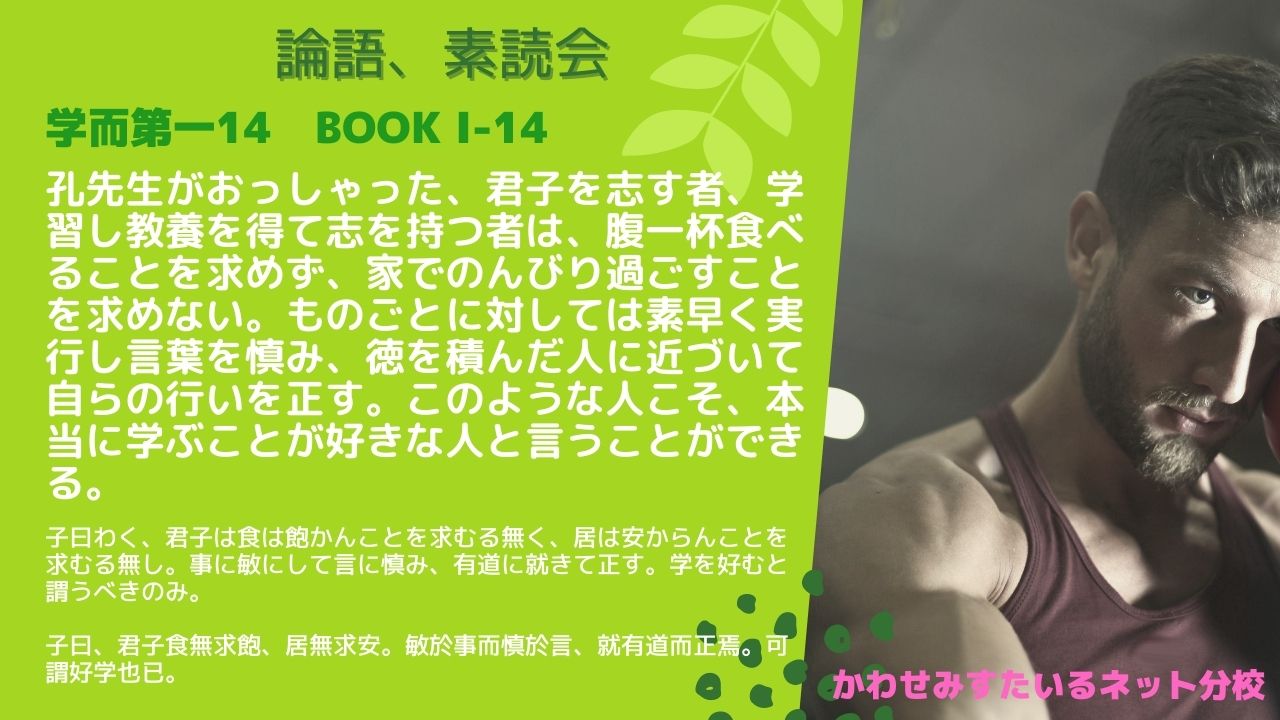「義」は正しい行い、正しい道。
信近於義、言可復也。
約束してそれが正しいことであれば、約束したことを実行するべきである。
信義に近きときは、言復むべきなり|「論語」学而第一13
子張問崇徳辨惑。子曰、主忠信徙義、崇徳也。愛之欲其生、悪之欲其死。既欲其生、又欲其死。是惑也。
子張は徳性を高くし迷いをなくすにはどうすべきか尋ねた。孔先生がおっしゃった、誠実さと約束を守り務めを果たすことを旨として正しい道へ向かうことは、徳性を高めることになる。あるものを愛してはいつまでも生きることを願い、あるものを憎んでは死ぬことなくなることを願う。終始、その生きることを希望して、またその死ぬことを希望する。これこそが迷いであるよと。
忠信を主として義に徙るは、徳を崇くするなり|「論語」顔淵第十二10
夫達也者、質直而好義、察言而観色、慮以下人。
そもそも志を遂げるひとは、性質が素直で正しい行いを好み、ひとの言葉を察して表情を観察し、深く考えてへりくだる。
夫れ達なる者は、質直にして義を好み、言を察して色を観、慮りて以て人に下る|「論語」顔淵第十二20
「義」(ぎ)は行わなければならないこと、正義。仁・義・礼・智・信はのちの儒教の中で五常として人の徳性を表すもの。
見義不為、無勇也。
正義だと知りながら行わないのは、勇気がないのだ。
義を見て為さざるは、勇無きなり|「論語」為政第二24
「義」(ぎ)は正しいこと。道義。
君子之於天下也、無適也、無莫也。義之与比。
人の上に立つ立派な人は物事を処理するにあたっては、必ずこうしようと固執することなく、また絶対にこうしないと心に決めることもない。ただ、道理に従って正しくあるのみだ。
君子の天下に於けるや、適も無く、莫も無し。義と之れ与に比う。|「論語」里仁第四10
子曰、君子喩於義、小人喩於利。
孔先生がおっしゃった、人の上に立つ立派な人は正しいこと道義を基準に理解するが、小人は目の前の利益を元に判断、解決する。
子曰わく、君子は義に喩り、小人は利に喩る。|「論語」里仁第四16
聞義不能徙
正しいことを聞いてもそれを行うことができないこと
義を聞きて徙る能わざる|「論語」述而第七03
上好義、則民莫敢不服。
上に立つ者が正しいことを好めば、民はどうして慕わずにおられようか。
上義を好めば、則ち民敢て服せざること莫し|「論語」子路第十三04
見利思義、見危授命、久要不忘平生之言、亦可以為成人矣
利益を得るときには「義」正しいこと、道義を思い、危機に際しては一命を掛け、古い約束や普段の発言であっても忘れなければ、「成人」と言っていいだろう
亦以て成人と為すべし|「論語」憲問第十四13
義然後取。人不厭其取
正しい行いをしてその後で受け取ります。ひとは受け取っても気に掛けないのです
義にして然る後に取る。人其の取ることを厭わざるなり|「論語」憲問第十四14
群居終日、言不及義、好行小慧
人々が集まって一日中、道義を議論するわけでもなく、好んでつまらぬ知恵だけで(議論を)行っている。
群居して終日、言義に及ばず、好んで小慧を行う|「論語」衛霊公第十五17
君子義以為質、礼以行之、孫以出之、信以成之
人の上に立つ立派な人・リーダーは、「義」正しいこと、道義を本とし、礼儀、しきたりを以て「義」を行い、相手を思いやって「義」を生み出し、信頼を以て「義」を実現する
君子義以て質と為し、礼以て之を行い、孫以て之を出し、信以て之を成す|「論語」衛霊公第十五18
見得思義
利益を目の前にしたときには道義を思う
得るを見ては義を思う|「論語」季氏第十六10
隠居以求其志、行義以達其道。
世を避けて仕官しないでいてもその志を追い求め、正しいことを行うことによってあるべき姿に達しようとする。
隠居して以て其の志を求め、義を行いて以て其の道を達す|「論語」季氏第十六11
君子義以為上。君子有勇而無義為乱。小人有勇而無義為盗。
君子は「義」(正義、道義)を尊重する。君子が勇敢で正義が無ければ、戦争が起こる。君子以外の徳がないつまらない人物が勇敢で正義がなければ、盗みを働くようになると。
君子義を以て上と為す。君子勇有りて義無ければ乱を為す。小人勇有りて義無ければ盗を為す|「論語」陽貨第十七23
道之不行、已知之矣。
正しい政治が行われていないことはすでに存じています。
道の行われざるや、已に之を知れり。|「論語」微子第十八07
見得思義
利益を得れば「義」正しいこと、道義を思い、
得るを見ては義を思い|「論語」子張第十九01
「不義」(ふぎ)は正しくないこと、道義から外れていること。
不義而富且貴、於我如浮雲。
正しくないことで得た俸禄と地位は私にとってはかないものだ。
不義にして富み且つ貴きは、我に於て浮雲の如し|「論語」述而第七15
「民之義」(たみのぎ)はひととしての道理。
務民之義、敬鬼神而遠之、可謂知矣。
ひととしての道理を務め、神仏を敬うが頼りすぎない、これを「知」という。
仁者は難きを先にして獲ることを後にす、仁と謂うべし|「論語」雍也第六20