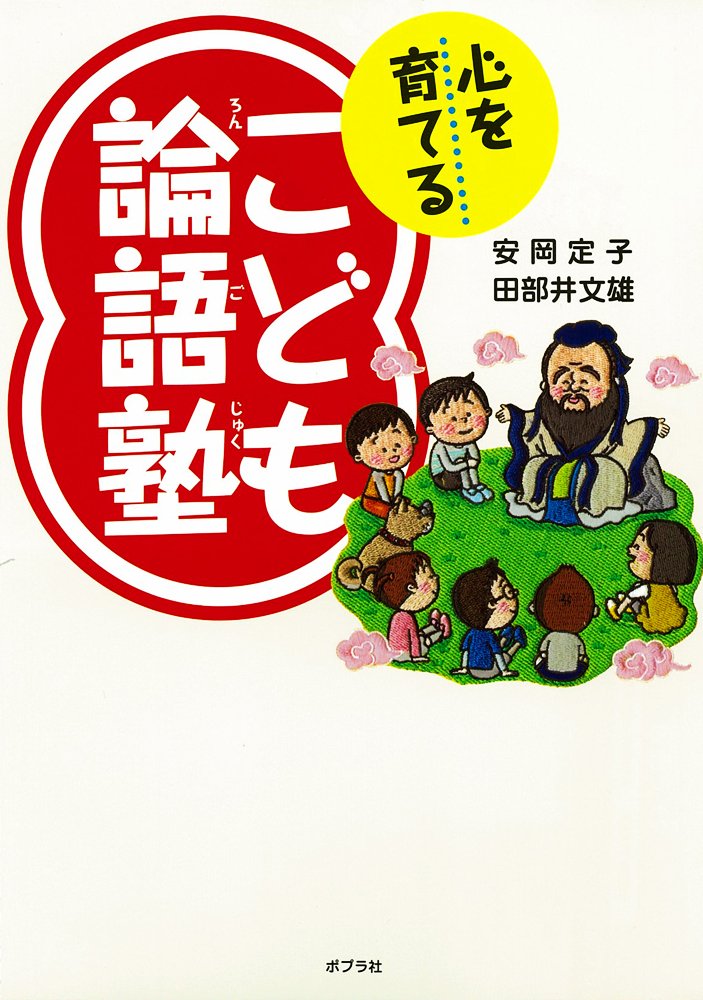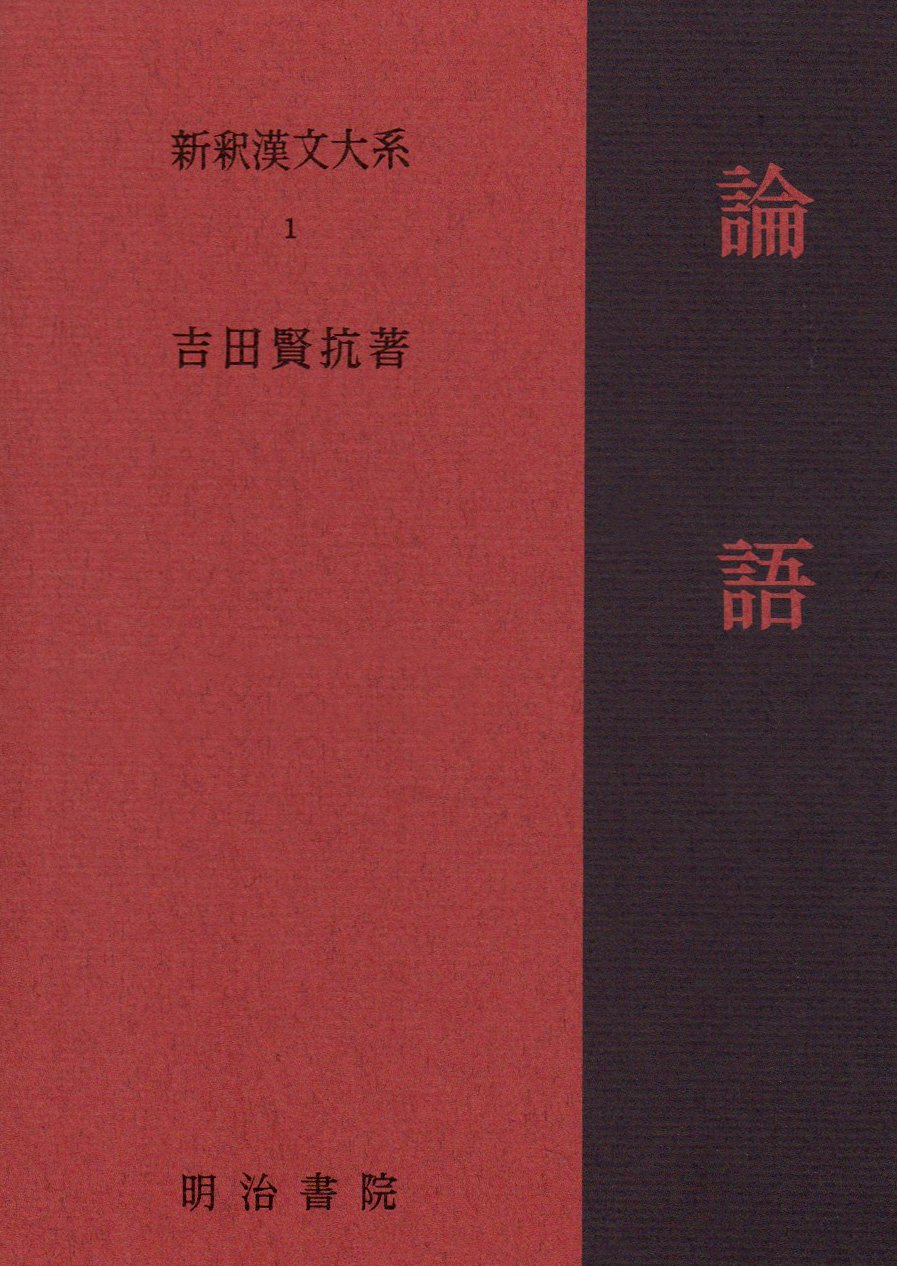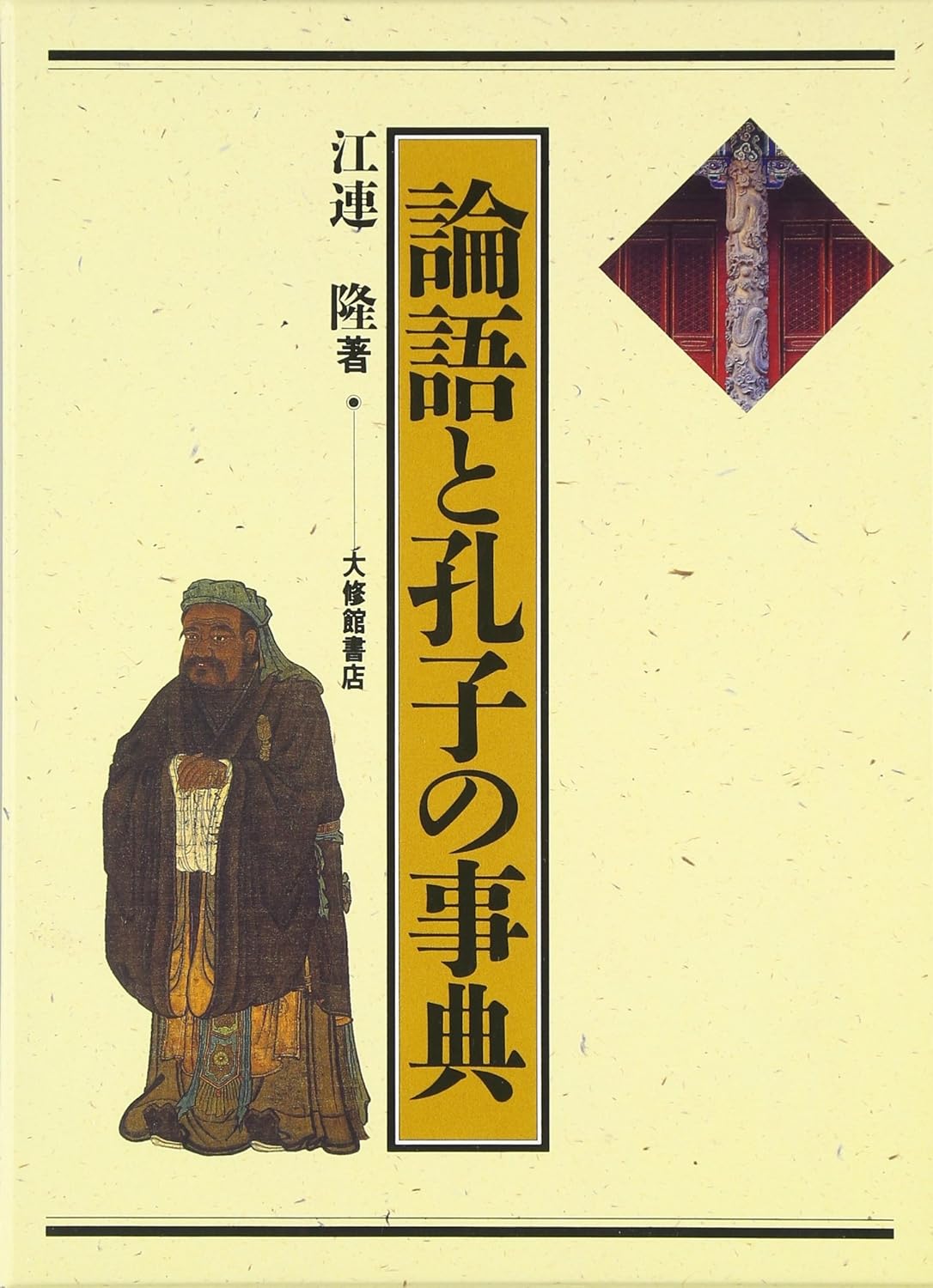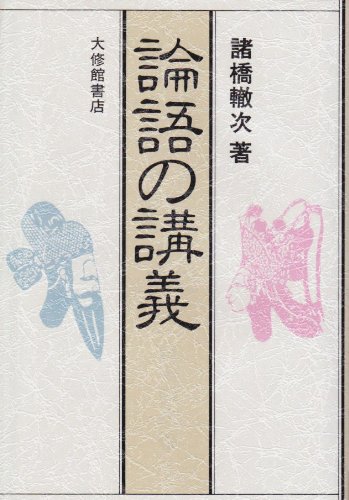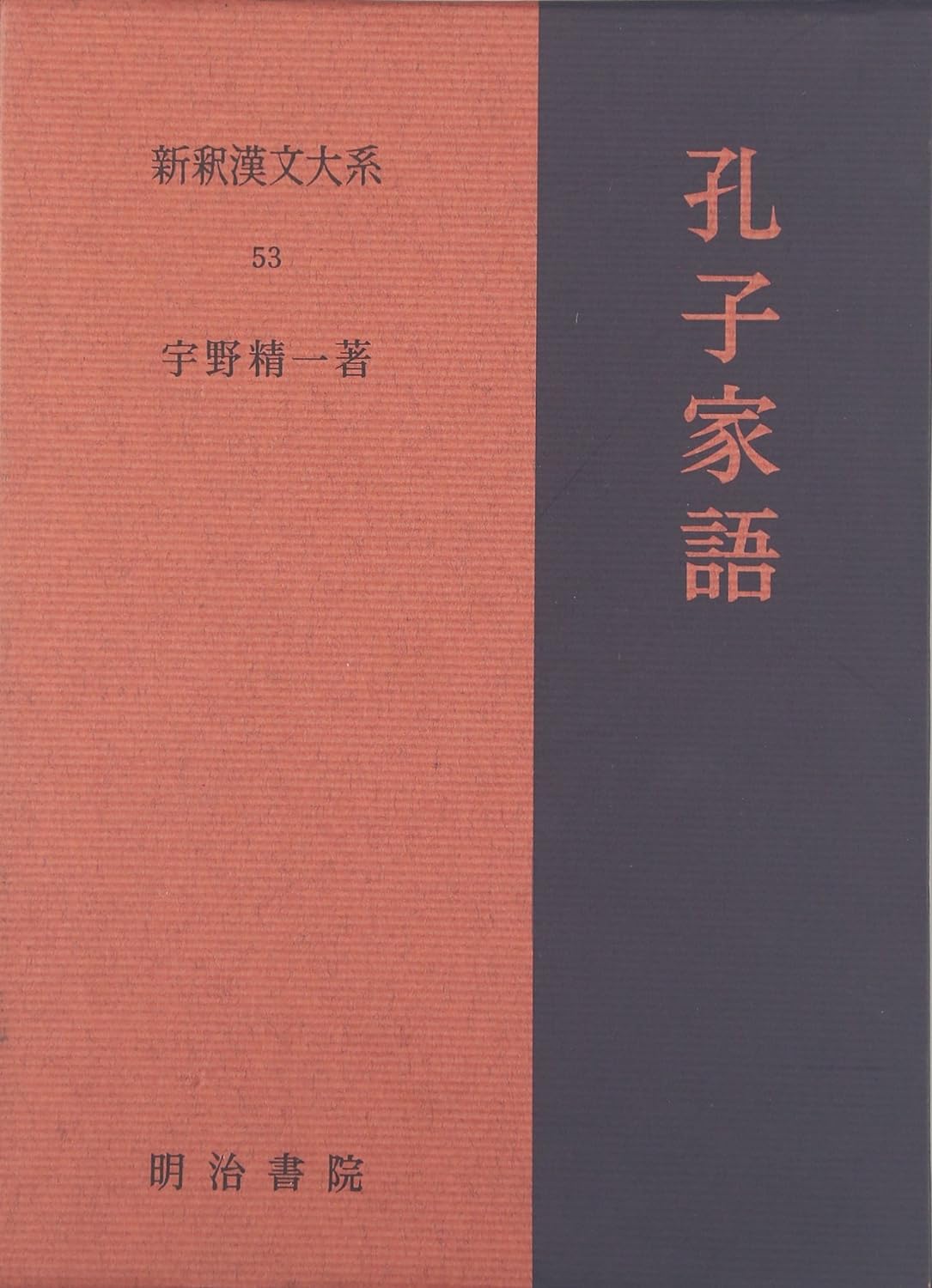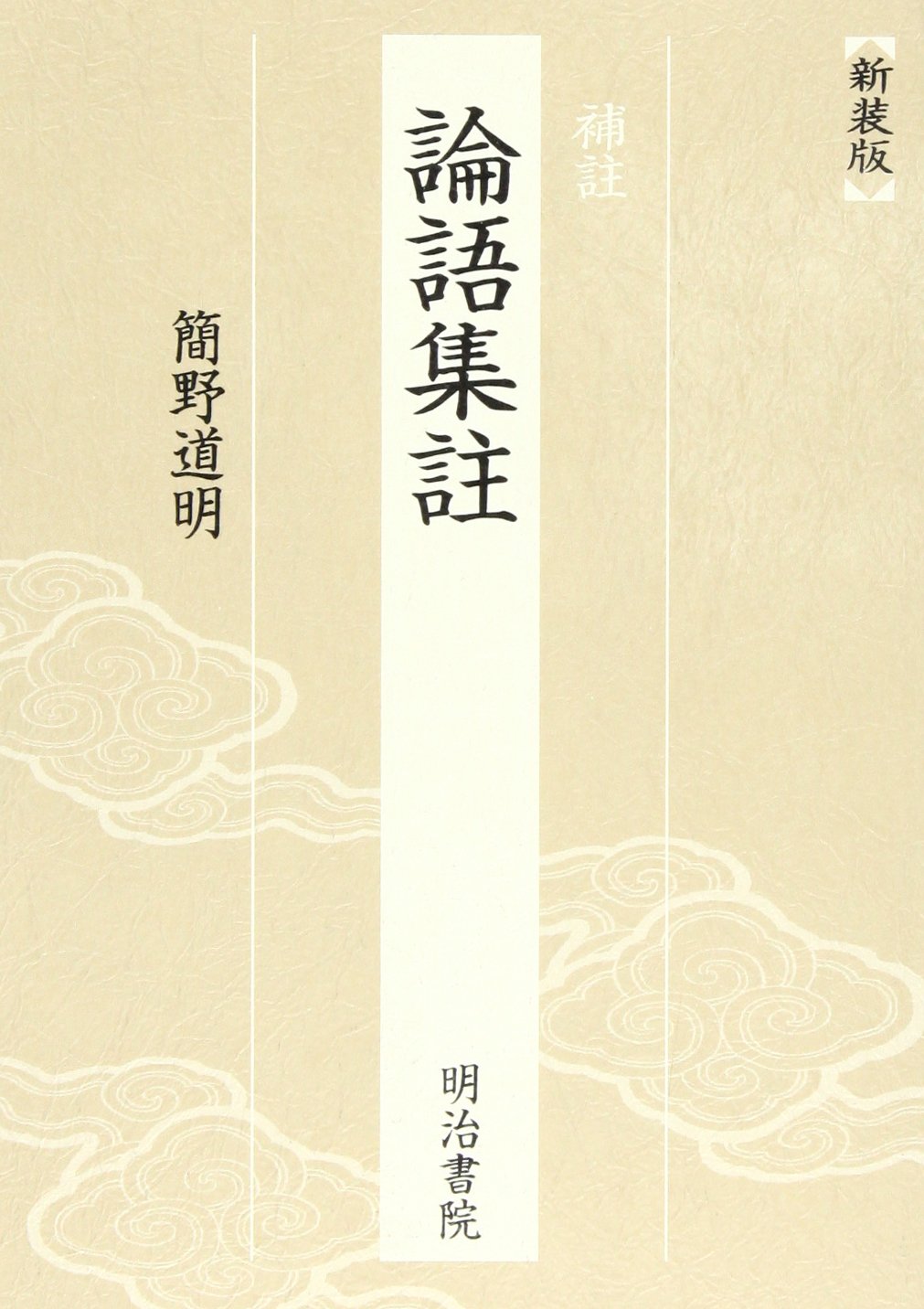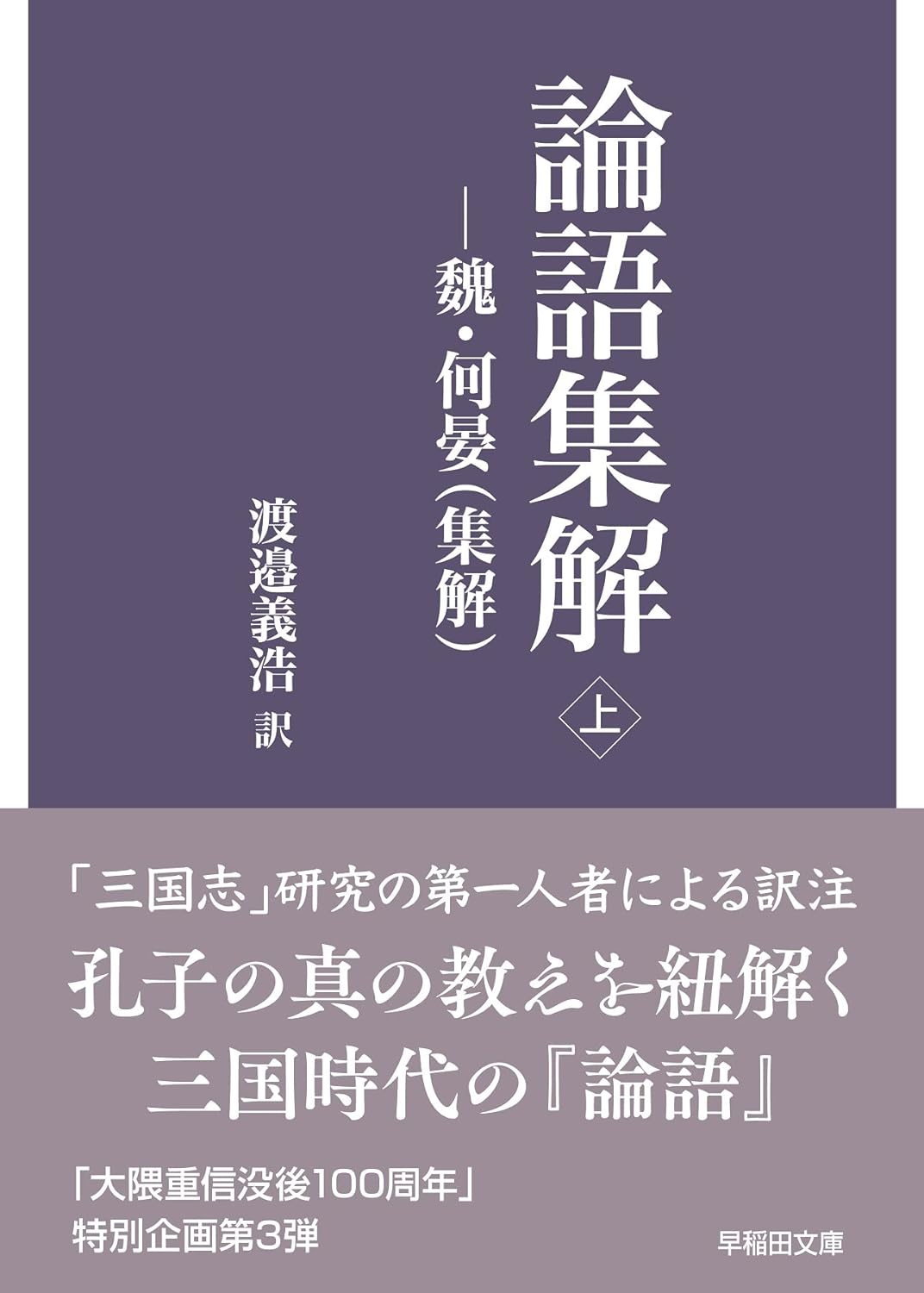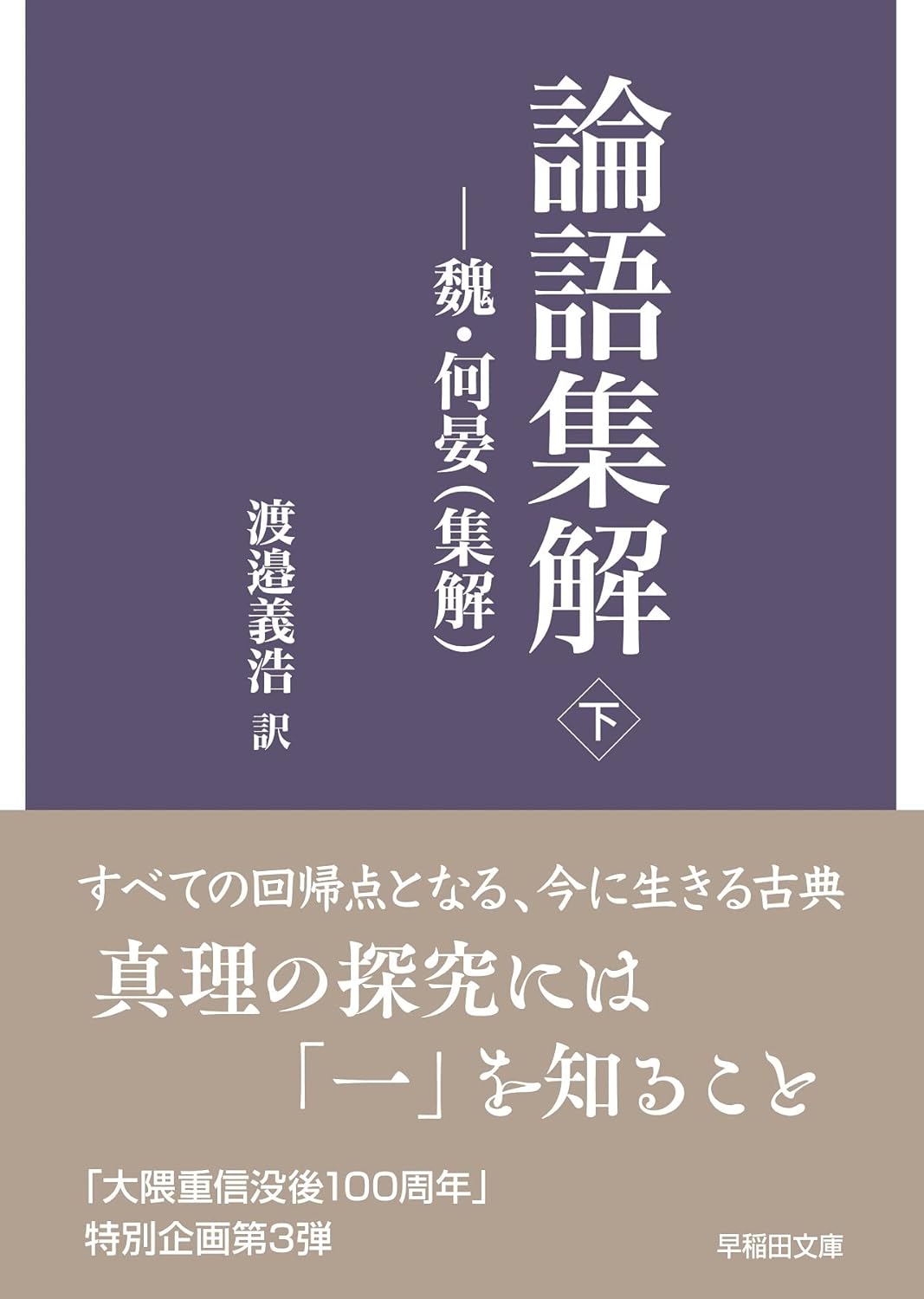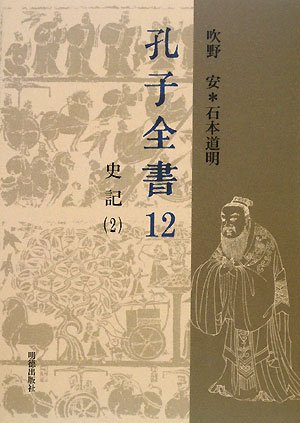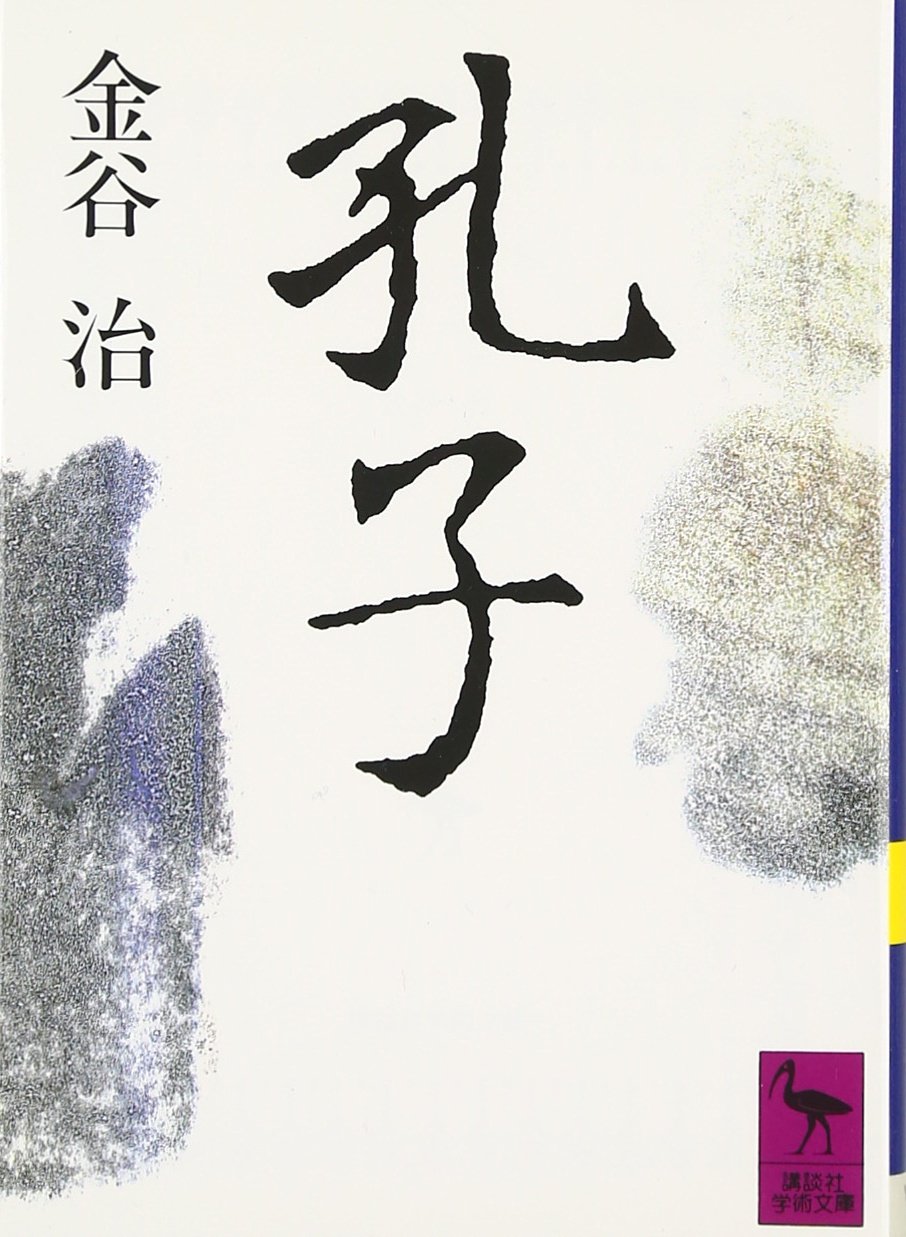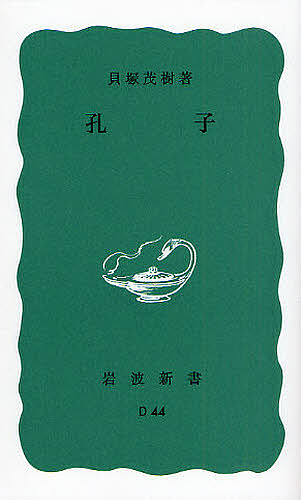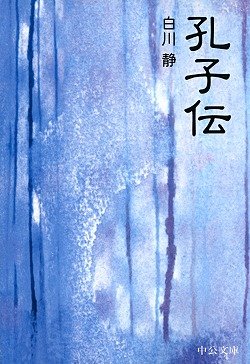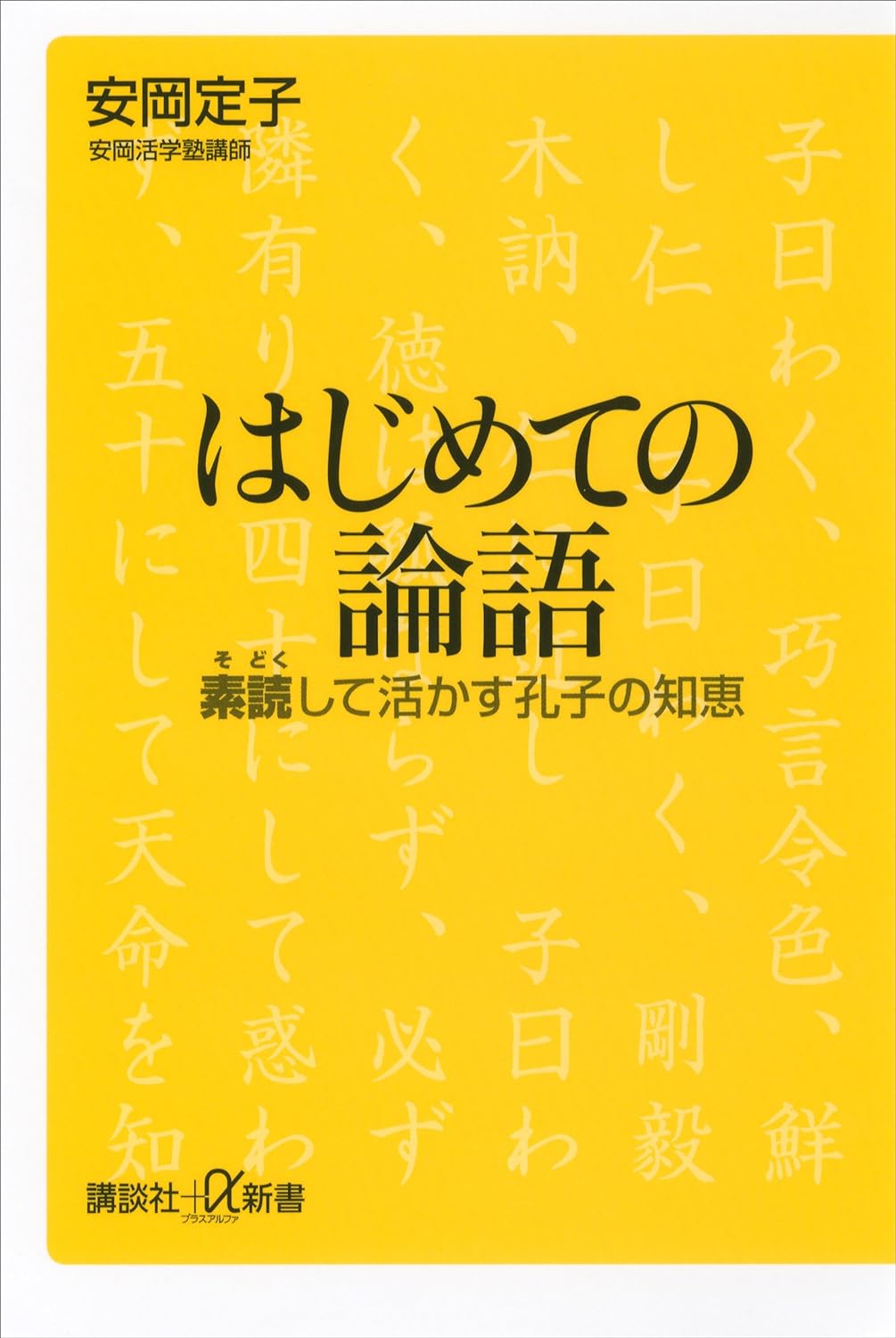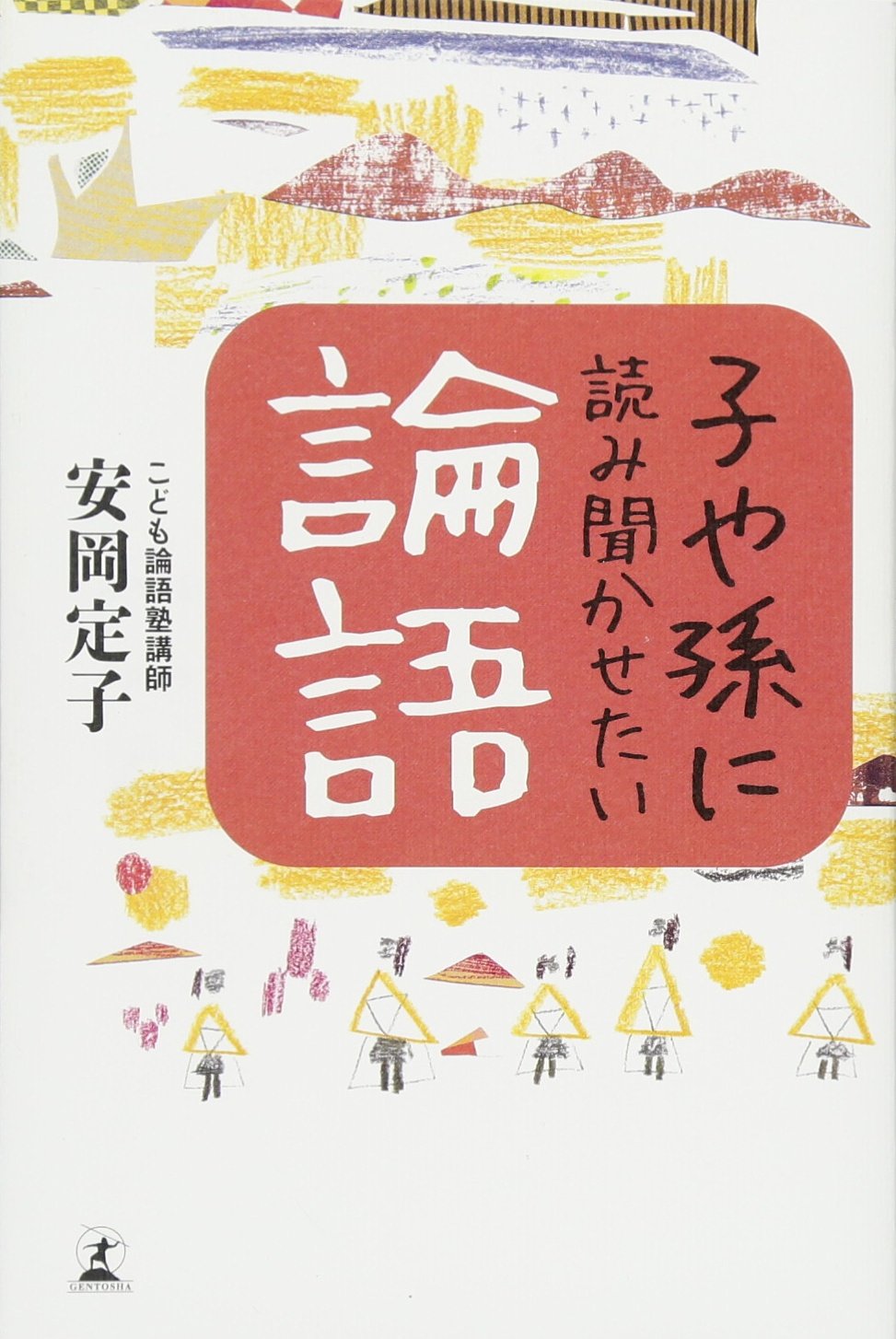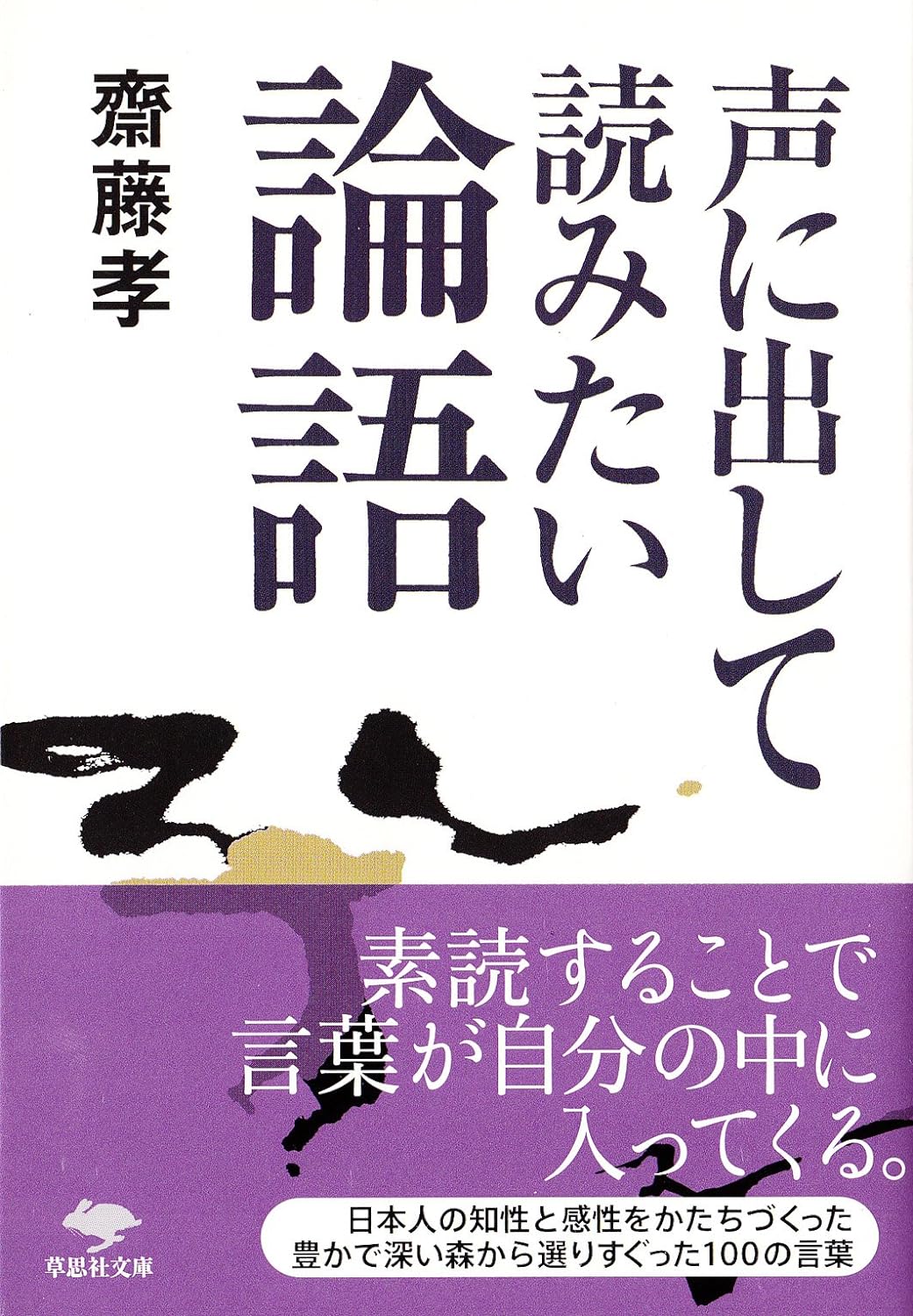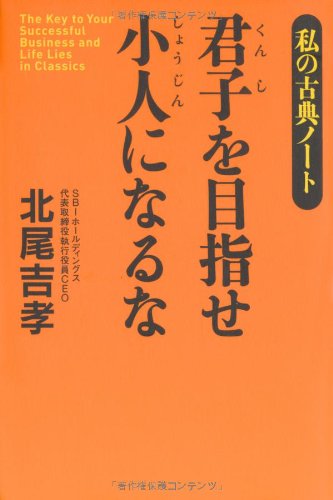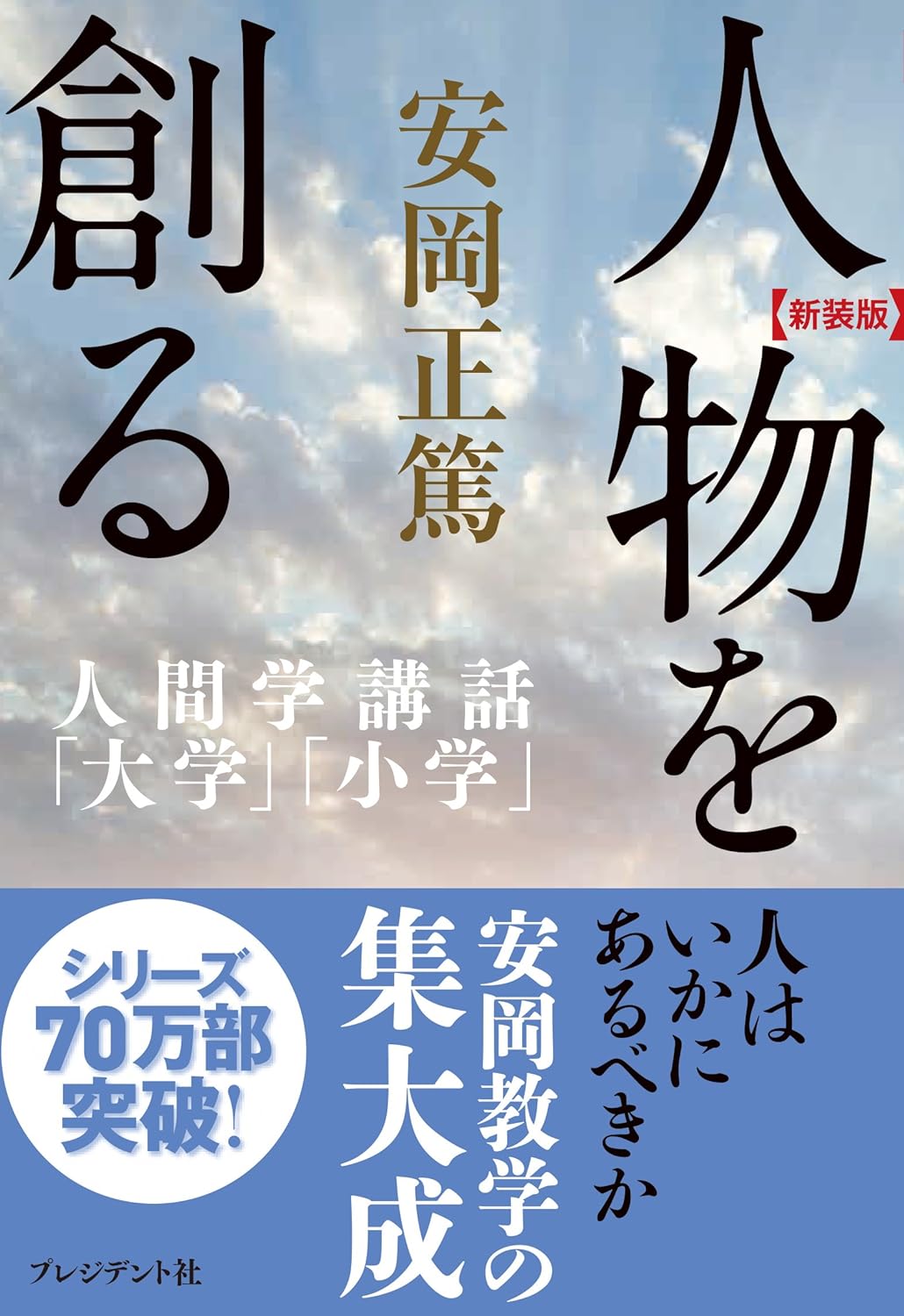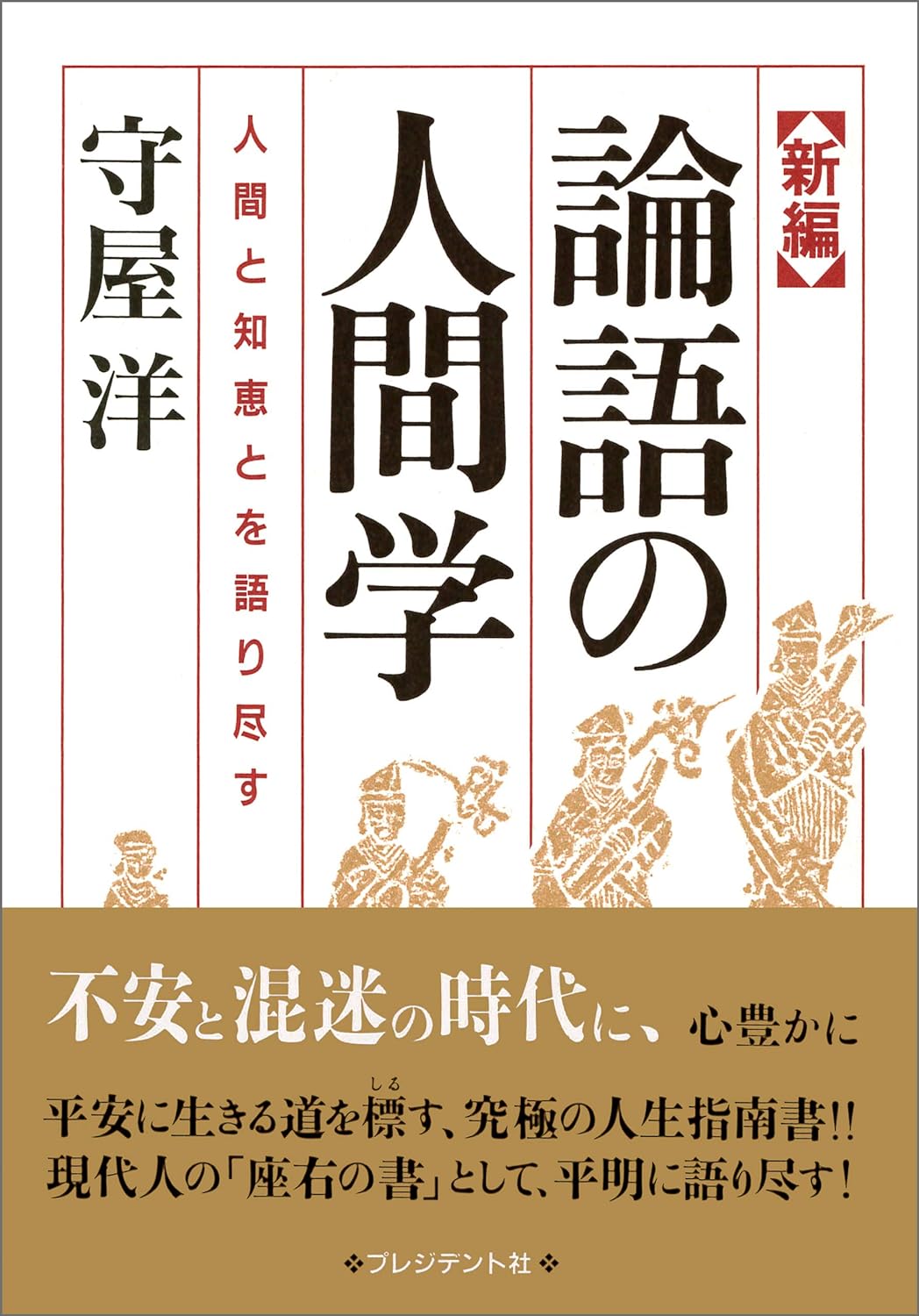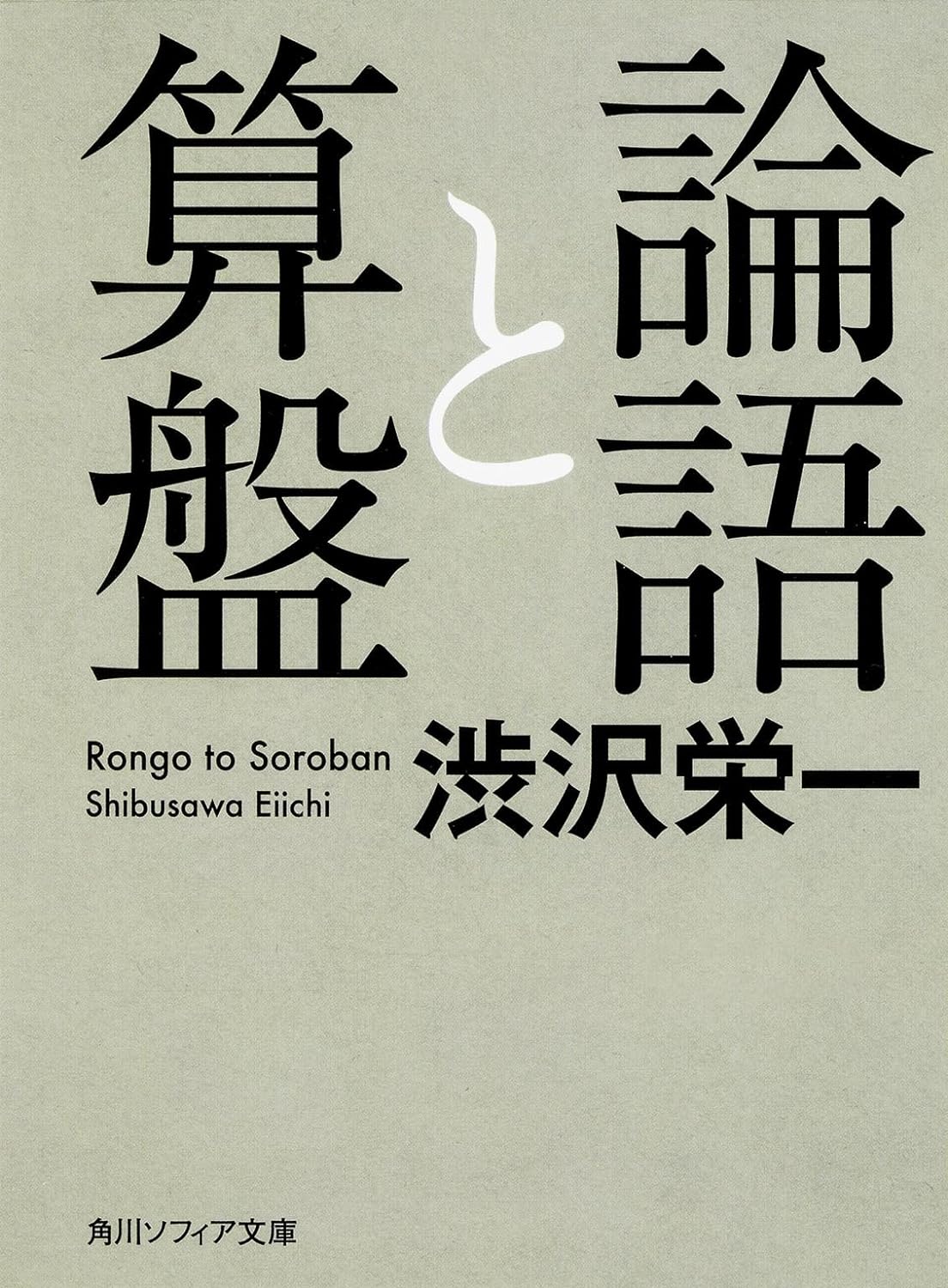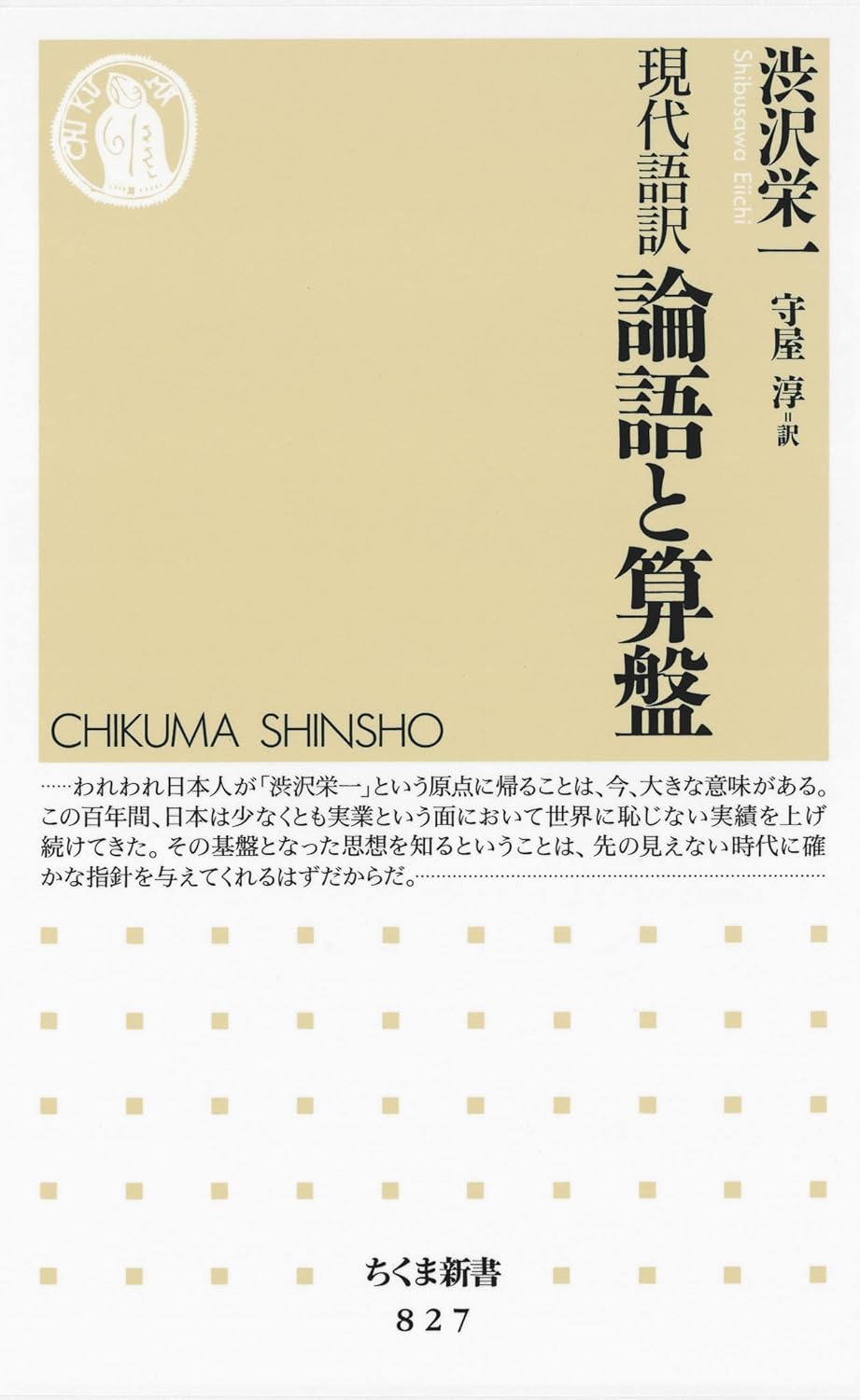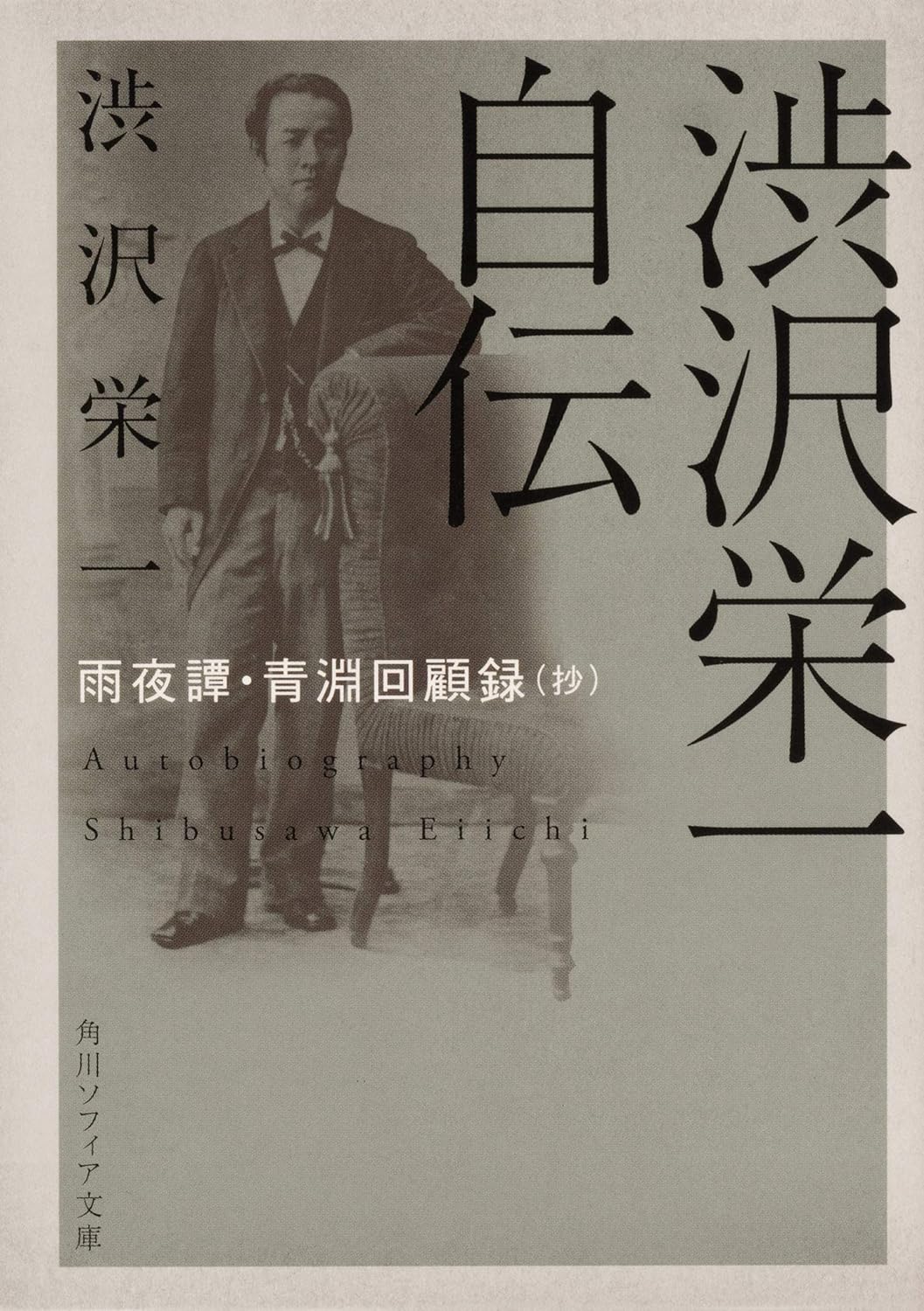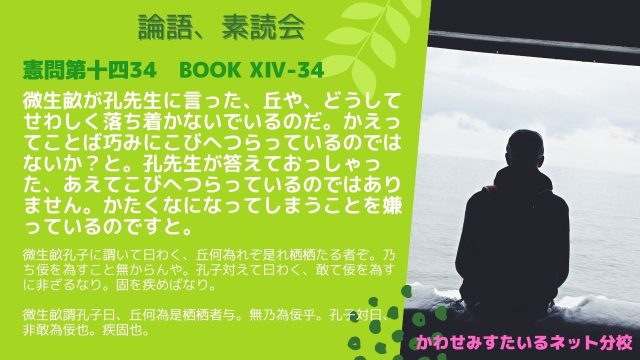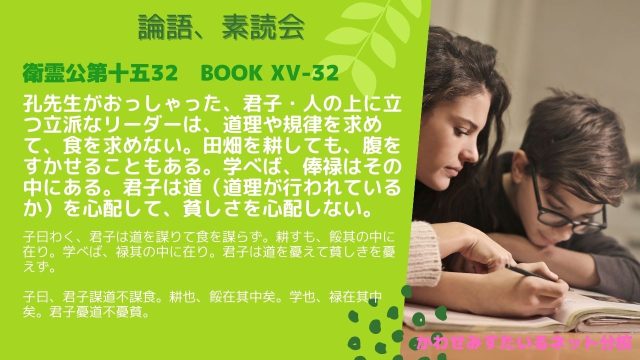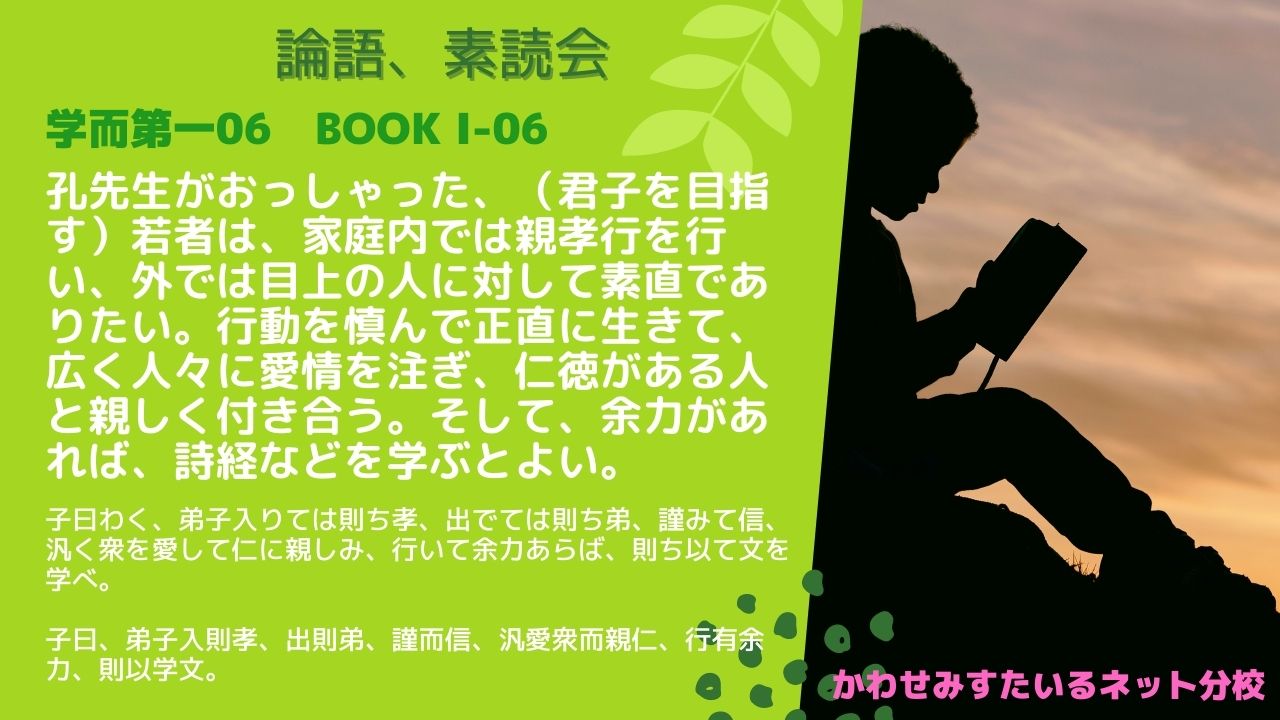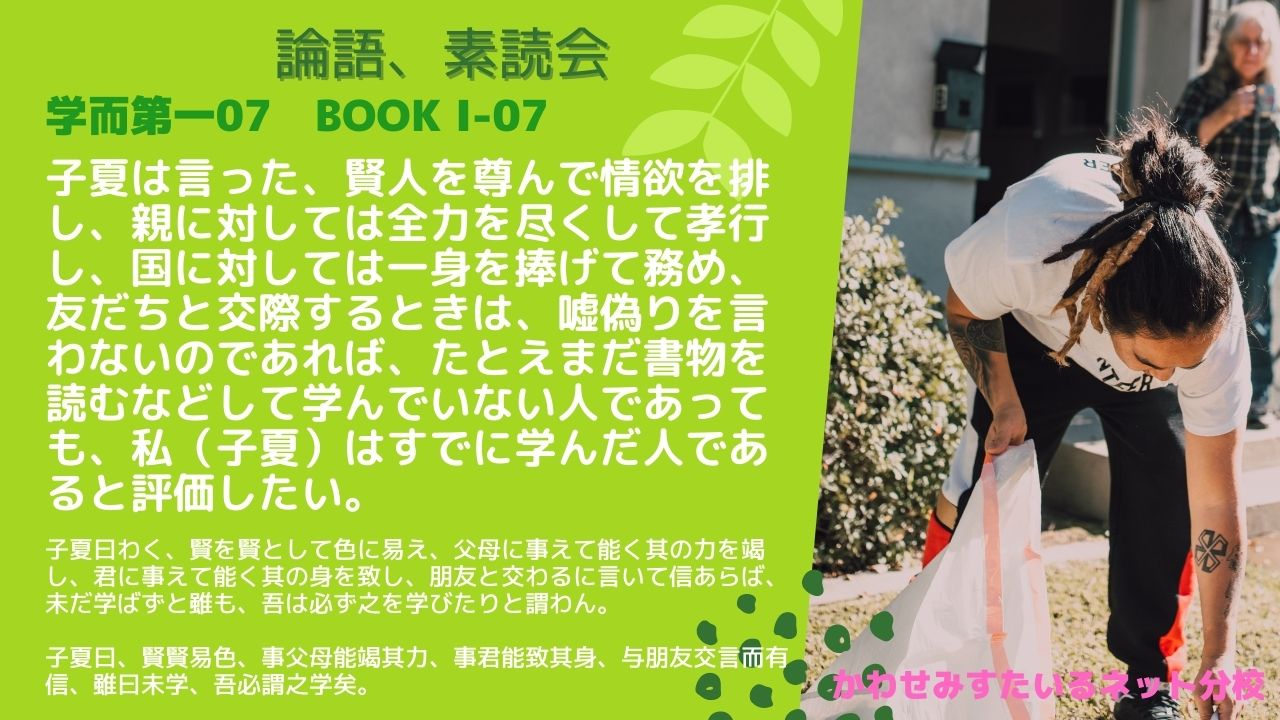素読会テキスト
田部井文雄 安岡定子
『こども論語塾』
(ポプラ社)
初めてのお子さんや未就学のお子さんが多い場合に利用します。
文字が大きく、解説が大人向け、子ども向けと2種類掲載されているので、お子さんと一緒に読み進め易い内容です。
参考文献
【原文】
吉田賢抗『新釈漢文大系 論語』(明治書院)で確認を取りました。
【解釈】
孔子の人となりやその生涯、弟子たちについてや、時代的な背景を学ぶことで、私なりの解釈を加えています。
『全訳漢辞海 第四版』(三省堂書店)、伊與田覺『現代訳 仮名論語』(論語普及会)、吉田賢抗『新釈漢文大系 論語』(明治書院)、江連隆『論語と孔子の事典』(大修館書店)、諸橋轍次『論語の講義』(大修館書店)、宇野精一『新釈漢文大系 孔子家語』(明治書院)、簡野道明『補註 論語集註』(明治書院)、渡邉義浩『論語集解: ―魏・何晏(集解) (上・下)』(早稲田文庫)、吹野 安・石本 道明『孔子全書 11: 史記 1・孔子全書 12: 史記 2(孔子世家)』(明徳出版社)、金谷治『孔子』(講談社)、貝塚茂樹『孔子』(岩波新書)、白川静『孔子伝』(中央公論新社)
論語の読み下し文について
当ブログでは、『全訳漢辞海 第四版』(三省堂書店)から筆者が思う最適解を選ぶようにしています。その際、伊與田覺『現代訳 仮名論語』(論語普及会)と、吉田賢抗『新釈漢文大系 論語』(明治書院)の読み下し文を参考にしています。検討をする際に参考にした表現は、できるだけ紹介するようにして理解に深度がでるようにしています。
「論語」関連書籍について
以下、素読会を行う際の心構えや、解説をする際の基本になっている書籍をご紹介します。
「論語」の素読を行うにあたって、参考にされるといい書籍です。
私が「論語」に出会い、論語の素読会を行うきっかけになった書籍です。
伝記
渋沢栄一翁のおすすめ書籍です。