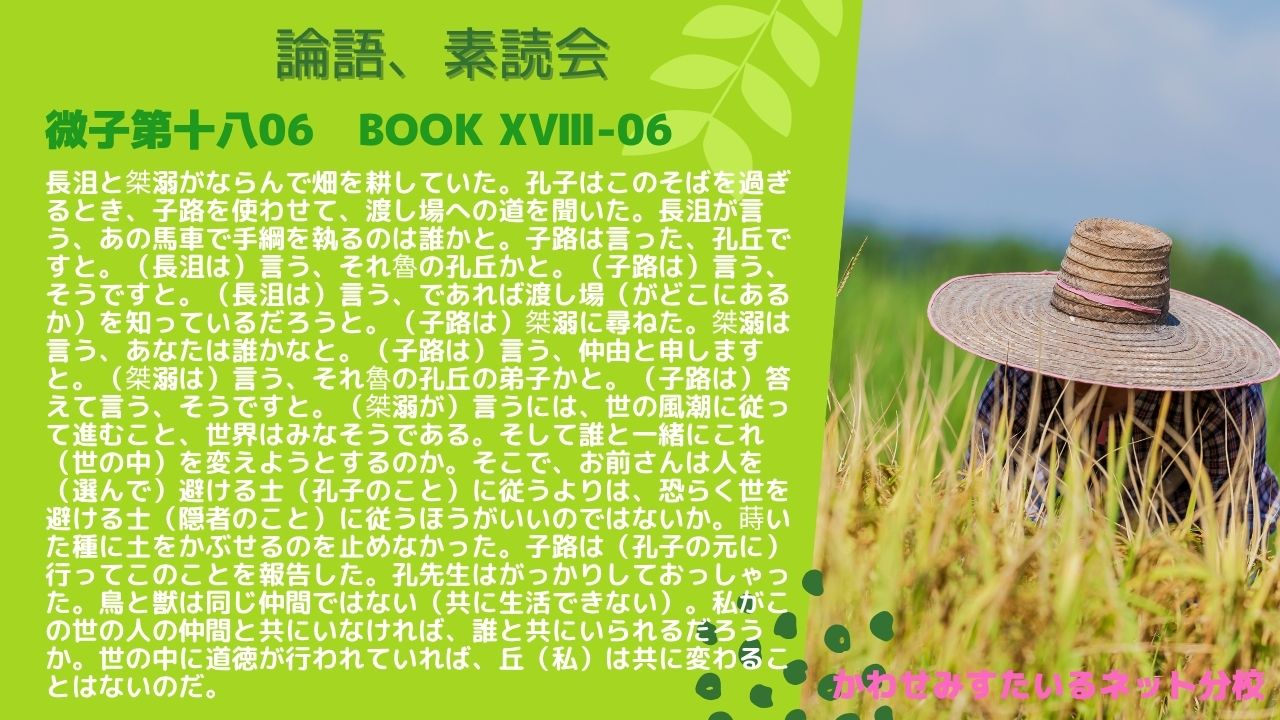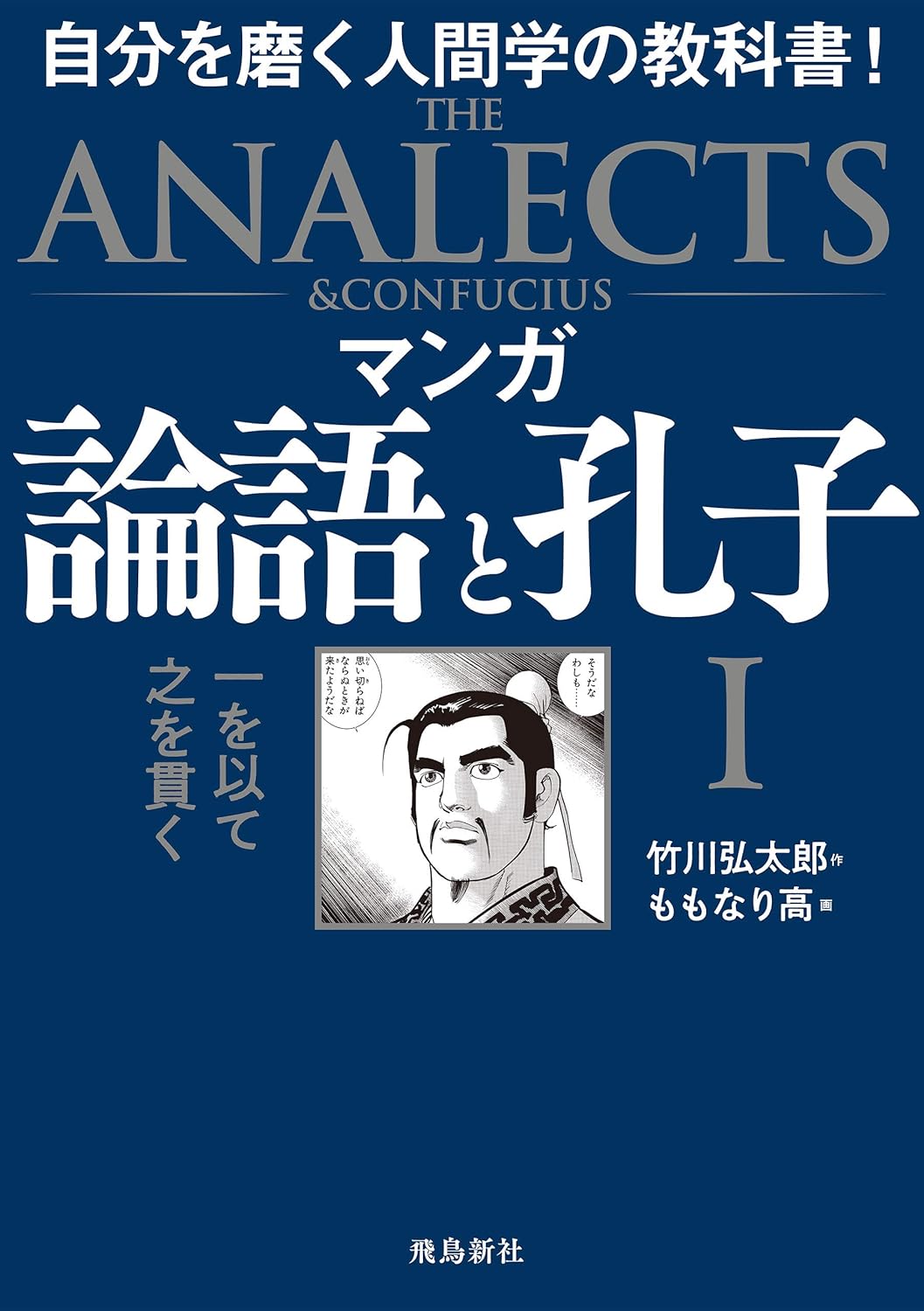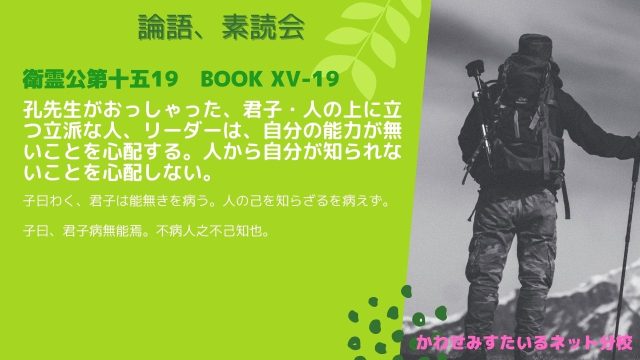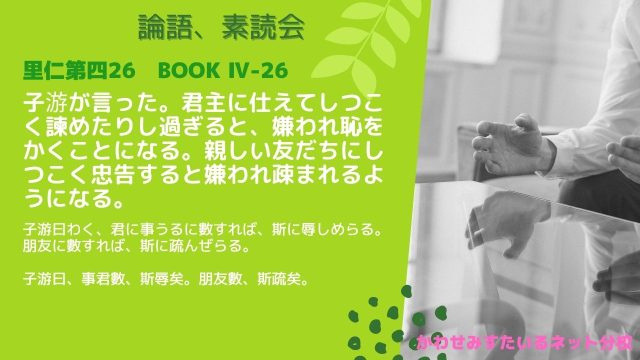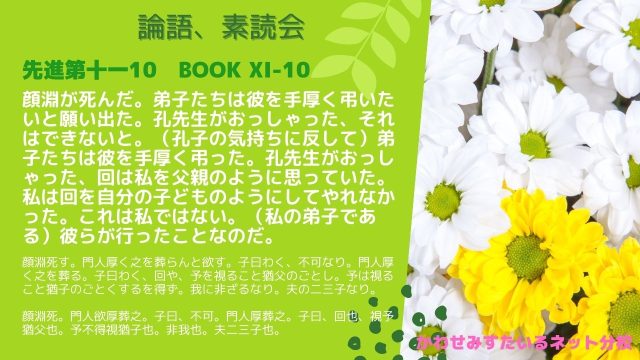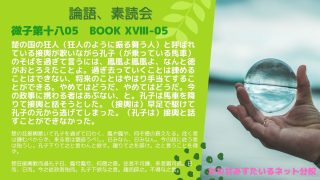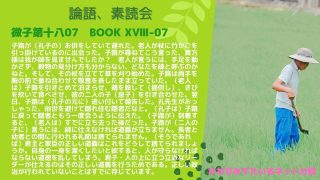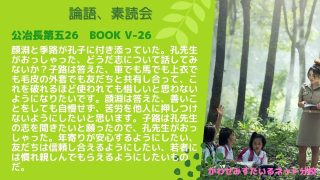長沮と桀溺がならんで畑を耕していた。孔子はこのそばを過ぎるとき、子路を使わせて、渡し場への道を聞いた。長沮が言う、あの馬車で手綱を執るのは誰かと。子路は言った、孔丘ですと。(長沮は)言う、それ魯の孔丘かと。(子路は)言う、そうですと。(長沮は)言う、であれば渡し場(がどこにあるか)を知っているだろうと。(子路は)桀溺に尋ねた。桀溺は言う、あなたは誰かなと。(子路は)言う、仲由と申しますと。(桀溺は)言う、それ魯の孔丘の弟子かと。(子路は)答えて言う、そうですと。(桀溺が)言うには、世の風潮に従って進むこと、世界はみなそうである。そして誰と一緒にこれ(世の中)を変えようとするのか。そこで、お前さんは人を(選んで)避ける士(孔子のこと)に従うよりは、恐らく世を避ける士(隠者のこと)に従うほうがいいのではないか。蒔いた種に土をかぶせるのを止めなかった。子路は(孔子の元に)行ってこのことを報告した。孔先生はがっかりしておっしゃった。鳥と獣は同じ仲間ではない(共に生活できない)。私がこの世の人の仲間と共にいなければ、誰と共にいられるだろうか。世の中に道徳が行われていれば、丘(私)は共に変わることはないのだ。|「論語」微子第十八06
【現代に活かす論語】
世の中をよくしようとする仲間と世の中は変わらないと諦め、距離を取る人たちとは、生活を一緒にするのは難しい。
【解釈】
長沮(ちょうそ) … 隠者(いんじゃ)の名。「論語」の登場人物|論語、素読会
桀溺(けつでき) … 隠者(いんじゃ)の名。「論語」の登場人物|論語、素読会
※隠者は俗世を避けて隠れ住む人。世を避けて仕官しない人。
子路(しろ)仲由(ちゅうゆう) … 姓は仲(ちゅう)、名は由(ゆう)、字は子路(しろ)・季路(きろ)。孔子より九歳若い。孔子のボディガード役を果たした。「論語」の登場人物|論語、素読会
孔丘(こうきゅう)丘(きゅう) … 孔子(こうし)。姓は孔、名は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。仲は次男のこと。「論語」の登場人物|論語、素読会
長沮・桀溺耦して耕す。孔子之を過ぐ、子路をして津を問わしむ。長沮曰わく、夫の輿を執る者は誰とか為す。子路曰わく、孔丘と為す。曰わく、是れ魯の孔丘か。曰わく、是なり。曰わく、是ならば津を知らん。桀溺に問う。桀溺曰わく、子は誰とか為す。曰わく、仲由と為す。曰わく、是れ魯の孔丘の徒か。対えて曰わく、然り。曰わく、滔滔たる者天下皆是なり。而して誰と以にか之を易えん。且つ而其の人を辟くる士に従わんよりは、豈世を辟くるの士に従うに若かんや。耰して輟まず。子路行き以て告ぐ。夫子憮然として曰わく、鳥獣は与に群を同じくすべからず。吾斯の人の徒と与にするに非ずして誰と与にかせん。天下道有らば、丘は与に易えざるなり。|「論語」微子第十八06
長沮桀溺耦而耕。孔子過之、使子路問津焉。長沮曰、夫執輿者為誰。子路曰、為孔丘。曰、是魯孔丘与。曰、是也。曰、是知津矣。問於桀溺。桀溺曰、子為誰。曰、為仲由。曰、是魯孔丘之徒与。対曰、然。曰、滔滔者天下皆是也。而誰以易之。且而与其従辟人之士也、豈若従辟世之士哉。耰而不輟。子路行以告。夫子憮然曰、鳥獣不可与同羣。吾非斯人之徒、与而誰与。天下有道、丘不与易也。
「耦」(ぐう)は二人ならんで畑仕事をする。「津」(しん)は渡し場、つ。「輿」(よ)は車の人や物を積載する部分、乗り物の車。「夫」(かの)はあの。「子」(し)はあなた。「徒」(と)は先生に従って学問や技芸を学んでいる門人、弟子。「滔滔」(とうとう)は世の風潮に従って進みゆくさま。「者」(もの)はもの、こと。「天下」(てんか)は国全体、または世界。「而」(しこうして)はそして、また。「而」(なんじ)はあなた、おまえ。「易」(かえる)は変化する。「辟」(さける)はかわす、のがれる。「士」(し)は人に対する美称。ここでは孔子のこと。「豈」(あに)は恐らく…であろう。「若」(しく)はAはBに及ばない。「耰」(ゆう)は種をまいたのち、土をかぶせる。「輟」(やむ)は中止する。「夫子」(ふうし)は孔子の尊称。「憮然」(ぶぜん)は失意でがっかりするさま。「鳥獣」(ちょうじゅう)は鳥や獣、禽獣。「群」(ぐん)は仲間。「徒」(と)は仲間、ともがら、とも。「与」(とも)はいっしょに何かをしたり、動作が関係する対象を表す。「道」(みち)は道義。正しい政治。『道』とは?|論語、素読会
長沮と桀溺がならんで畑を耕していた。孔子はこのそばを過ぎるとき、子路を使わせて、渡し場への道を聞いた。長沮が言う、あの馬車で手綱を執るのは誰かと。子路は言った、孔丘ですと。(長沮は)言う、それ魯の孔丘かと。(子路は)言う、そうですと。(長沮は)言う、であれば渡し場(がどこにあるか)を知っているだろうと。(子路は)桀溺に尋ねた。桀溺は言う、あなたは誰かなと。(子路は)言う、仲由と申しますと。(桀溺は)言う、それ魯の孔丘の弟子かと。(子路は)答えて言う、そうですと。(桀溺が)言うには、世の風潮に従って進むこと、世界はみなそうである。そして誰と一緒にこれ(世の中)を変えようとするのか。そこで、お前さんは人を(選んで)避ける士(孔子のこと)に従うよりは、恐らく世を避ける士(隠者のこと)に従うほうがいいのではないか。蒔いた種に土をかぶせるのを止めなかった。子路は(孔子の元に)行ってこのことを報告した。孔先生はがっかりしておっしゃった。鳥と獣は同じ仲間ではない(共に生活できない)。私がこの世の人の仲間と共にいなければ、誰と共にいられるだろうか。世の中に道徳が行われていれば、丘(私)は共に変わることはないのだ。
【解説】
集解(古註)では「子路曰、為孔丘。曰、是魯孔丘与。曰、是也。」
集註(新註)では「子路曰、為孔丘。曰、是魯孔丘与。対曰、是也。」
と記載されています。
続いて「曰、是魯孔丘之徒与。対曰、然。」は集解、集註とも同じです。「対」(こたえる)は下の者が目上の者に対して答える場合に使う言葉です。どちらも子路が答えていますので、揃えたのかも知れません。
当ブログでは、古註を採用しますが、素読は『現代訳 仮名論語』に倣って、新註で行っています。
この章句でいう、「人を避ける」というのは、世を避けると併記することで印象を残す表現で、道・道徳が分からない人を判断してその人から距離を取るということです。
章句の最後の「私は共に変わることはない」というのは、人々と生活しながら、よい世の中にしようと人に影響影響を与え、一緒に成長していく必要がない。という意味だと思います。
二人の隠者が畑仕事をする手を止めずに、子路と会話をする場面を想像してみます。一人目は孔子と知って(なんとなく予想していて)相手にしないという態度です。二人目は孔子の弟子でいることを考え直すように子路に促しています。二人は恐らく、知識を持っている知者であるにも関わらず、諦め・隠れることを選択しています。対して、世の中を変えようとする孔子をただ対岸から眺めているかのような態度に感じます。当時の世の中の知識層は概ねこのような雰囲気だったのではないでしょうか。孔子の悔しさが滲む章句です。
孔子は正しい政治が行われていない場合は、距離を取るように弟子に伝えています。この孔子の考えと、この隠者の考えの違いはなんでしょうか。
孔子は正論を振りかざして、疲弊することを心配しているように感じます。志は変えずに、政事が変わるのを待つという考えのようです。これは仮説ですが、当時は主君や大夫たちの在位が短かったことが関係するのではないかと思います。また、距離を取って違う場所で仕官することも選択肢にあったのではないかと思います。
「論語」参考文献|論語、素読
微子第十八05< | >微子第十八07
【原文・白文】
長沮桀溺耦而耕。孔子過之、使子路問津焉。長沮曰、夫執輿者為誰。子路曰、為孔丘。曰、是魯孔丘与。曰、是也。曰、是知津矣。問於桀溺。桀溺曰、子為誰。曰、為仲由。曰、是魯孔丘之徒与。対曰、然。曰、滔滔者天下皆是也。而誰以易之。且而与其従辟人之士也、豈若従辟世之士哉。耰而不輟。子路行以告。夫子憮然曰、鳥獣不可与同群。吾非斯人之徒与而誰与。天下有道、丘不与易也。
<長沮桀溺耦而耕。孔子過之、使子路問津焉。長沮曰、夫執輿者爲誰。子路曰、爲孔丘。曰、是魯孔丘與。曰、是也。曰、是知津矣。問於桀溺。桀溺曰、子爲誰。曰、爲仲由。曰、是魯孔丘之徒與。對曰、然。曰、滔滔者天下皆是也。而誰以易之。且而與其從辟人之士也、豈若從辟世之士哉。耰而不輟。子路行以告。夫子憮然曰、鳥獸不可與同羣。吾非斯人之徒與而誰與。天下有道、丘不與易也。>
(長沮・桀溺耦して耕す。孔子之を過ぐ、子路をして津を問わしむ。長沮曰わく、夫の輿を執る者は誰とか為す。子路曰わく、孔丘と為す。曰わく、是れ魯の孔丘か。曰わく、是なり。曰わく、是ならば津を知らん。桀溺に問う。桀溺曰わく、子は誰とか為す。曰わく、仲由と為す。曰わく、是れ魯の孔丘の徒か。対えて曰わく、然り。曰わく、滔滔たる者天下皆是なり。而して誰と以にか之を易えん。且つ而其の人を辟くる士に従わんよりは、豈世を辟くるの士に従うに若かんや。耰して輟まず。子路行き以て告ぐ。夫子憮然として曰わく、鳥獣は与に群を同じくすべからず。吾斯の人の徒と与にするに非ずして誰と与にかせん。天下道有らば、丘は与に易えざるなり。)
【読み下し文】
長沮(ちょうそ)・桀溺(けつでき)耦(ぐう)して耕(たがや)す。孔子(こうし)之(これ)を過(す)ぐ、子路(しろ)をして津(しん)を問(と)わしむ。長沮(ちょうそ)曰(い)わく、夫(か)の輿(よ)を執(と)る者(もの)は誰(たれ)とか為(な)す。子路(しろ)曰(い)わく、孔丘(こうきゅう)と為(な)す。曰(い)わく、是(こ)れ魯(ろ)の孔丘(こうきゅう)か。曰(い)わく、是(これ)なり。曰(い)わく、是(これ)ならば津(しん)を知(し)らん。桀溺(けつでき)に問(と)う。桀溺(けつでき)曰(い)わく、子(し)は誰(たれ)とか為(な)す。曰(い)わく、仲由(ちゅうゆう)と為(な)す。曰(い)わく、是(こ)れ魯(ろ)の孔丘(こうきゅう)の徒(と)か。対(こた)えて曰(い)わく、然(しか)り。曰(い)わく、滔滔(とうとう)たる者(もの)天下(てんか)皆(みな)是(これ)なり。而(しこう)して誰(たれ)と以(とも)にか之(これ)を易(か)えん。且(か)つ而(なんじ)其(そ)の人(ひと)を辟(さ)くる士(し)に従(したが)わんよりは、豈(あに)世(よ)を辟(さ)くるの士(し)に従(したが)うに若(し)かんや。耰(ゆう)して輟(や)まず。子路(しろ)行(ゆ)き以(もっ)て告(つ)ぐ。夫子(ふうし)憮然(ぶぜん)として曰(のたま)わく、鳥獣(ちょうじゅう)は与(とも)に群(ぐん)を同(おな)じくすべからず。吾(われ)斯(こ)の人(ひと)の徒(と)と与(とも)にするに非(あら)ずして誰(たれ)と与(とも)にかせん。天下(てんか)道(みち)有(あ)らば、丘(きゅう)は与(とも)に易(か)えざるなり。
「論語」参考文献|論語、素読会
微子第十八05< | >微子第十八07