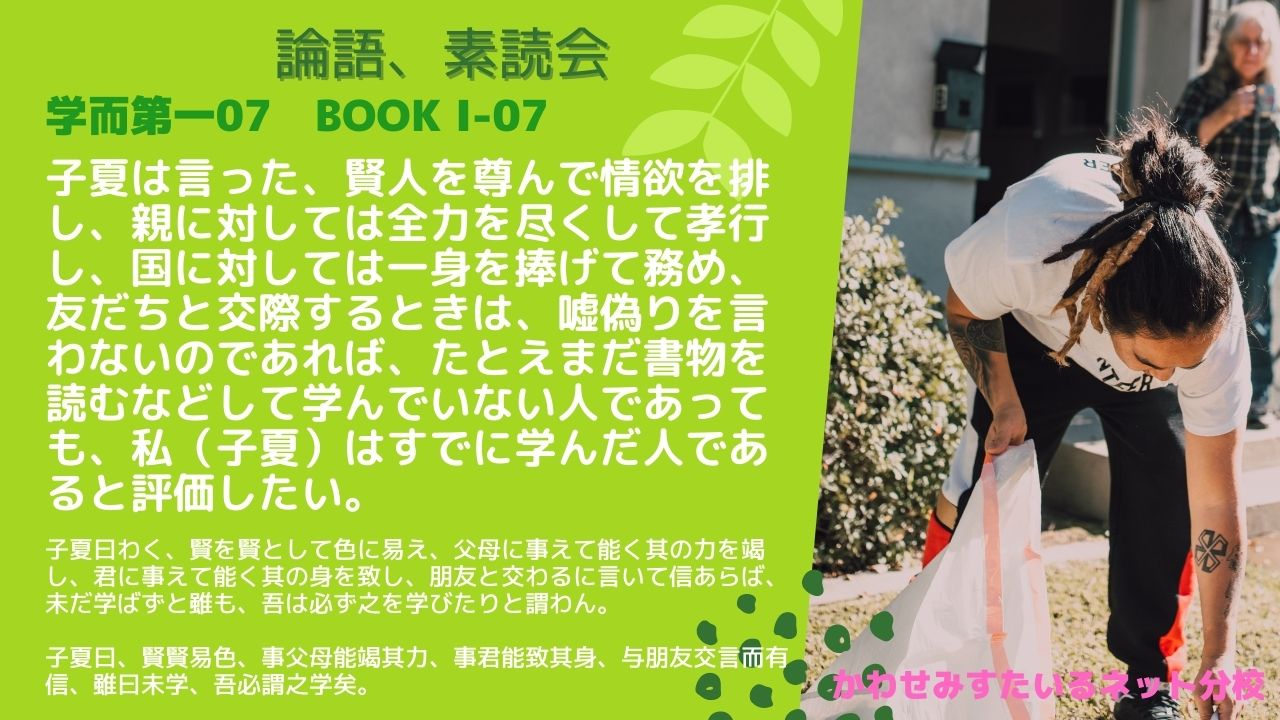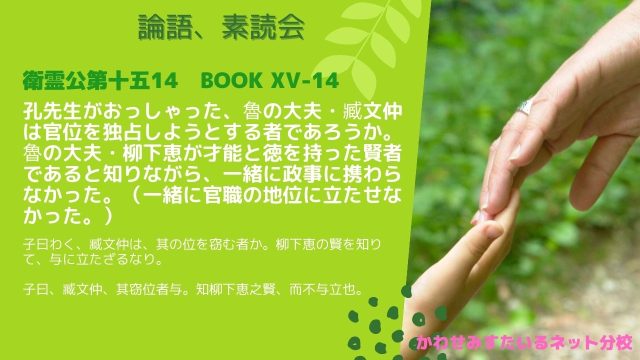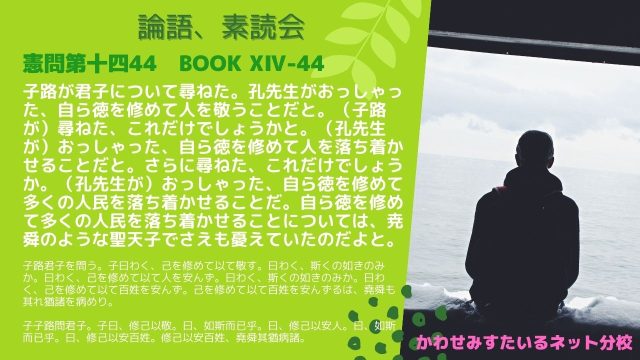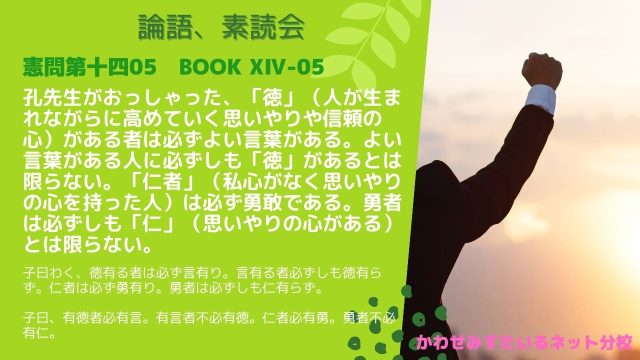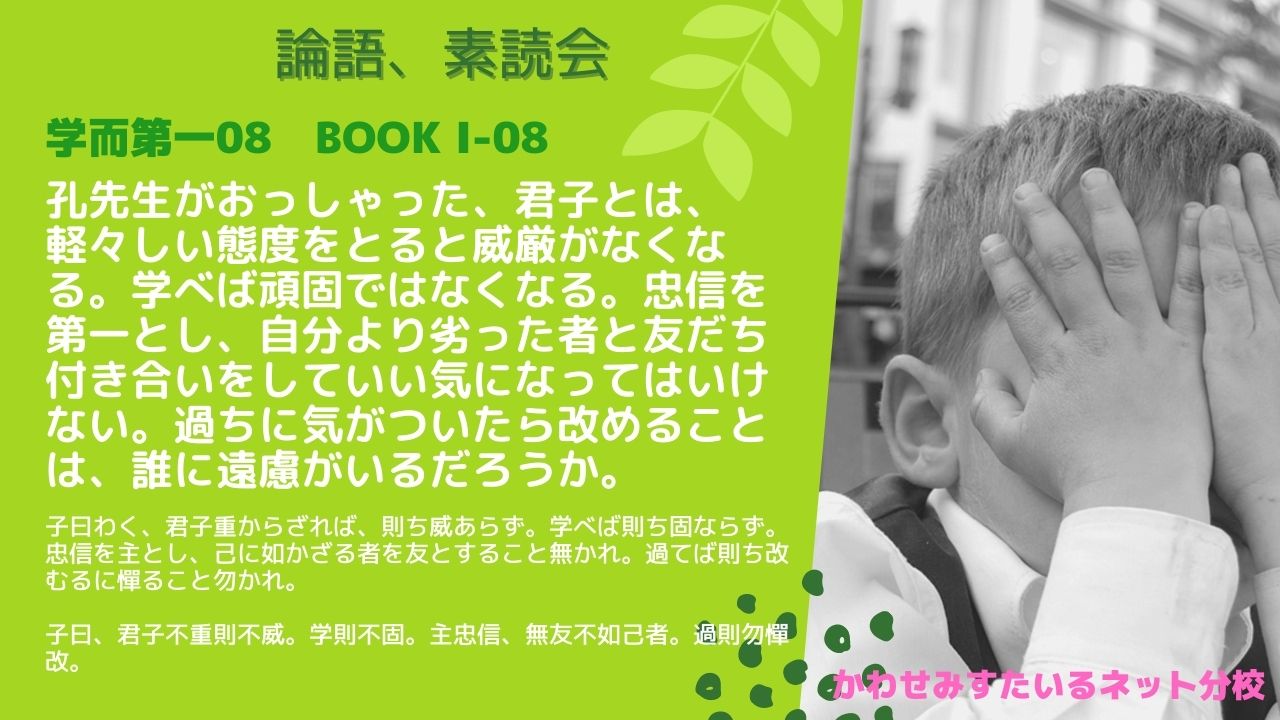子夏は言った、賢人を尊んで情欲を排し、親に対しては全力を尽くして孝行し、国に対しては一身を捧げて務め、友だちと交際するときは、嘘偽りを言わないのであれば、たとえまだ書物を読むなどして学んでいない人であっても、私(子夏)はすでに学んだ人であると評価したい。|「論語」学而第一07
【現代に活かす論語】
たとえ書物を読むなど学びが少ない人であっても、善い人の善い行いを見習って規則正しい生活をし、熱心に親孝行をし、懸命に仕事に励む。そして友人と嘘偽りなく付き合うのであれば、すでに学んだ人と評価することができる。
『論語、素読会』YouTube動画
00:00 章句の検討
19:15 「学而第一」01-16 素読
2021.2.23収録
【解釈】
子夏(しか) … 姓は卜(ぼく)、名は「商」、字(あざな)は「子夏」。孔子より四十四歳年下。衛の人。つつましやかでまじめな人柄で、また消極的だったらしい。「論語」の登場人物|論語、素読会
子夏曰わく、賢を賢として色に易え、父母に事えて能く其の力を竭し、君に事えて能く其の身を致し、朋友と交わるに言いて信あらば、未だ学ばずと雖も、吾は必ず之を学びたりと謂わん。|「論語」学而第一07
子夏曰、賢賢易色、事父母能竭其力、事君能致其身、与朋友交言而有信、雖曰未学、吾必謂之学矣。
「賢」(けん)は賢いこと、賢い人。「色」(いろ)は敬愛する気持ち、愛情。もしくはその対象である恋人を指す。「竭」(つくす)は尽くすの意。「君」とは国のこと。「致其身」は身を捧げて勤めること。「信」は信頼を重んじて欺かないこと。『信』とは?|論語、素読会 「雖」は、(いえども)と読む。
子夏は言った、賢人を尊んで情欲を排し、親に対しては全力を尽くして孝行し、国に対しては一身を捧げて務め、友だちと交際するときは、嘘偽りを言わないのであれば、たとえまだ書物を読むなどして学んでいない人であっても、私(子夏)はすでに学んだ人であると評価したい。
【解説】
孔子の死後も門人たちを教育し、自身も政治家から相談を受ける立場であったと伝わる「子夏」が残した言葉ですので、孔子が他の章句でも繰り返し伝えようとしている、実践を重要視する心が伝わってくる内容です。
「論語」参考文献|論語、素読会
学而第一06< | >学而第一08
【原文・白文】
子夏曰、賢賢易色、事父母能竭其力、事君能致其身、与朋友交言而有信、雖曰未学、吾必謂之学矣。
<子夏曰、賢賢易色、事父母能竭其力、事君能致其身、與朋友交言而有信、雖曰未學、吾必謂之學矣。>
(子夏曰わく、賢を賢として色に易え、父母に事えて能く其の力を竭し、君に事えて能く其の身を致し、朋友と交わるに言いて信あらば、未だ学ばずと雖も、吾は必ず之を学びたりと謂わん。)
【読み下し文】
子夏(しか)曰(い)わく、賢(けん)を賢(けん)として色(いろ)に易(か)え、父母(ふぼ)に事(つか)えて能(よ)く其(そ)の力(ちから)を竭(つく)し、君(きみ)に事(つか)えて能(よ)く其(そ)の身(み)を致(いた)し、朋友(ほうゆう)と交(まじ)わるに言(い)いて信(しん)あらば、未(いま)だ学(まな)ばずと雖(いえど)も、吾(われ)は必(かなら)ず之(これ)を学(まな)びたりと謂(い)わん。
「論語」参考文献|論語、素読会
学而第一06< | >学而第一08