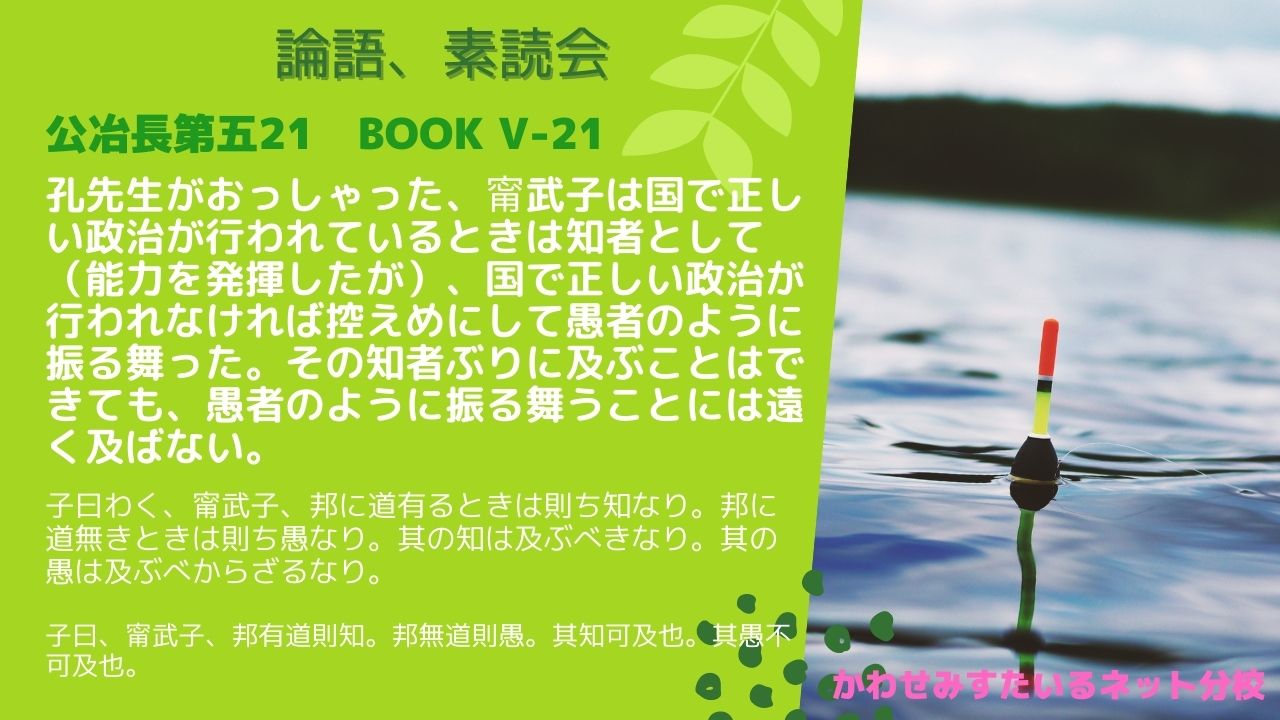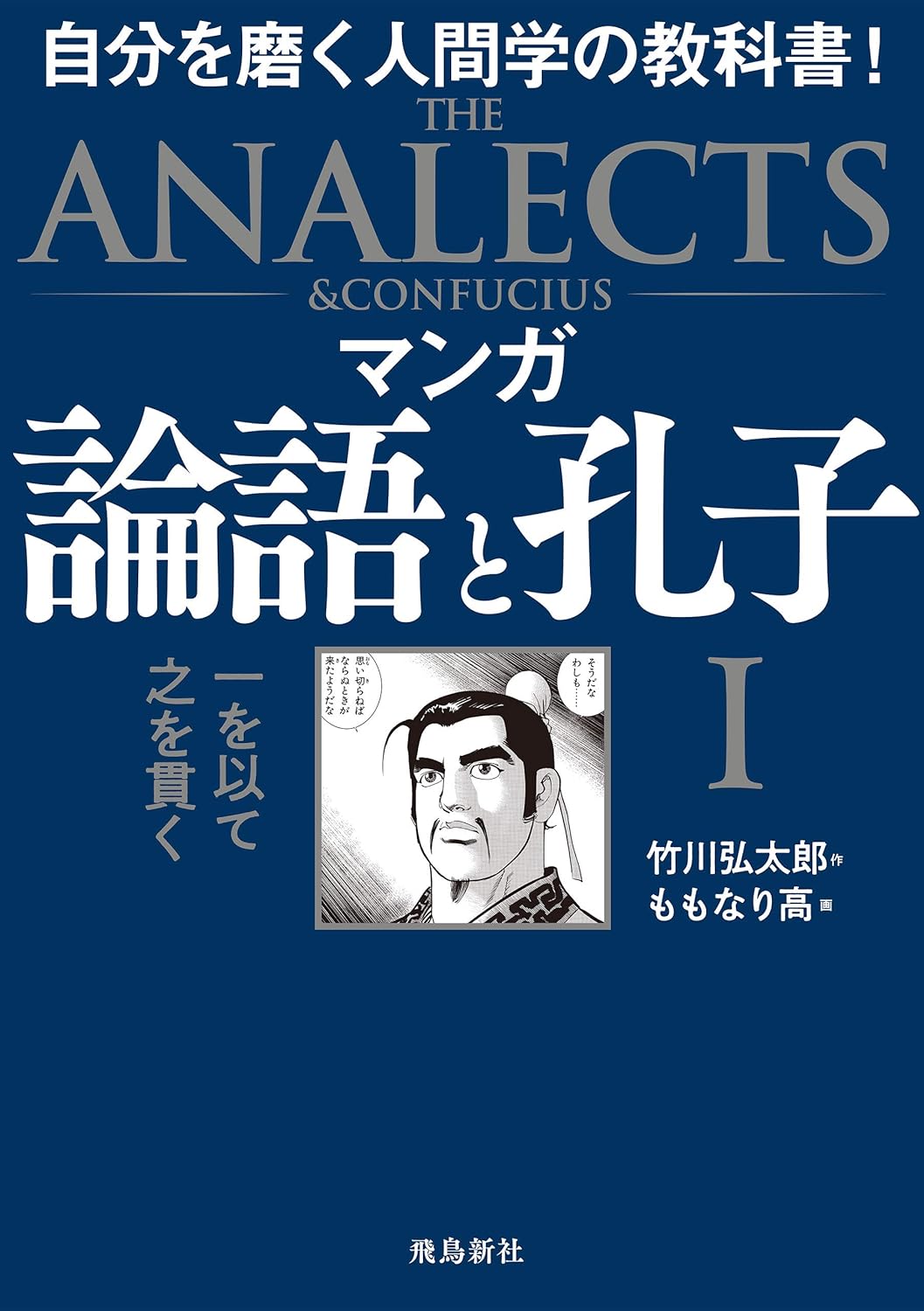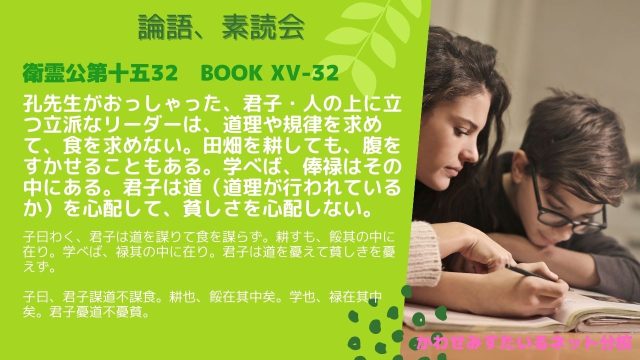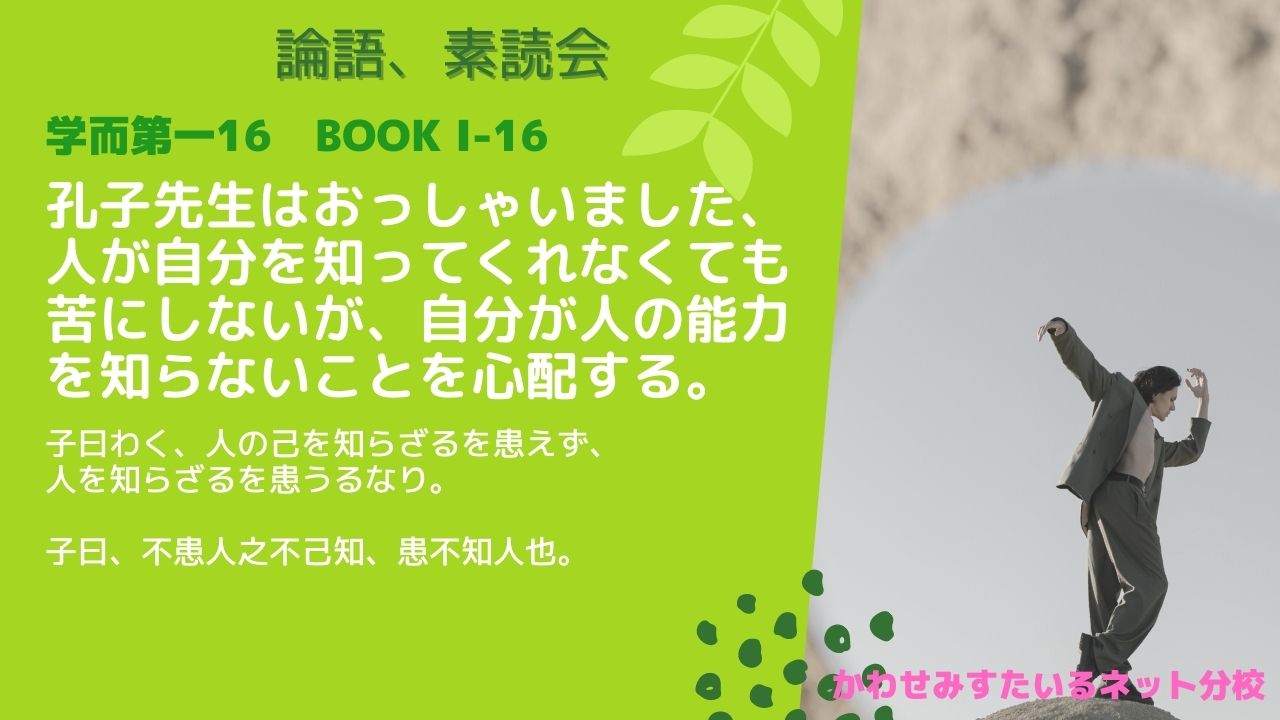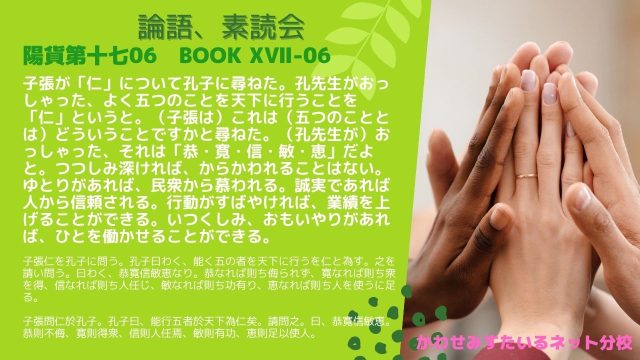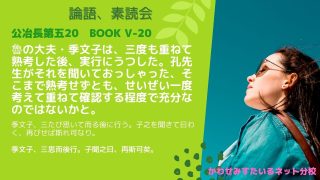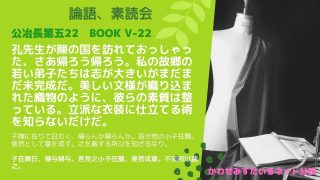孔先生がおっしゃった、甯武子は国で正しい政治が行われているときは知者として(能力を発揮したが)、国で正しい政治が行われなければ控えめにして愚者のように振る舞った。その知者ぶりに及ぶことはできても、愚者のように振る舞うことには遠く及ばない。|「論語」公冶長第五21
【現代に活かす論語】
組織がうまくいっているときに能力を発揮することは誰でもできる。自分のプライドを棄てて危機的な状況を救おうとする姿はなかなか真似できるものではない。
『論語、素読会』YouTube動画
00:00 章句の検討
06:20 「公冶長第五」前半16-28 素読
2021.8.3収録
【解釈】
甯武子(ねいぶし) … 衛(えい)の成公(せいこう)の時の大夫。姓は甯、名は兪(ゆ)、武は贈り名。「論語」の登場人物|論語、素読会
子曰わく、甯武子、邦に道有るときは則ち知なり。邦に道無きときは則ち愚なり。其の知は及ぶべきなり。其の愚は及ぶべからざるなり。|「論語」公冶長第五21
子曰、甯武子、邦有道則知。邦無道則愚。其知可及也。其愚不可及也。
「邦」(くに)は国。「道」(みち)は道義。『道』とは?|論語、素読会 正しい政治。「愚」(ぐ)は控えめで愚かな様子、そのようなひと、愚者。「知」(ち)は知者。『知』とは?|論語、素読会 「及」(およぶ)は同じようにできる、その域に達するの意。
孔先生がおっしゃった、甯武子は国で正しい政治が行われているときは知者として(能力を発揮したが)、国で正しい政治が行われなければ控えめにして愚者のように振る舞った。その知者ぶりに及ぶことはできても、愚者のように振る舞うことには遠く及ばない。
【解説】
「其愚不可及也」の解釈について、文献の比較を行ってみます。
まず、『論語集解』「論語」参考文献|論語、素読会 では、孔安国は「詳愚似実」故に及ばないと言っている。と解説しています。「詳愚似実」は本当の愚者のように振る舞うので真実のようだと解釈するといいのではないでしょうか。対して『論語集注』「論語」参考文献|論語、素読会 では、『春秋左氏伝』の記述をもとに、甯武子が仕えた衛の成公が無道であったため、国を滅ぼすことになったが、甯武子は逃げることなく立ち働いた。周りの士人が嫌がるような処し方であったが、自分の身を保ちさらに君主も救った。この愚直さには及ばないと解釈しています。
愚者のように控えめに振る舞うという解釈と、愚直に国難に立ち向かうという解釈。君主が道を行わなければ、距離を取るべきだという解釈と、あくまでも君主を助けよという解釈の対比です。この章句は解釈によって真逆の意味になるという典型的な例です。
本ブログでは前者の解釈を採用します。というのも、孔子は他の章句でも、道理が行われていない場合は隠れよ(距離を取れ)と言います。「孔先生が顔淵におっしゃった、任用されれば政治を正しく行い、退任すれば世の中からかくれる。ただこのように行えるのは私とお前くらいかなぁ。|「論語」述而第七10」「国に正しい政治が行われてなければ、行動を正しくし、言葉は控えめにする。|「論語」憲問第十四04」「立派なリーダーだな衛の大夫・蘧伯玉は、国の政事が正しく行われているときには国に仕え、国の政事が行われていないときには、(能力を)まとめて懐にしまってしまう。|「論語」衛霊公第十五07」
孔子のこの考えに則れば、自分の身を犠牲にするのではなく、正しい政事が行われるまで待つことを推奨しています。この章句も例外ではないと思うのです。
「論語」参考文献|論語、素読会
公冶長第五20< | >公冶長第五22
【原文・白文】
子曰、甯武子、邦有道則知。邦無道則愚。其知可及也。其愚不可及也。
(子曰わく、甯武子、邦に道有るときは則ち知なり。邦に道無きときは則ち愚なり。其の知は及ぶべきなり。其の愚は及ぶべからざるなり。)
【読み下し文】
子(し)曰(のたま)わく、甯武子(ねいぶし)、邦(くに)に道(みち)有(あ)るときは則(すな)ち知(ち)なり。邦(くに)に道(みち)無(な)きときは則(すなわ)ち愚(ぐ)なり。其(その)の知(ち)は及(およ)ぶべきなり。其(そ)の愚(ぐ)は及(およ)ぶべからざるなり。
「論語」参考文献|論語、素読会
公冶長第五20< | >公冶長第五22