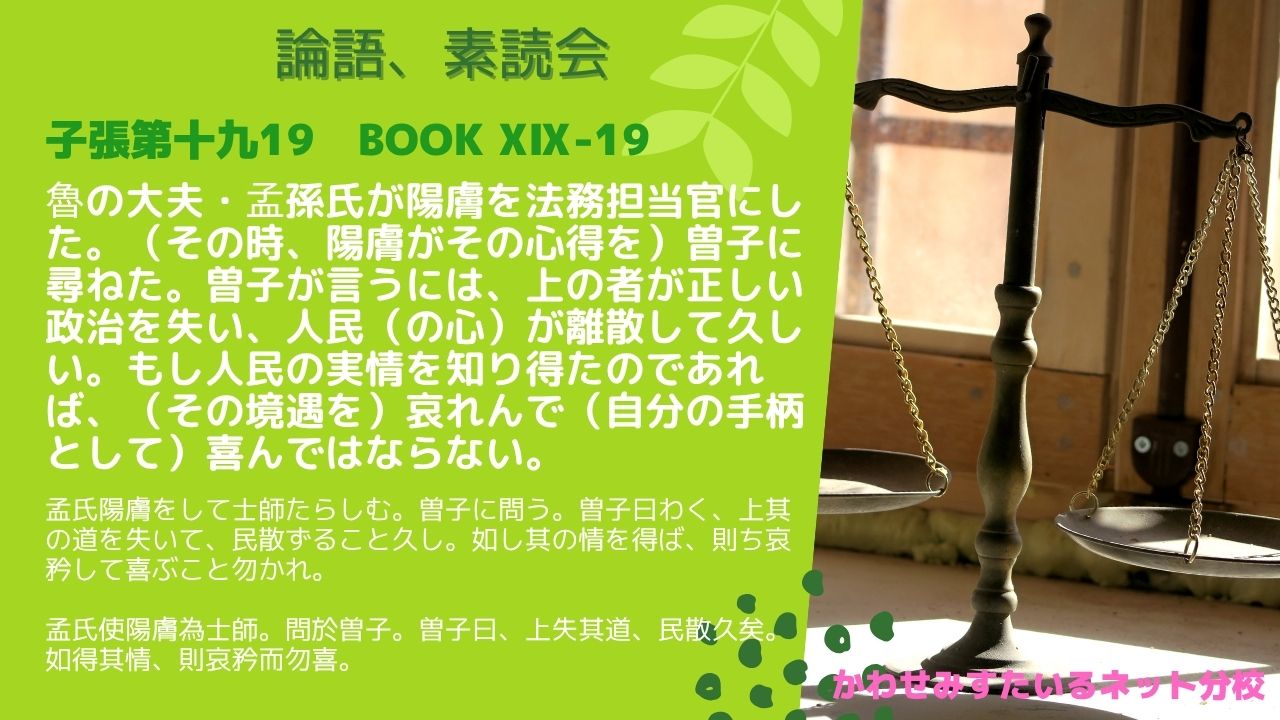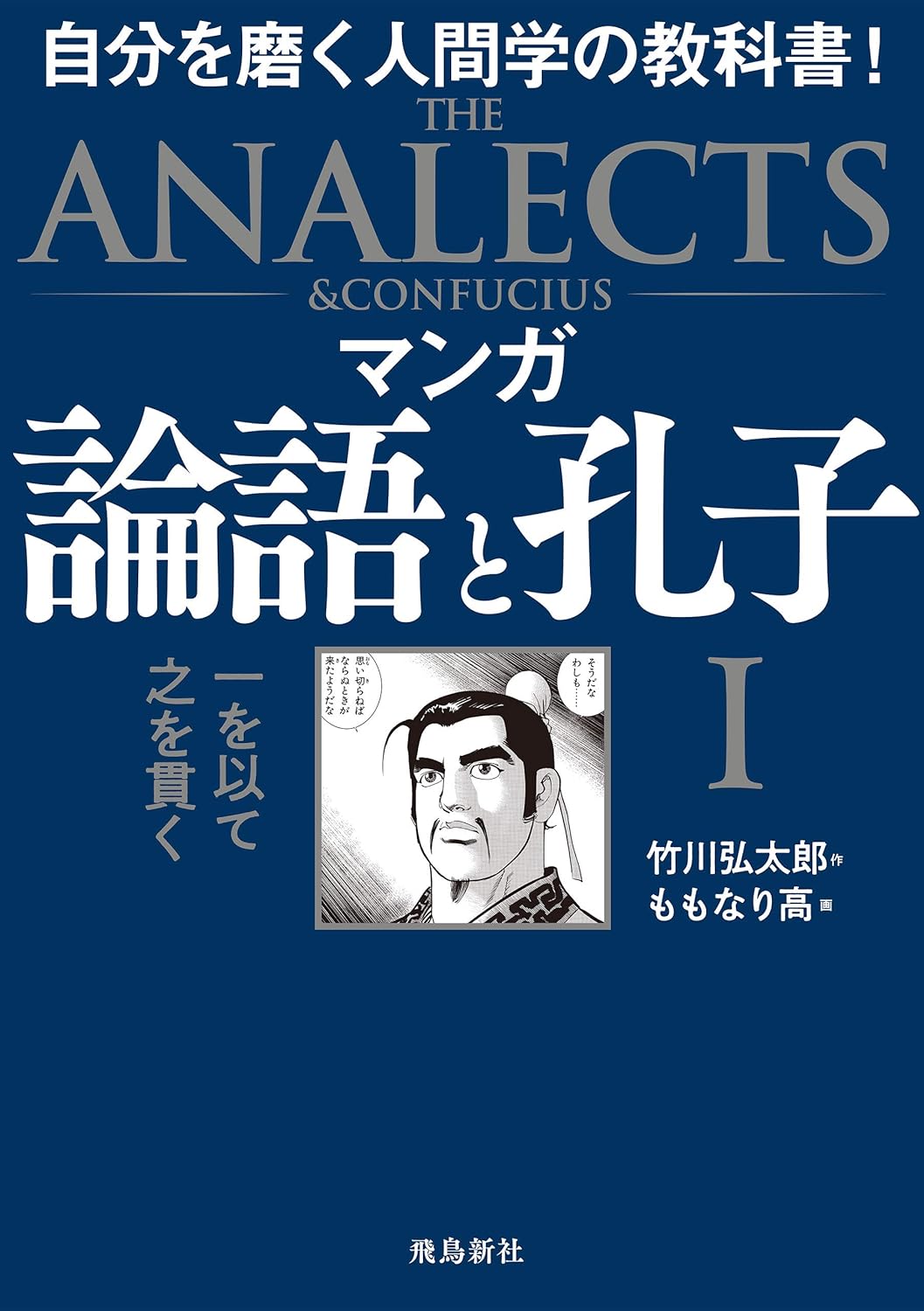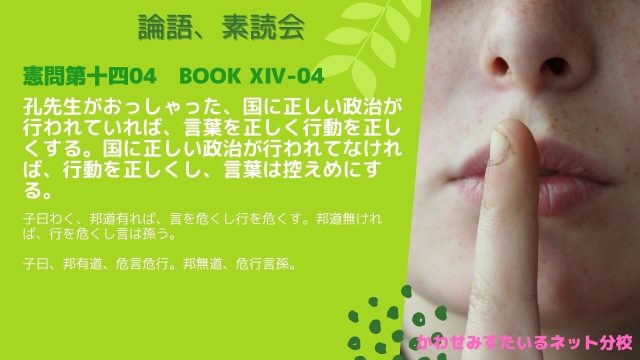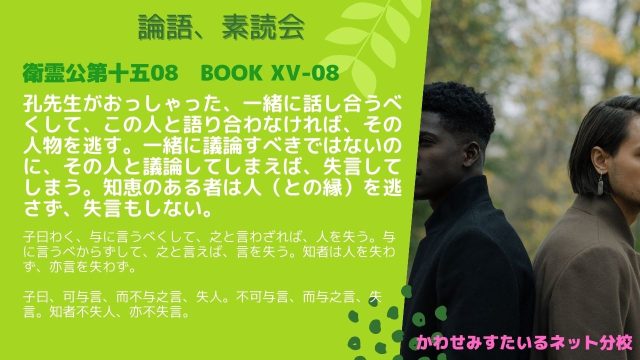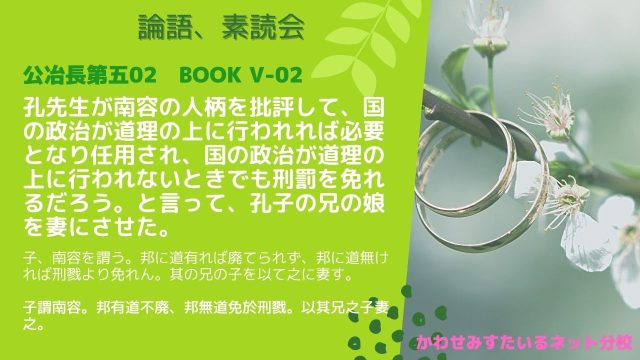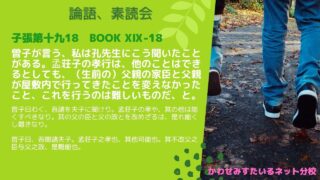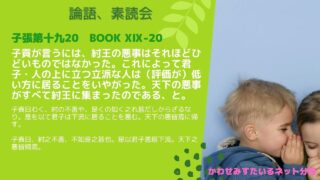魯の大夫・孟孫氏が陽膚を法務担当官にした。(その時、陽膚がその心得を)曽子に尋ねた。曽子が言うには、上の者が正しい政治を失い、人民(の心)が離散して久しい。もし人民の実情を知り得たのであれば、(その境遇を)哀れんで(自分の手柄として)喜んではならない。|「論語」子張第十九19
【現代に活かす論語】
政治を行うものは、自分の手柄を喜ぶのではなく、人民の実情や境遇を哀れむべきである。
【解釈】
孟氏(もうし) … 孟孫(もうそん)氏。魯(ろ)の大夫。
※三桓(さんかん)を参照。「論語」の登場人物|論語、素読会
陽膚(ようふ) … 曽子(そうし)の門人。「論語」の登場人物|論語、素読会
曽子(そうし) … 曾子(そうし)。姓は曾、名は参(しん)、字は子輿(しよ)。孔子より四十六歳若い。
孔子の教えを伝えた第一人者と言われています。「論語」の登場人物|論語、素読会
孟氏陽膚をして士師たらしむ。曽子に問う。曽子曰わく、上其の道を失いて、民散ずること久し。如し其の情を得ば、則ち哀矜して喜ぶこと勿かれ。|「論語」子張第十九19
孟氏使陽膚為士師。問於曽子。曽子曰、上失其道、民散久矣。如得其情、則哀矜而勿喜。
「士師」(しし)は官名、司法をつかさどった。「上」(かみ)は目上の人。「道」(みち)は道義。正しい政治。『道』とは?|論語、素読会 「散」(さんず)は分かれる、集合していたものから離れる。「久」(ひさしい)は時間が長い。「情」(じょう)は真実、実情。「則」(すなわち)は…ならば、それならば。「哀矜」(あいきょう)は不憫に思う、あわれむ。
魯の大夫・孟孫氏が陽膚を法務担当官にした。(その時、陽膚がその心得を)曽子に尋ねた。曽子が言うには、上の者が正しい政治を失い、人民(の心)が離散して久しい。もし人民の実情を知り得たのであれば、(その境遇を)哀れんで(自分の手柄として)喜んではならない。
【解説】
「如得其情」について先人の解釈では、「犯罪の事実を突き止める」とし、その後の手柄を「喜ぶ」という解釈に繋げています。こちらのブログではこの解釈を踏襲して解釈しています。
孔子が話した司法・法務関連の章句には次のようなものがあります。「訴えを聞くのは、私も他の人と同じである。必ずや訴えがないように(そんな世の中に)したい。|「論語」顔淵第十二13」
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九18< | >子張第十九20
【原文・白文】
孟氏使陽膚為士師。問於曽子。曽子曰、上失其道、民散久矣。如得其情、則哀矜而勿喜。
<孟氏使陽膚爲士師。問於曾子。曾子曰、上失其道、民散久矣。如得其情、則哀矜而勿喜。>
(孟氏陽膚をして士師たらしむ。曽子に問う。曽子曰わく、上其の道を失いて、民散ずること久し。如し其の情を得ば、則ち哀矜して喜ぶこと勿かれ。)
【読み下し文】
孟氏(もうし)陽膚(ようふ)をして士師(しし)たらしむ。曽子(そうし)に問(と)う。曽子(そうし)曰(い)わく、上(かみ)其(そ)の道(みち)を失(うしな)いて、民(たみ)散(さん)ずること久(ひさ)し。如(も)し其(そ)の情(じょう)を得(え)ば、則(すなわ)ち哀矜(あいきょう)して喜(よろこ)ぶこと勿(な)かれ。
「論語」参考文献|論語、素読会
子張第十九18< | >子張第十九20