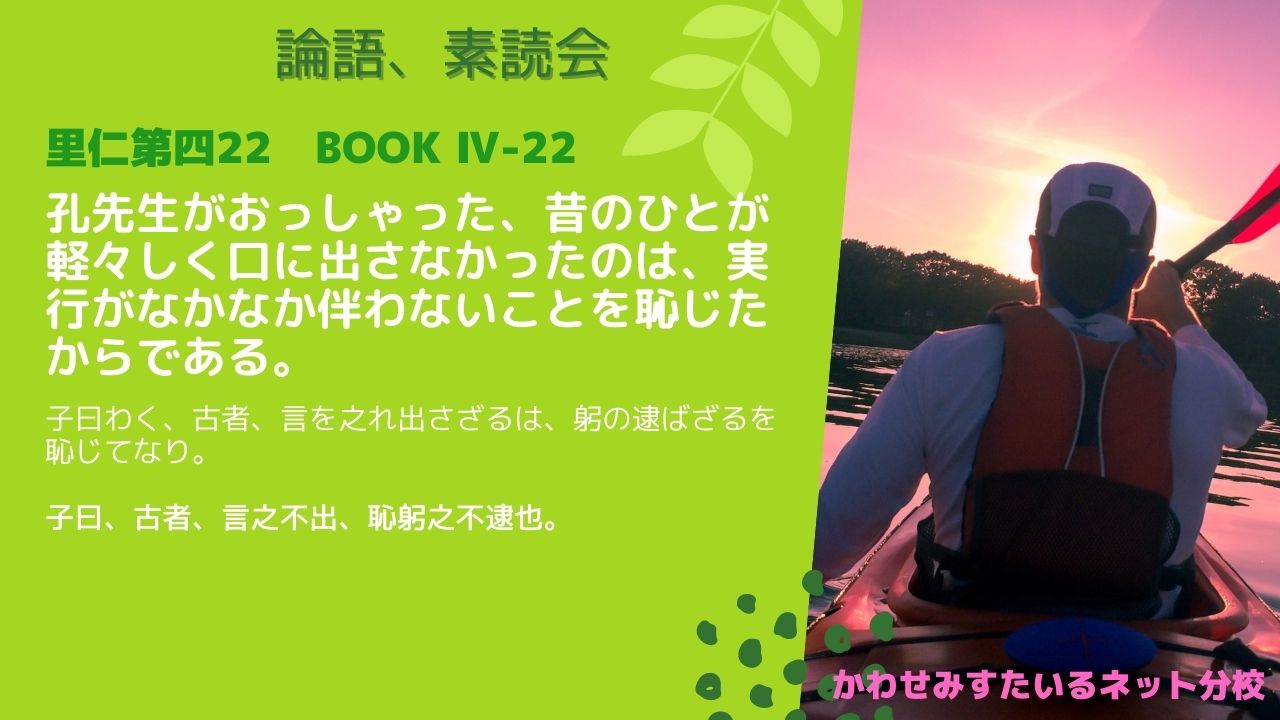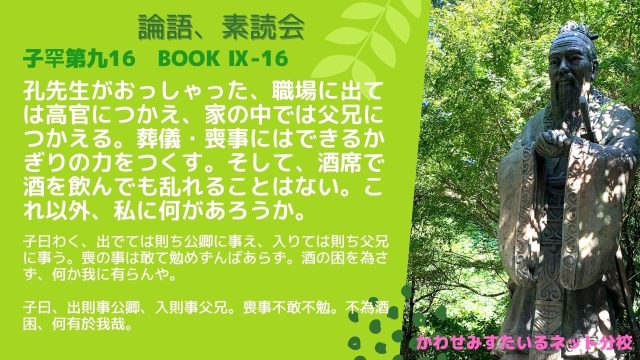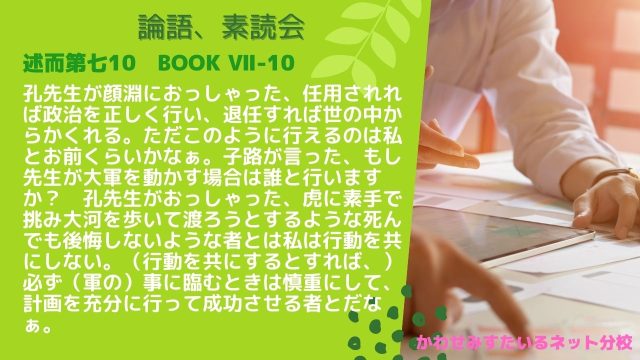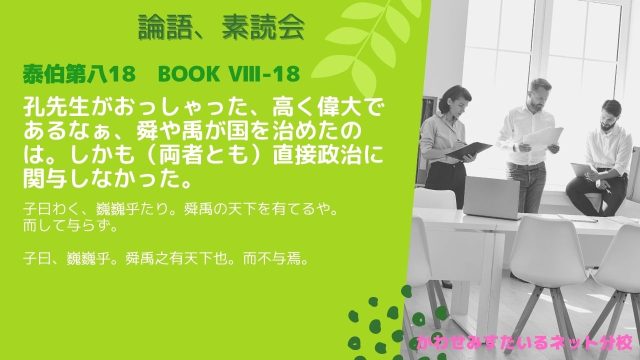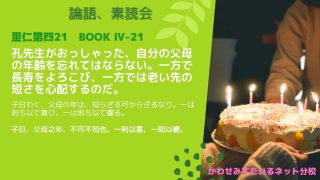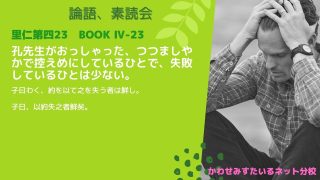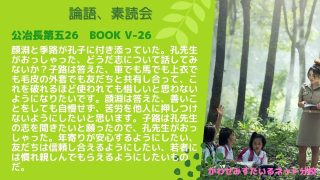孔先生がおっしゃった、昔のひとが軽々しく口に出さなかったのは、実行がなかなか伴わないことを恥じたからである。|「論語」里仁第四22
【現代に活かす論語】
昔のひとに寡黙な人が多かったのは、実行がなかなか伴わないことを恥じたからである。
『論語、素読会』YouTube動画
00:00 章句の検討 里仁第四22
03:25 章句の検討 里仁第四23
10:00 章句の検討 里仁第四24
15:30 「里仁第四」01-26 素読
2021.6.17収録
【解釈】
子曰わく、古者、言を之れ出さざるは、躬の逮ばざるを恥じてなり。|「論語」里仁第四22
子曰、古者、言之不出、恥躬之不逮也。
「古者」(いにしえ)は昔のひと。「躬」(み)は実行力。躬行実践(きゅうこうじっせん)は自ら動いて実践すること。「逮」(およぶ)は及ぶの意。
孔先生がおっしゃった、昔のひとが軽々しく口に出さなかったのは、実行がなかなか伴わないことを恥じたからである。
【解説】
昔のひとを例えに出しているということは、孔子の時代、多弁で口先ばかりのひとが多くなったということでしょう。言行一致は孔子の哲学です。
言行一致の章句を同時に味わうと、孔子の考えが明確になります。
自分の言葉を恥ることがなければ、その言葉を実行することは難しい。|「論語」憲問第十四21」
「君子は自分のことばが自分の行動をこえることを恥じる。|「論語」憲問第十四29」
「まず実行する、ことばはその後です。|「論語」為政第二13」
このように孔子の学び舎では、行動が伴ってこその学びでした。恐らく弁舌が立つものが多かったのか、言葉数が多いものが目立ちがちな中で、どうしてもことばが出てこない人物についても、評価する章句が存在します。このような章句に出合うと、孔子が弟子たちの性格を気遣いながら、必死に思いを伝えていた様子を感じることができます。
「私が回と一緒に話していても、彼は大人しく静かにしているだけで愚かな人物のようだ。ところが、私の面前を離れた彼の私生活を観察してみると、私の教えを充分に啓発している。|「論語」為政第二09」
「意思が強く屈しなく、寡黙で飾り気ない人は、思いやりの心に身を置いて生きることに近い。|「論語」子路第十三27」
「論語」参考文献|論語、素読会
里仁第四21< | >里仁第四23
【原文・白文】
子曰、古者、言之不出、恥躬之不逮也。
(子曰わく、古者、言を之れ出さざるは、躬の逮ばざるを恥じてなり。)
【読み下し文】
子(し)曰(のたま)わく、古者(いにしえ)、言(ことば)を之(こ)れ出(いだ)さざるは、躬(み)の逮(およ)ばざるを恥(は)ずればなり。
「論語」参考文献|論語、素読会
里仁第四21< | >里仁第四23