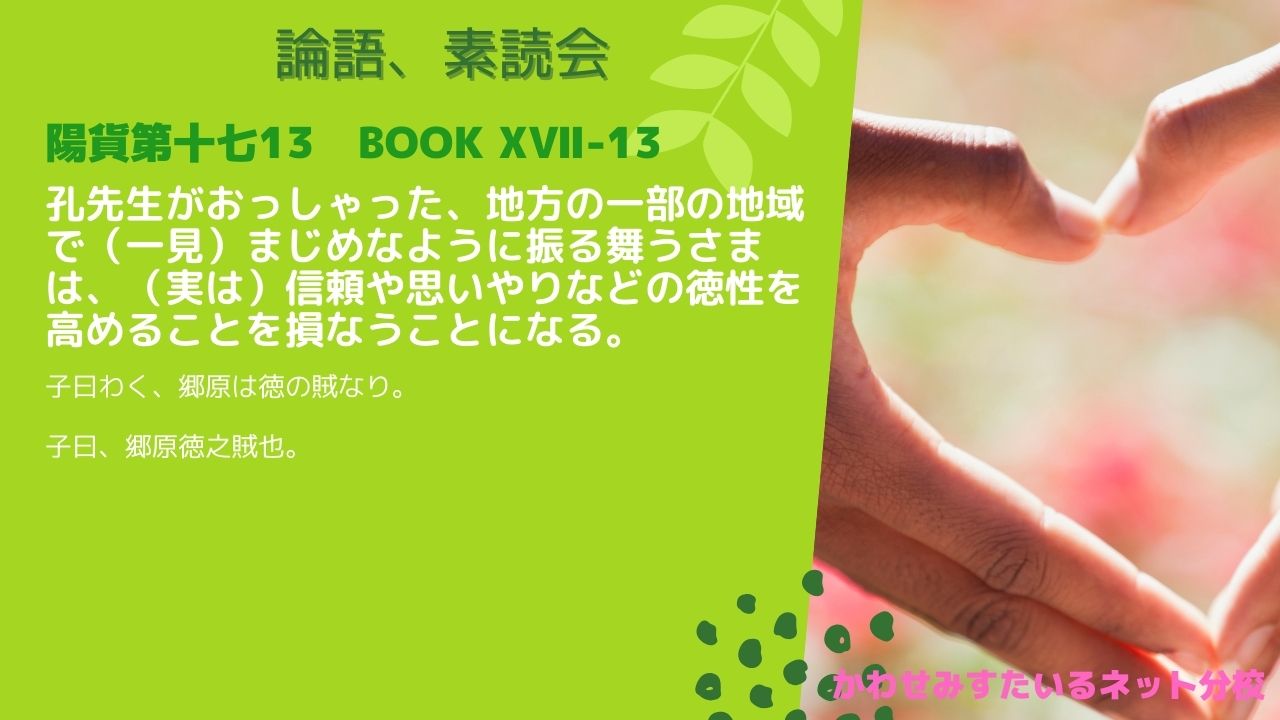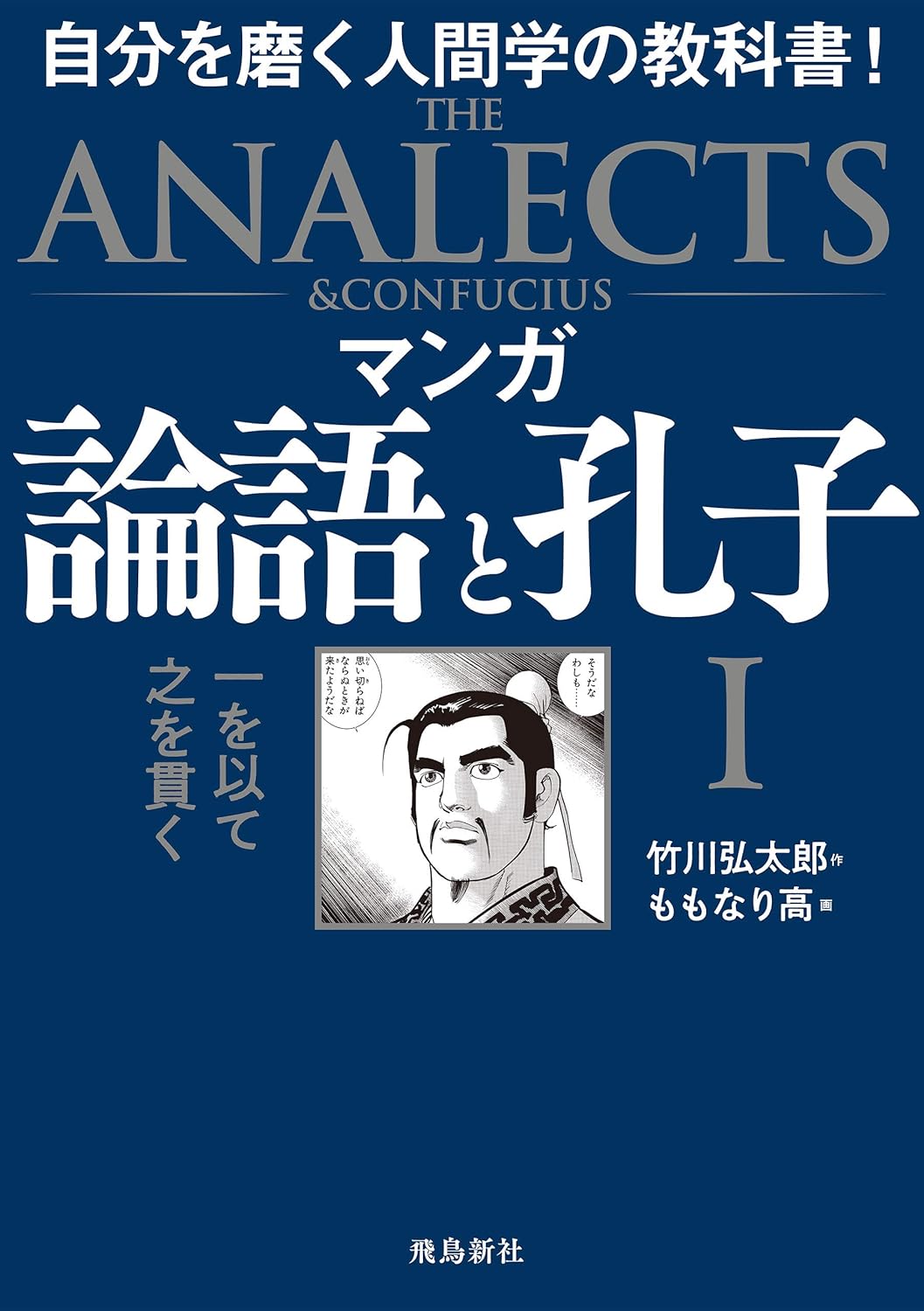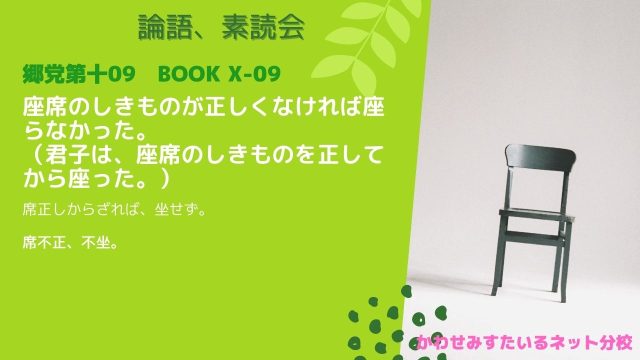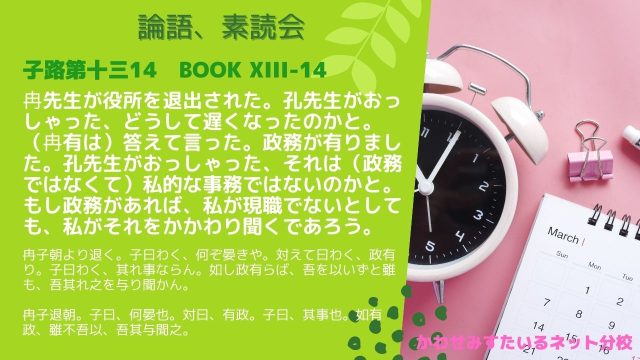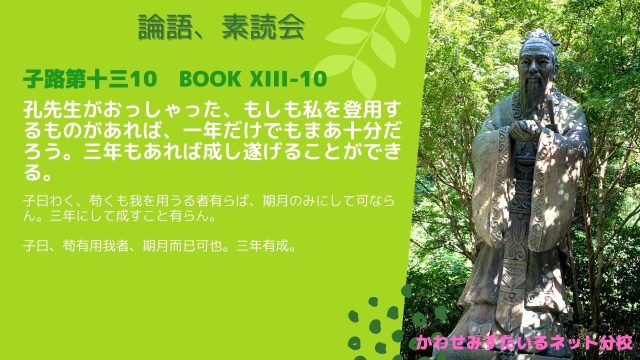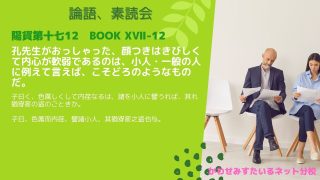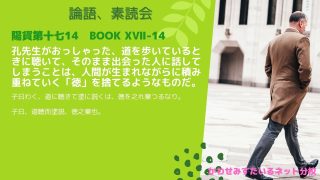孔先生がおっしゃった、地方の一部の地域で(一見)まじめなように振る舞うさまは、(実は)信頼や思いやりなどの徳性を高めることを損なうことになる。|「論語」陽貨第十七13
【現代に活かす論語】
ただただまじめに暮らして周りから認められても、それが徳性を高める(成長する)妨げになることがあります。満足せず日々研鑽を続けたいものです。
【解釈】
子曰わく、郷原は徳の賊なり。|「論語」陽貨第十七13
子曰、郷原徳之賊也。
「郷原」(きょうげん)は誠実でないのに世渡りがうまい、その地の偽善者。「徳」(とく)は人間が生まれながらに高めていく思いやり(仁)や信頼(信)の心。『徳』とは?|論語、素読会 「賊」(ぞく)は反乱を起こし国を傾ける反逆者。
孔先生がおっしゃった、地方の一部の地域で(一見)まじめなように振る舞うさまは、(実は)信頼や思いやりなどの徳性を高めることを損なうことになる。
【解説】
ある文献によると「原」は「愿」だといいます。「愿」(げん)は誠実なさま、まじめなさま。です。「郷」は集落編制単位、周制では一万二千五百戸。五百戸は「党」です。各文献から解釈に苦労しているさまが伝わってきます。本ブログではこの点を採用し解釈します。まず、この章句は、君子・人の上に立つ立派なリーダーを目指す弟子たちに向けた言葉であると設定します。徳の賊とは、徳性を重ねることを妨げること、もしくは徳性を高めない反逆者と考えます。「郷」はそれなりの規模です。そこで誠実であることが悪いのではなく、恐らく狭い地域に収まらず、大きな視点で物事にあたることが大事であるという気づきがあります。また、地方で落ちついてしまうと、その環境に満足してしまい、徳性を高めることが疎かになるということも示唆しているのではないでしょうか。
前の二つの章句をあらためて確認しこの章句にあたると、編者は上辺だけの態度に対して気づきを促していることに気づきます。このことからも、ただ生真面目にして周りから認められることに満足してしまうことへの戒めと理解するのがいいと思います。
「論語」参考文献|論語、素読会
陽貨第十七12< | >陽貨第十七14
【原文・白文】
子曰、郷原徳之賊也。
<子曰、鄉原德之賊也。>
(子曰わく、郷原は徳の賊なり。)
【読み下し文】
子(し)曰(のたま)わく、郷原(きょうげん)は徳(とく)の賊(ぞく)なり。
「論語」参考文献|論語、素読会
陽貨第十七12< | >陽貨第十七14