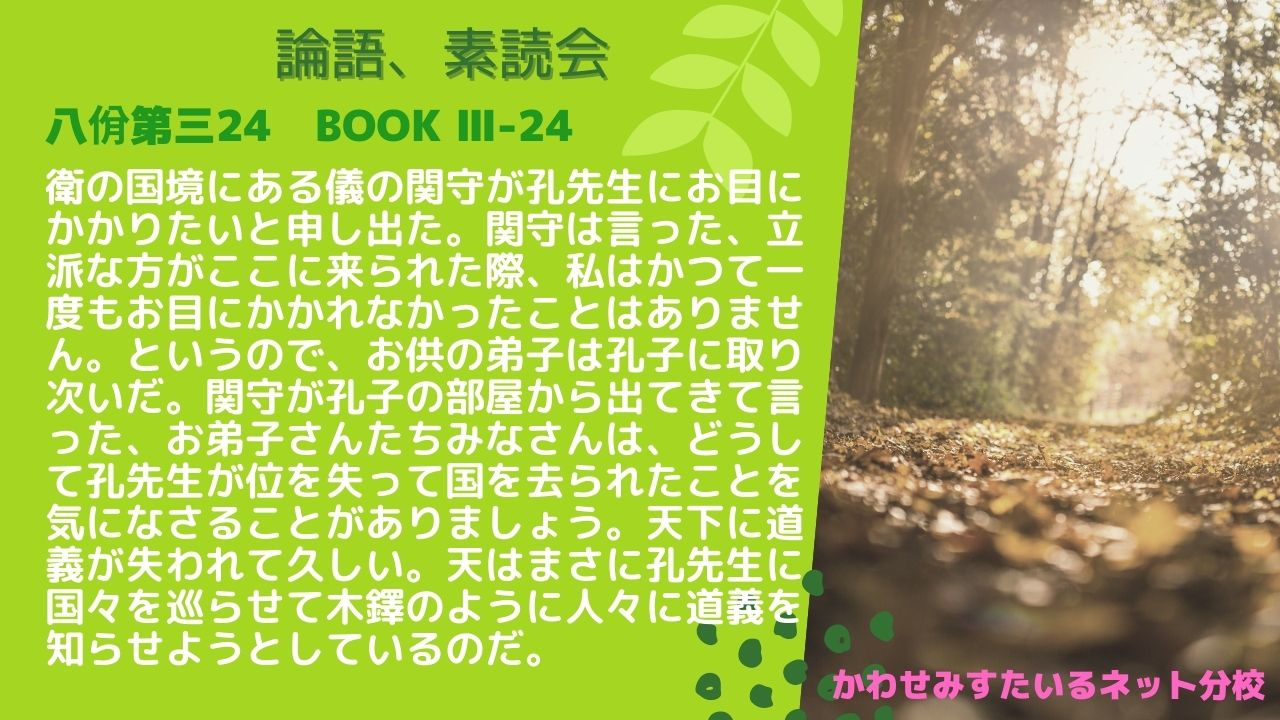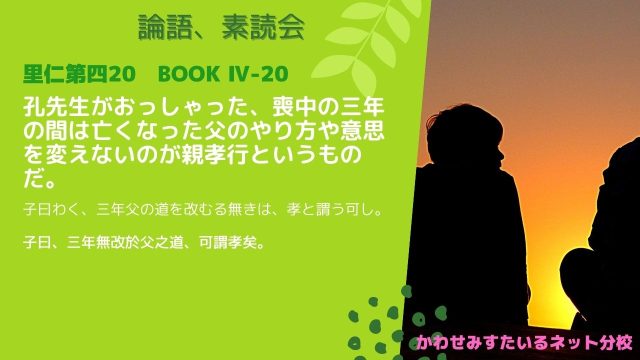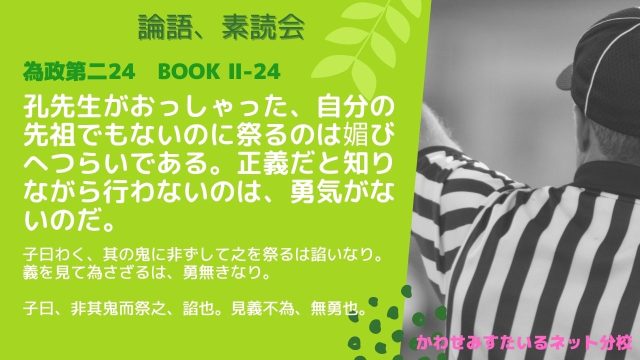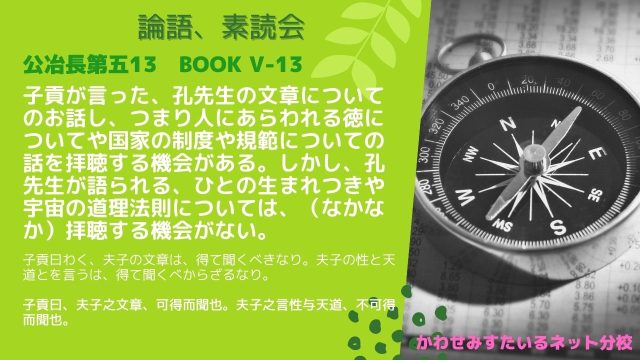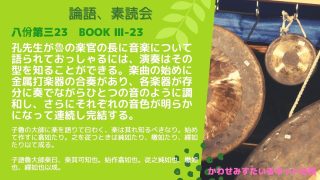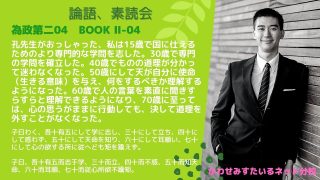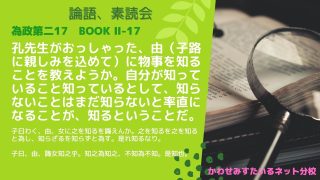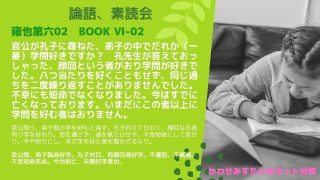衛の国境にある儀の関守が孔先生にお目にかかりたいと申し出た。関守は言った、立派な方がここに来られた際、私はかつて一度もお目にかかれなかったことはありません。というので、お供の弟子は孔子に取り次いだ。関守が孔子の部屋から出てきて言った、お弟子さんたちみなさんは、どうして孔先生が位を失って国を去られたことを気になさることがありましょう。天下に道義が失われて久しい。天はまさに孔先生に国々を巡らせて木鐸のように人々に道義を知らせようとしているのだ。|「論語」八佾第三24
【現代に活かす論語】
人々の深層に響く鈴の音のように、ひとびとに道義道徳を伝えるのも、リーダーとなるひとの役割です。もし環境が変わってそれが不遇なように思えても、そのビジョンを持ち続けることです。
『論語、素読会』YouTube動画
00:00 章句の検討
13:40 「八佾第三」01-26 素読
2021.5.6収録
【解釈】
「喪」は(うしなえるを)または(さまようことを)とも読み下す。
儀の封人見えんことを請う。曰わく、君子の斯に至るや、吾未だ嘗て見ゆることを得ずんばあらざるなり。従者之を見えしむ。出でて曰はく、二三子、何ぞ喪うことを患えんや。天下の道無きや久し。天将に夫子を以て木鐸と為さんとす。|「論語」八佾第三24
儀封人請見、曰、君子之至於斯也、吾未嘗不得見也。従者見之。出曰、二三子、何患於喪乎。天下之無道也久矣。天将以夫子為木鐸。
「儀」(ぎ)は衛の一地方。「封人」(ほうじん)は国境を守る関守(せきもり)。「請見」(まみえんことをこう)はお目にかかりたいと申し出る。「君子」はここでは立派な人。「至於斯也」(ここにいたるや)と読む。「嘗」(かつて)。「得見」(まみえることをえずんば)はお目にかかること。「従者」は孔子と共に旅をしていた弟子たち。「見之」(これをまみえしむ)は孔子に謁見させた、孔子に取り次いだの意。「二三子」(にさんし)は孔子が門人たちを呼ぶときに用いる。この場面では関守が従者である弟子たちをこう呼んだ。「患」(うれう)は気にする。「喪」(さまよう)は位を失い国を去ること。役人を辞めたこと。「道」(みち)は道義。「夫子」(ふうし)は孔子のこと。「木鐸」(ぼくたく)は大きな鈴のようなかね、役人が命令をふれ回る際に鳴らす。すずしい音がするそうです。
衛の国境にある儀の関守が孔先生にお目にかかりたいと申し出た。関守は言った、立派な方がここに来られた際、私はかつて一度もお目にかかれなかったことはありません。というので、お供の弟子は孔子に取り次いだ。関守が孔子の部屋から出てきて言った、お弟子さんたちみなさんは、どうして孔先生が位を失って国を去られたことを気になさることがありましょう。天下に道義が失われて久しい。天はまさに孔先生に国々を巡らせて木鐸のように人々に道義を知らせようとしているのだ。
【解説】
孔子が魯の国の長官を辞めて衛の国で同じ職につくも長くは続かず、衛の国を離れて諸国周遊の旅に出ようという時でしょう。孔子57歳、国境の関守の役人もそれなりの人柄で不遇な人だったようです。この事柄から諸国周遊の旅の目的を明確にし、ともすれば滅入りがちな弟子たちを勇気づけ奮起をうながしました。
木鐸は鐘を鳴らす舌が木でてきているので、甲高いというより柔らかく静かに響く音を奏でると思います。この木鐸を鳴らすように諸国で道義を知らしめたいとう覚悟のようなものも感じます。
「論語」参考文献|論語、素読会
八佾第三23< | >八佾第三25
【原文・白文】
儀封人請見、曰、君子之至於斯也、吾未嘗不得見也。従者見之。出曰、二三子、何患於喪乎。天下之無道也久矣。天将以夫子為木鐸。
<儀封人請見。曰、君子之至於斯也、吾未嘗不得見也。從者見之。出曰、二三子、何患於喪乎。天下之無道也久矣。天將以夫子爲木鐸。>
(儀の封人見えんことを請う。曰わく、君子の斯に至るや、吾未だ嘗て見ゆることを得ずんばあらざるなり。従者之を見えしむ。出でて曰はく、二三子、何ぞ喪うことを患えんや。天下の道無きや久し。天将に夫子を以て木鐸と為さんとす。)
【読み下し文】
儀(ぎ)の封人(ほうじん)見(まみ)えんことを請(こ)う。曰(い)わく、君子(くんし)の斯(ここ)に至(いた)るや、吾(われ)未(いま)だ嘗(かつ)て見(まみ)ゆることを得(え)ずんばあらざるなり。従者(じゅうや)之(これ)を見(まみ)えしむ。出(い)でて曰(い)はく、二三子(にさんし)、何(なん)ぞ喪(さまよ)うことを患(うれ)えんや。天下(てんか)の道(みち)無(な)きや久(ひさ)し。天(てん)将(まさ)に夫子(ふうし)を以(もっ)て木鐸(ぼくたく)と為(な)さんとす。
「論語」参考文献|論語、素読会
八佾第三23< | >八佾第三25